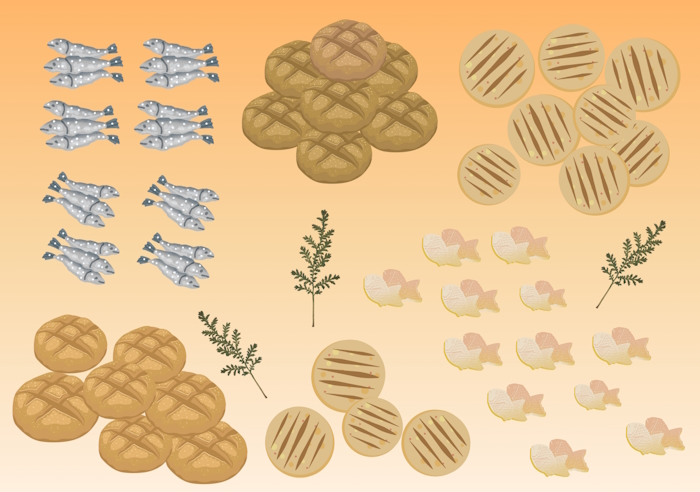文/矢島裕紀彦
今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「東京は晴れ。気温摂氏十度。北東の風五m。ロビンソン風力計が春の日に輝いて回っている」
--新田次郎
ベストセラー小説『八甲田山死の彷徨』で知られる作家の新田次郎が、まだ作家となる以前、婚約中のてい夫人に書き送った「ラブレター」のことばである。いかにも、この人らしい文面だった。
新田次郎は、明治45年(1912)長野県に生まれた。本名・藤原寛人。3歳の頃から中央気象台長官をつとめる伯父・藤原咲平の養子となり、無線電信講習所本科(現・電気通信大学)を卒業後、中央気象台に勤務。6年間にわたって富士山測候所で山岳気象観測に取り組んだ。その後、満州国中央気象台に転任。現地で敗戦を迎え、家族と別れて1年余りの抑留生活を体験した。
引き揚げる家族の方も大変だった。妻の藤原ていは、3人の子供の命をつなぐため、途中、乞食までした。「人間、これまでして生きなければならないのか」という屈辱、切なさを味わった。新田次郎が昭和22年(1947)にようやく帰国して、上諏訪駅で家族と再会したときには、思わず「ああ、おまえたち、生きていたのか」という叫び声が出たという。
昭和24年(1949)、てい夫人は引き揚げ体験をもとに『流れる星は生きている』を書いた。体調すぐれぬ中で、子供たちに遺書を残すようなつもりだった。これが思いも寄らず、100 万部をこえるベストセラーとなった。刺激を受けて、新田次郎も気象庁勤務の傍ら小説を書いた。それが『強力伝』だった。この作品は『サンデー毎日』の懸賞小説の一席となり、さらに単行本化されて直木賞を受賞。新田はその後さらに十年気象庁づとめをし、昭和41年(1966)、文筆一本の生活に入った。
新田の自然描写は抜群だった。てい夫人も、「山の描写をさせたら最高だと思います。多分、新田が気象学をやっていて、空や雲、山の風物のひとつ奥を知っていたことで、表現が違ってくるのだろうと思います」と語っている。
一方で、「女は書けない」といわれた。新田自身もこれを認めていて、夫婦でこんな会話を交わしたこともあったという。
「オレ、女は全然知らないものな」
「私は、女なんですけど」
「あっ、おまえ女だったか。まあ、女を上手に書く人はいくらでもいるから、オレ一人ぐらい書けなくたっていいだろう」
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。
※「サライおみくじ」で今日の運勢をチェック!おみくじには「漱石と明治人のことば」からの選りすぐりの名言が表示されます。どの言葉が出てくるか、クリックしてお試しください。
↓↓↓