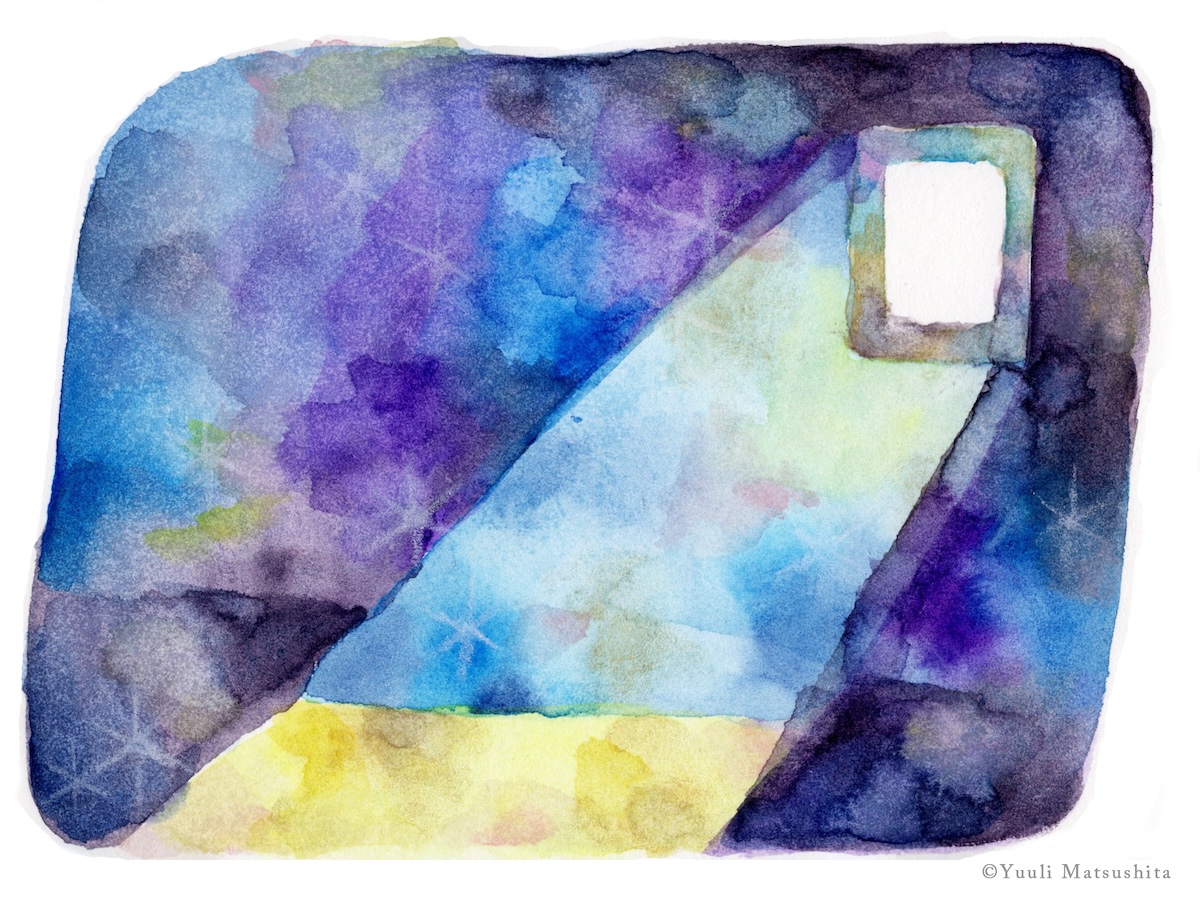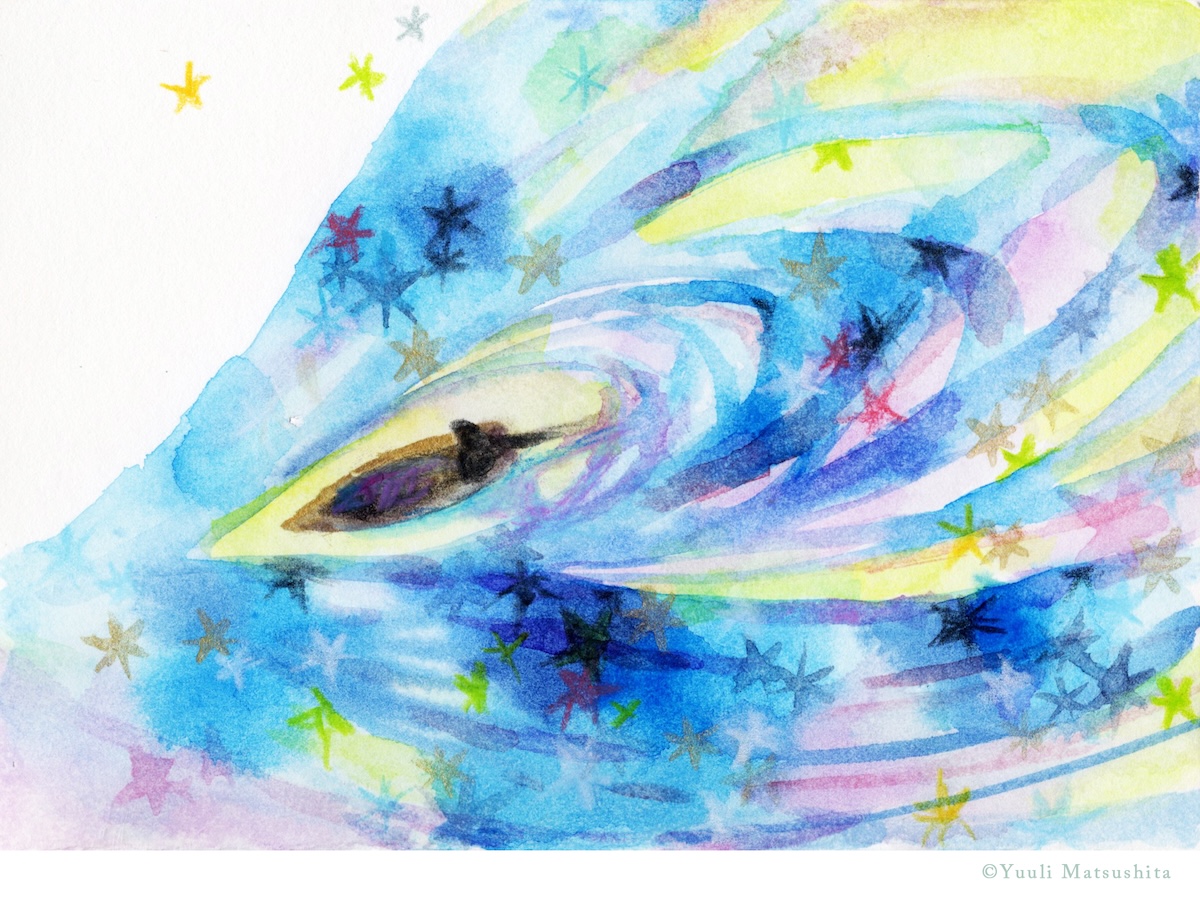一年で最も寒さが厳しくなる時期の入り口、「小寒」(しょうかん)。暦の上では1月上旬に訪れ、「寒の入り」(かんのいり)とも呼ばれます。冬の澄んだ空気や、星空の美しさ、伝統行事や季節の味覚を通して、日本人は古来よりこの季節の変化を味わってきました。
この記事では、旧暦の第23番目の節気「小寒」について下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。
小寒とは?
2026年の「小寒」は、【1月5日(月)】にあたります。一年でもっとも寒い時期を「寒」(かん)といい、「小寒」から始まるので、「寒の入り」といいます。「大寒」(だいかん)に向かって、寒さを増していく時期です。
七十二候で感じる小寒の息吹
小寒の期間は、例年【1月5日ごろ〜1月19日ごろ】。七十二候ではこの時期をさらに三つに分け、自然の細やかな変化を映し出しています。
初候(1月5日〜9日頃)|芹乃栄(せりすなわちさかう)
厳しい寒さの中でも、芹が力強く芽吹き始める頃。食卓に並ぶ七草の一つとしても知られています。
次候(1月10日〜14日頃)|水泉動(しみずあたたかをふくむ)
地中で凍っていた泉が、わずかに動き始める兆しを表す言葉。目には見えなくとも、自然は確実に春へ向かっています。
末候(1月15日〜19日頃)|雉始雊(きじはじめてなく)
雄の雉(きじ)が鳴き始める頃。静まり返った冬野に、命の気配が音となって現れます。
小寒を感じる和歌|言葉に映る小寒の情景
皆さま、こんにちは。絵本作家のまつしたゆうりです。雉の鳴き始めるこの頃、そんな季節にぴったりなこの歌を今月はご紹介します。
あしひきの 八つ峰(を)の雉(きぎし) 鳴き響(とよ)む 朝明(あさけ)の霞 見れば悲しも
大伴家持(おおとものやかもち)『万葉集』4149
《訳》あちこちの峰で雄の雉が鳴き声を響かせている。朝明けの霞を見ているともの悲しくなる。
《詠み人》この歌は、『万葉集』を編纂したと言われている大伴家持が詠んだ歌です。貴族で歌人でもある彼は、心の機微を自然に喩えた歌をたくさん残しています。

雉は日本の国鳥で、固有種。『古事記』にも登場する昔々から馴染みの深い鳥です。国鳥に指定される鳥はだいたい天然記念物が多く、食べている国は少ないのですが(フランスの鶏、ギリシャの鳩など)日本も固有種にもかかわらず身近で食べることができるなんて、なんとも有難く嬉しいですよね!
そんな雉が鳴き始めるのは、繁殖期に入った雌を雄が呼ぶから。「ケーン」と鋭く鳴く声は、空気を響かせるように感じるからか「響む」(とよむ)と万葉歌に詠まれました。
この歌は、そのうちの一首。別の長歌では「鶏は鳴く」に対し「雉は響む」と表現され、鳴き声の伝わる距離感や大きさまで伝わってくる言葉だなあ、と惚れ惚れします。
「響む」は他に雷、ホトトギスの声、山彦などにも使われていることからも、空間に広がり、波のように伝わっていく感覚の言葉なんだと思います。この歌では、遥か遠くの山で鳴いた雉の声が、朝の霞を通して響いてきている。そんな妻を呼ぶ切ない声に満ちた霞を見ていると「心が悲しくなる」という歌なんです。
朝霞のなか遠くで雉が鳴いているだけの景色が、なんともドラマチックに感じられ、まるで霞まで命を吹き込まれたよう……! この感覚を味わうには「今、この時」に集中して、「そこにあるものと繋がる感覚になる」ことでしか得られないと思うのです。
便利な時代になって「素敵!」と思ったときにすぐ写真を撮れる。けれどその時に、この感覚は同居できるでしょうか? 集中しているのは画角や撮れ方で、「この感覚」は置いてきぼりなんじゃないかなと思うのです。
これはスケッチと写真の違いにも似ていて、スケッチしているときに得られるのは対象と繋がる「今ここ」感覚で、写真を撮るだけより不思議とその感覚をよく覚えているんです。
「映え」が共感といいねを生む時代ですが、「わたしの中の感覚」に視点を向け、研ぎ澄ませて感じてみるのも、同じくらい大事なはず。むしろそこから生まれるものを、「映え」として伝える。その順番を、いつも忘れずに暮らしていけたらいいなと思うこの頃です。
皆さまの「今ここ」で心が動いたことは何ですか? ぜひ心を静かにして、見つめてみてください。
「小寒を感じる和歌」文/まつしたゆうり
小寒に行われる|年明けの心身を整える日本の知恵
一年の始まりと重なる小寒の頃は、健やかな一年を願う行事が各地で行われます。寒さが厳しさを増すこの時期は、体をいたわり、神仏へ感謝を捧げる風習が今も息づいています。
七草がゆ(1月7日)
正月7日には、春の七草を入れて炊く粥「七草がゆ」を食します。セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの「春の七草」を食べ、無病息災を祈願します。
本来は一年の邪気を払うための行事ですが、現代では正月のごちそうで疲れた胃腸を労わる意味でも知られています。

十日戎(1月10日)
近畿以西で行われる商売繁盛を祈願する行事が「十日戎」(とおかえびす)。大阪の今宮戎神社、兵庫の西宮神社、京都の恵美須(えびす)神社などで賑やかに開催されます。
境内では「福笹」(ふくざさ)と呼ばれる笹に、鯛や米俵、小判といった縁起物を飾り、商売繁盛を祈願します。
関西の冬を象徴する、活気ある祭礼の一つです。

鏡開き(1月11日頃)
年神様(としがみさま)に供えた鏡餅(かがみもち)を下ろしていただく行事。包丁ではなく、手や槌(つち)で割って雑煮やおしるこに調理するのが習わしです。
「切る」「割る」という言葉を避けて、縁起をかつぎ「開く」と表現する点に、日本らしい美意識が表れています。
小豆粥(1月15日)
京都では小正月に「小豆粥」(米に小豆を加えて炊いた粥)を食べる習慣があり、下鴨神社では「御粥祭」が斎行されます。本来は「御戸開神事」(みとびらきしんじ)と言い、東西御本殿の御戸扉を新年初めて開き、御内陣に神饌をお供えする神事を指します。そこでは、「粥」と呼ばれる「白米・赤米」がお供えされます。
参考:『日本の歳時記』(小学館)
小寒に見頃を迎える花|寒さの中に咲く、ぬくもりの色
寒さに耐え、凛とした姿で咲くその花々は、冬ならではの静かな美しさを私たちに届けてくれます。
水仙(すいせん)
凛とした白い花を咲かせる水仙は、冬の終わりに香り高く清らかな姿を見せる、春を待つ花の一つです。地中海沿岸を原産とし、シルクロードを経て日本へ伝来。越前海岸や淡路島、伊豆半島の爪木崎(つめきざき)などに群生地があり、寒さの中でも可憐に咲く姿は、多くの人に親しまれています。

福寿草(ふくじゅそう)
福と寿をあわせ持つ、いかにもめでたい花。別名「元日草」(がんじつそう)とも呼ばれ、元日に花を咲かせる縁起花として、江戸時代から人工的な栽培が行われてきました。
今も正月には、寄せ植えの鉢が床の間や玄関に飾られ、新年の訪れを静かに寿(ことほ)ぎます。地を照らすように咲く金色の花は、冬の中の太陽のようで、見る人の心を明るい幸福感で満たしてくれるかのようです。

小寒の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む
寒の入りを迎えるこの時期は、冷えた体を芯から温めてくれる旬の食材が出揃います。冬野菜や海の幸には、寒さに耐えて旨みを蓄えた滋味がたっぷり。台所に立つ手もほころぶ、冬のごちそうをご紹介します。
野菜|蕪(かぶ)
「すずな」「かぶら」などの名で親しまれる蕪は、春の七草にも登場する伝統野菜。寒さで甘みが増し、煮物や漬物、すり流しなどさまざまな料理に活躍します。葉も栄養豊富で、浅漬けや炒め物に最適。やわらかく煮含めた白いかぶは、冬ならではのほっとする味わいです。

魚|河豚(ふぐ)
厳しい寒さの中で旨みを増す「河豚」は、小寒の頃に旬を迎える高級魚。刺身の「てっさ」や、鍋の「てっちり」で味わうのが定番です。身は脂肪分が少なく、淡白ながらしっかりとした旨みを持ち、噛みしめるごとに滋味が広がります。身の弾力があるため、薄造りでいただきます。

京菓子|花びら餅
宮中の伝統「歯固」(はがため)に由来し、初釜の茶席で供される祝い菓子「花びら餅」。紅白の羽二重餅に、白味噌餡と甘く煮た牛蒡(ごぼう)を包んだ上品な味わいは、新春の喜びを優しく口に運んでくれます。茶人の心にも通じる、年の初めの特別な一菓(いっか)です。

写真提供/宝泉堂
まとめ
寒さが極まる少し手前、これから本格的な寒さを迎える「小寒」。冬の澄み切った空気が漂い、夜空の星が美しく輝く光景が見られます。また、新年の始まりにあたるこの時期は、古くから年中行事が多く、人々が集う時期です。
現代まで受け継がれる日本の慣習や文化を通じて、日本のよさを再確認できる季節かもしれません。
●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/
監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp
協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com
インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto
構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook