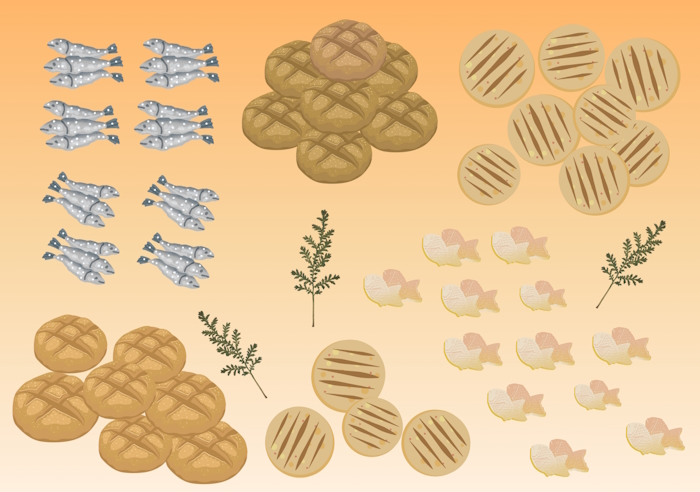今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「スポーツというものに気品があるのは敵が敵ではないからである。競技相手は明らかなその場の敵であっても」
--横光利一
作家の横光利一は明治31年(1898)福島県に生まれた。早稲田大学在学中から小説を書きはじめ、川端康成、菊池寛らと親交を結んだ。当時、文壇の主流をなしていた自然主義的リアリズムに対抗し、新感覚派の旗手として活躍した。
とくに、大正13年(1924)10月、雑誌『文藝時代』創刊号に掲載された『頭ならびに腹』は、書き出しの数行だけで文壇に大きな衝撃を与えた。
「真昼である。特別急行列車は満員のまま全速力で馳けていた。沿線の小駅は石のように黙殺された」
読む者の五感に訴えてありありと映像を想起させる、擬人法と比喩をからめた斬新な文体であった。
横光利一は学生時代からスポーツが得意でもあった。野球、柔道、陸上、水泳、射撃などに並外れた能力を発揮し、教師からも「運動の天才」の折り紙をつけられた。そんな経歴もあってか、昭和11年(1936)37歳の折には、東京日日新聞ならびに大阪毎日新聞の特派記者として、ベルリンで開催されたオリンピックを観にいき、記事を書き送っている。
掲出のことばは、そんな横光が『選手の徳望』と題する一文の中に綴ったもの。横光はこうつづける。
「しかし、これは相手を瞞す敵ではない。むしろ、自分から真の力を引き出さしめ、互に力を向上せしめる味方である。肉体の力の相打つ闘争である運動において、内部の精神が、これと全く相反した共和の美しい精神を抱いているという華々しさ」
ライバルがあってこそ互いに輝きを増すスポーツ選手の特性を、的確に描き出している。
先頃、フィギアスケートの浅田真央選手が現役引退を発表した。彼女には、韓国のキム・ヨナ選手という強力なライバルがいた。そのために五輪の金メダルを逃したのは非常に残念ではあったが、お互いの存在があったからこそ高め合えたことは間違いないだろう。
世界中のファンから愛され、笑顔の下に苦悩を隠し、26歳の若さで現役を退き第2の人生へ踏み出そうとする真央ちゃんを、今後も温かく見守っていきたいものだ。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。