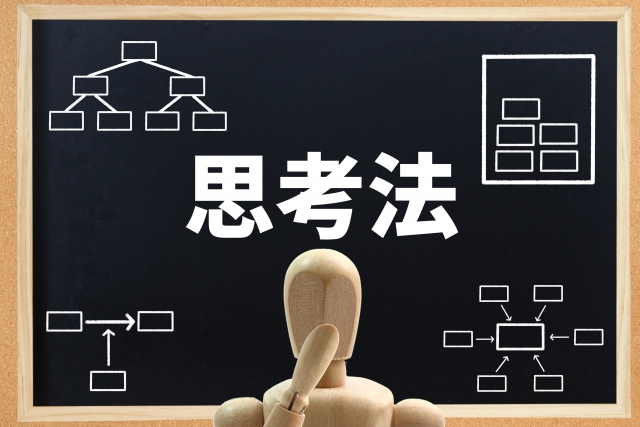文/後藤雅洋
■スタンダードは「結果」
ジョージ・ガーシュウィンはアメリカが誇る大作曲家です。彼は「スワニー」など、多くの人々に親しまれたポピュラー・ミュージックを作曲したばかりでなく、クラシックの管弦楽曲「パリのアメリカ人」や、クラシックとジャズを融合させた楽曲「ラプソディ・イン・ブルー」、そして有名なフォーク・オペラ『ポーギーとベス』など、幅広い音楽分野で優れた業績を残しました。
とりわけ彼がジャズ・シーンに与えた影響は大きく、彼の作曲した楽曲の多くが、「スタンダード・ナンバー」として現在でも多くのジャズ・ミュージシャン、ヴォーカリストたちによって演奏され歌い継がれています。『ジャズ・ヴォーカル・コレクション』第22号「ガーシュウィン・セレクション」(監修:後藤雅洋、サライ責任編集、小学館刊)がヴォーカリストではなく、作曲家を採り上げているのはこうした理由によっています。
ところでジャズ雑誌、ジャズの解説書などに必ず出てくる「スタンダード」という用語について、今一度おさらいしてみましょう。
もとの意味は、「標準」とか「基準」ということですから「スタンダード・ナンバー」とは、いわば「定番曲」とでもいった意味でしょう。ということは、曲が作られた当初は誰もその楽曲が「定番化」するかどうかはわからないのですから、「スタンダードとして作られた楽曲」などというものはありません。「結果として」スタンダード化=定番化するのですね。
またスタンダードは、ヒット曲や持ち歌、十八番ともちょっと違うのです。一時的に大ヒットしても、その後は「懐メロ特集」のような場面でしか聴けない楽曲は、とうてい定番楽曲とはいえないでしょう。また、美空ひばりの「リンゴ追分」など、特定の歌手が得意としても、他の歌い手さんがあまり採り上げないような楽曲は、たんに「その人の定番・十八番」にすぎません。
ちょっと紛らわしいのが、いわゆる「カヴァー」という現象でしょう。もともとは「代役」という意味ですが、転じて「他人の有名曲」を歌うことを意味するようになりました。
1960年代には、多くのアメリカン・ポップスが日本の歌手たちによってカヴァーされましたよね。ちょっと思いつくだけでも、ザ・ピーナッツが歌ったカテリーナ・ヴァレンテの「情熱の花」とか、中尾ミエによるコニー・フランシスの「可愛いベイビー」などは、私の青春時代を彩る名曲でした。まさに日本のポップス・シーンは、洋楽カヴァー歌手たちによって開かれたのです。
では、カヴァーとスタンダードはどこが違うのでしょう? どちらも複数の歌手たちによって歌われた有名曲という点では同じです。まず、カヴァーでいう「他人」はおおむね作曲家ではなく、カテリーナ・ヴァレンテやコニー・フランシスといった「歌手」を意味している場合が多いのですね。ここがポイントです。ご存じのように「情熱の花」はベートーヴェンの「エリーゼのために」をアレンジしたものですし、「可愛いベイビー」もコニー・フランシスが作曲したわけではありません。
■SMAPとスタンダード
また、先ごろ解散騒ぎが話題となったSMAPの「世界に一つだけの花」は、作詞・作曲した槇原敬之の曲というよりは「SMAPの歌」としてファンの間で定着しているようです。ですから、作曲者本人が歌うと「セルフ・カヴァー」などという、直訳すれば「本人が代役」といった不思議な形容が付けられてしまうのですね。こうした楽曲も名曲には違いありませんが、「多くの歌手が採り上げる定番曲」というスタンダードの概念からは少し外れるようです。
作曲者・槇原自身が、面白い主旨の発言をしています。要約すると、「自分が歌うと『借り物』のような気がする。まるでSMAPの歌を歌っているように感じる」。また彼は作曲家の心得として、「歌う人の声に合った曲を作る人がいい」とも言っているのですね。こうした発想は、あらかじめ歌う歌手のキャラクターを想定して作詞・作曲する場合には当然の配慮でしょう。
しかしこうした配慮は楽曲と歌手の結びつきを強くする半面、「汎用性」という観点からすると、どうなのでしょうね。微妙ですよね。私もあの歌は「5人が歌詞を歌い継いでこそ」、という気がどうしてもしてしまいます。
他方「スタンダード」は、ミュージカルや映画の挿入歌である場合が多く、必ずしも「特定の歌い手」を想定しているとは限りません。その結果、明らかに声質が異なる黒人歌手も白人歌手も同じ楽曲を歌いますし、男女の立場入れ替えや、陽性キャラ歌手と翳りの表現が得意なシンガーが同じ楽曲を取り上げることも珍しくありません。
というか、そうでなければ「定番化」などという現象は起こりようもありませんよね。
■スタンダード≠ジャズ
ここでちょっと話題を変えてみましょう。アメリカ・ポピュラー音楽史です。日本とアメリカの音楽文化でいちばん違うと思うのは、アメリカでは家族揃って歌を歌ったりピアノで演奏したりする文化が根付いているところです。そのためには何が必要か? 楽譜なのですね。
というわけで、まだラジオやレコードが未発達だった19世紀の末から20世紀初頭にかけては、楽譜が音楽産業の稼ぎ頭だったのです。その結果、ミュージカルなどで使われる楽譜の出版社がニューヨークのブロードウェイと6番街に挟まれた地域に密集していました。
そこではお客さんに楽譜の内容を聴かせるため、始終ピアノで「見本演奏」が行なわれていたので、通りのあちこちから楽器の音色が響いていました。それがまるでブリキの鍋を叩いているように聴こえたので、この通りはそのものズバリ「ブリキ鍋通り=ティン・パン・アレー」と称されたのです。
この通称地名から転じ、これらの音楽出版社で活躍する作曲家たちを「ティン・パン系作曲家」などというようになったのです。
そして今回の主人公、ジョージ・ガーシュウィンを含むミュージカル、ポピュラー作曲家のほとんどは、この「ティン・パン・アレー」で活躍していたのですね。結果として「スタンダード作家=ティン・パン・アレーの作曲家」という図式がほぼ成り立つのです。
ところで、ここで重要な指摘をしておきたいと思います。それは「スタンダード=ジャズ」ではないということです。
「スタンダード」はたんに「多くの歌手たちに歌い継がれた定番曲」という意味しかなく、それを「ジャズ的に」歌ってこそ、ジャズになるというところが大切なポイントです。「ジャズ的」とは、必ずしもスキャットをしたりすることを意味しません。そうではなくて、楽曲の魅力に打ち勝つほどの個性を込めた歌唱という意味なのです。