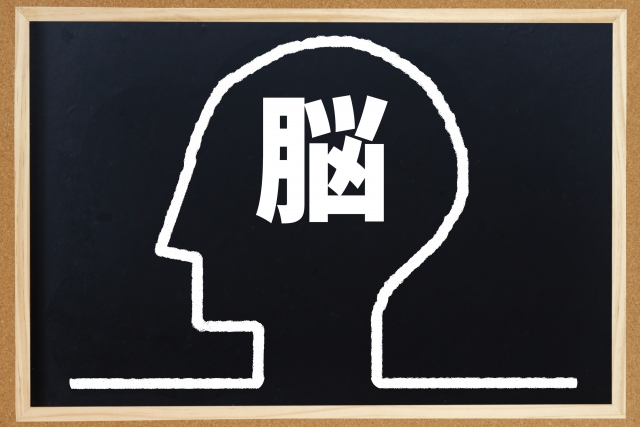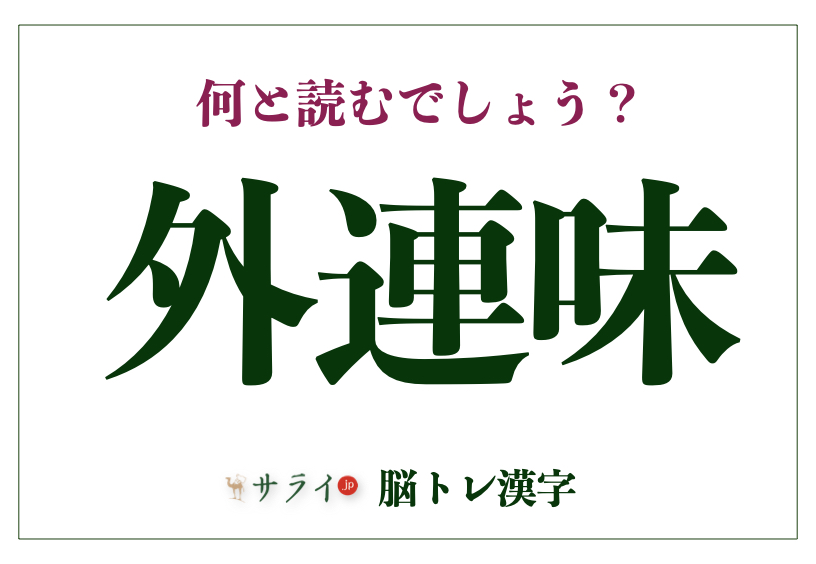文/鈴木拓也

高齢化社会の進展とともに、子の世話をしながら、親の介護にもあたる「ダブルケア」が社会問題となりつつある。
中心となる世代は、働き盛りの中高年。仕事との両立もせねばならず、「理解され難い苦悩がある」と指摘するのは、ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんだ。
旦木さん自身も、ダブルケアの経験者。父親が重篤な脳梗塞で倒れたものの、当時小学生の娘と仕事を抱える身。おいそれと遠方の実家に通えず、不安な日々を送ったという。
以来、旦木さんはダブルケアをテーマに、当事者らを取材した記事を発信。そうして得た知見をもとに、このたび『しなくていい介護 「引き算」と「手抜き」で乗り切る』(朝日新聞出版 https://publications.asahi.com/product/25493.html)を上梓した。
本書には、ダブルケアにとどまらず、親の介護に役立つ情報が、惜しみなく盛り込まれている。基本的なスタンスは、「介護はもっと楽にしていい」。手を抜けるところは抜くためのノウハウの集大成にもなっていて興味深い。
今回は、その一部を紹介しよう。
親が元気なうちに支援サービスを把握
旦木さんが最初に取り上げるのは、都内に住む澤田さんの事例。実家は、車で2時間ほどのところにあり、父親に先立たれた母親が一人で暮らす。その母親は、認知症を患い要介護3の状態で、ヘルパーが時折訪ねている。
澤田さんはフルタイムで働いており、そう簡単には実家に行けない。代わりに、室内に「見守りカメラ」を設置し、毎日欠かさず電話をして、母親の様子を随時確認する日々。しかし、認知症は次第に悪化し、施設への入所を考えるように。
澤田さんのように遠距離介護をする人は少なくないが、「最低限な帰省」で済むよう、さまざまなアドバイスが書かれている。
1つは、親がまだまだ元気なうちに、介護に関する知識を身につけておくことだ。参考となるのが、各自治体が発行している『高齢者福祉のしおり』といった名称の冊子。ひととおり目を通し、公的な支援サービスを把握しておく。これを、「知っているのと知らないのとでは、心持ちに大きな差が出る」ため、外せないとのこと。
もう1つが、帰省のおりに親の変化を「五感で観察する」こと。例えば「視覚」なら、「同じ話を何度もするか?」「偏ったものばかり食べていないか?」といった異変。あてはまる点があれば、親のかかりつけ医や地域包括支援センターなどで相談し、助言を仰ぐ。そのほか、元気なほうの親やきょうだいと情報を共有したり、ご近所さんたちとのコミュニケーションも確立させておくなど、やっておいていいことはたくさんある。面倒だが、介護は先憂後楽。決してムダにはならない。
介護費用を子が負担してはいけない
本書には、親の介護費用の負担がかさみ、苦境に陥った高蔵さんの事例も挙げられている。
高蔵さんは、20年あまりメーカーに勤務して退職。教育関係機関の事務員を経て、アパレル会社へ転職した。実家住まいで、母親と二人暮らし。離婚して出ていった父親とは疎遠となっている。
2019年に母親の認知症が発覚。その翌年には胃がんと診断され、胃の半分を切除する大手術を受けた。訪問看護やデイサービスを利用しつつ介護に努めたが、仕事との両立が厳しくなり離職。しかし経済的な不安から、まもなく派遣社員として働き始めた。2025年に入って、派遣先の子会社から正社員登用の話があり、時間的に条件が良くなるため、現在は正社員として働いている。
派遣社員時代の高蔵さんは、母親の医療費、介護費に多くのお金がかかり、貯金どころではない苦しい状況であったという。こうした事態を防ぐための対策についても、旦木さんは記している。
大原則は「親の介護費用は親が出す」だ。
もちろん、経済的に余裕があるなら良いだろう。しかしそうでないならば、「親しき仲にも礼儀あり」。介護費用のことで後々、親子関係、きょうだい関係を壊したくないなら、絶対になあなあにしてはならない。(本書168pより)
ここで言う介護費用には、介護のために仕事を休んで減給したぶんはもちろん、子が実家に通う際に発生した交通費も含む。これらは、親のお金でまかなうことを徹底する。また、制度を知らなかったばかりに、余計にお金が出ていく事態も防ぐ。例えば、親は課税世帯か非課税世帯なのか、障害者控除を受けられるかどうか、世帯分離をするのはどうかなど。調べるのは億劫に感じるかもしれないが、ここはしっかり把握しておくべきだ。
旦木さんは、「自分の人生は、自分を優先にしていい」と訴える。実の親だからと、自分の人生を犠牲にするのは、他ならぬ親だって望んではいない。ダブルケアだけでなく、親の介護に備えるために、本書は有益な手引書となってくれるはずである。
【今日の介護力を高める1冊】
『しなくていい介護 「引き算」と「手抜き」で乗り切る』
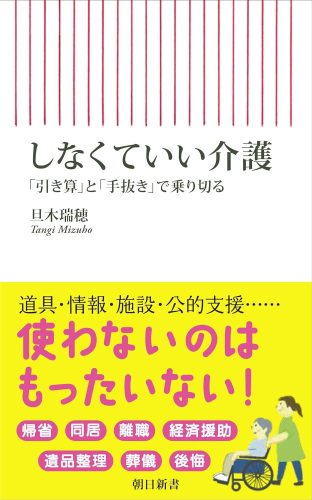
定価1045円
朝日新聞出版
文/鈴木拓也
老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。