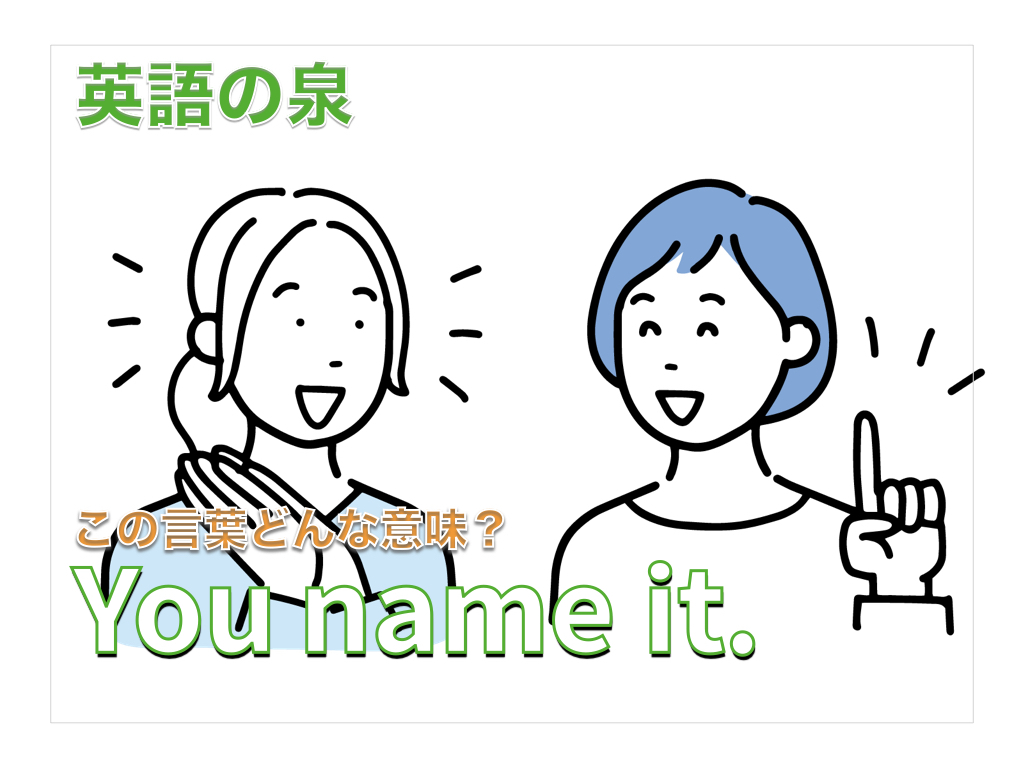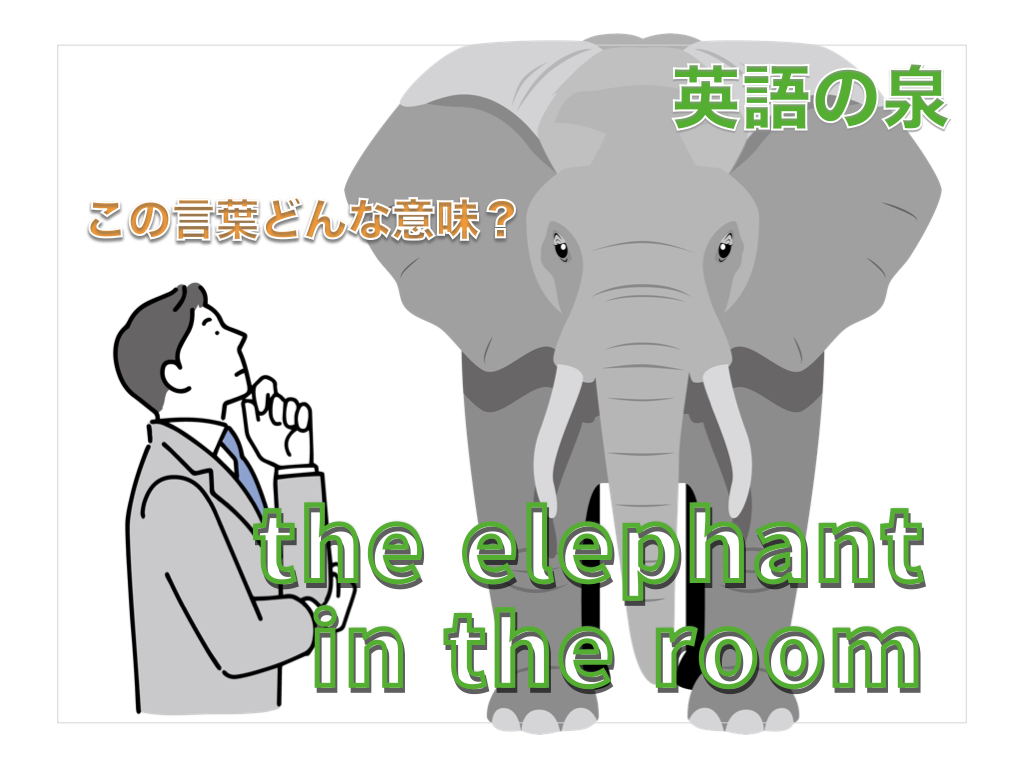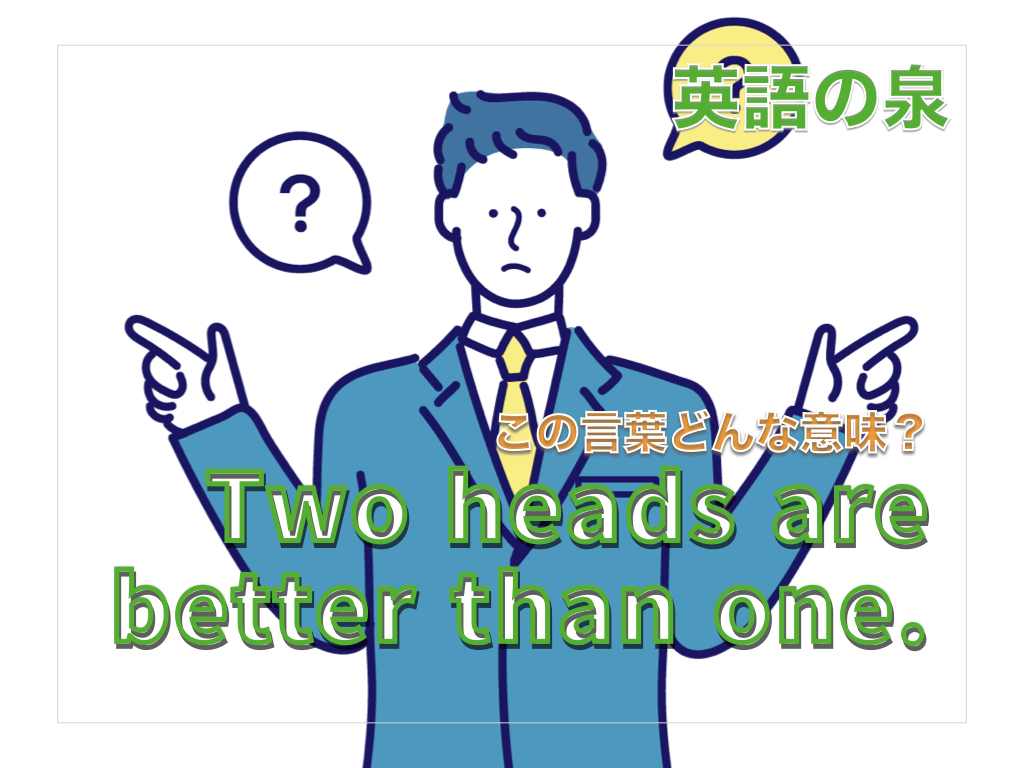英語を学んでいると、日常的に使われるシンプルな単語ほど奥が深いと気づくことがあります。その代表的な例のひとつが“OK”。とてもなじみ深い言葉ですが、どのように生まれ、なぜ世界中で使われるようになったのでしょうか。
今回は、“OK”の語源や意味についてご紹介します。

目次
「OK」ってどこからきた?
「OK」の意味は?
「OK」や「大丈夫」をめぐる表現
「OK」と文化のひろがり
最後に
“OK”ってどこからきた?
“OK”という言葉の起源については、さまざまな説があります。新聞にはじめて“OK”という表記が登場したのは1839年。当時、アメリカでは、ことばを略したり崩したりする遊びが流行し、“all correct” をわざと “oll korrect”と書いたのがはじまりだといわれています。
その後、アンドリュー・ジャクソン第7代アメリカ大統領が “All Correct”を誤って、“Oll Korrect” にしたというエピソードや、ネイティブ・アメリカンのチョクトー語「okeh」に由来する、という説などと共に、“OK”はアメリカ全土に広まりました。
ただ、これらの説には決定的な証拠がなく、今も議論が続いています。
それでも、“OK”という言葉は、そのシンプルな響きと使いやすさから、時代や国境を越えて広がり、今では世界中で使われるようになりました。
コロンビア大学で教鞭をとる言語学者ジョン・マクウォーター(John McWhorter)博士は、著書の中で“OK”は世界で最も広く使われている言葉のひとつであると記しています。
参考:John McWhorter 著 The Great Courses: The Story of Human Language, Manhattan Institute刊
“OK”の意味は?
“OK”は、「いいよ」「大丈夫」「わかった」などの意味で使われる便利な言葉ですね。たとえば、頼みごとに対して“OK”と返事をすれば「了解、やります」という意味になり、お誘いに“OK”と答えれば「いいね、参加します」となります。このように、さまざまな場面で肯定や承認を表す言葉として使われます。
また、 “How are you?” と聞かれたとき、私たちはよく “so-so.” と答えがちですが、英語話者には “Why?”(どうして?)や “What happened?”(何かあったの?)と聞き返されることが少なくありません。これは “so-so.” が「まあまあ」というよりも、「あまりよくないけれど、なんとかやっている」といった少しトーンの低いニュアンスを含むためです。そのため、日本語の「まあまあです」のニュアンスを伝えたいときには、“I’m OK.” を使うのがより自然です。
さらに、“OK”は場面や言い方によって微妙に意味が変わります。少し消極的な「まあ、いいけど……」という意味にもなります。また、“OK?”と語尾を上げて尋ねると「いいですか?」と承諾を確認する意味になり、状況によっては「わかった?」と問いただすニュアンスにもなります。このように、“OK”は一言で多様な意味合いを持つユニークな言葉なのです。
“OK”や「大丈夫」をめぐる表現
英語には、“OK”や「大丈夫」といった意味を持つ表現がたくさん存在します。それぞれに微妙なニュアンスの違いがあり、場面や相手に応じて使い分けます。
たとえば、誰かの提案や依頼に肯定的に応じるとき、“Sure.”(もちろんです)や “Of course.”(承知しました)がよく使われます。どちらも丁寧で柔らかな印象で、ビジネスシーンでも使える表現です。
もう少しカジュアルな場面では、“Sounds good.”(いいね)。さらに親しい間柄では “Yep.” (うん)のような軽やかな表現も使われます。“Absolutely.”(もちろん!絶対に!)は、より強い気持ちを伝えることができます。

また、“No problem.”(問題ありません)もよく用いられます。同様に、“Got it.”(わかった)や “Alright.”(了解です)も、カジュアルな場面からビジネスシーンまで幅広く使われています。
世界のさまざまな言語に存在する“OK”
“OK”という言葉と似た表現は、世界のさまざまな言語にもあります。しかし、文化ごとに微妙な違いがあるようです。
たとえば、日本語の「大丈夫」は、時に「本当は問題があっても平静を装う」という意味が含まれることがあります。何かを断るときに「大丈夫です」と言うこともあり、英訳が難しい表現のひとつといわれています。
またロシア語の「Ничего(Nichego)」は、直訳すると「何もない」ですが、実際には「問題ない、大丈夫」といった意味で使われます。これは、ロシアの伝統や文化に根付く「耐え忍ぶ」精神と関連しているとも言われています。
また、スワヒリ語には「Hakuna Matata」という言葉があります。ディズニー映画『ライオン・キング』でも登場するこのフレーズは、「どうにかなる」「心配ない」という意味があります。これは人々に、今この瞬間に集中し、自分の力ではどうにもならないことを気にしないよう促す言葉で、人生を楽しみ、悩みすぎないようにというメッセージが込められています。

このように、“OK”や「大丈夫」といった言葉の奥には、それぞれの文化が反映されています。ひとつのことばにも、その土地固有の考え方や価値観があるのはおもしろいですね。
最後に
アメリカのバンド、Imagine Dragons(イマジン・ドラゴンズ)に “It’s OK” という曲があります。
It’s OK to be not OK
Imagine Dragons「It’s OK」より
(大丈夫じゃなくても、大丈夫)
この歌には、完璧じゃなくてもいい。感情を抑え込まなくていい。そしてどんな自分も受け入れようとの、力強いメッセージが込められています。
多層的な意味が込められた“OK”という言葉。その柔軟さと寛容さがあるからこそ、文化や言語の壁を越えて広く受け入れられ、世界中で使われ続けているのかもしれません。
●執筆/池上カノ
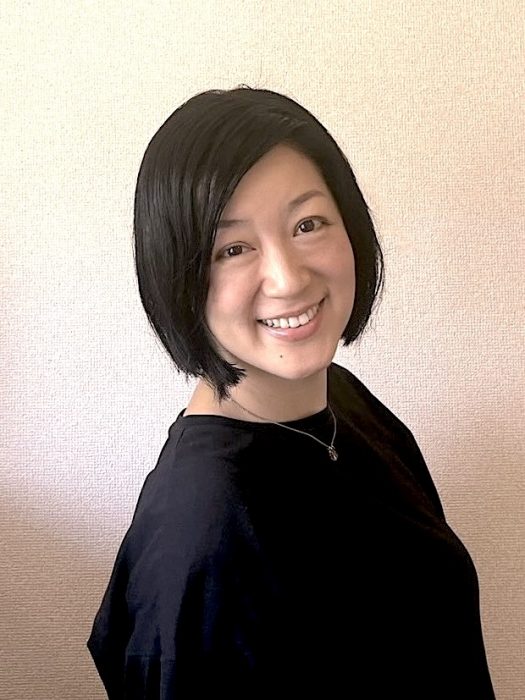
日々の暮らしやアートなどをトピックとして取り上げ、 対話やコンテンツに重点をおく英語学習を提案。『英語教室』主宰。 その他、他言語を通して、それぞれが自分と出会っていく楽しさや喜びを体感できるワークショップやイベントを多数企画。
インスタグラム
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com