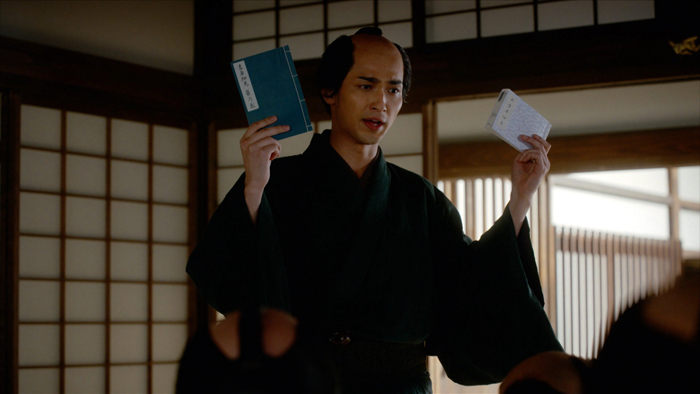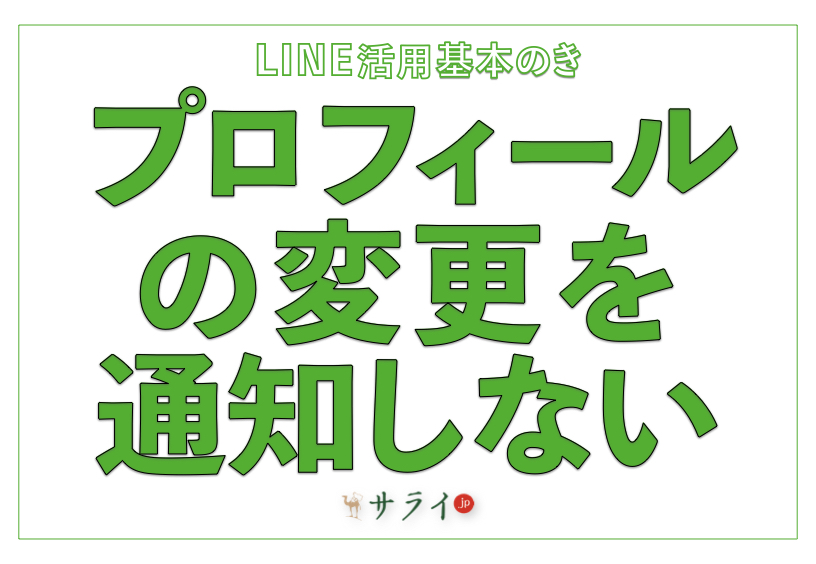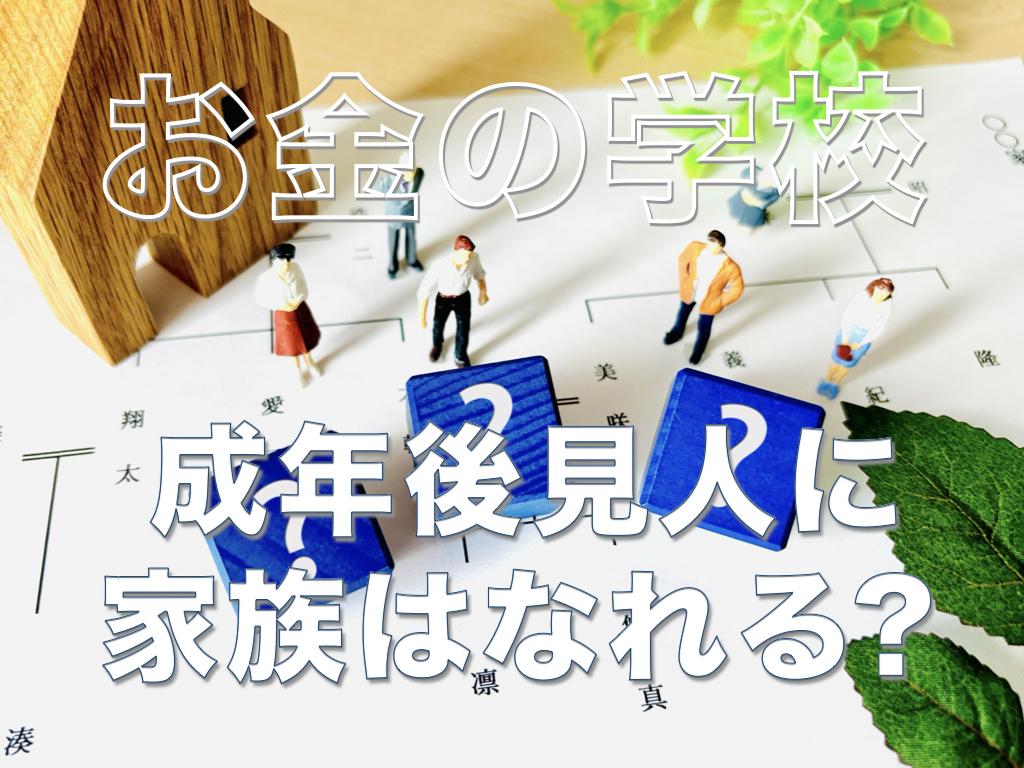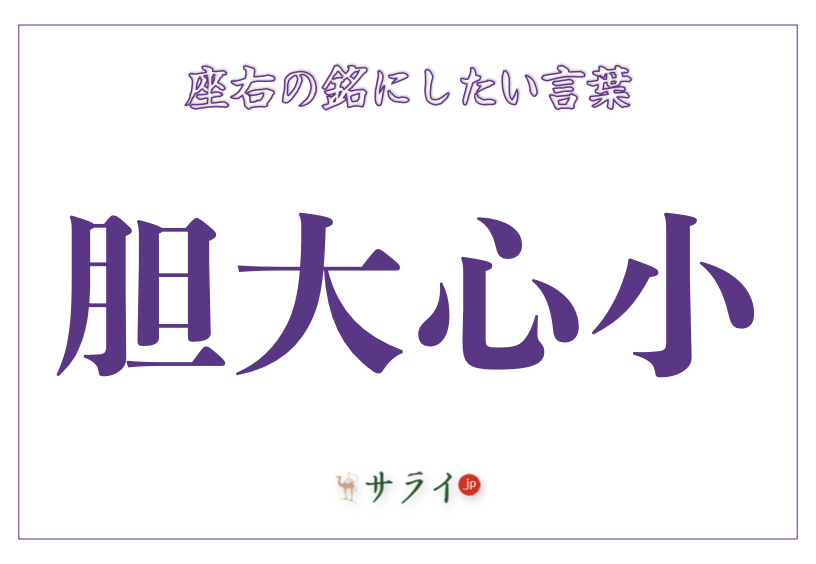ライターI(以下I):大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)の影響で、日本橋を散策する人が増えているようです。やっぱり天下の日本橋ですからね。
編集者A(以下A):『初めての大河ドラマ 「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』の受け売りですが、現在の日本橋は明治44年(1911)に架けられた20代目の橋ということです。
I:重要文化財なんですよね。その『歴史おもしろBOOK』には、『べらぼう』の時代から営業している日本橋の老舗も掲載されています。現代でも三越(越後屋)を筆頭に、にんべん、日本橋西川、小津和紙店、さらには、売上高が2兆円を超える「国分」(『べらぼう』当時は大国屋)など、名だたる企業が今も健在なのが日本橋という町なんですよね。
A:そして、蔦重のころからあるといえば、福徳神社がありますね。蔦重の時代どころか、江戸幕府第2代将軍徳川秀忠が参詣して「芽吹稲荷」と命名したといわれる神社。現在の社殿は平成26年に再興されたものです。この鳥居の前に立つと、道路を挟んで右後方にコレド室町1、2があるのですが、その道路の一部は江戸時代には川でした。川の終わるところに福徳神社があり、その先に浮世小路が伸びていて、そこには『べらぼう』でたびたび仕出し弁当が登場している江戸屈指の料亭『百川(ももかわ)』があったといわれています。ちょうど、今の福徳神社の社務所がある辺りです。
I:発酵学と食文化論の第一人者として知られている東京農業大名誉教授の小泉武夫さんの著書『幻の料亭「百川」ものがたり―絢爛の江戸料理―』『幻の料亭・日本橋「百川」―黒船を饗した江戸料理』などによると、百川は明治維新後に忽然と姿を消したといわれています。
A:江戸が東京に変わり、江戸とともに去った店と、三越(越後屋)やにんべんのように町とともに今日まで歩んできた店とがあったわけです。『べらぼう』のころといえば、現在は豊洲にある市場(魚河岸)は、もとは日本橋にありました。大正12年(1923)の関東大震災で壊滅的な被害に遭うまで約300年間、日本橋は江戸の台所だったわけです。築地に東京都中央卸売市場(築地市場)が開かれたのは昭和10年(1935)になってから。豊洲に移ったのが平成30年ですね。
I:今も日本橋のたもとに、魚河岸の碑がありますね。他にも、江戸時代の日本橋を偲ぶことができる場所がまだまだたくさん残っています。現在の地下鉄小伝馬町駅の方まで行くと、蔦重が経営していた耕書堂跡もありますし(大伝馬町)。
A:小伝馬町駅のすぐそばには、江戸の人々に時刻を知らせた時の鐘が今も残っています。現在の鐘は宝永8年(1711)に鋳造されたものですので、蔦重もこの鐘の音を聞いていたんだと思うと、感慨深いものがあります。
I:時の鐘がある十思公園の横には、平賀源内が獄中死したといわれる小伝馬町牢屋敷跡があり、展示館では牢屋敷の模型が展示されています。十思スクエアでは、「蔦重ギャラリー」も公開中なんですよね。黄表紙(複製)や浮世絵なども展示されています。
A:来週日曜日、10月26日には、日本橋・京橋まつりが開催されます。日本橋から京橋にかけて華やかなパレードが催されたり、五街道の起点であり江戸の台所として全国各地の食べ物などが集まった日本橋らしく、全国各地の名産品を集めた「諸国往来市」なども開催されるようです。
I:地下鉄三越前駅の地下道には江戸時代の日本橋の様子を描いた絵巻『熈代勝覧』(複製)が展示されていて、今の日本橋と当時の日本橋の様子を両方感じながら散策できますし、デジタルスタンプラリー「蔦重と歩く日本橋~べらぼうなる江戸の名所をたずねて~」といったイベントもあります。日本橋・京橋まつりと併せて、この際、思い切り日本橋を楽しんでもらいたいですね。
水路が発達していた江戸
A:以上のような話を日本橋の方々とお話している中で出てきた話題ですが、「そういえば、日本橋って出てきたっけ?」という問いがありました。当時は木の橋だったと思うのですが……。
I:そういう話なら、私も聞かれました。「そういえば、百川から吉原に仕出し弁当を届けるときは舟を利用したと思うし、蔦重なんかも水路をつかって移動したと思うんだけど、そういう場面あんまりないよね」っていうんです。
A:以前、取材で江戸の水路を体験したことがありますが、まさに「縦横無尽に江戸を奔る」という感じでしたし、船に乗って日本橋を潜るというのはレア体験でした。
I:江戸は水都だったという人もいますからね。小説なんかだと、わりと舟で行き来する場面が描かれますが、ドラマでは予算の都合もあるでしょうし、絵作りも難しいでしょうし、あえて描いてないということなんですかね。
A:なるほど。でも水路を奔る蔦重も見たかったかも。
I:そんなこといったら「べらぼうめ!」って叱られますよ(笑)。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり