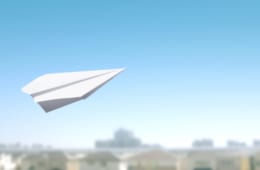文/印南敦史

1980年代初頭から中期にかけ、小さなレンタルレコード店で働いていたことがある。
ご存知の方も多いと思うが、かつてレンタルレコードは音楽ファン、とくにお金のない若者には欠かせない存在だった。
山下達郎、竹内まりや、松任谷由美、大滝詠一、杉山清貴&オメガトライブ、稲垣潤一などの人気が非常に高く、それらのアーティストの新譜が出ると、大学生を中心とした若者が次々と借りていった。
当時は、21世紀になってそれらの音楽が「シティポップ」と呼ばれることになるなど考えもしなかったが、1970年生まれだという『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』(栗本 斉 著、星海社新書)の著者も、レンタルレコードを通じてシティポップに触れていたようだ。
仲良くなった友だちが音楽好きだったこともあって、彼からレンタルレコードでダビングしたというたくさんのカセットテープを借りた。この中には、流行り物に混じって、大滝詠一、杉 真理、松任谷由美、稲垣潤一、佐藤 博などがあった。そして、当時の情報源はFMラジオだったので、暇さえあればラジオを聴いていた。NHK-FMの『サウンドストリート』では佐野元春、坂本龍一、山下達郎がDJをしていたし、FM大阪では日曜の朝に角松敏生が『FMライトアップタウン〜角松敏生のポップフリーク〜』という番組を持っていた。(本書「おわりに」より)
この記述からは、私がレンタルレコード店のカウンターでレコードを貸していたころ、彼は借りる側にいたことがわかる。また、著者の生まれ育った大阪と我が地元の東京とでは多少の違いもあっただろうが、NHK-FM『サウンドストリート』など、聴いていたラジオ番組にも共通点がある。
記憶に残っているアーティストにも、そこにまつわる記憶の断片にも重なる部分が少なくないのはそのせいだ。
しかし、それは当時を知る人すべてに当てはまることでもあるだろう。そして、1980年代に青春時代を過ごした多くのサライ世代の方々の思い出とも、どこかでつながっているに違いない。
さて、著者のそんな実体験をバックグラウンドに持つ本書は、1975年に発表されたシュガー・ベイブ唯一のアルバム『SONGS』をそのジャンルの始祖と位置づけ、おもに1970年代後半から80年代にかけての作品を中心に、シティポップの名盤100枚を紹介したディスクガイドである。
懐かしいアルバムが網羅されているだけに、パラパラとページをめくっているだけでも楽しめるはずだ。ただし、そうはいっても本書の目的は昔を懐かしむことだけではない。過去の名盤のみならず近年の“ネオ・シティポップ”にも焦点を当てることによって、シティポップが持つ音楽的な魅力を掘り下げているのである。
だが冒頭でも触れたように、そもそもシティポップとは明確な音楽ジャンルを指すものではない。著者もまた、本書の序文でそのことを指摘している。
シティポップはジャンルというよりは、その音楽から醸し出される印象を重視している。もちろん、ソウル・ミュージック、AOR、ソフトロック、フュージョンといった音楽性の根幹があるとはいえ、それらのジャンルがそのままシティポップに当てはまるというわけではなく、あくまでも雰囲気なのだ。(本書「はじめに」より)
納得できる話だし、「無理やり定義づけるならば」と前置きしたうえで、著者がその音楽を「都会的で洗練された日本のポップス」と表現していることにも共感できる。ある意味で当時のリスナーは、それ以前のフォークやニューミュージックとは異なる“洗練”を求めていたのではないだろうか。無意識のうちに、ではあると思うが。
その点については、以下の記述が興味深い。
「いかに洋楽に近付けるかが命題だった」というのは、当時のシティポップ系のアーティストに関わっていたスタッフから、直接聞いた言葉だ。70年代に入り芽が出始めたシティポップ系アーティストは、歌謡曲やフォークが全盛だった日本の音楽シーンと差別化するために、とにかくスタイリッシュな洋楽のサウンドをお手本にしていった。当時のレコード会社ではどうしても歌謡曲やフォークのような売れ線がメインだったこともあり、シティポップ系の音楽にはそのアンチテーゼとしての側面もあった。それだけに貪欲に洋楽を取り入れ、実験的なまでに新しい試みを行なっていたのである。(本書168〜169ページより)
まさにうなずける話である。あのころたしかに、洋楽は目指すべき音楽だった。だから先鋭的な国内アーティストたちは洋楽に追いつこうと切磋琢磨していたのである。
しかし、そういったシティポップの実験精神を皮膚感覚として知っているからこそ、「いま、海外のクラブではDJがプレイするシティポップに合わせて多くの客が盛り上がっている」などという話を聞くと、時代は変わったんだなあと感じずにはいられない。
だが本書で取り上げられている作品を改めて聴いてみれば、たとえ時代が変わろうと、その本質は決して変わらないということを実感できるだろう。

星海社新書
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。