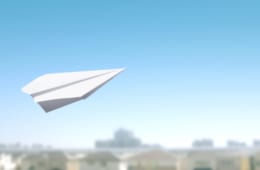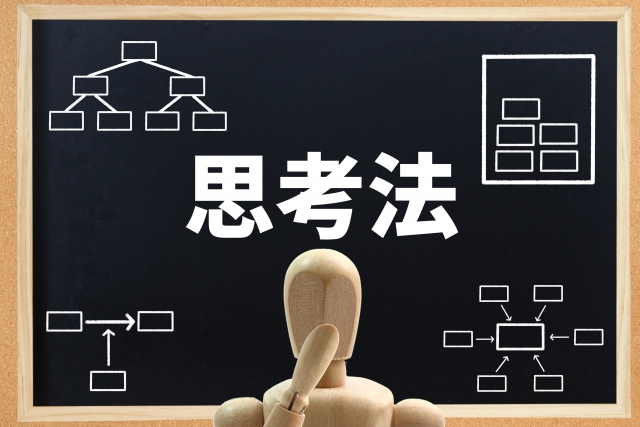文/印南敦史

ご存知の方も多いかと思うが、『昭和歌謡は終わらない』(近藤勝重著、幻冬舎)の著者は社会派で知られるジャーナリスト。ニュースコメンテーターとして出演されているTBSラジオ「荒川強啓デイ・キャッチ」は私もよく聴いており、そのたび説得力に満ちた言葉に感心している。
そんな著者は、昭和歌謡に対する深い愛情の持ち主でもある(同番組でもときどき、「DJ勝重」として昭和歌謡のDJ役を務めているほど)。1945年生まれということなので、団塊世代よりも少し上。まさに昭和歌謡全盛の時代を生きてきたということになる。
昭和歌謡ブームというのは、きのうきょうに始まったものではありません。また、あすあさってに終わるものでもありません。
ですから、じっくり時間をかけ、はてさてこのブームは何ゆえに巻き起こり、人々に何をもたらし、日本の音楽文化、いやいや日本の文化全体にどんな影響を与えてきたのか、などなど熟慮すべきテーマなのです。(本書「はじめに〜今宵も昭和歌謡となるその理由(わけ)は」より引用)
特徴的なのは、昭和歌謡ブームについて、いくつか興味深い考え方を示しているところだ。まず最初は、「昭和歌謡には、とことん『売らんかな』で作られた歌が多かった」という指摘である。
歌謡曲がビジネスである以上、根底にそうした意図があるのは当然の話。それは、歌謡曲がJ-POPと呼ばれるようになった現代においても同じだろう。しかし、その思いの強さが、昭和歌謡全盛期は明らかに違っていたというのだ。
阿久悠さんの詞だってヒットしたのは5000曲のうち200曲、打率は4分だと。だからこその「売らんかな」なんですね。(中略)力のある作詞家や作曲家、それに編曲家、歌手によっては振付師のみなさんが、これまた業界では知らぬ人のいないレコード会社やプロダクションの敏腕プロデューサーの元に結集しての「売らんかな」ですから、あっといわせたいとか、ウラをかいて一発逆転に出たいとか、意見の集約は大変だったと思われます。(本書「はじめに〜今宵も昭和歌謡となるその理由(わけ)は」より引用)
ひとことで昭和歌謡といっても、スタイルや表現方法は多種多様。だが、誰がどのように歌ったものだったとしても、それら一曲一曲に並々ならぬ情熱が込められていたということだ。
たしかにあの時代は、ちあきなおみ「喝采」から山本リンダ「どうにもとまらない」まで、いまの時代では考えられないほど個性豊かな楽曲であふれていた。しかも、そこにいるだけで目立ってしまうような、ユニークな存在感を放つ歌い手がゴロゴロしていた。
しかし、彼らの存在感や歌は、我々からは見えない場所で動いていた人たちの力があったからこそ際立ったのだ。昭和歌謡が持つ普遍性の根拠として、それは十分に納得できる話ではないだろうか。
そして、昭和歌謡が広まった大きな要因として著者が指摘しているのが、カラオケの影響だ。名曲は数あれど、カラオケ抜きに今日のような昭和歌謡ブームはなかっただろうというのである。そのことを語るにあたっては、歌手・五木ひろしの自著『昭和歌謡黄金時代』中の文章が引用されてもいる。
カラオケがない時代を振り返ると、たとえばお酒が出る場所での「歌」といえば、ジュークボックスであったり、有線放送であったりで、それは絶対的に「聴く」ものでした。それがカラオケによって、お客さん自らが「歌う」時代になったのです。革命的変革です。(本書「はじめに〜今宵も昭和歌謡となるその理由(わけ)は」より引用)
個人的にはカラオケが苦手なので、そんなことは考えたことすらなかった。だが言われてみれば、なるほどそのとおりなのかもしれない。現代においては「つながり」の重要性が説かれるが、ある意味においてカラオケは、人と人とをつなぐ先駆的なツールだったと考えることもできそうだ。
さて、昭和歌謡の特徴について、著者がもうひとつ挙げているのは「生き方」。すなわち人生との関わりだ。豊かな叙情性によって心模様を表現したものが多かった昭和歌謡には、聴き手に「あり得たかな、別の人生が……」と思わせるものが多かったというのである。
可能性という言葉は本来確率の問題ですから「ある」と続くもので、「ない」はおかしい。しかしながら年齢を重ね自分の何たるかがわかればわかるほど「可能性ーーない」となる不条理。
さはさりとて生きていかねばならない。歳月は人を待たず、です。寂しいことです。だからでしょう、可能性がまだまだあったあの頃にふと引き戻されて思いがこもる。思い出は死にませんから。
(本書「はじめに〜今宵も昭和歌謡となるその理由(わけ)は」より引用)
社会のあらゆる構造がアナログからデジタルへと移行し、いまやソーシャルメディアによるコミュニケーションが当然のものとなっている。その結果、LINEなどでのやりとりが増えた。飛び交うのは、短文化し、含みのない言葉だ。
もちろんそれが世の流れである以上、闇雲に否定してみたところで意味はない。しかし、そんな時代だからこそ、情感豊かな昭和歌謡がなおさら心に響くと著者は主張するのだ。思い入れの強さがそう言わせている部分もあるだろうが、とはいえ共感できる話でもある。
「なかにし礼&阿久悠」「吉田拓郎とフォーク歌謡」「百恵ー聖子ー明菜」「昭和歌謡とかしの力」などなど、本書において著者は、昭和歌謡をさまざまな角度から捉え、独自の考え方を提示している。「なるほど、たしかにそうだなぁ」と思える話がポンポン飛び出してくる。
しかも、語りかけるような文体だから、なおさらリラックスして読み進めることができる。そのため読者は読んでいるうち、カラオケスナックのカウンターで著者のうんちくに耳を傾けているような気分になれるかもしれない。
そんなテイストを備えた本だからこそ、お気に入りの日本酒などを舐めながらゆっくり楽しみたいところだ。BGMには、もちろん昭和歌謡を流して。
『昭和歌謡は終わらない』
幻冬舎
2018年8月発売

文/印南敦史
作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』などがある。新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。