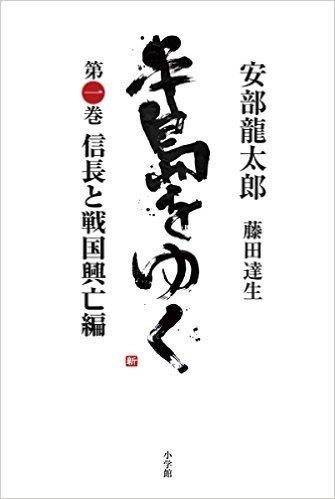『サライ』本誌連載の歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」と連動して、『サライ.jp』では歴史学者・藤田達生氏(三重大学教授)による《歴史解説編》をお届けします。
文/藤田達生(三重大学教授)
「半島をゆく」渡島半島編の楽しみは、道南の和人が築いた館群「道南十二館」のうち、代表的な館跡を訪問することである。
「道南十二館」の名称は、享徳3年(1454)に津軽十三湊(青森県五所川原市)の安藤政季が南部氏に追われ武田信広らとともに道南に渡り、配下の武将を12の館に配置したことに由来するといわれる。
取材初日の最初に訪ねたのが、北斗市の郷土資料館。来館の目的は、矢不来館跡(北斗市)からの出土品を拝見することである。実は、志苔館と勝山館と花沢館(発掘中)以外の館は、発掘がほとんど進んでいないという。したがって、矢不来館跡からの発掘データはきわめて貴重なのである。


北斗市郷土資料館蔵の注口土器
発掘を担当された学芸員の森靖裕さんからは、同館は箱館(函館)近郊の志苔で和人とアイヌとの間に起きた対立をきっかけとする長禄元年(1457)のコシャマインの蜂起直後の1460年頃に築かれ、下国安藤盛季の一族が入ったと解説された。なお、この戦いで12館のうち、茂別・花沢以外の10館は落城したという。
道南の中世史は、箱館から松前、上ノ国にかけての海岸沿いの12館を橋頭堡とする和人と、アイヌとの交流史にほかならない。ただし困難を伴うのは、同時代史料が伝存しないことである。これまでの研究は、基本的に松前藩が正保3年(1646)に編纂した『新羅之記録』によるものだから、当然のこととして「松前藩史観」が貫かれており、客観性という問題がクリヤーできない点にある。
出土品のなかでひときわ目を引いたのは、すばらしい天目茶碗と青磁碗だった。これらからは、戦国時代の安藤氏が、明との交易をおこない、高級陶磁器を輸入したことがわかる。実は、他の館跡からも茶の湯に関係するこのような遺物が出土するという。北の武士たちが、文化的な環境にあったことがうかがわれる。

安藤一族が明との交易で入手したと思われる天目茶碗。
もうひとつ重要だと感じたのは、中国銭をはじめとする質量とも豊富な出土銭である(郷土資料館では117枚が整理されている)。12館の館主は、奥羽各地から渡海したと思われるが、武田信広のように由緒を若狭守護武田氏に求める者がいる。
元来、道南から十三湊さらには加賀から若狭にかけての広域流通ネットワークがあり、海の商人的領主の一部が道南地域に根を下ろし、先住の和人集団を従えて館主となったとみるべきであろう。なお、出土品のなかには越前焼が含まれている。
『新羅之記録』には、中世の最盛期には若狭から箱館に年3回商船が来航したと書かれている。中国や本州からもたらされる商品は、和人が消費するだけではなく、アイヌとの交易に必要不可欠な物品でもあった。アイヌからは、昆布・鮏・鰯・鰊やアシカ・アザラシ・トドなどの皮革がもたらされた。
アイヌ交易がもたらす富は、莫大なものだったといわれる。たとえば、奥州藤原氏の繁栄は、蝦夷地も含む北方との交易にあったとする指摘がある。あるいは、源頼朝がわざわざ奥州に出兵した理由に、北方との交易権の奪取にあったとする説がある。執権北条氏は、「関東御免津軽船」といわれる大船で日本海交易に乗り出している。これらから考えられることは、貨幣経済が早期に浸透していたことである。
●松前に遺された巨大城郭「大館」
資料館を後にした私たちは、森さんのご案内で茂別館跡(国指定史跡)に向かった。この館は、嘉吉3年(1443)に十三湊の城主安藤盛季が渡海して普請したものという。大手前の道筋にクルマを止めて、海が近いことから交易を前提とした立地であること、縄張は「大館」と「小館」からなることの説明があり、そのうえで矢不来天満宮の鎮座する「大館」跡に向かった。
ここは、大型土塁に囲まれており、広大な曲輪が切岸によって独立していることが確認できた。このような遺構からは、筆者がかつて訪れた奥羽の諸城郭が思い起こされた。たとえば、天正19年(1581)の九戸一揆の際の有力拠点となった姉帯城をはじめとする南部氏配下の城郭である。やはり、道南の館は奥羽の南部氏や安藤氏の城郭の影響を受けているに違いないと確信した。
懇切にご案内いたいた森さんとはここで別れて、私たちは松前町の大館(国指定史跡)をめざした。海岸沿いの道路を走るのだが、はるか遠くに下北半島の先端に位置する大間付近が見えた。私たちは、北海道新幹線の玄関口となった木古内町を経由して松前町に向かった。車窓からは、新たな木古内駅の立派な駅舎が目に焼き付いた。松前線や江差線が廃止された結果、北海道最南端の駅になったという。
大館跡からは、松前町教育委員会の学芸員・佐藤雄生さんにご案内いただいた。永正10年(1513)に、アイヌ人の攻撃をうけて大館は陥落した。翌年には、蠣崎(松前)光広が入って徳山館と名を改めて、蝦夷地の支配拠点とする。慶長11年(1606)に福山館(後の松前城)を築いて移転したため、廃されたといわれる。ただし遺物の残存状況からは、松前氏の隠居城として維持されていたと佐藤さんは指摘される。

松前町教育委員会の佐藤雄生学芸員とともに(右が筆者)。
佐藤さんのご案内で、徳山大神宮近くの小道から登城する。ところで、大神宮の脇にはロシア人提督「ブローウニン幽閉地」の石碑があった。ブローウニンとはゴローニンで、高等学校の教科書では「ゴローニン事件」として登場する。ディアナ号に乗船して測量をしていた彼は、国後島で松前奉行配下の役人に捕縛され、松前城下そしてこの地であわせて約2年3か月間も抑留された事件である。
最初に向かった「小館」は、先端まで歩いたが、至近に海が見えた。やはり、ここも交易を意識した拠点だったのだ。一同、引き返して「大館」に向かう。広大な遺構である。佐藤さんは、元はアイヌの城郭「チャシ」があったのではないかとおっしゃる。
「大館」内は広大であり、谷あり畑ありである。ここに多くの居館が普請されており、先端には柵が結ばれ大規模な堀切があった。そこを越えると墓地になっている。巨大な城域には、松前氏が居住したと思われるが、踏査した印象では、家臣団屋敷も十分に営める規模である。
一般的に、戦国、織豊期には大名権威が高まり、主郭(本丸)の規模と高度が突出してゆく傾向にあるが、ここでは感じられなかった。大館から現在の松前城までの距離は、一キロにも満たない。新たに城下町と港湾施設を普請するための海岸部への移転であろう。ただし、城下町には商人町はあったが職人町はなかったという。手工業品については、交易を通じて購入することで事足りたからだそうだ。
茂別館といい大館といい、土塁や堀切を伴う大規模で大味な縄張だった。海運を意識した立地であり、内部には館主を中心とする家臣団と商人らの和人、そしてアイヌが混住したようである。館とは、交易都市といってもよいのではないかとの印象をもった。
文/藤田達生
昭和33年、愛媛県生まれ。三重大学教授。織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とする歴史学者。愛媛出版文化賞受賞。『天下統一』など著書多数。
※『サライ』本誌の好評連載「半島をゆく」を書籍化。
『半島をゆく 信長と戦国興亡編』
(安部 龍太郎/藤田 達生著、小学館)
https://www.shogakukan.co.jp/books/09343442