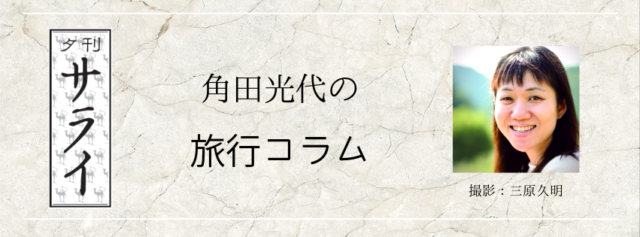
夕刊サライは本誌では読めないプレミアムエッセイを、月~金の毎夕17:00に更新しています。木曜日は「旅行」をテーマに、角田光代さんが執筆します。
文・写真/角田光代(作家)

東京・神楽坂の胸躍る赤提灯。旅ではないのですが、こういう夜の光景には旅している錯覚を感じます。
国内の旅は圧倒的に仕事で行くことが多いので、出版社の人といっしょのことが多い。編集という仕事は、私よりも断然、出張仕事が多いのだろう。みんな、その土地のことをよく知っていて、なおかつその土地の名物料理とそれを食べさせる店をセットで知っている。だれと旅しても、感心してしまう。
おもしろいことに、出版社は違えど、編集という仕事にかかわる人のほぼ全員が、旅先に着くなり、同じことを口にする。タクシーに乗ったらタクシーの運転手さんに、乗らなければ旅館やホテルに人に、あるいはその土地の仕事相手に、かならず訊く。「飲み屋街はどこですか」と。
たいていの町に飲み屋街がある。これは日本のおもしろい特徴だと思う。どんな町にも飲み屋はあるし繁華街はあるが、おもに飲み屋さんばかりがぎゅっとかたまっている通りだとか地域は、全世界的には、ない町のほうがずっと多い。新宿でいえばゴールデン街とか、北海道でいえばすすきのとか。

昨年(2017年)訪れた鹿児島駅付近の屋台村。屋台村的な場所があると、必ず足を運びます。
その日の仕事を終えて、名物料理を出す店で食事をして、それから教えてもらった飲み屋街に行く。居酒屋やバーもあるけれど、店内の見えないスナックも多い。編集者たちは、無数にある飲み屋の中から嗅覚で一軒を選ぶ。
私は旅先で飲むのが好きだけれど、居酒屋に行くのがほとんどで、飲み足りなければ外から店内が見えるバーにいく。ドアが閉まっていて、店内の見えないスナック風の飲み屋さんには、まず行ったことがない。
だから編集の人が、嗅覚としかいえない選択基準で「よし、ここにしよう」といって、ドアを開けるときにはいつもどきどきする。そういう店はメニューがなかったり、お品書きに値段が書いてなかったりするから、会計時にふっかけられるのではないかとか、実はおもに男性客をもてなす店で、迷惑がられたりするのではないかとか、口やかましい常連客が絡んでくるのではないかとか、いろいろネガティブな想像力を働かせてしまう。
けれどもたぶん編集者の嗅覚というものはたしかなのだろう、一度もへんな思いをしたことがない。スナックであれ、バーであれ。おもしろいなあと思う造りの店も多い。カウンター席にテーブル席、テーブル席にはソファ、というのは一般的だけれど、コの字型のカウンター席しかなくて、お客さん全員が顔を見合わすことになる店とか、スナックなのに山小屋風な内装だとか。ほかですでに飲んでから行く場合が多いから、飲み屋街の店で私はたいてい記憶が曖昧になる。

どこの飲み屋でもたいてい、レモンサワーを頼んでしまいます。レモンサワーは日本以外のどこにもないので、異国の旅ではレモンサワーが恋しくてならないのです。
翌日起きて、前日のことを思い出す。「どこそこで食事をして……のどぐろがおいしかったなあ……その後、飲み屋街に行ったんだった……」と、思い出せるのはたいていこのあたりまでで、飲み屋街のどこの、なんという店だったか、もう思い出せない。
ただ、色あせた赤いソファとか、ミラーボールとか、知らない人の歌う演歌とか、レーザーディスクのカラオケセットとか、そんなものが断片的に思い出される。そうしてもっと時間がたつと、各地のスナックの断片が混ざり合って、どこだかまったくわからない場所で飲んだ記憶が、妙にしあわせな旅の思い出として残っている。
文・写真/角田光代(かくた・みつよ)
昭和42年、神奈川県生まれ。作家。平成2年、『幸福な遊戯』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。近著に『私はあなたの記憶の中に』(小学館刊)など。




































