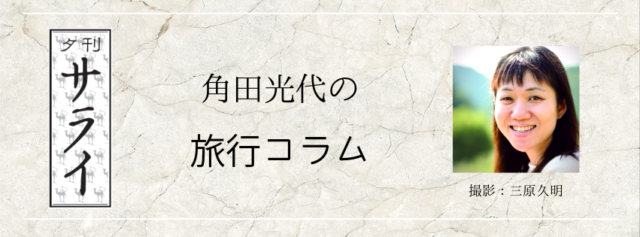
夕刊サライは本誌では読めないプレミアムエッセイを、月~金の毎夕17:00に更新しています。木曜日は「旅行」をテーマに、角田光代さんが執筆します。
文・写真/角田光代(作家)
一度訪れた国を再訪する、ということが年齢を重ねてから増えた。それとは異なり、若き日から「同じ場所を旅しない」という自分内ルールを無視して何度も何度も訪れ、いまだにくり返し旅している国がある。タイだ。
はじめてタイを旅したのが1991年、すっかり取り憑かれたようにタイが好きになってしまい、以後、ラオスに行くのにもマレーシアに行くのにもわざわざタイの国境を通過する旅程を組んだ。一時期、パスポートにタイの(しかもあらゆる場所のイミグレーションの)出入国スタンプが多いので、「タイに何かあるんですか」と税関で訊かれたことがある。もちろん荷物も入念に調べられた。何か輸出入しているのかと思われたのだろう。「いいえ、ただ好きなんです」と答えたら、職員は不審な顔をしていたが、好きだから行く、これ以上シンプルな渡航の理由があるだろうか。いちばん最近では2016年にパンガン島とバンコクを旅した。とはいえ前年にも、そのまた前年にも旅している。
27年も旅していると、刻々と街が変わっていくのを物理的に見ることができる。バンコクを走るスカイトレインの工事がはじまったときは、「きっと半永久的に完成の日はこないのではないか」と思ったが、もちろんすぐにスカイトレインは開通し、さらには地下鉄まで走るようになった。あれよあれよという間に物乞いはいなくなり、近代的なビルが建ち並び、街は近未来のような変貌を遂げていく。

1999年末に開通した高架式の鉄道スカイトレイン(BTS)。バンコク中心部の繁華街を走る。(撮影:角田光代)
変わったなあと思いながら街を歩いていると、不思議に、変わらない部分ばかりが目につく。ひしめく露天商や、路地のにおい、寝そべる犬と人なつこい野良猫、それから、困っている人を見過ごせないタイの人たち。道を尋ねた24歳の私を目的地まで送ってくれたのと同じように、48歳の私の訊いた目的地を、いっしょに探して歩いてくれる人がいる。

漢字の看板が連なるバンコクのチャイナタウン。この街の雰囲気は以前と変わらない。
1991年、私は旅の途中でタオ島という小さな島に行った。いまだに私のなかで、パラダイスと同義の島だ。この島での滞在が、現在の私の内で支柱のようなものになっている。この島だけは再訪できずにいる。この27年、数え切れないくらいタイに行っているというのに、その思い出のパラダイスにだけは行くことができない。
旅好きの人から、ごくまれにタオ島の話を聞く。24年前は電気も通っていない、商店も数えるほどしかない島だったのだが、今は電気も水道もあり、豪華リゾートホテルがあり、商店街もあり、コンビニエンスストアや日本料理店まであるという。本当に変わったのだなあと、そういう話を聞くたびに思う。そして、その変化を見るのがこわくなる。
発展しないでほしい、というのではない、私の知っている姿のままでいてほしい、というのが正直な思いだが、これもまた、とんでもなく勝手な旅人の感傷だということもまた、わかっている。
2016年に訪れたパンガン島は、じつはこのタオ島の隣にある。フェリーで1時間もせずに行くことができる。タオ島に行けないかわりに、ここ最近、私はこの島を訪れている。タオ島に行きたい、でも知らない島みたいになっていたら、と思うとこわくて行けない、でも行きたい、ならば、その手前の島に行こう、というわけなのだが、人が聞いたら意味不明の旅だろう。

パンガン島の静かな海。パンガン島はタイの南西部、タイ湾に浮かぶ大きな島。
元ヒッピーだったとおぼしき知人の外国人は、40年前にパンガン島を訪れたことがあるという。彼によれば、その当時パンガン島には4軒のゲストハウスしかなかったらしい。パンガン島はいまだにひなびた島だが、しかし今では無数の、超高級から格安まで取りそろえての宿泊施設があるし、道は舗装されていて、レストランが並ぶ一角があり、コンビニエンスストアだって数軒ある。もし私が40年前を知っていたら、今のパンガン島に複雑な思いを抱いただろうか。でもきっと、どんなに街の様相が変われど、この島独特のゆったりした時間の流れ方は、きっと変わっていないだろうと思う。
「ずいぶん変わったけれど、本質的なところは変わっていない」ということを、ほんの少し先のタオ島まで行けば、私は確信できるのだと思う。でも、行けない。はたしてこの先、行けるときがくるのか、私自身にもよくわからない。しかしこの気持ち、30年後の初恋の人に会いたいけれど会いたくない、という気持ちとまったく同じだと思う。
文・写真/角田光代(かくた・みつよ)
昭和42年、神奈川県生まれ。作家。平成2年、『幸福な遊戯』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。近著に『私はあなたの記憶の中に』(小学館刊)など。




































