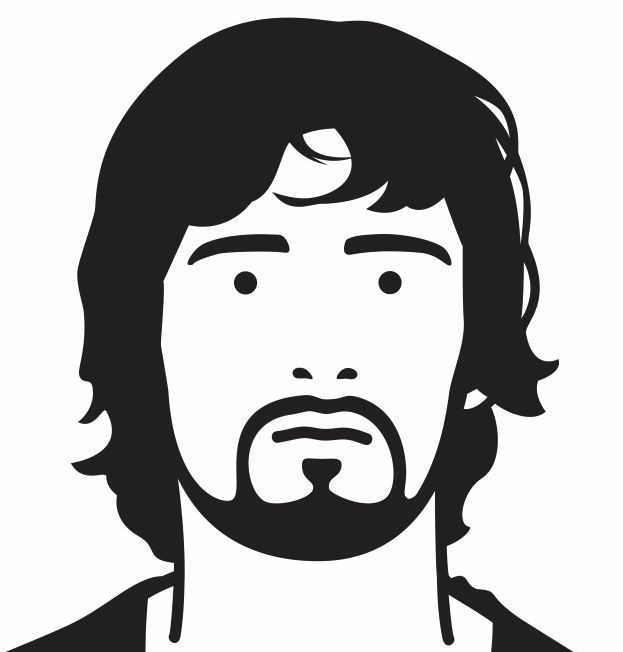文/平野久美子 写真/藤田修平
世界が注目するクリエイター
『台湾クラフトへの旅』という単行本の取材で感じたのは、「Z世代」(1990年代半ば以降に生まれ、幼いときからデジタル器機に慣れ親しみ、社会問題にも比較的関心の高い世代)と呼ばれる若者たちの活躍ぶりと、その潜在能力の高さである。
彼等は得意のデジタルスキルを駆使して政治から芸能まで広範にわたって新風を吹き込み、社会を活性化させている。
現在の台湾のモノ作りの現場で、こうした動きがどの程度浸透しているのか興味を持った私は、注目のクリエイターたちを訪ねた。彼等の生み出す「Made in Taiwan」の品々は、ネットを通じて日本をはじめ海外のファンを増やしている。
例えば台北市に拠点を構える『Woo Collective』(ウー・コレクティブ)は、その良い事例かも知れない。いまや世界的に知られ、実力を高く評価されているこのデザイン集団は、国立台北科技大学の同窓生が集まって2015年に結成された。驚くことにブランドを立ち上げたその年に、台湾最高峰のデザイン賞を受賞。続く2016年、2017年にも世界的なコンペで数々の賞を獲得している。
新しい意味の創造
『Woo Collective』のデザインコンセプトは「新しい意味を創り出す」というひとことにつきる。「伝統の未来的変換」と言い換えることもできそうだ。
例えば、台湾のどの廟(現地の神々を祀る宗教施設)にもある伝統的な祭礼の器は、ほとんどが錫からできている。若者たちから見向きもされない素材だが、クリエイターたちは軟らかで錆びず、水の浄化作用や酒を旨くする効用など錫の持つ特性に注目して新しい意味を加えた。

伝統職人の協力も得て、ワインのエアレーター(空気に触れさせ、香りや味わいを高めるアイテム)や口吹きガラスと組み合わせた特製の茶器を開発したのである。もちろん、斬新なデザインを採用して。
すると、忘れられていた素材が脚光を浴び、使いやすく美しい『Woo Collective』の品物は、国境も年齢も超えて広く支持されるようになった。
こうした、伝統を未来に変換する試みが、台湾のあちこちの工房で進められている。
Z世代が目覚めた郷土愛
故郷にUターンをして、より良い暮らしのための陶器創作に奮闘している若きクラフトマンにも出会った。
『魂生製器』のオーナーの張靚妤さんは、台北の広告代理店を退職した後、一念発起して日本各地の窯元を訪れる一方、ネットを駆使して陶芸の技術や情報を集め、「独学で器作りを学び、ブランドを立ち上げた」という。
広告会社で身につけたノウハウを、さらにIT技術やAIを駆使しながら形にしていったZ世代の思い切りの良さと自信を感じる。

創作の基本になっているのは、生まれ育った花蓮県の雄大な自然とドラマチックな色彩、名産の大理石へのこだわりだ。器はどれもシンプルなデザインながら、粉末にした大理石と釉薬のかけあわせによって、独自の作風を編み出し、花蓮の風合いを作品化することに成功している。
日本時代の遺産を発展継承
ところで、バラエティーに富む台湾クラフトの制作現場へ出向いて話を聞くと、彼等の先輩たちが日本統治時代に身につけた技術や知識が、現在も継承されていることに驚かされる。
同時に、作品に向き合う姿勢から、まるで日本の職人のような謙虚さとひたむきさを感じることすらある。
そんな感慨を、私は古都・台南の散歩中によく抱くのである。特に、廟の界隈に広がる路地へ入っていくと、小さな工房で職人が一心に鋼を叩いたり、竹ひごを組み立てたり、木材を削ったり、と仕事に没頭している。
手を休めている職人たちに声をかけると、彼等は、日本人から祖父や父親が受け継いだという木彫や家具、板金などの古びた指南書を見せてくれるのだ。
そして日本の技術やデザインを、どのように祖父たちが工夫して台湾人の生活に即した道具に変換していったかを、胸を張って語ってくれる。

そうした思い出ばなしからは、職人たちがいかに工夫をして、日本から伝わったモノづくりの考え方を、時代と生活に即した「Made in Taiwan」へ変換していったかがうかがえる。
思えば、台湾が近代化を遂げた背景には、1895年から1945年まで続いた日本統治時代に、法制や社会のインフラ整備というハード面にとどまらず、特に大正時代に芸術や開明的な思想がもたらされたことも大きく影響したと言えるだろう。
内地(日本)へ移出する工芸産業が奨励され、各種学校の開設も相次ぎ、日本人の専門家が続々と渡台した。こうして漆、わっぱ、組子、竹細工、指物、和紙など日本の伝統技術を、当時の台湾の若者は学ぶチャンスを得たのである。
21世紀に入るころから「Made in Taiwan」の新たな機運が盛り上がり、日本の一村一品運動を思わせる活動が行われるなど、さまざまな文化戦略も奏功し、海外市場での台湾の存在感は増すばかりだ。
そして日台の交流で育まれたクラフト精神は、今もZ世代の若きクリエイターたちにも脈脈と受け継がれている。

台湾土産を買って帰るなら、作り手の気持ちに共鳴できる品々がいい。ありふれた土産物店を離れて工房や小さな手作りの店を訪ねると、「Made in Taiwan」の自負にあふれた逸品に出会える。
詳しいことはぜひ本書『台湾クラフトへの旅』をお読みいただきたい。
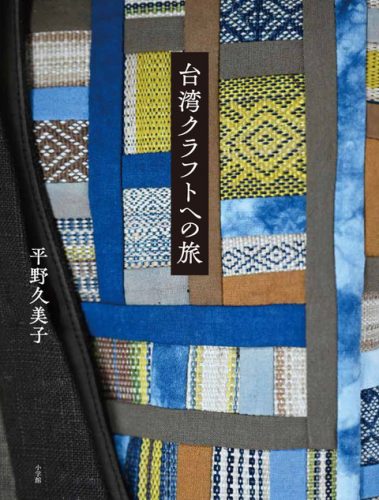
『台湾クラフトへの旅』
B5変形判・160ページ 3300円(税込み)
著者/平野久美子 発行/小学館
平野久美子
ノンフィクション作家。東京都出身。学習院大学文学部仏文科卒業。出版社勤務を経て執筆活動へ入る。著書に『淡淡有情―日本人より日本人の物語』(小学館、第6回小学館ノンフィクション大賞)、『台湾好吃大全』(新潮社)、『トオサンの桜 散りゆく台湾の中の日本』(小学館)、『水の奇跡を呼んだ男』(産経新聞出版、日本農村土木学会著作賞)、『テレサ・テンが見た夢 華人歌星伝説』(筑摩書房)、『ユネスコ番外地 台湾世界遺産級案内』(中央公論新社)ほか多数。「台湾世界遺産登録応援会」会長、「宮古島市国際交流会」顧問を務める。日本文藝家協会会員