取材・文/ふじのあやこ
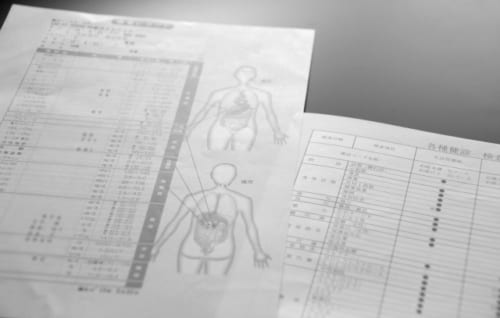
家族との関係を娘目線で振り返る本連載。幼少期、思春期を経て、親に感じていた気持ちを探ります。(~その1~はコチラ)
今回お話を伺ったのは、東京の通信機器を扱うメーカーで事務の仕事をしている桃子さん(仮名・40歳)。山梨県出身で、両親と4歳上に姉のいる4人家族。桃子さんが“気分屋”という父親が大学生の時に入院しますが、一度もお見舞いに行かず、その行為により両親との不仲が浮き彫りになります。
「父親が入院したのは、勉強を必死に頑張って、都内の大学で一人暮らしを始めていた時で、父のお見舞いだけではなく、帰省もほぼしていませんでした。帰省していたのは親族が集まるお正月休みくらい。あの時はとにかく家を出られた解放感でいっぱいで、もう二度と戻りたくないって、強く思っていました。私がお見舞いに行かなかったことを父がどう思っていたかなんて、まったく考えていませんでしたね」
母親からの定型文メールは、父の体調報告メールへ。親族の集まりの度に親が小さく見えていった
そこから父親は入退院を繰り返すようになったそうですが、母親との連絡は相変わらずメールのみ。電話にはわざと出なかったと言います。
「母親は逐一私に父親の様子をメールしてきました。正式には、一度着信を残して、しばらくしてからメールという流れです。私は一度も母親からの電話を取ることはありませんでした。母親はきっと父の言葉を代弁してくるだろうと思ったし、それに弱音を吐かれたら同情してしまうんじゃないかって。家族といると自分ではコントロールできないいろんな感情に支配されてしまうから、関わり合いになりたくなかったというのが本音でした」
そのメールだけの連絡は社会人になってからも続き、家族とはその間も親族の不幸や、法事などで顔を合わせるだけ。常に一緒にいない分、親の老いをとても強く感じたそう。
「両親は少しずつ小さくなっていった気がしたというか、弱々しく感じてしまうことが増えました。それに、親族で会うと席が決められていないのに、食事などでは家族ごとに固まって座るんですが、そこで父親が私にビールを注ぐようになりました。いつも自分自分だった人が。私ももう大人で、周りの目もあるから避けたりはしませんが、『今さら』ってずっと思っていました。
そんな関係を何度も姉から戒められましたね。でも、そのことでさえ、なぜ私が注意を受けなければいけないんだとイライラしちゃって。姉から『大人になりなさい』と言われる度に、私が子供だった時に大人な振る舞いをしてこなかったのは両親のほうと聞く耳を持たず。もう意地になっていたんだと思います」
【次ページに続きます】






























