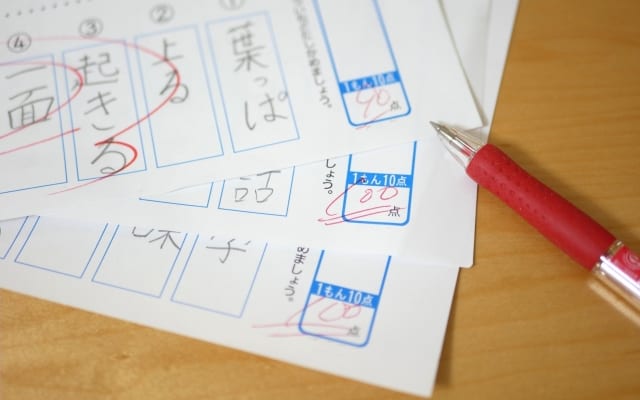取材・文/ふじのあやこ
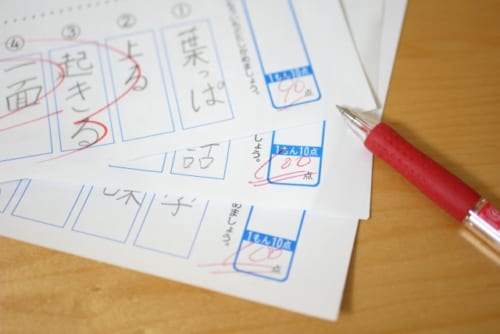
近いようでどこか遠い、娘と家族との距離感。小さい頃から一緒に過ごす中で、娘たちは親に対してどのような感情を持ち、接していたのか。本連載では娘目線で家族の時間を振り返ってもらい、関係性の変化を探っていきます。
「父親は知られまいと必死に虚勢を張っていただけだったのかもしれません」と語るのは、桃子さん(仮名・40歳)。彼女は現在、東京の通信機器を扱うメーカーで事務の仕事をしています。おだやかな口調に、ゆっくりとした所作などから、彼女の第一印象は、おっとり。そんな優しそうな彼女が、両親、特に父親とずっと不仲だったと話始めた時は強烈な違和感を覚えました。
外食の時間にお酒をゆっくりと嗜む父親。その待つ時間が大嫌いだった
桃子さんは山梨県出身で、両親と4歳上に姉のいる4人家族。両親は職場で出会って結婚したようで、父親のほうが4歳上。小さい頃から家で一番偉いのは父親だと植え付けられていたと語ります。
「いつの記憶かわからないんですが、家でずっとムスっとした父の顔を覚えているんです。若い父の顔で覚えているのはそのひとつだけ。何をしても褒められたこともないし、ずっと否定し続けられた記憶しか残っていません」
父親は桃子さんにだけではなく、姉はもちろん、母親に対しても高圧的な態度だったそう。専業主婦だった母親が父親の機嫌を常に伺っている様子を覚えていると語ります。
「中学生くらいの時まで月に1回あるかないかくらいのペースで外食をしていたんですが、運転するのは母親。それは父親が飲食店でお酒を飲むからなんです。家族で行くようなお店でも、父親は最初にビールを頼み、時間をかけて食事をします。苦痛だったのは、その父をずっと待っていなくてはいけなかったこと。しかも、会話が盛り上がることもなく、2、3時間も。じっと待っていないといけなかったので、私も姉も家族で外食するのが大嫌いでした。父の会話に合わせて文句も言わずに付き合っている母親の姿も好きじゃなかったですね」
【次ページに続きます】