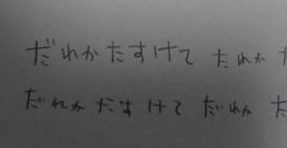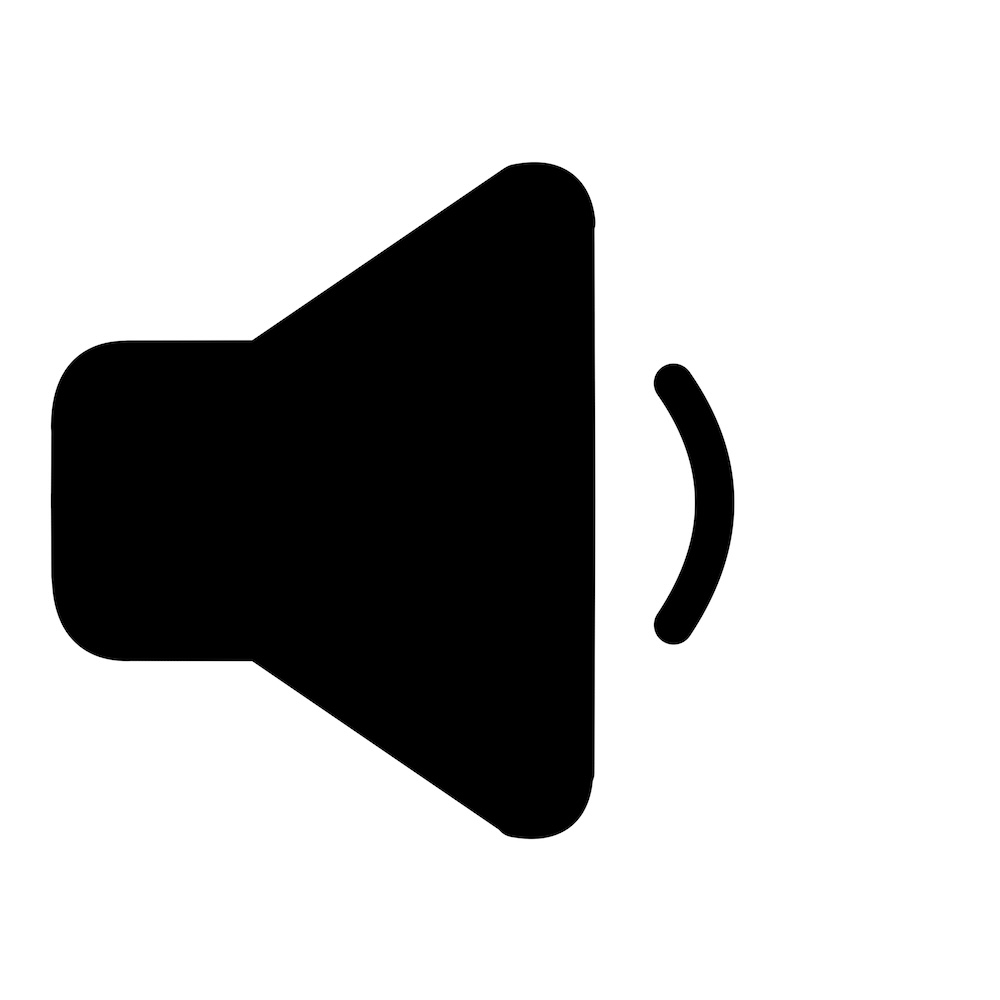文・写真/かくまつとむ
海外では“ジャパン”と呼ばれる漆器。堅牢で美しいその塗り物は、なんと9000年前の縄文早期から日本列島で作られていたそうです。
近年の分析研究では、漆液を採取するウルシの木が、縄文の集落周辺で計画的に栽培されていたこともわかっています。
まさにジャパンの名にふさわしい、日本を代表する工芸品であるところの漆器ですが、現在使われている漆のほとんどは中国産で、国産漆は2%ほどしかありません。
その数少ない漆の産地が、岩手県の浄法寺と、茨城県の奥久慈です。

漆掻き職人。従事者は非常に少ない。
漆液は害虫や病原菌から身を守るための分泌液で、動物の皮膚に対しても強い炎症(アレルギー反応)を起こさせるウルシオールという成分を含んでいます。
ウルシの木は、傷つくとすぐに漆液を分泌させて傷口をふさぎます。液は次第に粘度を増し、最後はかさぶたのような硬い被膜になります。この漆液を集めて精製した塗料が「漆」です。
この、ウルシの木から漆液を採取する作業を「漆掻き」といいます。漆液は、刃物で幹に傷をつけることによって採取しますが、その専用道具「漆掻き鉋」(うるしがきかんな)は、数ある日本の刃物の中でも形状が特殊で、使い方も独特です。

(右から)「腰鎌」。鉋の刃が乳管のある層を確実にとらえるために樹皮の凹凸を削る道具。なめらかに削ることで、にじみ出た漆液が樹皮の亀裂に吸い取られてしまうことも防ぐ。(中)鉋。今は作れる鍛冶職人も少ない。(左)溝ににじみでた漆液を採取する「掻き取りベラ」。

鉋の切れ味で作業能率は大きく変わる。
鉋という名前が示すように、基本的には樹皮を削るための道具です。先端は幅の狭いU字状の、引き削り用の刃になっており、背側には鶏の蹴爪状の小刀がついています。
漆液を分泌する組織は、幹の形成層と厚い外樹皮の間にある内樹皮の中にあります。漆液は、そこを均一に走る乳管の中で作られます。
鉋で傷をつけるのは乳管がある内樹皮。この層を狙い、鉋を幹へ当て、横一文字に外樹皮と内樹皮を削りとります。乳管が切断されるとこの溝に漆液が溜まるので、それを「掻きベラ」という道具で筒の中へ落とし込んでいきます。

鉋で樹皮を横一文字に削る。

削り跡(溝)の中心を、目サシと呼ばれる突起状の小刀で一筋切り込む。
切り込みが深いと、木にとって大切な形成層まで傷つき、一気に弱って漆が出なくなってしまうそうです。逆に切り込みが浅ければ、漆液の出る層まで傷が届きません。
そこで鉋はやや浅めに切り込み、背側の小刀で溝の中央に一筋の切り込みを入れるのです。こうすると形成層を傷つけることなく、乳管全部をきれいに切断することができます。
興味深いのは、いきなり傷をつけてもウルシの木は漆液を分泌しないこと。最初はわずか2cmほどの長さで、一定の日数をあけながら等間隔で切り込み傷を長くしていきます。
すると木は、日に日に危機が迫っていると感じるようで、漆液の分泌量を増やし、かつ成分濃度も高くなるそうです。

にじみ出てきた漆液。はじめは乳白色で次第に褐色を帯びる。
こうして、良質な漆液が十分に出るようになったところで採取を始めますが、一度にたくさん採ろうと木に負担をかけすぎると、漆液は出なくなってしまいます。幹につける傷も、最後の止め漆という作業までは一定の幅以内に決められていて、一周ぐるりと削ることはありません(縄文時代はリング状に傷をつけていたそうです)。
漆掻き職人は、鉋という刃物を通じて、物言わぬウルシの木と対話をしているのです。

漆掻きを半世紀続けてきた職人の手。道具を握る形に指が曲がっている。
漆掻きの季節は、6月から9月。漆かき職人は変わりやすい夏の空模様を気にしながら、木から木へと移動する忙しい毎日を送ります。
それでも、1本の木から採れる漆液の量は平均すると牛乳瓶1本分(180ml)ほど。漆が貴重で、輸入品に置き変わってしまった理由はここにあります。

掻き取った漆液は毎日少しずつ木の桶に貯めていく。
いまちょうど、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館で、企画展『URUSHIふしぎ物語 人と漆の1200年史』が開催されています(~2017年9月3日まで)。会場では、漆掻きの貴重な映像も見ることができます。漆のすべてがわかる充実した展示です。興味のある方は、ぜひともお見逃しなく!
【URUSHIふしぎ物語 人と漆の1200年史】
■開催期間/開催中~ 9月3日(日)
■会場/国立歴史民俗博物館 企画展示室A・B
■開館時間/ 9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)
■休館日/月曜(休日の場合は翌日が休館日となります)
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/
文・写真/かくまつとむ
かくまつとむ(鹿熊勤) 自然や余暇、一次産業、ものづくりなどの分野で取材を続けるライター。趣味は日本の刃物文化の調査、釣りと家庭菜園&酒。『サライ』には創刊号から参画。著書に『鍛冶屋の教え』(小学館)、『日本鍛冶紀行』(ワールドフォトプレス)、『糧は野に在り』(農山漁村文化協会)など。立教大学兼任講師。