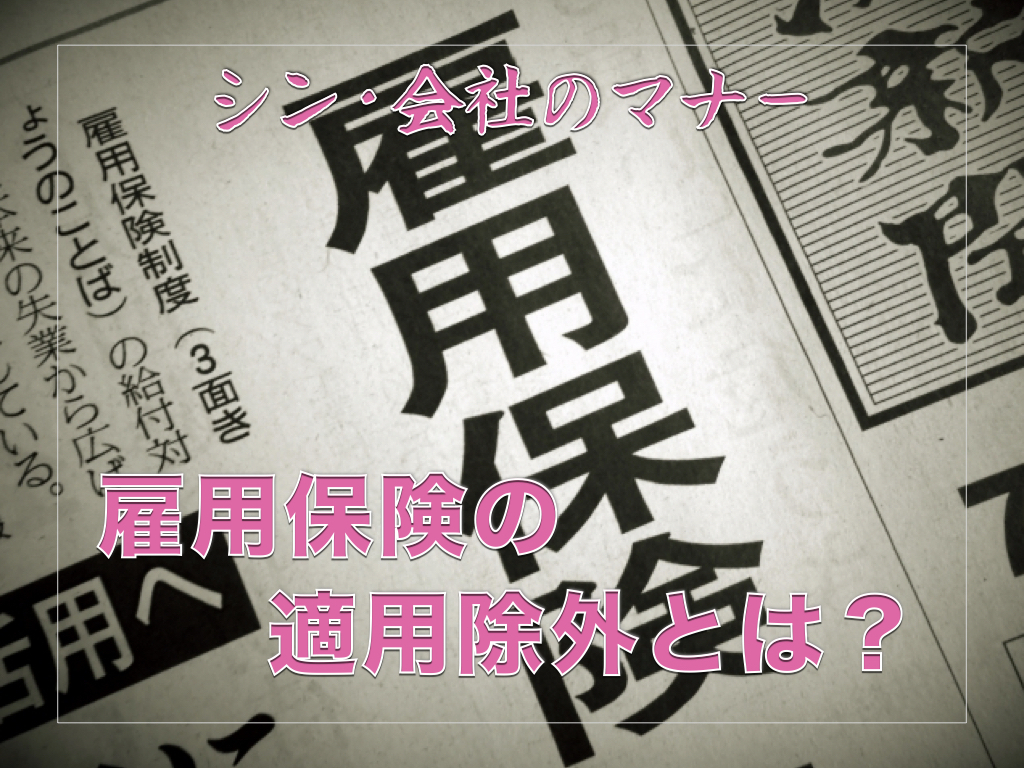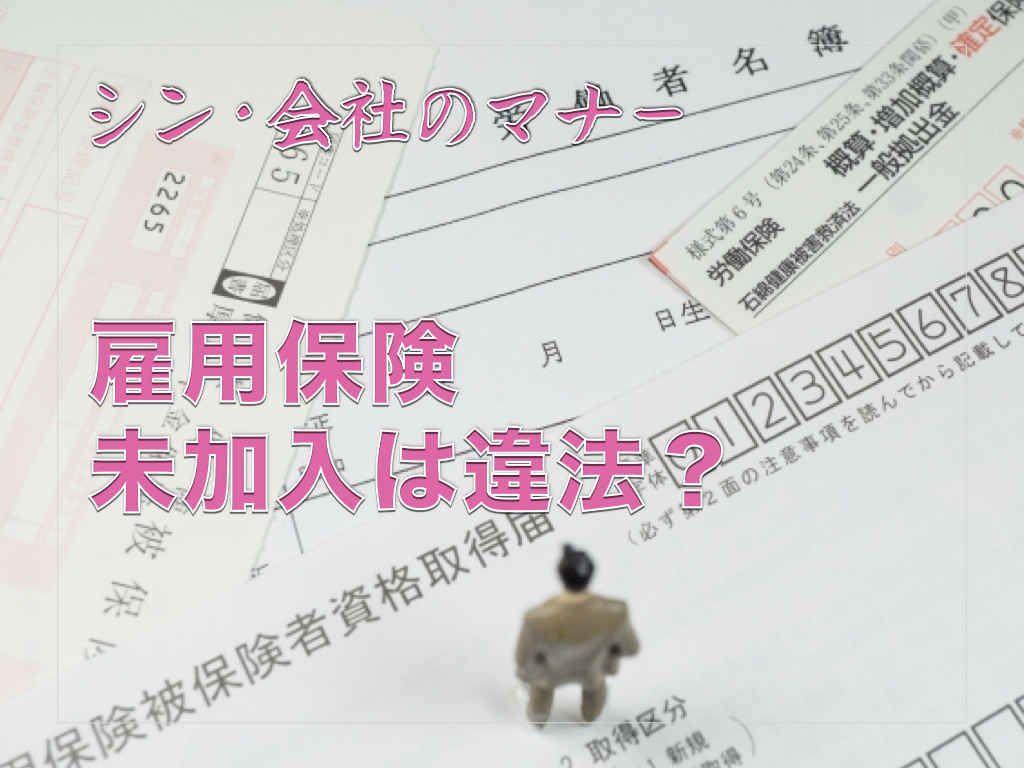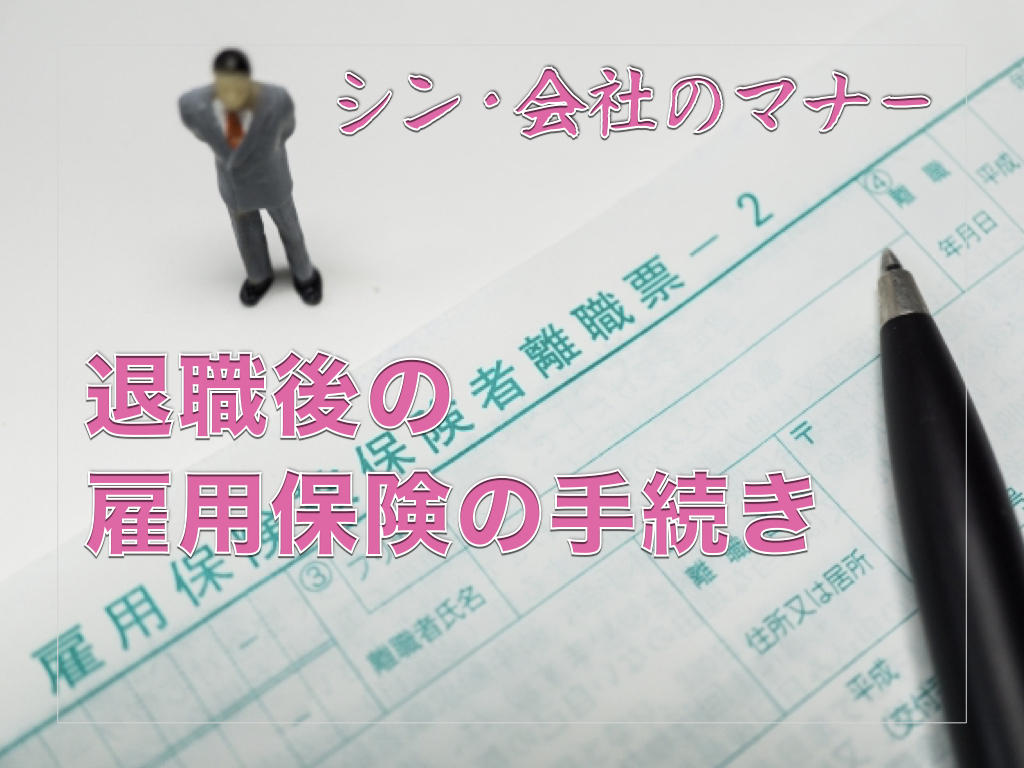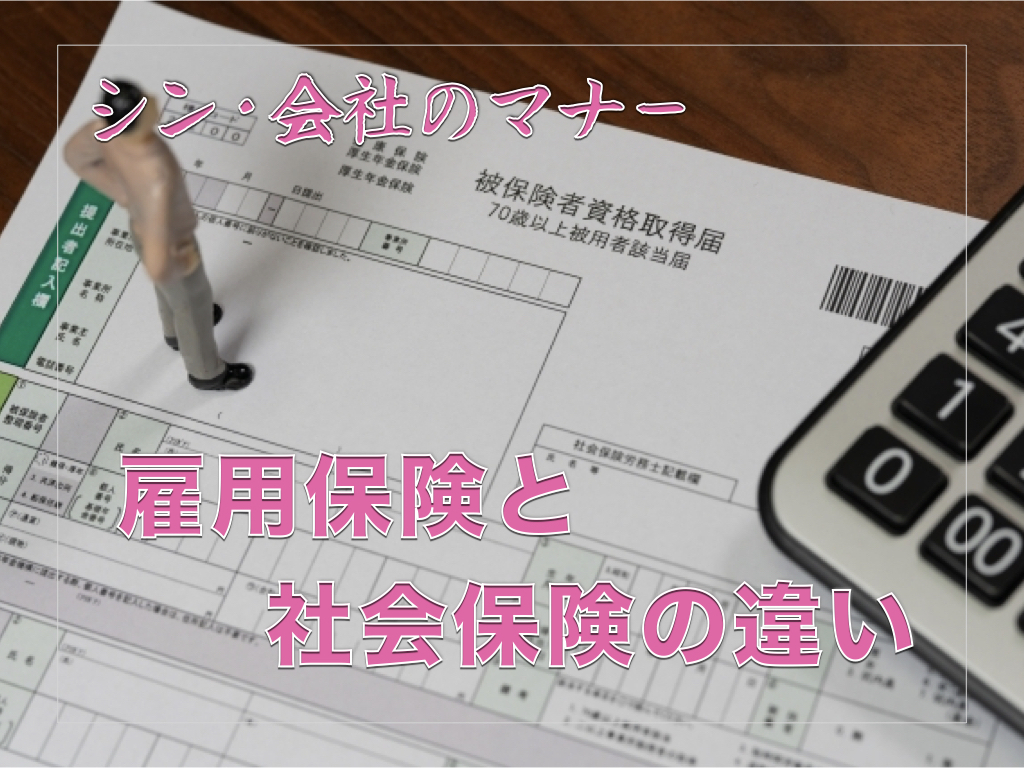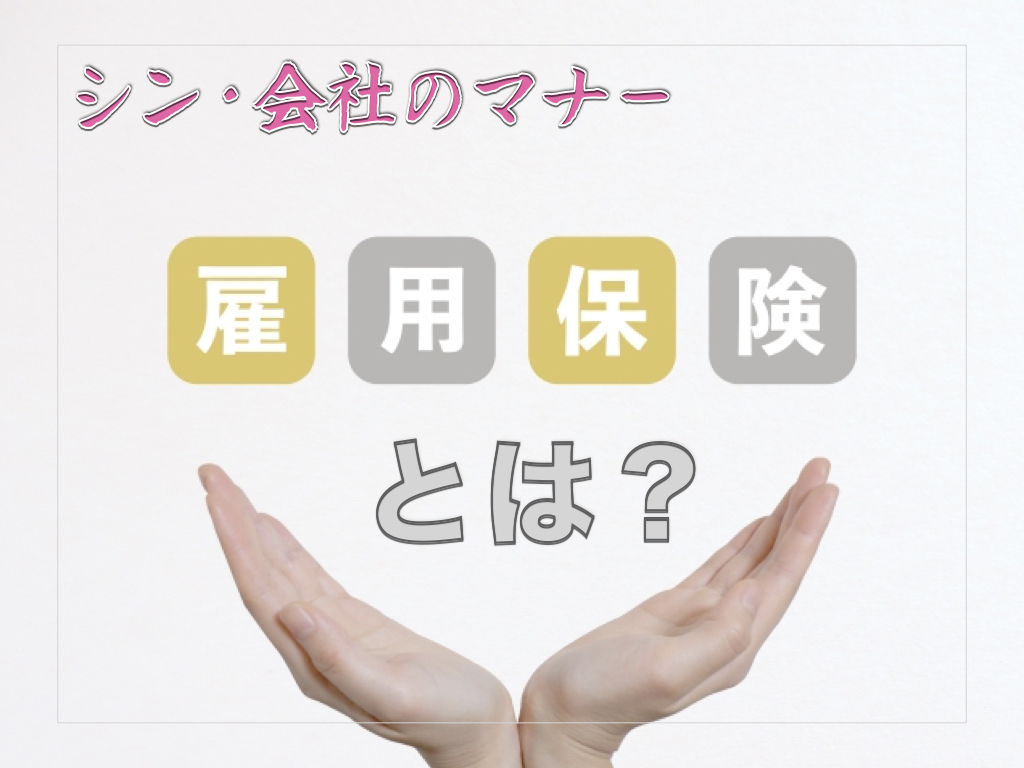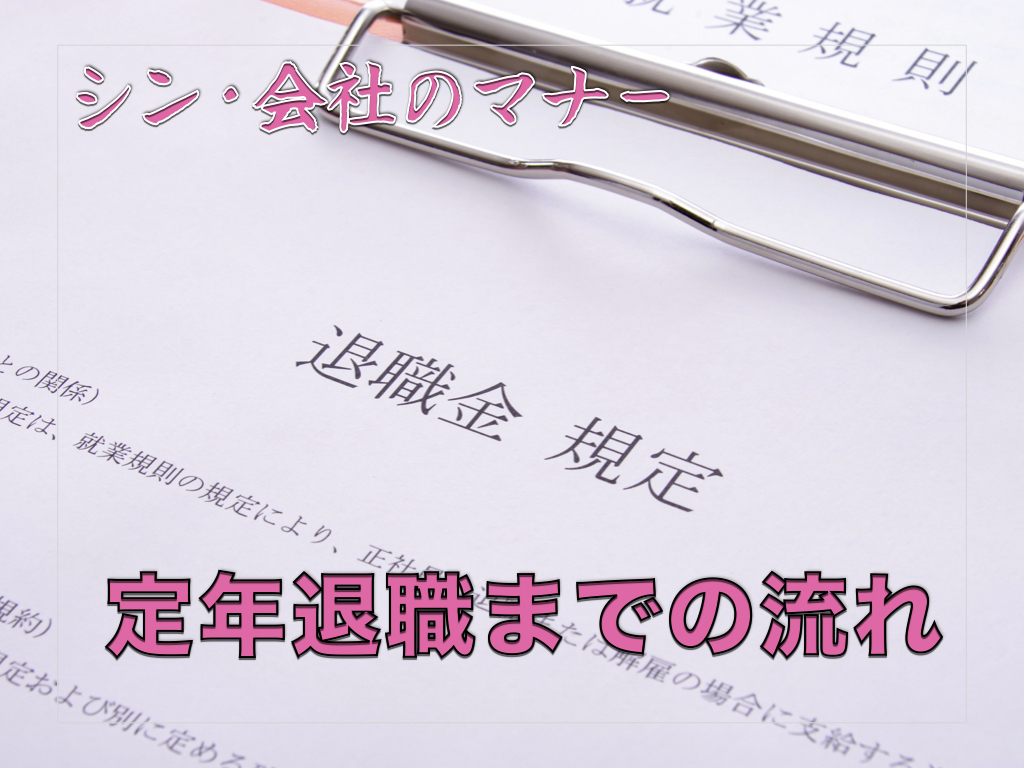働き方は人それぞれです。多様な働き方という言葉が広く認知されている今、働く日数や時間などを選択して働く人が増えています。リモートワークなどの新しい働き方も普及しました。どんな立場で仕事をするかという視点で働き方を考えた場合、会社などの事業所に雇用されている人と、フリーランスの人との2種類に分けられると思います。
雇用されている人の多くは雇用保険に加入していますが、フリーランスの人はどうなっているのでしょうか? 今回は、フリーランスと雇用保険というテーマについて、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
フリーランスは、雇用保険に加入できる?
雇用保険の代わりとなる制度はある?
フリーランスでアルバイトを雇った場合、雇用保険は必要
まとめ
フリーランスは、雇用保険に加入できる?
フリーランスとは、特定の組織や団体などに属さず、会社などと自由に契約して働く人たち、またはその働き方を指します。広い意味では、個人事業主として事業を行なっている人も含まれます。個人事業主というのは、法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人のことです。個人事業主となるためには、税務署に「開業届」を提出しなければなりません。
個人事業主には、小売店、飲食店などの経営者、税理士や社会保険労務士などの士業、イラストレーターや写真家、芸能タレントなど、様々な職業の人がいます。個人事業主ではないフリーランスというのは、開業せずに企業などから仕事を委託されて働く人です。一般的にはこちらの人たちをフリーランスと呼ぶことが多く、個人事業主よりも働き方の自由度がより高いと言えるでしょう。
雇用契約が、労働者を使用して労働の対価である賃金を支払うものであるのに対し、業務委託契約というのは、会社などが第三者に業務を委託し、その成果を受け取るものです。請負契約もその中に含まれます。
フリーランスというのはいわゆる労働基準法上の労働者ではありません。労働基準法の労働者の定義は、事業所などに使用されて、賃金をもらって生活する者となっています。したがって労働基準法の適用もないということになります。雇用保険は基本的に、事業所で雇用されて働く労働者のための制度です。
個人事業主はもちろん、業務委託契約を結んで働くフリーランスの人も、雇用保険の被保険者になることはできません。
雇用保険の代わりとなる制度はある?
フリーランスで働くということは、組織や時間に縛られない、自ら仕事を選択できるなどのメリットがあります。けれども、自由度が高い反面、リスクもあります。フリーランスは、労働基準法によって保護される対象ではなく、雇用保険の適用もありません。病気になった場合の補償もなく、不安定な立場であることは否定できない事実です。
それでは、フリーランスの人は、契約の打ち切りなどで仕事を失うリスクには、どのように備えたらいいのでしょうか? 一般的には、損害保険や所得補償保険などの民間の保険に加入している例が多く見られます。個人型確定拠出年金(iDeCo)などで、将来の収入を確保するのも一案です。ただ、フリーランスとして働く人が雇用保険に加入する方法がないわけではありません。
複数の仕事をしている場合でも、その中の1社と雇用契約を結ぶことは可能です。雇用保険の被保険者となる条件は、「週の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上雇用される見込みがあること」。そして「昼間学生でないこと」です。この条件を満たせば、被保険者となることができます。
基本的に雇用保険は2つ以上の事業所で資格取得することはできませんので、1社で雇用保険に加入し、他の仕事は自由な立場で受託するという働き方も可能になります。この場合、相手先とどのような契約を結ぶのかということがポイントになってきます。仕事の契約が業務委託なのか、雇用契約なのかというのは重要な点です。
実は、この業務委託契約というのは一部で問題視されている点もあるのです。業務委託契約とは名ばかりで、実際は自由な裁量で働ける内容ではなかったというケースは少なくありません。本来は雇用契約であるべきものを業務委託で受注したため、はるかに報酬が低いものになったというケースもあります。
なぜこのようなことが起こるかというと、雇用契約ですと労働法が適用され、残業代や社会保険の負担などが発生しますので、コストの増加を避けたい会社があるということです。雇用保険の対象となる労働者かどうかは、勤務の実態によって判断されますので、疑問を感じた時は、ハローワークに相談しましょう。現在フリーランスで働く人を保護するための法整備は進んでいます。
この法律は、業務を中途解約することの制限や、労災の加入、育児や介護などの就業環境に配慮することなどの内容が盛り込まれており、2024年秋頃施行予定となっています。

フリーランスでアルバイトを雇った場合、雇用保険は必要
フリーランスであっても、アシスタントや事務員などの従業員を雇うことはあると思います。アルバイトなどを雇う時は「労働条件通知書」を発行しますが、その人が雇用保険の被保険者の要件を満たす場合は、雇用保険の加入手続きが必要になります。雇用保険が適用される事業所は法人とは限りません。
被保険者となる労働者を一人でも雇っていたら、適用事業所ということになります。労働基準監督署に労働保険成立届を提出し、雇用保険関係はハローワークに適用事業所設置届、被保険者となる人の資格取得届を提出します。労働保険成立届を出すことによって、従業員には労災も適用されます。
また、税務署には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。今まで会社勤めをしていた人にとっては、これらの手続きを自分でやるのはなかなか面倒なものですが、フリーランスでも人を雇うとなったら、法律上当然の義務なのです。働く環境を整備することは、フリーランスにとっても不可欠の心得と言えるでしょう。
まとめ
フリーランスにも会社員にもそれぞれメリットがあり、どちらが良いとは一概に言えません。ただ、業務委託契約を交わす場合は、その内容についてきちんと確認することは大切です。そして、自らが人を雇う立場になったら、法令を遵守して必要な手続きを行ないましょう。どのような働き方でも、みんなが安心して働ける社会の実現を目指すことが大切です。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com