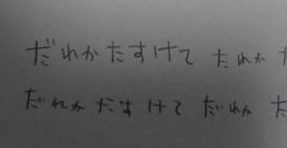取材・文/坂口鈴香

南九州から関西に呼び寄せた義父(88)を介護する迫田留美子さん(仮名・50)は、白内障の進んだ義父に白内障の手術を受けてもらった。糖尿病があったため、かかりつけの総合病院に入院して手術したところ、退院後、病院でコロナ患者が発生して義父は濃厚接触者だと連絡が来た。PCR検査を受けたところ陽性が判明。義父は再び入院することになった。
介護にはゴールがあった【1】はこちら。
絶対に大丈夫だ
「やはりPCR検査を受けに行っておいてよかった」と、迫田さんは検査結果にショックを受けるより逆に安心したくらいだったと振り返る。そして、「絶対にお義父さんは大丈夫だ」と自分に言い聞かせた。
「そのときは、そんなに重篤な症状はありませんでした。お医者さまから延命治療の説明を受けたときも、『皆さんに説明している』ということだったので、『念のため説明しているだけだ。まだ大丈夫だ』と思い、延命治療はしなくていいと答えました。義父本人には聞いたことがありませんでしたが、主人と話し合っていましたので」
点滴をされた義父は、看護師からの「さあ! 今から病室に向かいますので」という言葉とともに、病室に連れて行かれた。
迫田さんは一瞬、「なんか嫌だな」と感じたという。
その感覚を振り払うように「お義父さん、お医者さんや看護師さんの言うことを聞いたら、絶対早く退院できるからね!」と言うと、義父は小さくうなずいた。
「そして、『入院しないとあかんの?』と言いました。『コロナやからね、仕方ないわ』と、お義父さんの手を握りしめました。看護師さんも大きくうなずいていましたが、助からないとわかっていたんだろうと思います」
電話のたびに状況が悪くなっていた
迫田さん家族も隔離生活を送っていたが、夫、迫田さん、娘、と次々に発熱。夫と迫田さんはPCR検査で陽性となり、同室に入院することができた。関西でコロナ感染者が急増し、自宅療養者が相次いだのはこの少しあとのことだ。入院できたことが幸運だったと感謝する迫田さんだが、娘は高熱が出ていたにもかかわらずずっと陰性で自宅で療養するしかない。迫田さんの不安は大きかった。
義父の症状も良くなかった。病院からはたびたび連絡が来た。
「入院した当初は熱が下がって順調だったんですが、認知症が進んで、起き上がっては転倒するようになったようです。次には酸素マスクを外して体を動かそうとしたということで、精神安定剤を投与してもいいかと聞かれました。このときは、『あの穏やかなお義父さんが?』とかわいそうになりました」
トイレに行きたいだけやったのと違うかな、コロナ病棟だし、看護師さんの手を煩わす高齢者はみなそう扱われるのかなと考えてしまったという。担当医には「ご面倒をおかけしました」と詫びたが、「毎日お見舞いに行けたらこんなことにはならなかっただろう」と何度も考えた。
「6日入院している間に5回連絡が来ました。連絡が来るたびに状況が悪くなっていて、延命治療のことも確認されたんです。5回目に連絡が来たときには『もうダメかもしれない』と覚悟しました」
病院からの連絡は、家で療養している娘経由で聞いた。義父の命はもう時間の問題だと伝えられた娘は、泣きじゃくりながら迫田さんに電話してきた。「こんなつらい思いをさせてごめんね」と謝った。
「娘はワーワー泣きながら、『電話の向こうからピコンピコンって機械の音がして、まだおじいちゃん生きてるねん。来られますか? って言われたんやけど、30分はもたないかもって言われた』と。それで主人の電話番号を伝えてもらいました。次の電話は死亡報告でした。コロナでなければ、間に合わなくても駆けつけました。世の中が許すのであれば、駆けつけたかったですよ、本当に……」
電話を切って、迫田さんは泣き続けた。信じられない思い。良かれと思ってやった白内障の手術で亡くなる悔しさ。病院が悪い、というのも正直な思いだ。あんなに手術を嫌がっていた義父の気持ちを優先していればこんなことにはならなかった。「私が義父を死なせたんだ」と自分を責めもした。
介護にはゴールがあった【3】につづく。
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。