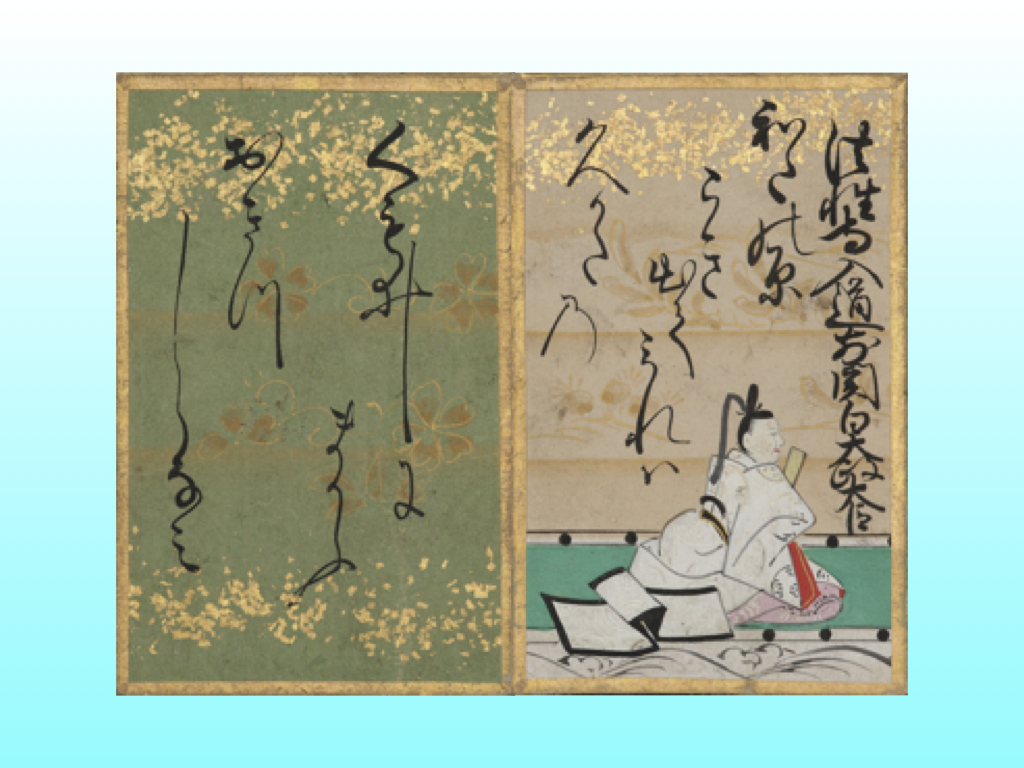今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「蓮花の泥田に生じてなお廉潔なるところがよい」
--下岡蓮杖
幕末明治の風俗史をたどるとき、下岡蓮杖の名前は欠かせない。長崎の上野彦馬と並んで、日本に写真の技術を輸入し定着させた先駆者なのである。
その下岡蓮杖が、日頃から口にしていたのが掲出のことば。泥にまみれ、そこに根を張りながら栄養を吸収し、やがて開花する蓮の花の清廉な美しさ。個人的には、映画『男はつらいよ』の主題歌の2番の歌詞をつい思い出してしまうのだが、諸事情により歌詞の詳細は記さない。いずれにしろ、蓮杖の写真師としての道のりは、まさにそのようであった。
文政6年(1823)伊豆国下田の生まれ。久之助と名づけられた。
下田の砲台付きの足軽として働いている折、仲間から偶然に「自分の弟は江戸の絵師狩野菫川の門弟だ」という話を聞かされた。子供の頃から画家になりたい夢を持っていた久之助は、頼み込んで紹介状を書いてもらい、狩野菫川の門下生となった。久之助はめきめき腕を上げ、師から菫円という号も授けられた。ところが、そんなある日、師匠からオランダ渡来の銀板写真を見せられ、心を鷲掴みにされてしまう。
なんとか「写真」というものに接近したいと思い定めた久之助は、じっとしていられない。国禁をおかしてでも外国人と接触する機会を探ろうと、外国船が出入りする浦賀へ向かう。師匠はそんな久之助のわがままを受けとめてくれた。
江戸を離れるに際し、久之助は彫師に頼んで長さ5尺(約1・5メートル)の蓮の杖(唐桑製)をつくらせた。以前から胸奥に抱いていた「蓮花」への思いを、ここでひとつの形にしておきたかったのだろう。と同時に、久之助はその杖に、師の恩を忘れまいという気持ちも込めたという。蓮杖の雅号も、ここから生まれていく。
再び足軽となって浦賀の平根山砲台付きとなった蓮杖だが、チャンスはなかなかめぐってこない。ようやくタウンゼント・ハリスの通訳のヒュースケンと秘密裏に接触し写真技術の原理を教えられるのは、江戸を離れて10年ほど経過したのちだった。
その後、次のステップに踏み出したい蓮杖を後押ししたのは、やっぱり師の狩野菫川だった。菫川は江戸城本丸の襖絵などの制作を蓮杖に手伝わせ、蓮杖の手元には100 両という巨額の手間賃が転がり込んだ。
蓮杖はこれを元手にして、横浜へと繰り込む。そこでウィルスンというカメラマンに出会い、その周辺から少しずつ知識を獲得。ウィルスンの帰国に際しては器械や薬品、暗室などを譲り受けた。こうして、蓮杖はとうとう念願の写真館を開くに至るのである。写真への思いに目覚めてから、20年近い歳月が流れていた。
それでも、なお障害はあった。「写真は生き血を吸う」という迷信があり、はじめ日本人客は皆無に近かった。日増しに借金がかさみ、夜逃げを考えたこともあった。だが、文久2年(1862)の生麦事件のあと、死を覚悟した侍たちが撮影に駆け込んだあたりから、次第に客が増えていったという。一方で蓮杖は、江戸城周辺や各種の職業風俗写真などの撮影にも、旺盛に取り組んだ。いつしか、写真は時代の先端を行く流行となっていった。自身の好きなことば通り、這い回った泥田に根をはり、蓮が見事に花開いたのである。
大正元年(1912)には、写真術への多大な貢献により、東京府から下岡蓮杖に木杯が贈られたという。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。