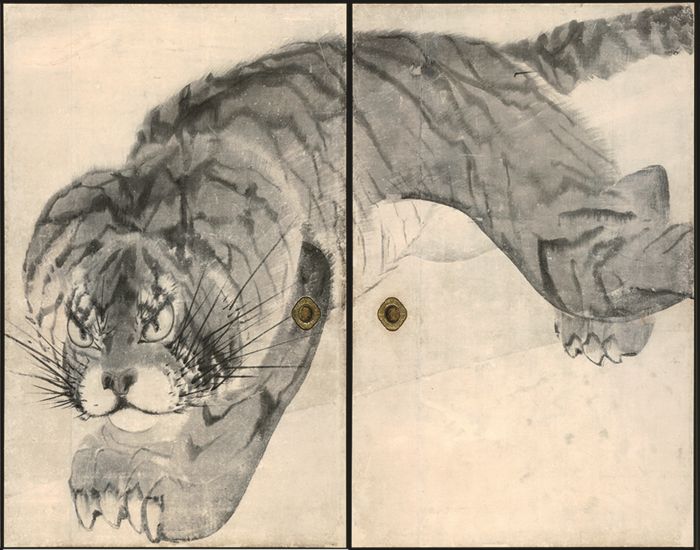今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「私には妙な癖があって、煮えたぎった湯が、自分の目の前にないと、どういうものか気が落ち着かず、不安でならないのである」
--泉鏡花
泉鏡花は30歳の頃、赤痢に罹患した。このことが後を引き、胃腸に持病のある身となった。以来、その紡ぎ出す絢爛の美文に比肩するほどの、ちょっと風変わりなエピソードに彩られた食生活を送ることになる。
たとえば、刺身はなまものだから見たくもない。酒はぐらぐらと煮立て、熱燗ならぬ煮え燗にして飲む。アンパンは表、裏、横とすべて火にあぶってから指先でつまんで食べ、指の当たっていた部分は最後にポンと捨ててしまう。とにかくバイ菌が怖いのである。コレラが流行したある時期には、煮豆と湯どうふだけで100 日余りを過ごしたこともあった。
その湯どうふも、強火で煮立てて鍋の中で踊りをおどるようになったのを、「ひょいと挟んで、はねを飛ばして、あつつと慌てて、ふッと吹いて、するりと頬張る。人が見たらおかしかろうし、お聞きになっても馬鹿々々しい」という次第。「腐る」という字さえ見るのが嫌で、「豆腐」と書かず「豆府」と書いた。
掲出のことばも、そんな鏡花ならではの台詞。つづけて、こうも語っている。
「あの黒い煙を吐いて走る長い怪物に身を任せていると、そこには鉄瓶の『松風』の音が聞けず、渋茶をすすることが出来ないから、私は堪え難い寂寥に襲われて、到底我慢がならないのである」
ここでいう「怪物」は蒸気機関車のこと。汽車の中では湯を沸かして渋茶を喫することもできないから、もともとは好きだった旅行も行かなくなってしまったと訴えているのだった。
こんな話を伝え聞いた女流作家の岡田八千代が、鏡花に、固形アルコール入りの携帯用コンロをプレゼントした。これさえあれば、チンカラリンと湯の音を聞きながら渋茶をすするという「何物にも換えがたい三昧境」が、汽車の中でも、うだる暑さの真夏の旅宿でも確保できるのだった。
ある日の車中では、こんなハプニングもあった。シートの上でめらめらと燃える青い炎を見た乗客が、汽車が火を吹いたものと勘違いして車掌に知らせ、車掌が泡を食って飛んできたというのである。そのとき、鏡花は落ち着き払ってコンロの効能書きの一節を復唱し、車掌は狐につままれたような顔をして引き上げたという。
ことは飲食関係にはとどまらない。
鏡花は執筆の際、原稿用紙にお清めの水をふりまき、書き損じた文字は、言霊のよみがえってくることのないよう、墨くろぐろと塗りつぶした。そんな独自の、過敏すぎる神経の使い方があったことも、ここに記しておこう。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。