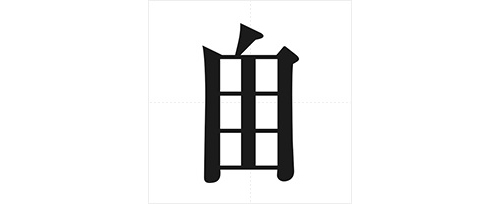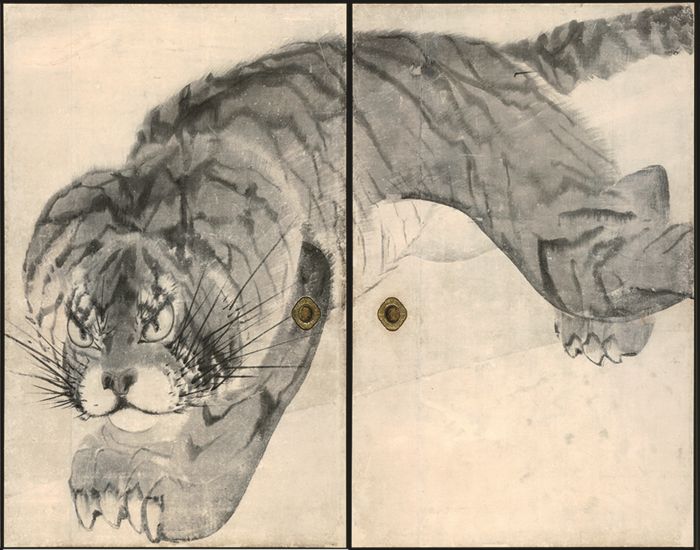文・構成/鈴木隆祐
そもそも料理の味というのは、舌の上だけで感じるものではない。
おいしい料理は、まず調理の「音」が厨房から聴こえるところから始まり、蠱惑的な「匂い」が立ちこめることで食欲を否応にも沸かせる。そして皿が運ばれてくると「美味そうな盛りつけ」を目にして唾を呑み、鼻腔いっぱいにその「香り」を吸い込んでは陶然となる。
ナイフとフォークでカットする際にも、得も言われぬ「触感」がその先から伝わり、一片を口に運んでは、ようやく舌の上で「味」を楽しむ。かように食事とは、五感を駆使する総合的な悦楽行為なのだ。
そして食は、今や科学的な研究対象としてもビッグバンを迎えている。
世界一との称賛を集めたレストラン、スペインの「エル・ブリ」のオーナーシェフのフェラン・アドリアは、2011年に同店を閉め、食のイノベーションのための財団を立ち上げた。2015年には「近未来味覚ラボラトリー」なる研究施設を開くと宣言した。
「分子ガストロノミー(美食学)」を提唱したアドリアは、レストラン併設の2つのラボ(スペイン語でタジェール)に半年立てこもり、半年は店を閉めていた。そして自然な流れとして、レストラン経営より研究成果をネット上のデータベースで公表していくほうが面白くなった。
アドリアの発想は本当に奇抜で、調理法を決定するのは材料(当人は「プロダクト」と呼ぶ)ではなく、化学や生物学、物理学、心理学、あるいはメカニクスやテクニックであってもいいのではないか、との自問自答から、すべての料理を考え出す。そうして24年間で1,846種類もの料理を、アドリアはラボで生み出した。
つまり、料理との接点が科学や数学でも構わないわけだ。大体において、レシピとは「解法」である。むろん材料次第で公式通りに解けないケースがあり、臨機応変さも要求されるが、前提としては料理は「解法の暗記」といえる。だからサライ世代でも、特に理系出身者が料理にハマることが多い。
料理は綿密にして即興的なアートだ。公式通りでなく、「こうとも解ける」という発見が、レシピに微細な変化を加えていく。
どれだけ多くの難問に打ち当たり、その解決に励んできたか。仕事に人生に、クリエイティブに取り組んできた人であればこそ、その経験も注ぎ込める。料理が楽しくなって当たり前である。
こうなると料理は、老師に教わる合気道のようになってくる。ただの受け身ではいられない。仮に享受に徹するにせよ、作る側の立場に立てれば、料理をよりいっそう深く味わえるというものだ。
「男子厨房に入る」
文・構成/鈴木隆祐
監修/前刀禎明
【参考図書】
『とらわれない発想法 あなたの中に眠っているアイデアが目を覚ます』
(前刀禎明・著、鈴木隆祐・監修、本体1600円+税、日本実業出版社)
http://www.njg.co.jp/book/9784534054609/