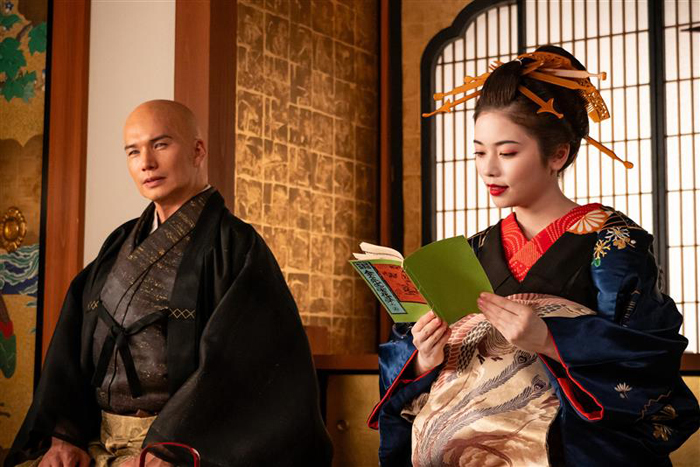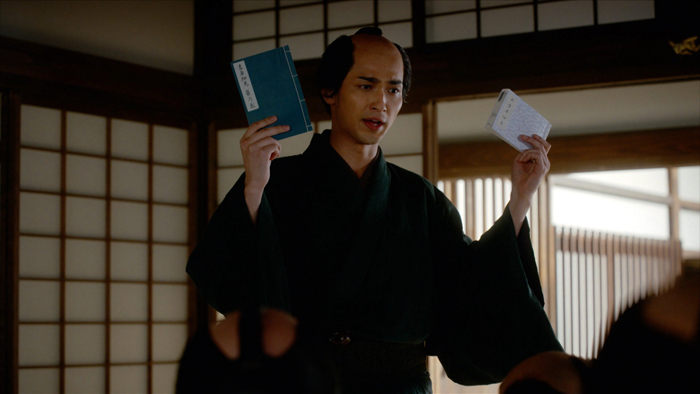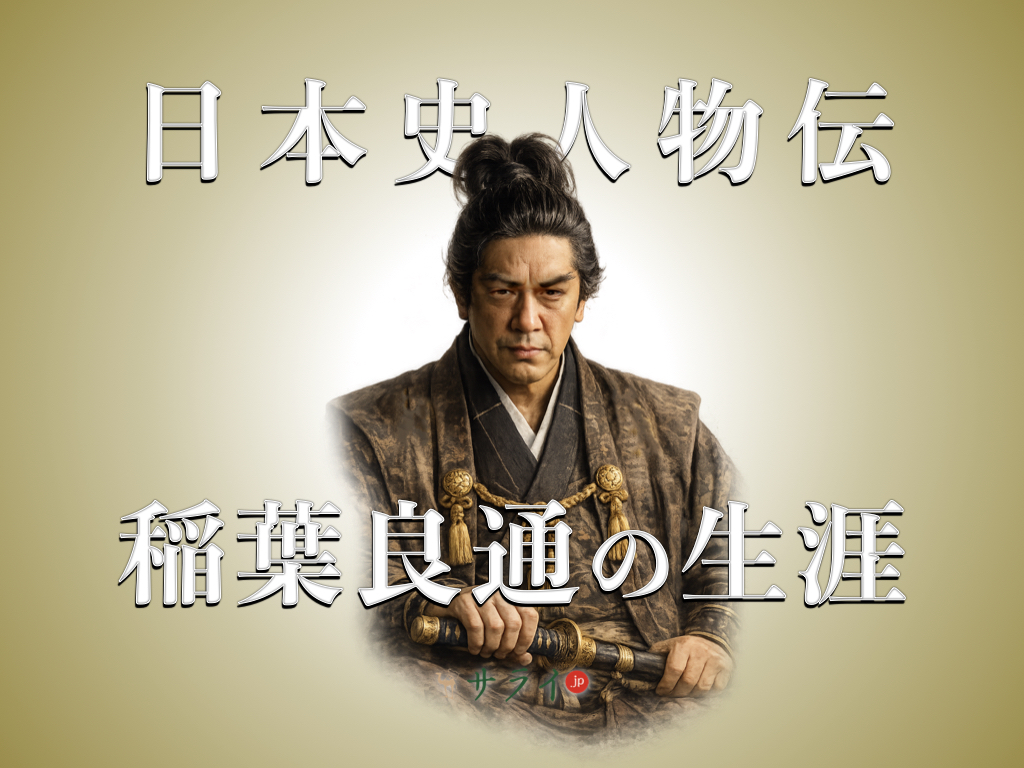「わいせつ」について考える
A:ところで、当時の春画では局部が極端にデフォルメされているという話が出ましたので、少し脱線しますが、現代では、局部があらわになっている画を頒布することは刑法175条のわいせつ物頒布等罪で違法ということになります。
I:『べらぼう』劇中のころはそのような規制がなかったということなのでしょうが、現代は、『べらぼう』の時代から250年ほど経過しています。この間でも「表現」に対する感覚は変遷してきています。例えば、昭和25年『チャタレイ夫人の恋人』の無修正邦訳内容がわいせつにあたるか否かを問うた裁判や、昭和55年に最高裁の判決がでた「四畳半襖の下張事件」などわいせつ表現をめぐる裁判がありました。
A:今考えると「それがわいせつ?」という感がしなくもないですが、それが歴史の流れというもの。そして、1980年代後半から1990年代にかけては「ヘアヌード解禁」の流れがあったりして、わいせつの概念もその時々で「揺れ動く」ことが鮮明になりました。同じような描写でも世代間で受け止め方が異なるという場合もあるかと思います。というわけで「大暴れ」した喜三二の「分身」の登場を視聴者はどのように受け止めたでしょうか。
I:うーん。私はちょっと引いたかな。
A:なるほど。でも、はちゃめちゃな発想で、エネルギーがみなぎっていた時代の空気は伝わってきた気もします。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり