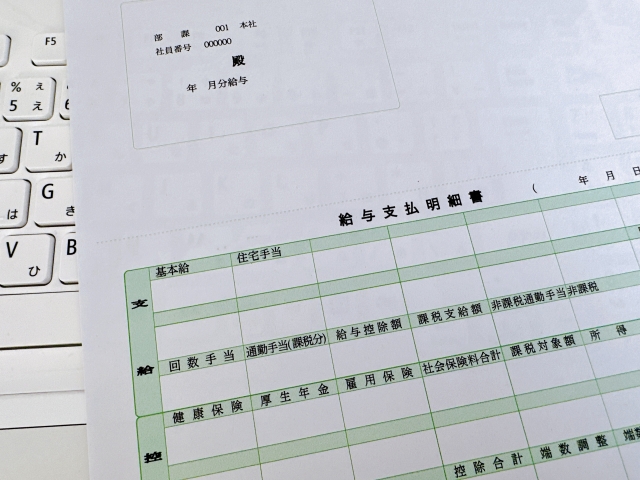マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
はじめに
部下・社員の成長を最適化させ、部署・会社の継続的な成長に繋げるための環境として、評価制度を構築し運用されている会社や、これから構築・運用に取り組んでいこうと考えている会社があると思います。
この評価制度に関して肝要なことは、「平等」な目標設定ではなく、「公平」な目標設定が行われる設計を行うことです。
なぜ「公平」な評価制度・目標設定が必要か?
人は、目指すべき目標が不明確だと、「迷う」「悩む」状態のまま集中力が阻害され行動の着手が遅れます。このため、部下の集中力を高めて仕事の質を上げさせるためには、目標を明確に設定することがまず求められます。
一方、目標を明確に設定し、それが上司側から見て達成可能だと推察される水準だとしても、当該部下が、自分と同じ役割を担っている同僚の目標設定が経験年数や評価制度上の等級などに比して明らかに低い水準だと捉えた場合、不公平に感じるばかりか、自分の目標達成が難しくなった場合の言い訳を思考するようになり、行動量が増えていかない状態に陥りかねません。
不公平感を感じると部下が動かなくなる理由
そのため、まずは「同じ土俵で闘っている」という感覚を部下に持たせることが肝要です。それはすなわち、「同じルールの環境下で働いている」という認識であり、同僚に対して「仲間であるとともに、適正な競争相手である」との認識に繋がるものとなります。
社歴2年の若手社員が、社歴10年のベテラン社員と同じ目標が設定され、かつ、実際にその目標をベテラン社員の方が容易に達成しやすい(あるいは大幅な達成率を果たしやすい)状態であれば、若手社員が考えることは「どうにかしてこの目標を達成させよう」ではなく、「同じハードルなら、それはベテラン社員の方が達成しやすいでしょ」「どうせ勝てっこないし。途中の進捗が遅れていることを指摘されても納得いかない」といった思考を持つことになります。
同僚に対して「適正な競争相手である」と認識するメリット
同じルールの下で稼働する仲間を適正な競争相手だと認識したとき、上述した不公平感や言い訳思考は最小化に向かい、自身に課せられた目標を達成させるための行動に意識が向かいます。
それは、KPI(重要業績評価指標)を達成させるためのKDI(重要行動指標)の最大化に繋がるだけでなく、上司が何ら指示せずとも、KPIの進捗が良い同僚に対して、“部下自ら取り組み方を同僚にヒアリングしに行く” といった事象が自然発生しやすくなります。ハイパフォーマーに対して、その事実を懐疑的に捉えるのではなく、「適正な競争相手である」と認識するが故にその差分を自身の不足と捉え、それを埋めるための行動を自発的に取り組み始めるということです。
実際、そういった状態に至ると、上司自身が部下にしてほしい行動を指示しなくとも、部下が自ら思考し、競争(共創)しながら組織全体として改善に向かうことになるため、KGIもより達成しやすくなり、上司としては楽(ラク)と楽しさを両方得られる状態に向かいます。
ランニングフィーがある場合、不公平感や言い訳思考が発生しやすい
営業職を担っている人の中には、ビジネスモデル上、商談で新規契約やリピート受注でのショット型の収入高を得るだけでなく、サブスクや顧問契約などで継続的に毎月ランニングフィー(ストック収入)を得るケースもあるかと思います。その際、経験年数や評価制度上の等級などの目標設定だけでは公平性が担保されません。
なぜなら、既存顧客の数が多ければランニングフィーを多く獲得しやすくなり、ランニングフィーの多寡を目標設定に加味しない場合、目標達成の難易度が下がることになるため、既存顧客の数が総体的に少ない社員は「既存顧客をそれだけ持ってたら、それは達成しやすいよ」と不公平感を抱くことになります。
一方、ランニングフィー自体を目標値に組み込まない場合、既存顧客を多く抱えている社員側が「これだけ既存顧客の対応に時間を使っているのだから、新規契約を獲得するための時間は取れない」と言い訳思考を持つようになってしまいます。
ランニングフィーの一定割合を目標値に加えることで、公平感を担保する
このため、ランニングフィーを得る場合は、過去実績を基に標準継続率を設定し、その標準継続率に基づく想定ランニングフィーを経験年数や等級とは関係なく目標値に加えることを推奨します。例えば、以下のような形です。
1:等級に基づく3か月間のショット売上の目標値が1,000万円。
2:ランニングフィーの標準継続率が90%で設定され、前3か月のランニングフィーが500万円だったとすると、500万円×90%=450万円が目標値に加算される。
3:当該社員の3か月間の総売上目標値は1,000万円+450万円=1,450万円と設定される。
このような設定をされた社員としては、既存顧客のフォローを徹底して継続率100%を果たしたなら、ランニングフィーが500万円となり、ショット売上の必要額は950万円に抑えられます。逆に継続率が80%となったなら、ランニングフィーが400万円となり、ショット売上の必要額は1,050万円に膨らみます。
既存顧客数の多寡で目標達成の難易度が左右されるのではなく、既存顧客のフォロー徹底による継続率によって目標達成のしやすさが決定される仕組みになれば、既存顧客数の差によって不公平感や言い訳思考が生まれることを最小化できるということです。
※新規のショット売上を獲得した場合、期中のランニングフィーも増加するケースが多いと思いますが、シンプルにご理解いただくために、上記の説明に当該ケースは含めておりません。
公平感を担保する要素として、上司の部下への距離感がポイント
会社や上司が設定するものである以上、すべての部下にとって不公平感が皆無の状態にすることはできません。一方、部下が多少なりとも不公平感を抱いたとしても言い訳思考にならずに「まあ、これならやるしかないな」と行動を起こせるようになれば、組織運営としては問題ないと判断できます。
そして、部下がそういった行動を起こせるようになるには、上司と部下の役割を明確にし、精神的にも物理的にも距離感を均等に保つことが肝要です。距離感が近いとどうしてもお気に入りの部下ができてしまい、称賛の程度や頻度、あるいは采配に差が生じ始め、それが他の部下の「同じ土俵で闘っている」という感覚を目減りさせてしまうからです。
制度としての評価の在り方だけでなく、上司の評価に類する言動も公平性を担保する上で重要となるため、部下との距離感を均等に保つことを推奨いたします。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/