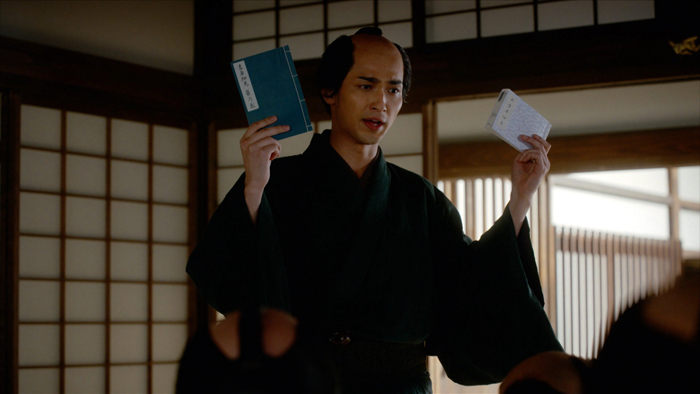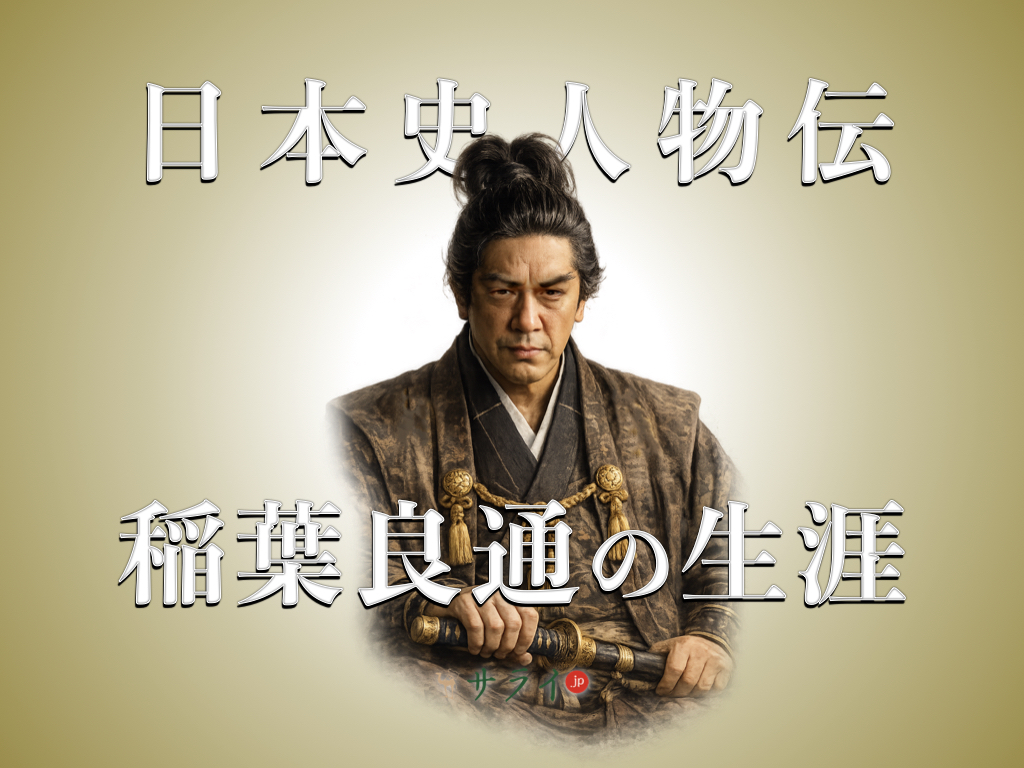ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第14回ですが、花魁瀬川(瀬以/演・小芝風花)のことを思うと、胸が締め付けられる思いがします。おそらく子供のころに「売られて」きて(建前上は奉公)、客を取るようになってからの日日は、現代の私たちの想像をはるかに超えた日常だったと思われます。そして花魁になって、鳥山検校(演・市原隼人)に身請けされて、晴れて吉原を抜け出すことができたわけです。
編集者A(以下A):せっかく幸せを掴んだと思ったら、夫の検校が摘発されるという事態になってしまったということですね。確かに切ないですね。
I:当時の女郎が心の奥底で、どのような思いでいたのか、なかなか想像できませんが、ほんとうに涙がこぼれてきます。
吉原の親父たちに冷水が
I:吉原の親父たちが和歌の「五七五七七しばり」で会話をするという寄合をしていました。以前にも猫語で会話する場面(第4回)がありましたが、今度は和歌なんですね。実は、「和歌しばり」は、元はもっと高尚なもので、貴族社会などでは会議のときに和歌を使って表現するといったことがあったようです。時代は違いますが、戦前、神社界では有力神社の宮司を決める際に、神社界のトップたちが会合で和歌を詠み合って意志を伝え合っていたこともあったそうです。こういうのは古代の中国でも詩で行なっていたらしいんですよね。
A:ドラマの中では、五七五七七で会話をするということで「なんちゃって和歌しばり」だったわけですが、文化人を気取りたかったのでしょうか。『べらぼう』劇中では、当時の高級料亭「百川」から仕出しをとっている場面も登場していますから、そういう意味では、「上流気取り」で実際に金持ちだったのでしょう。
I:そう考えると、大文字屋(演・伊藤淳史)が神田で地所を求めた際に、手付まで払ったにもかかわらず、最終的に「拒絶」されたという描写は、当事者の大文字屋だけでなく、吉原の親父たち全体に思いっきり冷水を浴びせる事態だったんですね。このエピソードは『譚海(たんかい)』という随筆に記された実際にあった出来事のようですね。
A:『譚海』の著者は、秋田藩出入りの人物だったといいます。秋田藩留守居役の朋誠堂喜三二(演・尾美としのり)とつるんでいたのかもしれないですね。さて、吉原という場所は苦界であり悪所という認識は当時からありました。しかも働く女性たちのほとんどが借金のカタに吉原で働かざるを得なかった女性たち。吉原以外の江戸の人たちは遊ぶときは遊んでおいて、いざ自分たちのテリトリーに吉原の人たちが寄ってくる気配をみせると拒絶するということですね。まあ、町人が街中で武士に無礼をはたらいた際には「切り捨て御免」が認められていた社会ですから、現代とはいろいろと社会の仕組みが異なりますね。
I:一方で、吉原の女郎たちはファッションリーダーでもありました。吉原という街じたいも「観光地」として足を運びたいという場所だったといわれています。『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」~歴史おもしろBOOK』の受け売りですが、当時すでに日本橋に店を構えていた「にんべん」ですが、もとの出身地である伊勢の方の親戚の奥様方が江戸にきた際に吉原を見学しにいったといいます。

【平賀源内に悲劇が襲う。次ページに続きます】