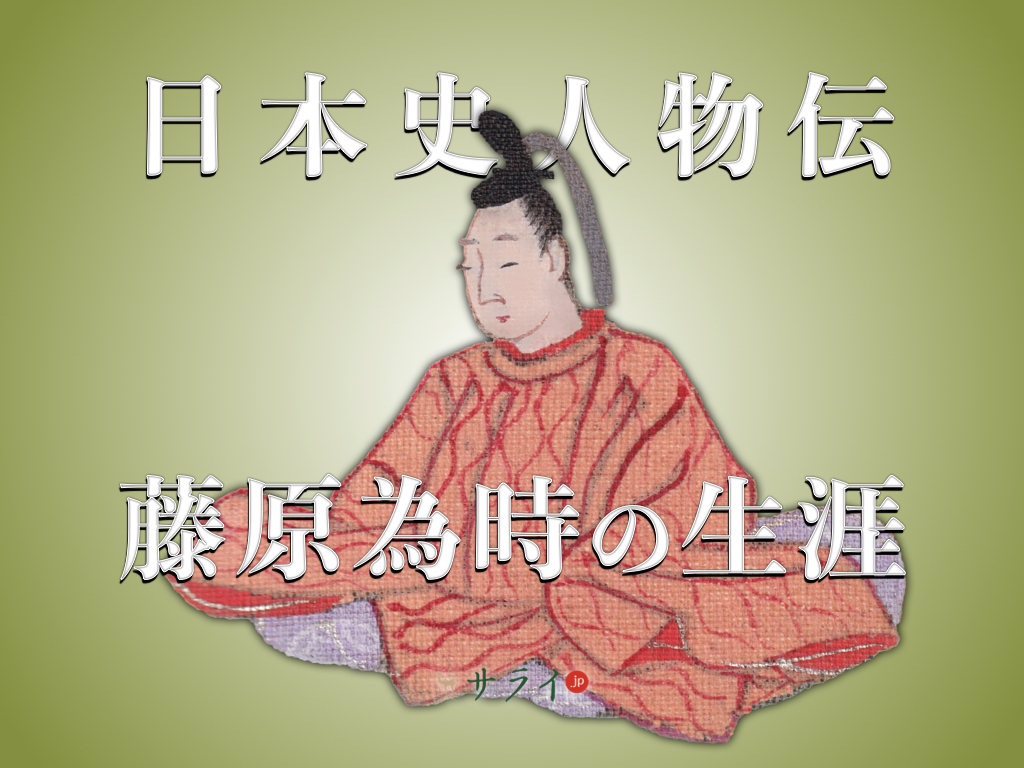「長徳の変」その後
二人を左遷した道長は、左大臣に上り、名実ともに政治のトップに君臨。伊周と隆家は、長徳3年(997)、東三条院(藤原詮子)の病気平癒のための大赦を受けて、都へ戻ることが許されましたが、ついに権力をその手に握ることはありませんでした。
ところで落飾した定子は、出産後、彼女を寵愛する一条天皇により、第一皇女・脩子内親王(しゅうしないしんのう)と共に宮中に迎え入れられます。その後、長保元年(999)11月7日、一条天皇の第一皇子・敦康親王(あつやすしんのう)を出産。長保2年(1000)の暮れには第二皇女・媄子内親王(びしないしんのう)を出産しますが、間もなく息を引き取りました。25歳の若さでした。
道長は、長保2年(1000)の2月に娘の彰子を中宮に立て、定子がいるのにもかかわらず皇后の座につけ、着々と自らと一族の権威付けをしていきました。一条天皇の皇太子にも定子の産んだ親王ではなく、彰子の産んだ敦成親王(あつひらしんのう)が立てられ、道長は念願だった摂政に。以降、道長は栄華を極め、ここに摂関政治は全盛期を迎えて、子の頼通へと受け継がれることになりました。
まとめ
「長徳の変」の最大の要因は、一族同士の権力争いでした。藤原兼家・道隆と続いた中関白家は、伊周の代で失墜。道長は権力の高みに駆け上がり、あの有名な「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の かけたることも なしと思へば」の歌を詠むまでになります。絵に描いたような政権トップの交代劇でした。
伊周と隆家は、政権の中枢から滑り落ちたとはいえ、後年、復位し、道長との和解も叶います。しかし、こうした男性たちの争いの陰に、中宮定子らのように人生を翻弄され、時に悲しい最期を迎えた女性たちのいたことを忘れたくはありませんね。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/深井元惠(京都メディアライン)
HP: https://kyotomedialine.com FB
引用・参考文献/
『日本大百科全書』(小学館)
『国史大辞典』(吉川弘文館)