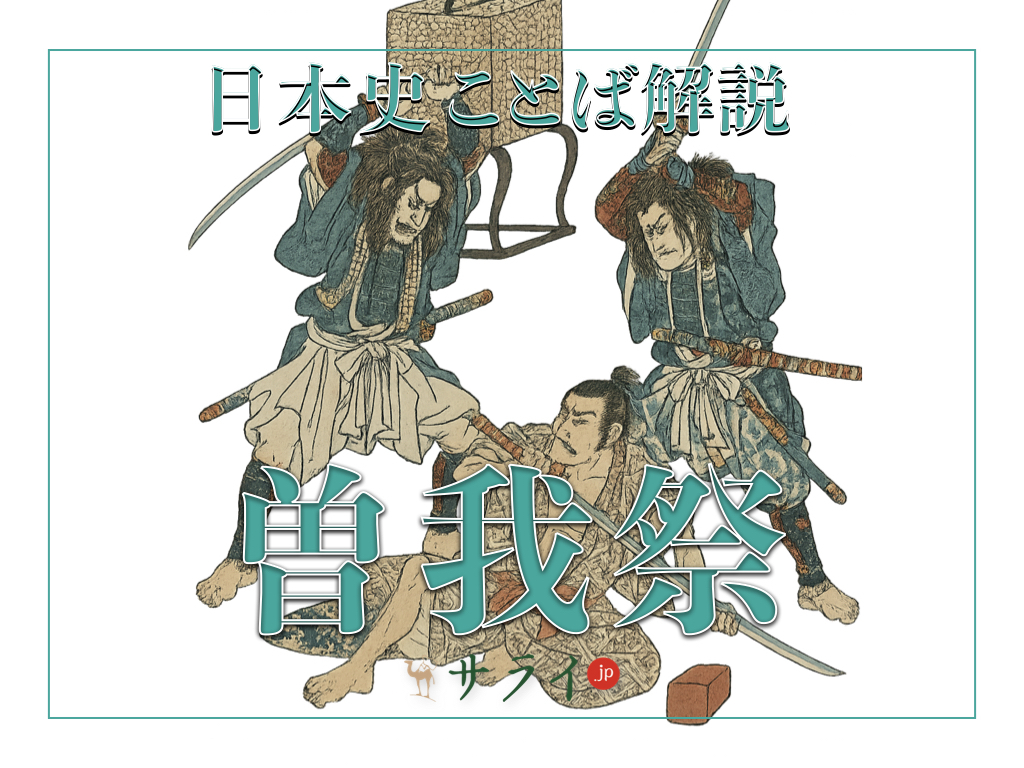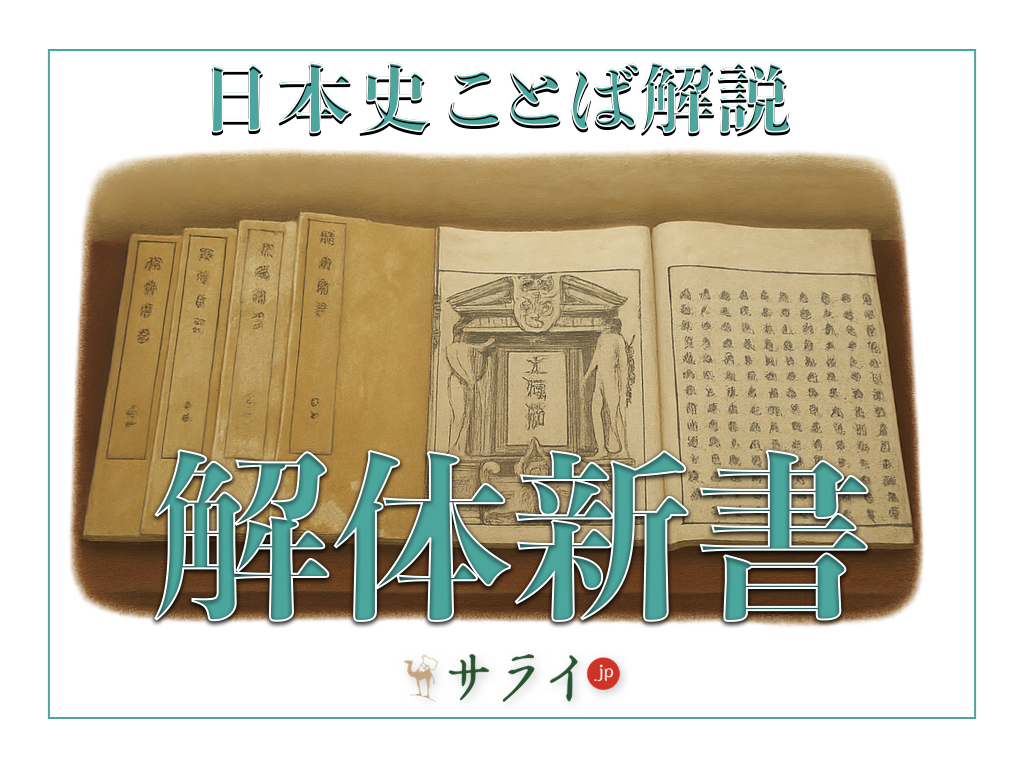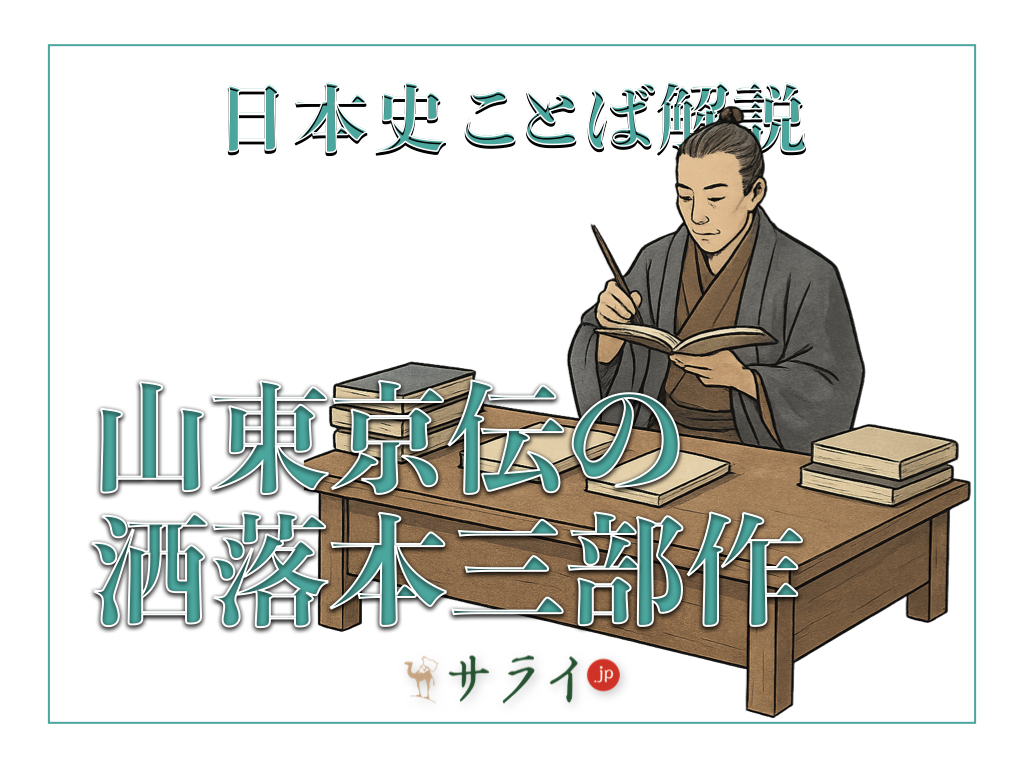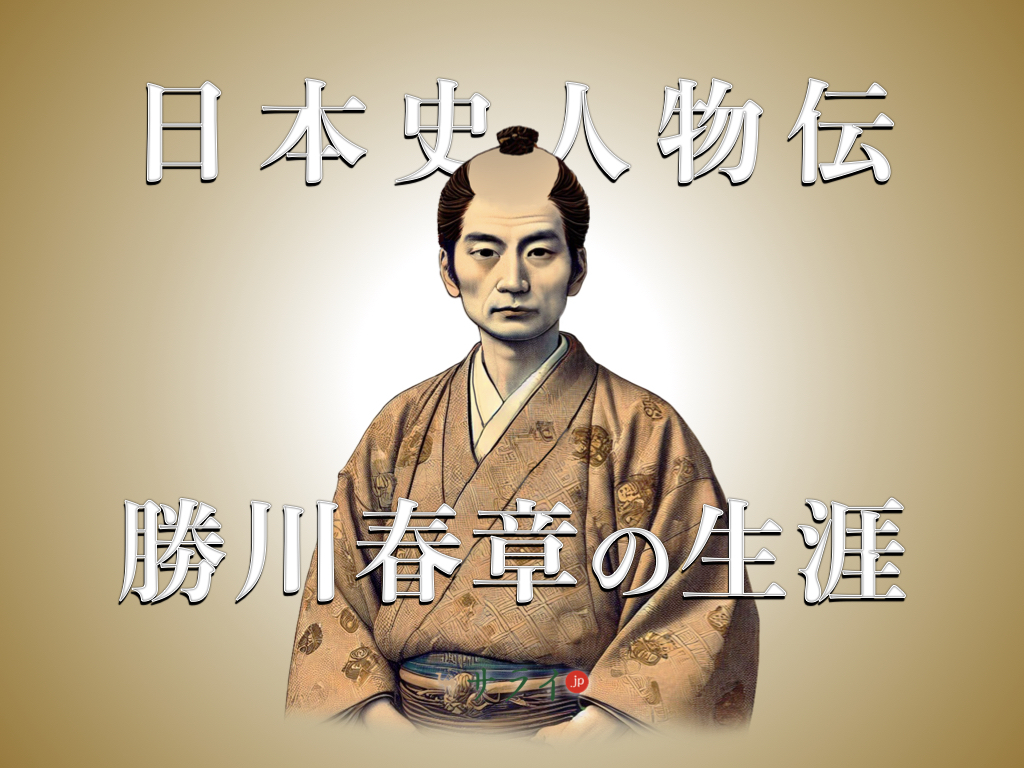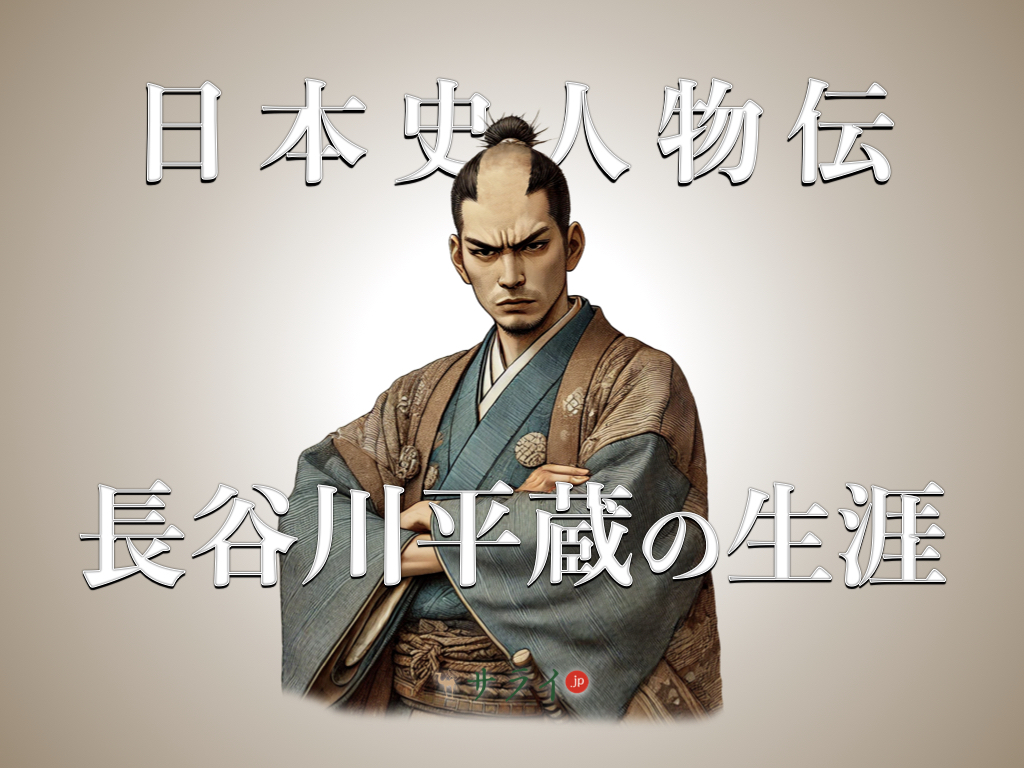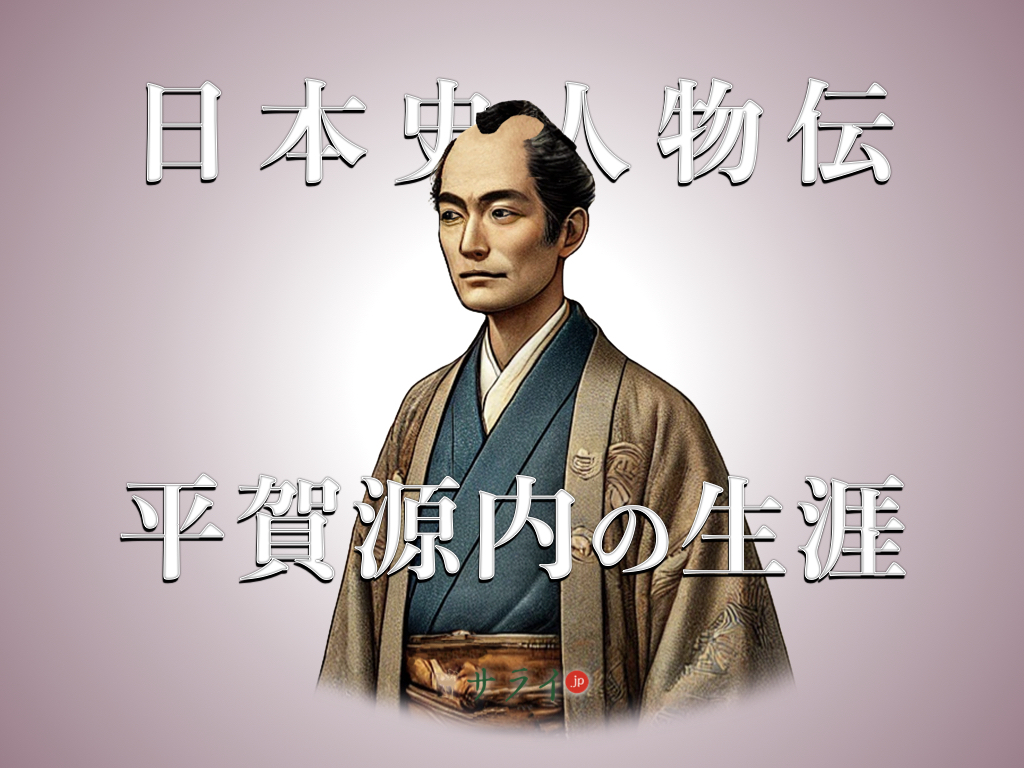はじめに—曽我祭とはどのような祭礼だったのか
江戸の芝居小屋が一年でもっとも華やぐ瞬間——それが「曽我祭」(そがまつり)でした。芝居の守護神をまつり、役者や町人たちが一体となって繰り広げたこの祭礼は、単なる舞台行事にとどまらず、江戸の歌舞伎文化を象徴する一大イベントとして親しまれてきました。
「曽我祭」は、役者たちの熱演を支える信仰と、舞台裏の熱気、町の賑わいが一体となった、まさに江戸の粋を体現した風物詩です。
この記事では、「曽我祭」についてご紹介します。

広重『(五郎時宗・十郎祐成)』,〔伊場屋仙三郎〕.
国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/1309288
「曽我祭」とは?
「曽我祭」とは、江戸の歌舞伎劇場において、曽我兄弟の仇討ちを題材にした「曽我狂言」が正月から5月まで継続興行した年に、曽我兄弟の討ち入りがあった5月28日を中心に催された祭礼行事のことです。
芝居の守護神として楽屋に祀られていた「曽我荒人神」(そがのあらひとがみ)のお祭りが起源で、もともとは楽屋内で執り行われる内輪の行事でした。
しかし、宝暦3年(1753)、中村座での初春興行が大成功を収めた際に、初めて舞台上でこの祭礼を披露したことで注目を集め、以後は江戸三座(中村座・市村座・森田座)において恒例行事となり、文政期(1818〜1830年)ごろまで続けられました。
「曽我祭」の特徴と魅力
曽我祭の最大の魅力は、舞台と楽屋、そして町中が一体となったそのスケールの大きさにあります。仕切場(しきりば)には神輿(みこし)が飾られ、幕間には神楽が奏でられました。
舞台では座中総出演による豪華な舞踊が「大切」(おおぎり)として披露され、観客にとっても特別な一日となりました。
また、楽屋でも賑わいは続き、打ち出し(公演の終了)後には酒宴が催され、その後は練物(ねりもの)や余興を演じながら町内を行列するなど、江戸の人たちにとっては、人気の役者の素顔が見られる貴重な機会でもありました。
その一方で、あまりの豪華さや贅沢さが幕府の風紀取締りに抵触し、しばしば弾圧の対象になるという一面も持ち合わせていました。
まとめ
「曽我祭」は、江戸の歌舞伎文化における華やかさと信仰が融合した象徴的な年中行事でした。
贅沢さゆえに幕府から警戒される一方で、町人文化の豊かさや役者たちの誇りを示す晴れ舞台でもあったのです。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『新版 歌舞伎大辞典』(平凡社)
『デジタル大辞泉』(小学館)