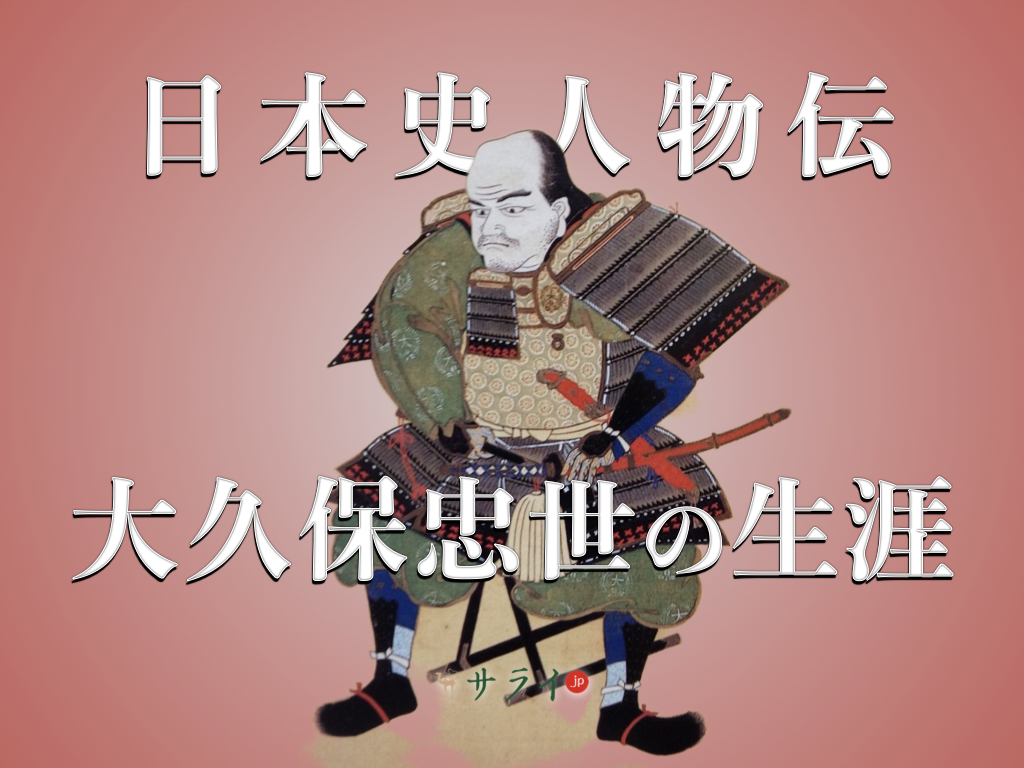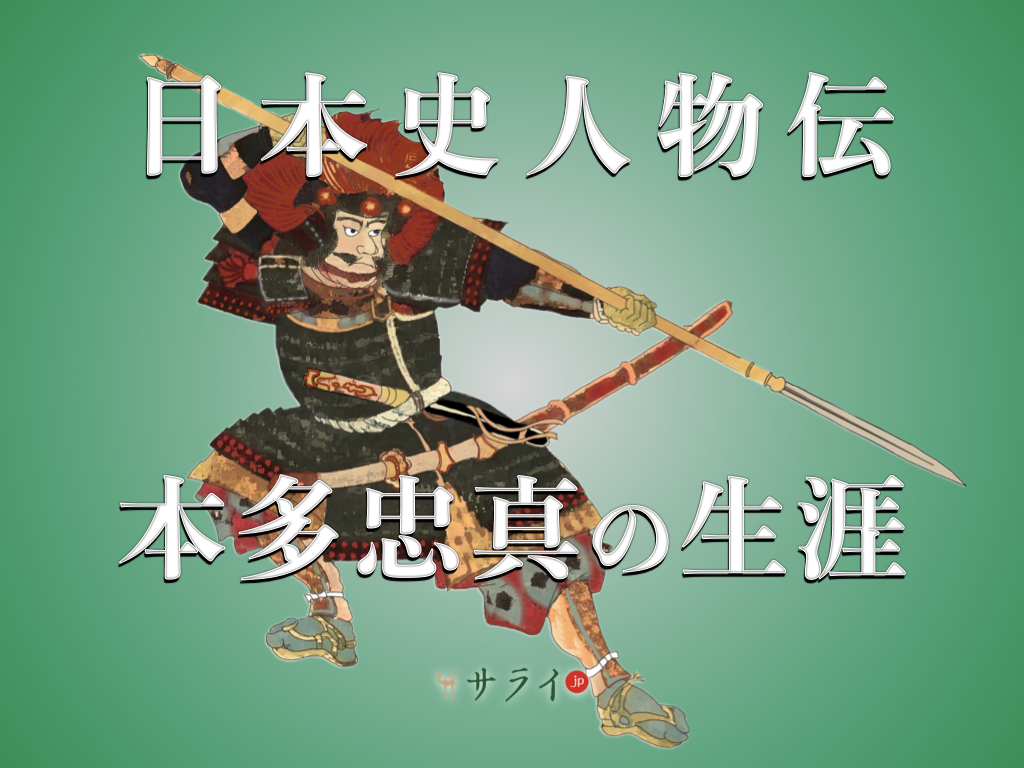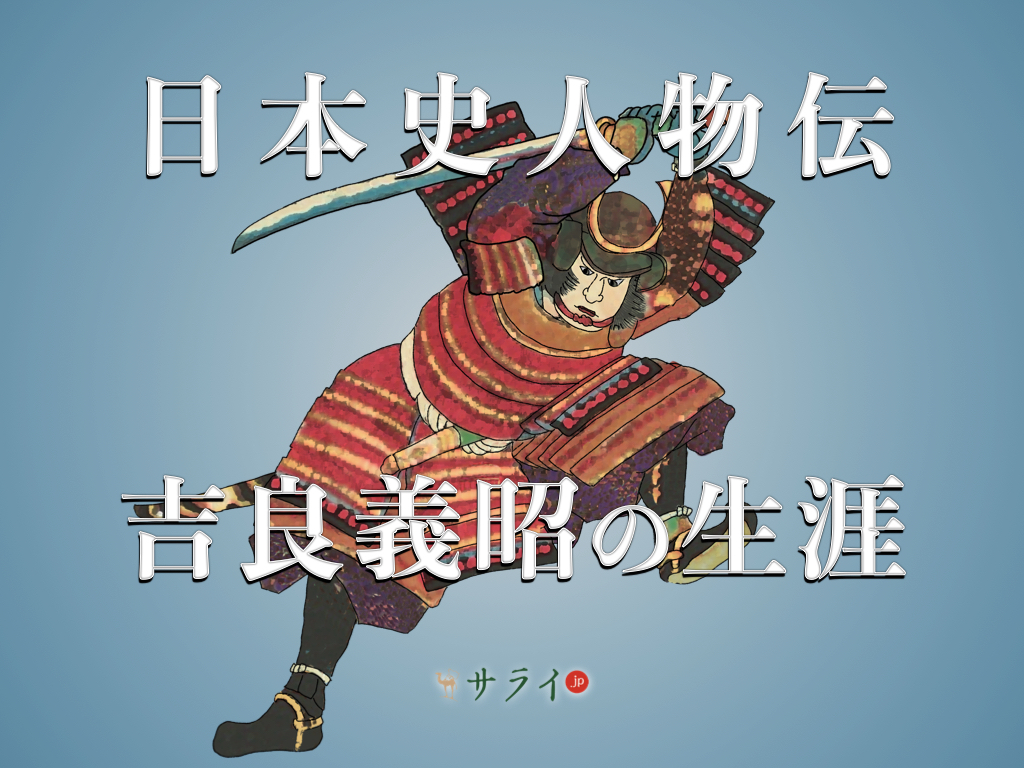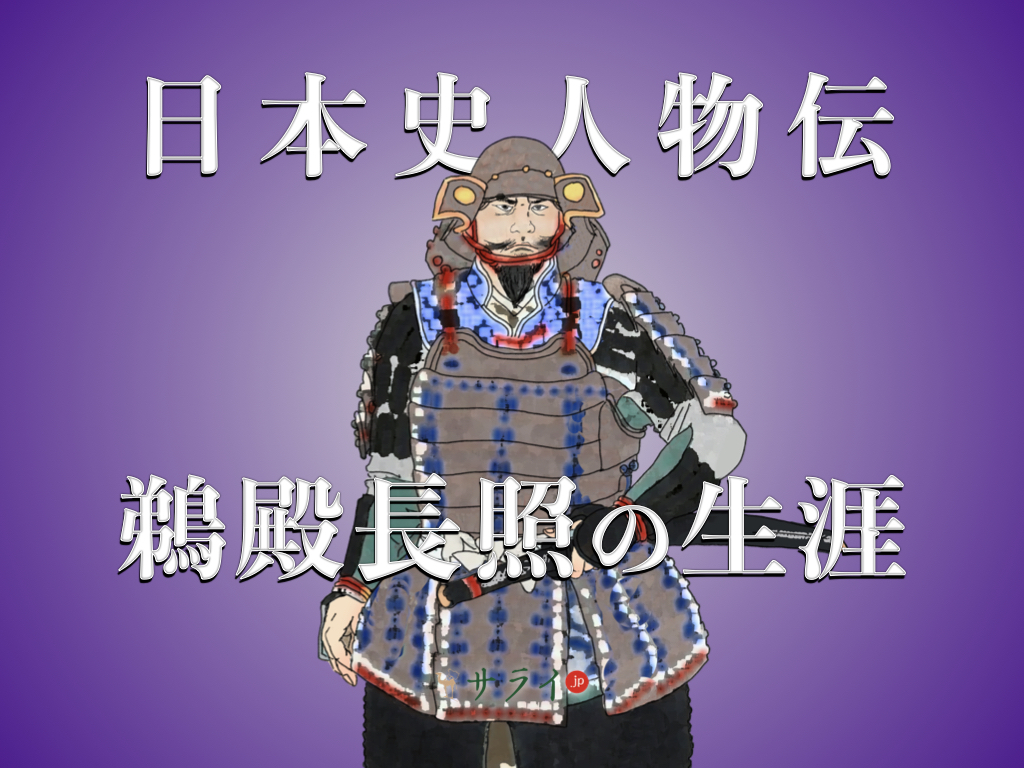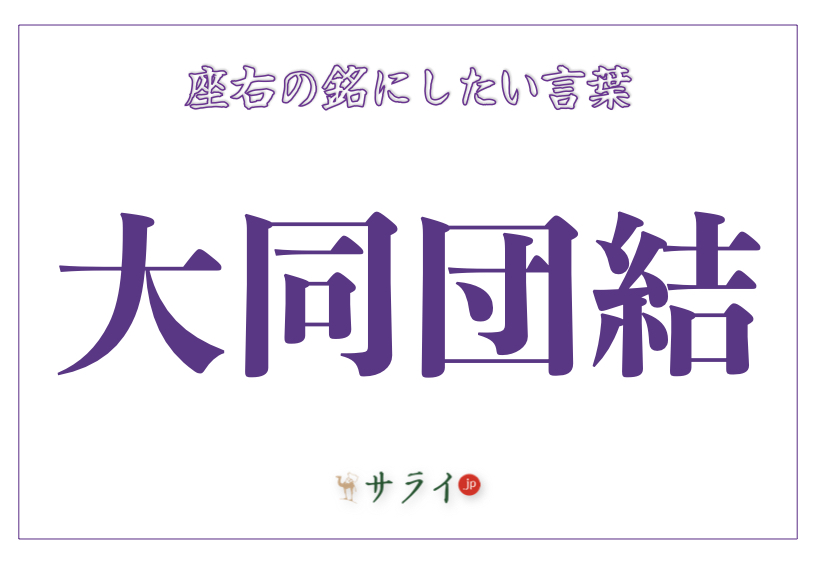様々な合戦で戦功を立てる
永禄6年(1563)、三河の一向一揆(いっき)では、父・忠員とともに上和田砦(とりで)を守り、家康を支えました。永禄末年には、一軍団を預かる部将・一手役(ひとてやく)となっています。
また「三方原の戦い」「長篠の戦い」などの合戦において、多くの戦功を立てたと伝えられています。天正3年(1575)に武田軍を破り、二俣城(ふたまたじょう)を与えられました。二俣城は遠江(とおとうみ)国(=現在の静岡県浜松市)に位置する山城です。天竜川と二俣川が合流する地点の丘陵上に築かれました。戦略の要地であったことから、戦国時代には武田氏と徳川氏が攻防を繰り返したことで知られます。

現在は曲輪、石垣などが残る。
小田原城主となる
天正18年(1590)4月に、豊臣秀吉による小田原征伐が行われます。徳川家康に従った忠世は戦功を挙げ、小田原城主となりました。小田原の地、4万5000石の大名となった忠世はその後、文禄3年(1594)9月15日に死去。63歳でした。

昭和35年(1960)に再建された。
忠世の伝説「酒匂川」
小田原を治めた忠世が行ったこととして「酒匂川(さかわがわ)の治水事業」が伝えられています。酒匂川は現在の神奈川県西部を流れ、小田原市の東で相模湾に注ぐ川です。古くはたびたび洪水が起こったことで知られる暴れ川でした。
文禄・慶長年間(1592~1615)に、忠世とその子・忠隣(ただちか)は、大口堤(=現材の南足柄市など)および岩流瀬(がらぜ)土手という堤防を築きました。流路を変えることで、川の水を足柄平野全域の用水に利用したのです。しかし、江戸中期の富士山の噴火で降った火山灰で本流がせき止められ、堤防は決壊しており、現存はしていません。
大久保氏のその後
相模国・小田原の地を与えられた忠世は、大久保小田原藩の藩祖となりました。その子・忠隣は11歳のとき家康の近習となって以来、忠世とともに「三方ヶ原の戦い」のほか、諸戦に軍功を重ねます。江戸幕府が開かれると、第2代将軍・秀忠(ひでただ)の重臣となりました。その後父・忠世の死により小田原藩主となりますが、讒訴(ざんそ)により蟄居されています。
その後、藩は近江国・美濃国・播磨国・肥前国へ転封を繰り返します。そして貞享3年(1686)、5代忠朝(ただとも)のときに小田原へ返り咲きました。11代忠真(ただざね)は、大阪城代、京都所司代、老中などの幕府要職を歴任し、藩政においては二宮尊徳を始め多くの人材を登用し、大久保家中興の名君として知られています。以降、大久保家は明治時代に廃藩置県が行われるまで小田原藩主を務め続けました。
まとめ
徳川十六神将に名を連ね、徳川家康を支えた「大久保忠世」。多くの功績が戦場での勇猛果敢な姿を思い起こさせます。その一方、領国での治水事業など、領主としての顔もうかがい知ることができます。色々な角度からの知識を得ると、より活き活きとした人物像が描けるのではないでしょうか。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/トヨダリコ(京都メディアライン)
HP:https://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『世界⼤百科事典』(平凡社)
『日本人名大辞典』(講談社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)
『日本歴史地名大系』(平凡社)