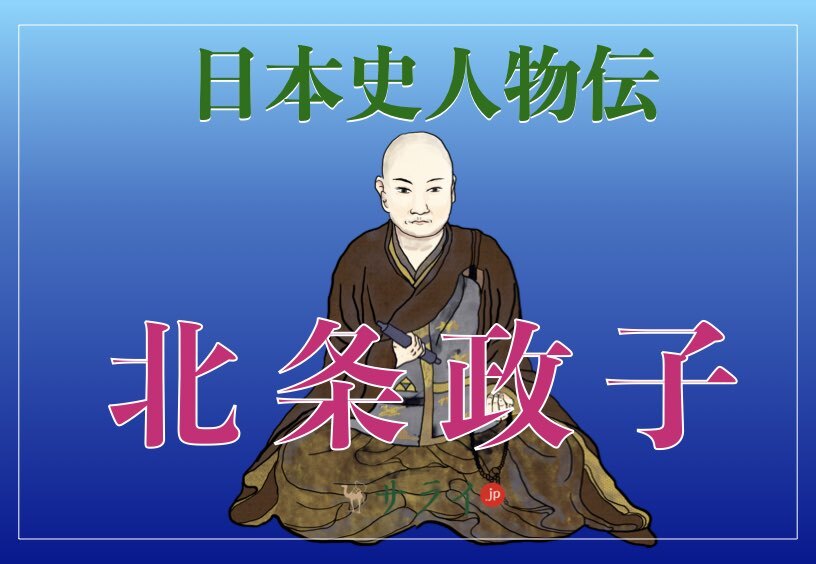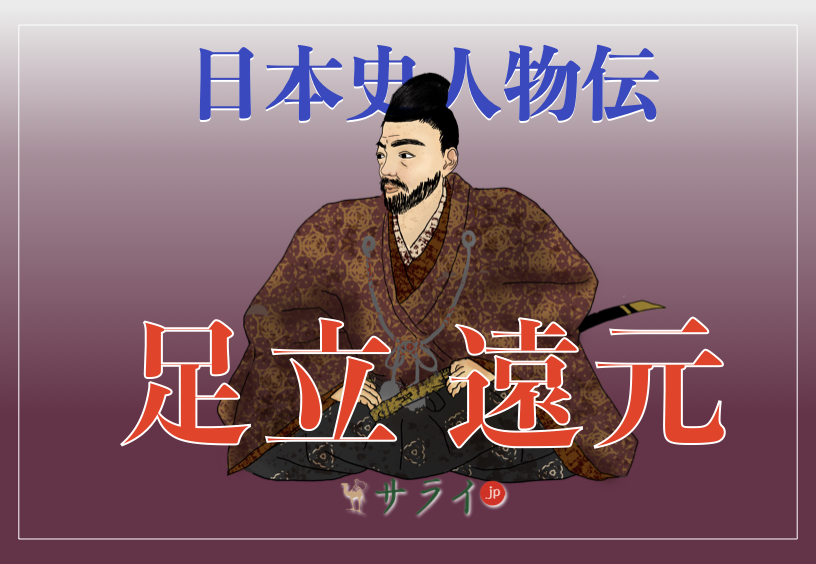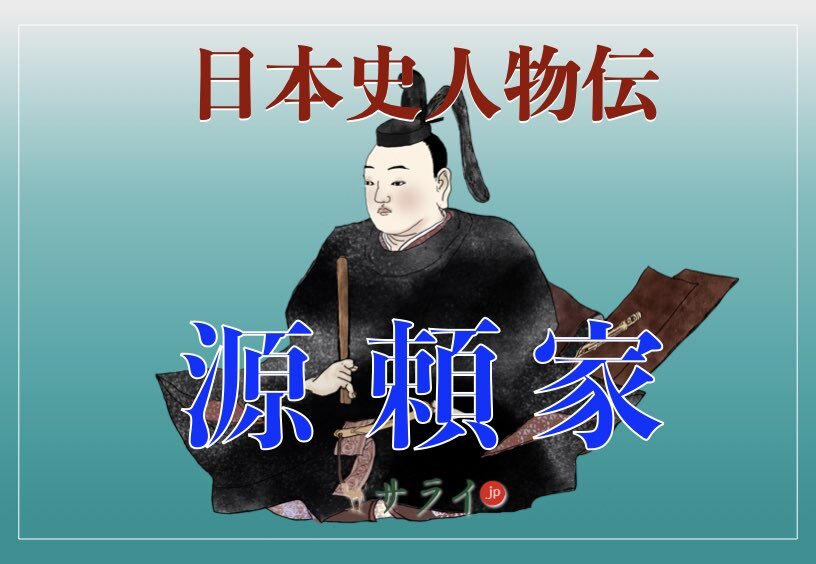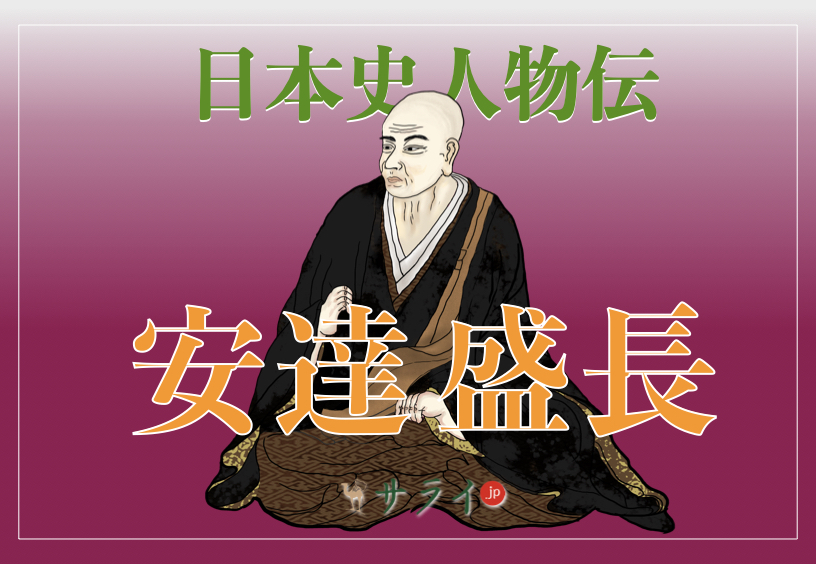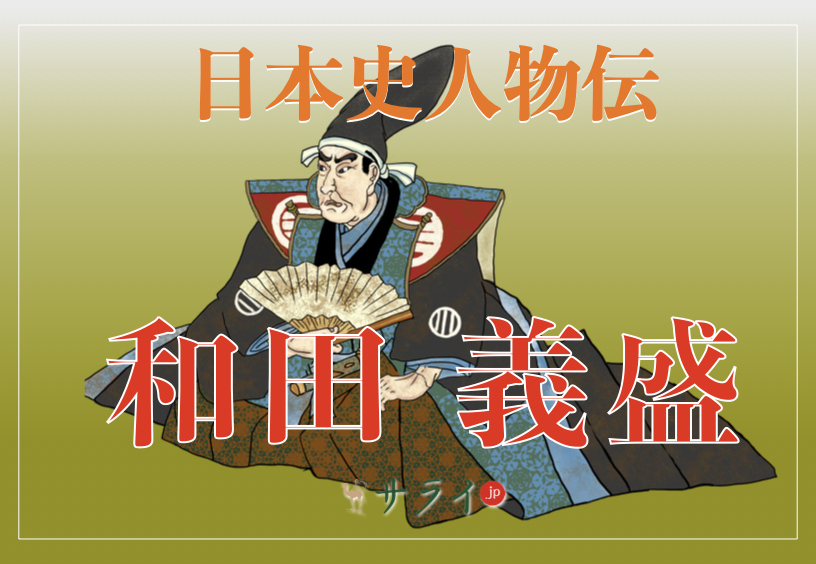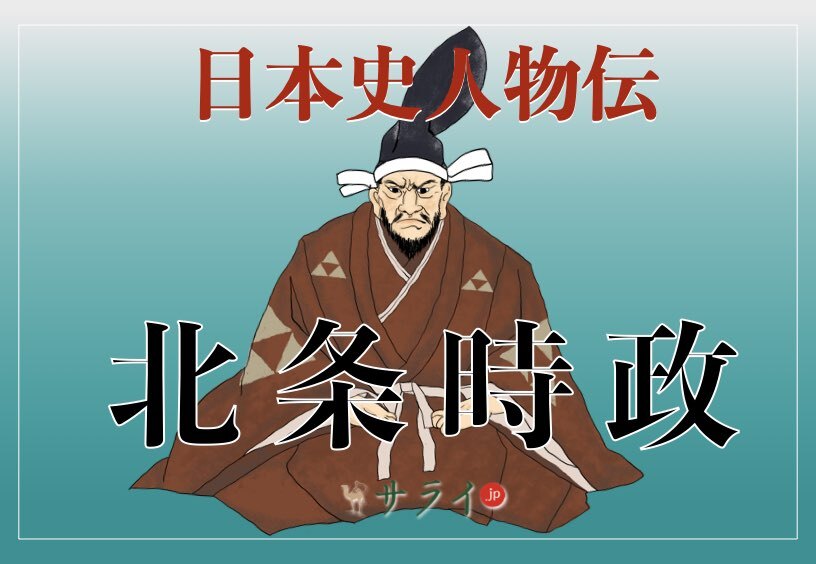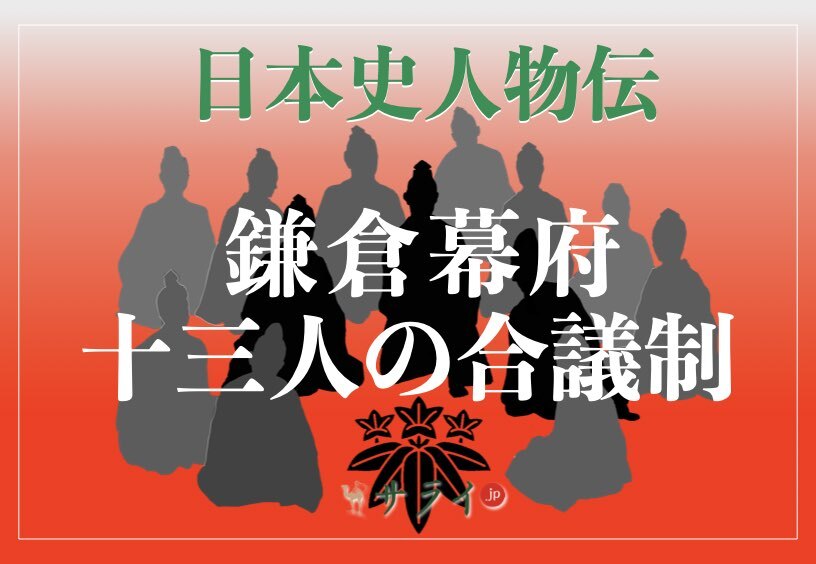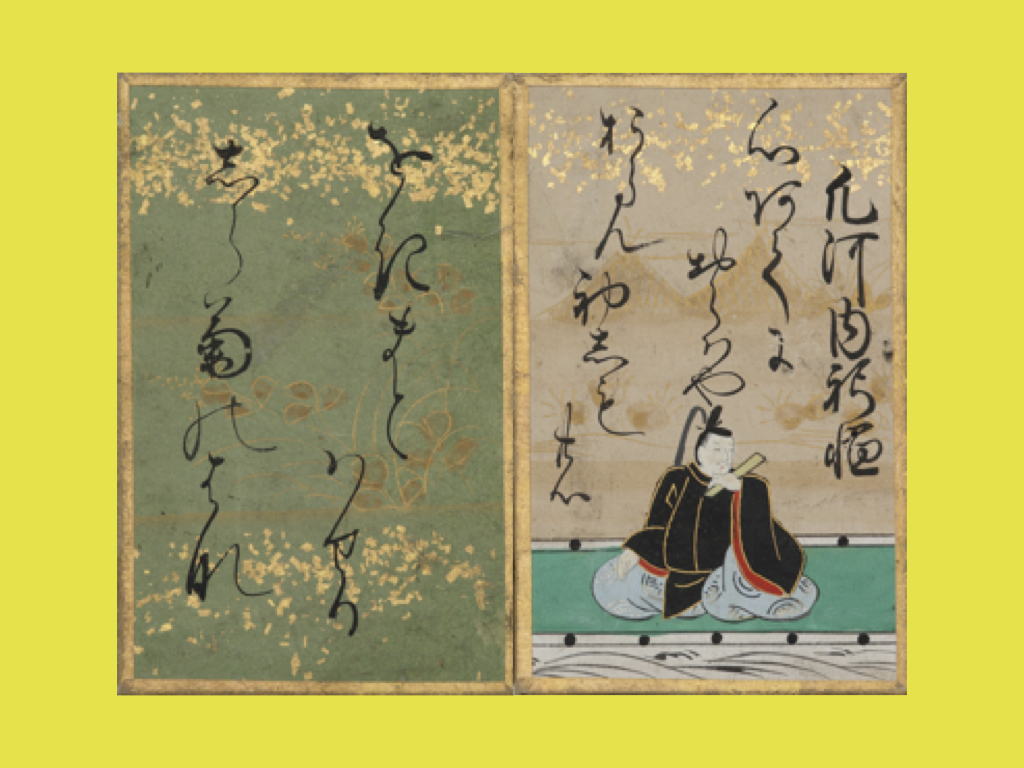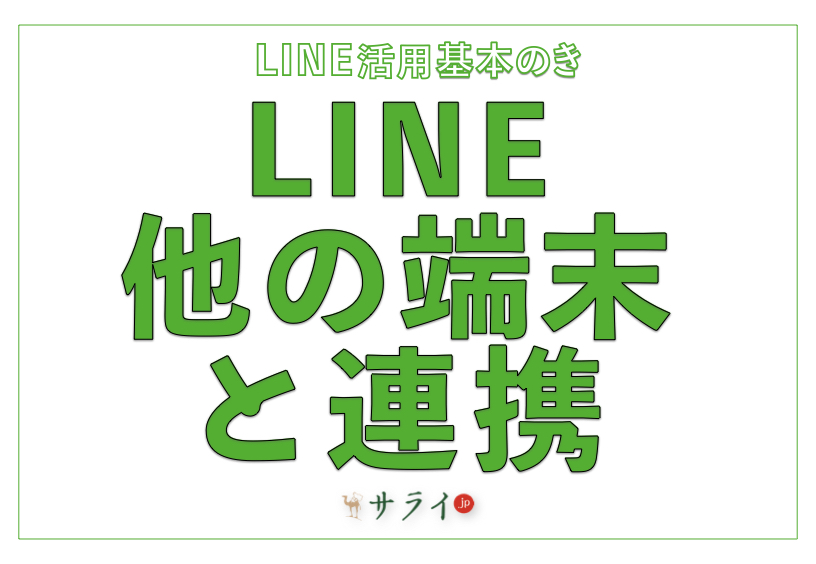はじめに―北条政子とはどんな人物だったのか
北条政子は源頼朝に嫁ぎ、二男二女をもうけ、頼朝の死後は将軍となった息子の後見人として幕府の実権を握りました。後鳥羽上皇が幕府を倒そうと蜂起した際、政子は御家人に幕府の御恩を呼びかけて結集させ、見事勝利へ導いたとされている女性です。
2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では、小池栄子が演じます。
北条政子が生きた時代

北条政子が生きた時代は、まさに武士の社会が始まろうとしている時代でした。幕府の政治は、伊豆から鎌倉入りを果たした源頼朝によって行われ、将軍と御家人が主従関係を結ぶ封建制度が確立します。しかし、頼朝の死後、御家人中心の政治を求める動きが強くなる中で、御家人同士の勢力争いが激しくなっていきました。
北条政子の足跡と主な出来事

政子が「尼将軍」と呼ばれていたことは、ご存じの方も多いかと思います。武士の社会において、女性である政子が「尼将軍」と呼ばれるようになるまでには何があったのでしょうか。彼女の足跡を辿ってみましょう。
北条時政の娘として誕生
政子は、保元二年(1157)に伊豆国田方郡北条(現在の静岡県田方郡韮山町)を拠点とした豪族だったとされる北条時政の長女として生まれました。
源頼朝と結婚
政子の父親である時政は、伊豆の在庁官人だったとされている説があります。その関係から、平治の乱で伊豆に流された源頼朝の監視を命じられていました。政子はそこで源頼朝と出会ったのでしょう。頼朝と結婚することになります。
結婚した時期は定かではありませんが、長女である大姫の年齢などから推測すると、治承元年(1177)ごろであったとされています。
なお、政子は当時当たり前であった一夫多妻制を認めず、頼朝の浮気相手の家を破壊させるほどの嫉妬心の持ち主であったそうです。
二男二女をもうける
頼朝と結婚した政子は二男二女の母に。寿永元年(1182)に頼家を出産し、その10年後の建久三年(1192)に実朝を出産します。
頼朝の急死、尼になる
夫となった頼朝は、治承四年(1180)に挙兵し鎌倉入りを果たします。それに伴って政子も鎌倉へ。しかし、頼朝は正治元年(1199)の暮れに落馬が原因で急死してしまいました。
しかし、この落馬も、事実であるかどうかは定かではありません。というのも、鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』には、建久7年(1196)からの9年間分の記事が丸々欠落してしまっているのです。
頼朝の死の原因が、本当に落馬による事故であったのか、誰かによる企てであったのかは定かではありませんが、この頼朝の死によって政子は尼となりました。
また、初代将軍である頼朝が亡くなったことにより、鎌倉幕府の構図も少しずつ変化していくことになるのです。
長子・頼家が二代将軍となる
頼朝が急死したことで、急遽、頼朝と政子の長子である頼家が二代将軍となります。しかし、『吾妻鏡』によると、まだ21歳であった頼家は年齢的にも人間的にも幼く問題視される部分があったようです。
そこで、有力な御家人たちは、頼家の暴走を抑え、権限を抑制するために「十三人の合議制」を導入することに。2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』は、この「十三人の合議制」に登場する御家人に焦点が当てられています。
次子・実朝が三代将軍となり、後見役として幕政に参画
建仁三年(1203)、頼家が病に倒れると、政子は、関西の38か国の地頭職を実朝に、関東の28か国の地頭職と惣守護職を頼家の長男一幡に分与するという案を立てました。しかし、一幡の外祖父かつ、「十三人の合議制」の一人でもあった比企能員が異を唱えたため、北条時政等が謀殺します。
その後、実朝を三代将軍に擁立して後見人となり、幕府に参画していきます。このタイミングで時政は執権を子の義時に継承したことで、執権は北条氏が世襲していくという構図が出来上がったのです。
「牧氏の変」で父・時政を追放
元久二年(1205)になると、父である時政が、後妻の牧の方(まきのかた)と共に将軍廃立を企てたため、政子は弟の義時と共に実朝を守り、時政を伊豆へ配流したとされています。
実朝が暗殺され「尼将軍」に
建仁三年(1203)に二代将軍頼家が廃されたことで、実朝が征夷大将軍に。実朝は、政子の尽力もあり三代将軍となりましたが、承久元年(1219)、鶴岡八幡宮に参詣していたところを、二代将軍頼家の遺子・公暁によって暗殺されてしまいます。
その結果、頼朝の遠縁にあたる九条家の頼経(よりつね)を後継者として迎え入れることになりますが、頼経は幼かったため、実質的に政子が将軍としての政務を後見することに。このことから、政子は「尼将軍」と呼ばれることになりました。
北条政子の名演説
京都の朝廷では、勢力が拡大する鎌倉幕府に憂慮していました。三代将軍実朝が公暁に暗殺され、後継者問題により朝廷と鎌倉幕府の関係が不安定になったことをきっかけに、朝廷側はかつての勢力を挽回する動きに出ました(承久の乱)。
この時、政子は頼朝の正妻として、御家人たちを前に頼朝の恩義を説いてみせたのです。この演説によって、御家人たちは動揺を収め、結束し、朝廷との戦いに圧倒的勝利を収める結果となりました。
『吾妻鏡』によると当時の演説は下記のようなものであったと言われています。
「皆、心を一つにして承るように。これが最後の言葉である。故右大将軍(源頼朝)が朝敵を征伐し、関東を草創して以後、官位といい、俸禄といい、その恩は既に山よりも高く、海よりも深い。名を惜しむ族(やから)は三代の将軍の遺跡(ゆいせき)を守るように。
今ここで、京方について鎌倉を責めるのか、鎌倉方について京方を責めるのか、ありのままに申し出よ」
義時の子・泰時を執権に
承久の乱後は、当時執権を継いでいた義時を全面的に補佐し、義時が亡くなると義時の子・泰時に執権職を継がせます。同時に義時の弟である時房を連署として泰時の補佐役のポストに置き、執権政治の体制を盤石なものにしました。
そして、嘉禄元年(1225)7月、当時としては長寿の69歳で病気により亡くなります。
まとめ
現在の研究では政子の役割を、武士政権成立の過程において、貴族社会から武士社会への移行を進めた立役者として評価することに重点が置かれているようです。政子と実朝のお墓は、政子が創建した鎌倉の寿福寺にありますので、興味のある方は一度訪れてみてはいかがでしょうか。
文/清水愛華(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com)
アニメーション/貝阿彌俊彦(京都メディアライン)
肖像画/もぱ(京都メディアライン)
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)