
文/原田伊織
「徳川近代」――。何やら聞きなれないフレーズを打ち出した本(『消された徳川近代 明治日本の欺瞞』)が密かに話題を集めている。著者は『明治維新の過ち』を嚆矢とする維新三部作のベストセラーで知られる原田伊織氏。近代は明治からというこれまでの常識に挑んだ書だ。
幕末の日本でいち早く近代化を推進した小栗上野介忠順は、「徳川近代」を象徴する幕臣である。その小栗が維新後、さしたる理由もなく新政府軍に斬首されたことに「維新の実像」が見えて来る。
【前回はこちら】
誰が小栗を殺したのか
小栗はどこまでも主戦派であった。
将軍慶喜が鳥羽伏見の戦場を捨てて、兵たちをも放置したまま江戸へ逃げ帰ってからも、小栗は慶喜に徹底抗戦を主張したが、容れられなかった。小栗の抗戦論は精神論ではなく、具体的な戦術論を伴うもので、その戦術の優位性は後に官軍の大村益次郎が認めている。
その翌日、慶応四年一月十五日、小栗は勘定奉行を罷免された。小栗罷免の後、小栗同様の主戦派水野忠徳も徹底抗戦を唱えるが叶わず、一月十七日、幕府は幕議にて正式に恭順を決定したのである。
幕府が恭順を決めた以上は、もはや仕方がない。幕臣としては従わざるを得ない。一月二十八日、小栗は、知行所である上州権田村土着願を提出、これは翌日受理された。権田村土着のため、小栗一家が江戸を離れたのは、二月二十八日のことである。
婦女子を伴った小栗一行が権田村に着いたのは、三月二日であるが、権田村は既に百姓や博徒たちが混然となった一揆勢に包囲されていた。この時期、上州にも世直し一揆廻状が出回っており、打ち壊しや放火が続発していたのである。
一揆勢が狙うのは、小栗が江戸から持ち運んできたとみられた財宝であった。小栗が、貯め込んだ財宝を持って権田村へ移住してくる……実は小栗は、そのようにみられていたのである。小栗は、武器弾薬を千両箱に詰めて運んでいたのだ。
小栗が大金を持って権田村へ移住してきたという誤解は、この千両箱だけが原因ではない。小栗が来るという風聞が流れただけで、一揆勢の組織化は始まっていたのだ。
小栗は、天下に名の知れた勘定奉行であった。しかも、この重職を四度も務めている。五百万両は貯め込んだに違いない。少なくとも百万両は固いだろう。その大金を持って、権田村に土着するのだ。小栗は、このようにみられていたのである。
小栗の収入は、実にはっきりしている。確かに小栗は、十カ村に別れていたとはいえ二千七百石の知行所をもつ大身旗本である。知行所からの年貢は、多い年で約千両、これに役職による足高などが加わる。小栗家の収入がもっとも多かったのは、渡米直前の安政六(1859)年で、その額は二六九〇両余であった。これについては、小栗直筆の小まめな家計簿が残されているのだ。
この収入で一族郎党を養わなければならないのだが、これを無視してこれに一切手をつけなかったとしても、一体何百年分を貯め込めば百万両という蓄えができるというのか。よほどの不正を働かない限り、一代では無理であるが、小栗は立場を利用して運上を詐取していたと噂されていたのである。
この風聞は奇妙である。大体、小栗を待ち構えていた一揆勢は二千に達するという大規模なものであったが、権田村の百姓は加わっていないのだ。権田村を囲む岩永村、川浦村、水沼村、三ノ倉村の百姓が殆どであった。この四カ村は、小栗の知行所ではない。そして、参加しなければ打ち壊す、焼き払うと脅されて動員された者が多かったようだ。つまり、博徒と考えられるプロが首謀者であったとの推測が成り立つのだ。その首謀者は三ノ倉村に本陣を置いていることまで分かっている。その博徒の後ろには誰がいたのか。運上詐取などという風聞は、上州土着の者だけの間で発生したものとは思えないのだ。
小栗は、事を荒立てることを避けたいと考え、村役人を通した交渉を行うことにした。三月三日、家臣大井磯十郎を立てて、一揆の首脳陣と談判を行ったのである。
ところが、これが決裂した。一揆勢は、表向きは金が狙いであったから、これは決裂するであろう。となると、襲撃は避けられない事態となった。
翌三月四日、一揆勢襲撃。小栗勢は少人数ながらこれを迎え撃った。烏合の衆と戦術によって動く集団との戦闘では人数差が影響するウェイトは小さくなる。更に、小栗は約二十名のフランス式調練を受け、最新鋭の小銃を駆使する歩兵をもっていた。加えて、権田村から百名ほどが動員されていた。
一揆勢の死者十八名。生捕り多数。小栗勢は無傷。これが戦闘の結果である。四カ村の村役人が詫びに来て、案の定、博徒に脅されてという言い訳をしたようだが、小栗は詫び状一札を取って和解に応じた。
この襲撃事件の後、小栗は村内の観音山に住居の建設に取りかかった。小栗は、この地に永住するつもりであったようだ。ところが、この一件は、小栗が要害の地に城館を築造しているという話になって拡散していくことになった。
四月二十二日、東山道総督府は、高崎藩、安中藩、吉井藩に対して小栗捕縛を命じた。要害の地に拠り砦を構え、大小砲を所持し、浪人を召し抱えて官軍に抗する構えであるというのが、その理由である。
高崎藩以下三藩とは、閏四月一日に談判がもたれ、三藩の使節たちは疑いを解き、小栗が恭順していることを総督府に報告している。三藩の使節たちにしても、総督府を名乗る薩摩・長州・土佐の朝廷権威をかさにきた横暴には戦々恐々としている。総督府に対する万全を期して、大砲を預けること、嗣子又一を同道させることを求めたので、小栗はこれを了承したのである。
閏四月三日、総督府は、長州・原保太郎と土佐・豊永貫一郎を監察使として高崎に派遣、二人は小栗の罪状明白として即刻誅滅すべしという総督府命令を突き付け、三藩がやらないのなら東山道軍本隊が出兵すると脅したのである。
これは、この時期よくみられたパターンである。やらなければ自分たちがやられる……多くの藩がこの恐怖で薩長に従っている。そして、これも多くの事例があるが、薩長や土佐の者の若さやレベルの低さが問題であった。原はこの時、二十二歳、まだガキである。土佐の豊永に至っては十六歳、まだ洟垂れ小僧であった。それが官軍である、朝命であると言っていれば、大名までもが平伏するのだ。この時期の彼らは完全に我を失って、舞い上がっていたのである。これは、決してこの二人だけの話ではないのだ。そもそも、薩摩、長州、そこへ土佐を加えたとしても、どれほどの人材がいたというのか。
特に、土佐という国はもともと文化レベルが低かった。それが先進地域へ押しかけて、傍若無人に振舞うだけならともかく無理難題を押し付ける。文化度の高い隣国の伊予松山藩の民は、いい迷惑であったろう。
長岡戦争を前にした小千谷会談において、あの長岡藩河井継之助と談判したのは土佐の岩村精一郎であるが、これがまだ二十四歳という若輩で、何のキャリアもなく、ただ土佐人であるという理由だけで突如軍監に起用されたのだ。もし、河井の相手が岩村でなければ、長岡戦争は或いは回避されていたかも知れない。それほど官軍という小さな組織には人材が欠乏していたのである。この時の、原、豊永は、岩村のケースより更に酷いと言っていいだろう。
小栗斬首
閏四月六日、小栗は三ノ倉村烏川河原に引き出され、家臣三名と共に有無を言わさず斬首された。高崎藩で牢に繋がれていた又一も、翌七日、惨めにも牢の前で斬首された。
小栗斬首のこの経緯をみると、はっきりしていることは、東山道総督府は端から小栗を殺す心算であったということだ。何が何でも生かしておいてはならぬという方針があったように感じられる。
それは、東山道軍だけで意思決定できることなのか。対象は、あの小栗である。答えは否であろう。
では、どこで決定されたのか。まだ確かな裏付けは取れないが、私は、西郷吉之助の意向が働いてはいなかったかと疑っている。東海道を受け持った西郷が、東山道軍にも“指示”するというケースは、他に幾つも存在する。西郷にとって小栗は巨大であった。長州征伐にも、自分の謀略とはいえ、三田の薩摩藩邸焼打ちにしても、背後に小栗がいる。これが西郷の確信であり、これは筋違いとも言えないのだ。
粘着質の西郷は、一度怨んだら、とことん怨みをもち続ける。そして、常に独断先行する武断派である。西郷なら、一存で小栗抹殺を命令しても、全く不自然ではなく、不可能でもないのだ。取り調べの恰好をつけるといった、最低限の体裁さえも、西郷という仮定を設けると不要となることに違和感はなくなるのだ。
更に、無視できない説がある。
小栗を襲撃した一揆勢の中に、赤報隊崩れが混じっていたというのだ。小栗は、関八州の不逞の輩に対しては厳しい対応をしてきて、上州博徒からも恨まれていたろう。しかし、西郷が放ったテロ集団赤報隊崩れが周辺にいたとなると、単なる荒くれ者たちが、という話ではなくなってくる。赤報隊の不逞の輩とは、雑多な種類の者の寄せ集めであり、隊長相楽総三に対するロイヤリティとは無縁の者も多かったのである。
そのことを思うと、奇妙な一致に気づく。
小栗主従の斬首を実行したのは、先の原保太郎と豊永貫一郎、そして、元彦根藩士大音龍太郎である。いずれも、岩倉具視の用心棒のような連中である。そして、この三人こそ上州へ入る前に、諏訪で相楽と相楽率いる赤報隊一番隊の首を斬ってきた者たちであった。
小栗という名前は、討幕軍にとっては主戦派の代名詞であった。しかし、論理的に言えば、勘定奉行を罷免された時点で幕府の採った対応や施策に対する彼の責任は消滅しているのだ。徹底抗戦の主張も評定の上でのことであり、ひとたび幕議が恭順と決し、それに従う限りは咎めを受ける筋合いはない。感情的に咎められる立場に陥ったとしても、問答無用でいきなり斬首ということは、残虐なテロを展開してきた討幕勢力の間でも他に例のないことであった。
理屈を言っても詮ないことである。
いずれにしても、原や豊永のような者たちは勿論、これを使っていた西郷や討幕軍の幹部たちにとって、小栗という人物は、政治的にも軍事的にも存在するだけで怖かったのであろう。

なお、小栗の身重の妻や母を始めとする家族は、生き残った郎党や権田村中島三左衛門らに守られ、裏街道を会津へ逃れた。
六月十日、薩長軍とこれに従う諸藩の大軍が会津攻めに向かう中、会津城下で長女クニという新しい命が誕生したのである。
小栗の妻道子を無事に会津まで守り届けたのは、中島三左衛門を始めとする約三十名の村人であったが、その一部は戦禍の会津で冬を過ごし、翌春、母子を江戸から静岡、そして、再び江戸へと守り届け、母子が無事に過ごせることを確認してから村へ戻った。村へ帰り着いたその姿は、乞食同然であったという。
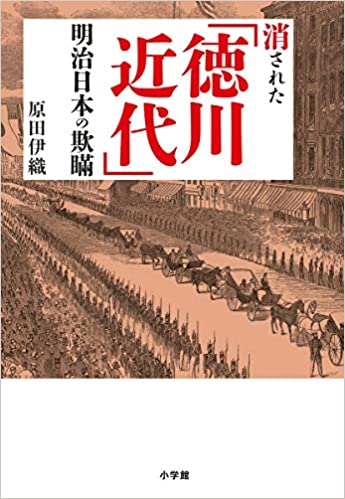
原田伊織/著 小学館刊




































