
文/原田伊織
「徳川近代」――。何やら聞きなれないフレーズを打ち出した本(『消された徳川近代 明治日本の欺瞞』)が密かに話題を集めている。著者は『明治維新の過ち』を嚆矢とする維新三部作のベストセラーで知られる原田伊織氏。近代は明治からというこれまでの常識に挑んだ書だ。
幕末の日本でいち早く近代化を推進した小栗上野介忠順は、「徳川近代」を象徴する幕臣である。その小栗が維新後、さしたる理由もなく新政府軍に斬首されたことに「維新の実像」が見えて来る。
【前回はこちら】
旗本が近代軍隊に生まれ変わらなければ、幕府の明日はない
小栗を評価する専門家は少なくないが、その殆どが、小栗の経済面、財政面の知見を高く評価している。それは決して間違った見方ではないが、小栗の真の凄さは軍事が解ることである。端的に表現すれば、文治と武断のバランスに秀でた人物であったということだ。
例えば、最後の将軍徳川慶喜と比較してみれば分かり易いだろう。
慶喜は、典型的な文治派である。平時においては理論家で、よく通る美声で弁も立つ。自らイギリスの議会制を志向する姿勢をみせるところなどは、いかにも慶喜らしい。もっとも議会制については、徳川主導の諸大名会議をどう成立させるかという観点から関心を示したものと思われ、今日的な議会創設の構想をもっていたと評価するのは、これもまたとんでもない麗しい誤解であろう。
慶喜という平時の“秀才”は、ひとたび事が起こると豹変する。何らかの精神障害の疑いさえ否定できないほど、豹変して、錯乱、狂乱するのである。先にも触れたが、森田健司氏は、双極性障害の可能性を指摘している(『明治維新 司馬史観という過ち』悟空出版)。私も、この指摘を否定することはできない。
思えば、岩瀬忠震も水野忠徳も川路聖謨も、果ては松平春嶽に至るまでが、この慶喜という平時のみの秀才に対して麗しい誤解をしていたといえるだろう。
ところが、小栗にはそれがなかった。彼は、かなり早い段階で(一橋)慶喜という人物の本性を見切っていたと思われるところがあるのだ。
前述したが、文久の兵制改革においても、小栗は主導的な役割を担っている。
文久二(1862)年六月五日、小栗は勘定奉行に初めて就任したが、九月には「破約攘夷」という無茶な論がもち上がってこれに反対して辞任した。ところが、「兵賦令」が発令された十二月に、新設された歩兵奉行と勘定奉行の兼帯を命じられたのである。
小栗は、旗本として知行所支配に精通しているし、幕府財政にも通じている。軍事政権が近代軍隊を保持しようとする時、やはりこの男を使うしか手はなかったのである。
しかし、旗本を否定してでも鉄砲主体の集団戦を想定した銃隊編成への転換を狙ったこの改革は、なかなか進まなかった。旗本知行地からの兵士の徴発が順調には進まなかったのである。
旗本が近代軍隊に生まれ変わらなければ、幕府の明日はない。小栗のこの危機感を、旗本連中は理解できなかったのである。幕府も業を煮やし、元治元(1864)年四月、「督責令」を発令して「兵賦」の義務を果たすよう催促し、どうしても兵士を出せない事情がある場合は「兵賦金」を上納するよう命じている。
オランダ式の三兵訓練そのものに限界を感じた小栗は、きちんとした指導者を招いて本格的な訓練をしないと日本陸軍の見込みが立たないとし、栗本鋤雲、フランス公使ロッシュを通じてフランス政府と交渉、慶応二(1866)年八月、軍事顧問団の招聘契約を締結した。これに基づき、慶応三年一月、シャノアーヌ大尉以下十五名の軍事顧問団が来日、即、教練が始まったのである。幕府は、遂に旗本御家人の武力に見切りをつけたわけで、直参の軍役はすべ
て金納となった。
来日したフランス人士官の中に、ブリューネ砲兵大尉がいた。土方歳三、大鳥圭介らと共に箱館へ渡って新政府軍と戦った男である。ブリューネたちの指導を受けた伝習兵たちの壮絶な、時に珍妙な戦いの日々については、次章に譲りたい。
小栗は、第二次長州征伐の苦戦に直面し、この時期フランスから大量の軍需品を買い付けている。その中に、シャスポー銃が含まれていた。
フランス士官の教練を受けた兵を、伝習兵、その部隊は伝習隊などと言われて、この時期のことを叙述する歴史書などには頻繁に登場するが、伝習隊といえばシャスポー銃と言われるほど、この最新式の後装銃は伝習隊と共にやや伝説化したところもある。これについても次章で詳述したい。
軍事以外の小栗の注目すべき施策を、更に一つ、二つみておこう。
日本最初の株式会社「兵庫商社」を設立
慶応三(1867)年四月、小栗は兵庫開港を見通して、日本最初の株式会社「兵庫商社」の設立を提議している。
小栗は、「薄元手」(小資本)の日本商人がバラバラに「厚元手」(大資本)の外国商社組合の商人と競争する不利を説き、商社(コンパニー)のやり方が必要だとした。具体的には、大坂の商人二十人ほどに出資させ、商人組合を設立し、役員を選任して定款を定め、一株いくらで希望者の加入を促し、この組合を通して貿易をするというものである。
そして、注目すべき点は、コンパニーの利益でガス灯の設置、郵便・電信制度の開始、鉄道敷設を実現しようとしていたことである。日本の郵便制度は前島密の発議によるもの、などという単純な官軍正史は一度忘れた方がいい。社会基盤の整備も含めた小栗構想には、書信館(ポストオフィシー)構想が明確に描かれていたのだ。
小栗の「兵庫商社」設立案を受け入れた幕府は、慶応三(1867)年六月五日、鴻池屋、加島屋など大坂の豪商二十名を京都に集めて、商社結成を要請した。彼らはこれを受け、頭取、肝煎、世話役といった役員を決め、大坂・中之島に事務所を開設して活動を始めたのである。
ところが、活動開始から半年を経ずして「大政奉還」、そして、「鳥羽伏見の戦い」……本格稼働の前に活動を休止せざるを得なくなったのである。
株式会社といえば、小栗は、やはり株式会社という手法で日本初の本格的な洋風ホテルの建設・営業を推進した。築地ホテルである。小栗は、訪米した時滞在した、ホワイトハウスの近くに立地するウイラードホテルをイメージしていたのであろう。

小栗の構想では、民間資本を集めて組合をつくり、一株何両かで出資金を集めて建設し、その後の運営で出た利益を株主に配当するというもので、まさに株式会社の概念を導入したものであった。清水屋(今の清水建設)二代目・清水喜助、工事を請け負った平野弥十郎らがこれに応じたが、一株百両の出資に対して配当が年百両というのは、如何にも気前が良過ぎた感がある。
アメリカ人プリジェンスの設計によるこのホテルは、講武所のあった勝鬨橋右袂辺りの敷地七千坪に二階建てで建設され、水洗トイレ、シャワー付き客室は百二室、バー、ビリヤード室も備えるという本格的なもので、一時外国人からは「エドホテル」と呼ばれて人気があった。しかし、明治三年に身売りされ、明治五年、「銀座大火」で焼失
してしまった。
その他、小栗の構想は軍事、民生を問わず多岐に渡っているが、それらを概観しただけでも、彼が既に徳川という政権の枠を超越し、日本国という国家を基準にして発想・企画していたことが分かるのだ。明治になって後、新政権の重鎮大隈重信が、「我々が今やっていることは小栗の模倣に過ぎない」と正直に語ったことが、そのことを明白に物語っている。
私が、テロリズムが成立させた明治維新を民族の過ちと解釈し、江戸がそのまま近代へ移行していたら日本が天皇原理主義に支配された国粋主義軍国国家になることはなかった、即ち、大東亜戦争(太平洋戦争)に突き進むことはなかったと主張すると、多くの人がまだ嘲笑する。しかし、小栗は、将軍を大統領とし、郡県制を敷いて、徳川による近代国家構想を描いていた。その幕政改革とは、この方向を目指した近代化施策に他ならず、その詳細をみればみるほど、徳川政権が少なくとも欧米列強と同じ政体を採るに至ったであろうことを確信するのだ。
つまり、「徳川近代」があと十年続いていれば、日本に国粋主義軍国国家は生まれなかったはずである。
次回につづく。
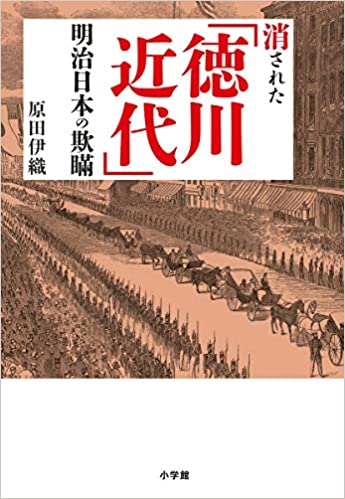
原田伊織/著 小学館刊




































