
文/原田伊織
「徳川近代」――。何やら聞きなれないフレーズを打ち出した本(『消された徳川近代 明治日本の欺瞞』)が密かに話題を集めている。著者は『明治維新の過ち』を嚆矢とする維新三部作のベストセラーで知られる原田伊織氏。近代は明治からというこれまでの常識に挑んだ書だ。
幕末の日本でいち早く近代化を推進した小栗上野介忠順は、「徳川近代」を象徴する幕臣である。その小栗が維新後、さしたる理由もなく新政府軍に斬首されたことに「維新の実像」が見えて来る。
【前回はこちら】
幕末の動乱期を最も支えた幕臣
直参旗本とは、将軍直属の最精鋭直轄部隊のはずである。ところが、徳川政権は徹底した平和主義を統治の基本理念とした。軍事政権として軍事組織を生かしながら、文治政治に徹した統治を行ったのである。その結果、武人であるはずの直参は、文人としての素養も必要とされるようになり、官僚化していった。
およそこの政権ほど「武」の行使を忌み嫌い、固く禁止した政権は、我が国の歴史に例をみないであろう。テレビドラマや映画では、サムライは何かにつけて直ぐ刀を抜いて斬り合っているが、こういうことはあり得なかった。個人のレベルに至るまで「武」の行使には厳しい制約が付けられており、帯刀を許されていた武家といえどもこの制約を無視して抜刀するとなると、それはもう切腹覚悟の行為であったのだ。
徳川政権は、こういう平和至上主義の社会を創っておきながら、統治のための組織は簡素な軍事組織のまま、殆ど手を加えていなかった。こういう背景もあって、五二〇〇人の旗本に用意されていた役職は百八十余しかなかったのである。
小栗忠順は、一般の旗本と違って実に多くの役職に就いている。彼が経験した役職は、書院番、目付、外国奉行、小姓組番頭、勘定奉行、南町奉行、歩兵奉行、講武所御用取扱、陸軍奉行並、軍艦奉行、海軍奉行並等々、実に多岐に渡り、こういう例は他にはないであろう。要するに彼は、任命と罷免を繰り返したのである。エリート中のエリートといってもいい勘定奉行には、何と四度も任命されているのだ。
幕臣の世界では、一度罷免されたら同じ役職は当然、同程度の役職へ復帰することは極めて難しい。小栗の例は、異例中の異例なのだ。
小栗という男は、先に述べた岩瀬忠震と同じように、幕閣に対しても実にズケズケとものを言い、信ずるところは譲らない人物であった。世辞も言わず、忖度も全くしないが、業務能力は誰よりも優れているこういう男は、凡庸な幕閣には使い難い。何とか理由をつけては罷免する。しかし、幕府は、財政面でも、薩長が足を引っ張る外交面においても難題山積、危機的な状況にある。忌々しいが、やはり小栗を使うしかない。
こうやって小栗は、解任されたかと思えばまた登用され、ということを繰り返すことになった。徳川近代という時代は、外交という新しい政治ジャンルのウェイトが増し、近代工業化が社会の変革を求め、このことが軍事組織の近代化を促すなど、単なる固陋な保守感覚では対応できない時代になっていたのだ。阿部正弘政権、堀田正睦政権が生んだ急進的な改革派テクノクラートたちは、旧来の幕閣では使いこなせなかったということである。とはいえ、老中たちは彼らの力を必要としたのだ。
幕閣は、特に小栗の力を必要とした。
小栗が幕政に顕著な存在感を示すようになるのは、万延年間以降のことである。万延とは、江戸城の火災や「桜田門外の変」という水戸・薩摩藩士による凶悪テロを受けて、安政七年(1860)三月十八日に改元された元号で、万延年間とは正味一年に満たず、万延二年の二月には文久と改元された。
つまり小栗は、幕末の動乱がもっとも激しく燃え盛った時期に幕府を支えた幕臣であった。
万延遣米使節団
動乱の時代へ登場せざるを得なかったきっかけとなったのが、日米修好通商条約の批准のために太平洋を渡って訪米したことである。
この批准書交換を目的とした使節団は、「万延遣米使節団」と呼ばれているが、日本を出発したのは安政七年一月十八日、帰国したのは九月二十八日であった。これが、史上初めて公式にアメリカを訪問した使節団であった。
正使は新見豊前守正興、副使は村垣淡路守範正、小栗豊後守忠順は「目付」として加わった。随行する官吏、従者、小者たちを含めると、総勢七十七人という大使節団であった。蛇足ながら、この時点の小栗はまだ「豊後守」である。

この使節団については、正使・副使について「見てくれだけのボンクラ」というような評が、多くの歴史書で語られ、今やこの人物評は定着している。司馬遼太郎氏も、正使、副使を「封建的ボンクラ」と決めつけているが(『「明治」という国家』日本放送出版協会)、二人は決して単なる「飾り物」ではなかった。
そもそもこういう使節にとって、「見てくれ」は大事な要素である。正使新見は、美男で品格があり、堂々とした立ち居振る舞いをする男で、正使としての風采を備えた人物であった。決して経済・財政に明るいなどという才覚はなかったが、批准書交換というような儀礼的要素を含んだ外交団の正使としては適任であろう。彼は、大統領ブキャナンに謁見、国務長官ルイス・カスと批准書交換を行っているが、堂々とした態度でその任を果たしている。
新見はこの時、外国奉行と神奈川奉行を兼任、帰国後は外国奉行専任となった。つまり、その立場・役職からして正使を務めておかしくない人物であったのだ。
彼は、とにかく美男子であったので、後世の歴史家までもが「見てくれ」だけの男と言い過ぎるきらいがある。確かに、新見が小姓務めの頃から大奥の女たちがうるさかったことは事実である。また、そのイケメンぶりから「陰間侍」というあだ名があったこともまた事実である。
余談ながら、新見の三人の娘たちがまた美貌で評判であった。特に、次女ゑつと三女りょうは養女に出されてから柳橋に売られたが、二人は柳橋きっての艶やかな芸者として有名になっている。伊藤博文と公家出身の柳原前光が、三女りょうの奪い合いを繰り広げたことは有名な話で、りょうは柳原を選んでその妾となり女児を産み、これが後の柳原白蓮である。一方、えつは吉原を仕切る飯島三之助の妾となり、昭和十九年まで生き永らえた。
新見本人は、維新の世替わりに際して「帰農」したが、明治二年、四十八歳の若さで他界している。大正九年、アメリカ駐日大使R・モリスが帰任に際して、新見の墓に詣でているが、維新から六十年経ってもアメリカ側にとっては正使新見は記憶に残る人物であったのであろう。
副使の村垣も新見とセットにして無能扱いされることが多いが、それは新見の場合以上に乱暴と言うべきであろう。村垣は、一貫して海防・外交畑を歩いている。ロシアのプチャーチンとの日露交渉においては、川路聖謨、筒井政憲らの交渉団(応接掛)に加わっている。岩瀬忠震の従兄弟に当たる堀利熙と共に、蝦夷地の調査・開拓に尽力し、安政三(1856)年、堀の後を受けて箱館奉行に昇進、安政五(1858)年には「安政の大獄」で罷免された岩瀬に代わって外国奉行に就き、神奈川奉行も兼任した。また、帰国後には日普修好通商条約締結に際し、全権大使として調印している。
決して「切れ者」ではなく、国政に関して高い見識をもっていたとは観察できないが、ひと言でいえば文才のある能吏というところであろう。渡米の際の随伴艦・咸臨丸を指揮した木村摂津守も「機敏にして吏務に練達〜」と評している。しかし、福地桜痴は「俗吏」と言い切り、全く評価していない。この評価の差は、当事者仲間とメディアの差と言えようが、木村と福地の人柄の違いも反映されていると思われ、その分均ならして理解する必要があるだろう。
ここへ「目付」として小栗が抜擢された。この使節団を送り出した大老井伊直弼は、小栗に大量の金貨(小判)流出(濫出)に対する対処を指示したと言われている。
使節団は、米艦ポーハタン号(タットナル提督・ビールソン艦長)で太平洋を渡ることになったが、この時、随伴艦として従ったのが、咸臨丸である。
官軍正史は、咸臨丸物語は一生懸命語るが、正使一行を乗せたポーハタン号のことには殆ど触れない。渡米の目的からすれば話は逆なのだ。万延遣米使節団とは、正使たちと正使一行を乗せたポーハタン号が主役であって、咸臨丸という艦はどこまでも“ついで”に過ぎない。益して、“ついで”の咸臨丸でもお荷物でしかなかった勝麟太郎が、太平洋横断という別テーマで主役になるお話というのは奇妙としか言い様がないのである。
さて、小栗が目付を務める正使一行は、以下のような行程で批准書交換という任務を全うし、帰路は喜望峰回りの航路を採り、世界を一周するような航程で帰国したのである。
・安政七(1860)年一月十八日 築地を出発、川崎沖に停泊するポーハタン号に乗り込みアメリカへ向かう。
・二月十三日 ハワイ諸島オアフ島ホノルル港に寄港
・二月十八日 カメハメハ四世に謁見
・三月九日 サンフランシスコ入港
・三月十八日 パナマへ向けサンフランシスコ出港
・万延元(1860)年閏三月六日 ポーハタン号に別れを告げ、パナマ港上陸、パナマ鉄道に乗車
・同日大西洋側アスペンウオール着、米艦ロアノウク号に乗船、三月七日出港
・行先変更で河船フィラデルフィア号に乗り換え、閏三月二十四日、ワシントン着
・閏三月二十七日 ホワイトハウス訪問、第十五代大統領ジェームズ・ブキャナンに国書奉呈
・四月五日 ワシントン海軍造船所訪問
・四月十九日 ワシントンを汽車で出発、ボルチモア経由フィラデルフィアへ
・四月二十八日 フィラデルフィア出発ニューヨークへ
・五月十三日 アメリカ海軍最新鋭艦ナイアガラ号でニューヨークを出発
・大西洋からアンゴラ、インド洋、バタビア、香港を経由して、万延元年九月二十八日帰国
この正使一行の旅については、多くの関係者が豊富な記録を残しているが、不思議なことに小栗の手による記録が何もないのだ。こまめな小栗が、我が国初の公式使節としてアメリカを訪問して、それについて何も記録を残さないということは考えられない。これについては、官軍が小栗を殺害した直後、小栗邸の掠奪破壊が発生しており、その際奪われたものと推測されている。
このことについて、小栗は無口な実行家で文章を残さなかったとか、沈黙が彼の人格表現であるなどという人がいるが、これは全くの見立て違いである。彼は、家計簿のような記録まで残している。
このアメリカ訪問で、使節団一行は異例の歓迎を受けた。そして、温かい好意と高い評価に包まれたのである。中でも小栗は、アメリカ合衆国にとって非常に手ごわい交渉相手として一目置かれると共に、その知性、品格を絶賛されたのである。
次回につづく。
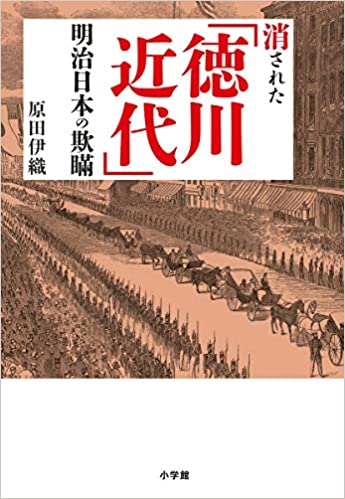
原田伊織/著 小学館刊



































