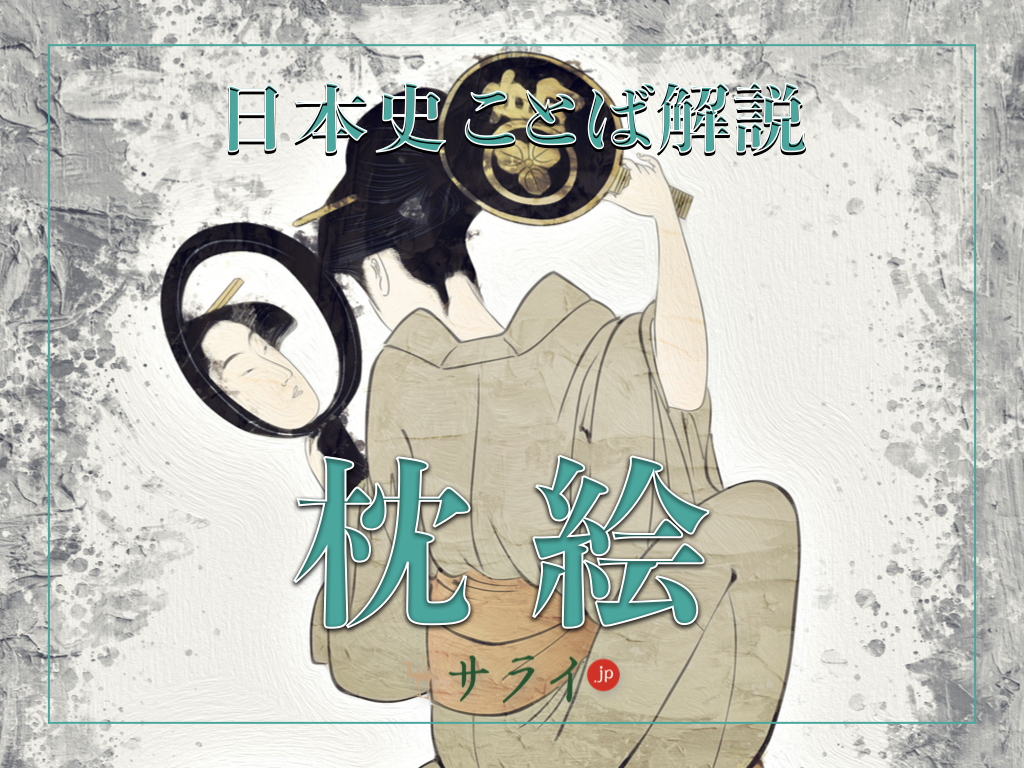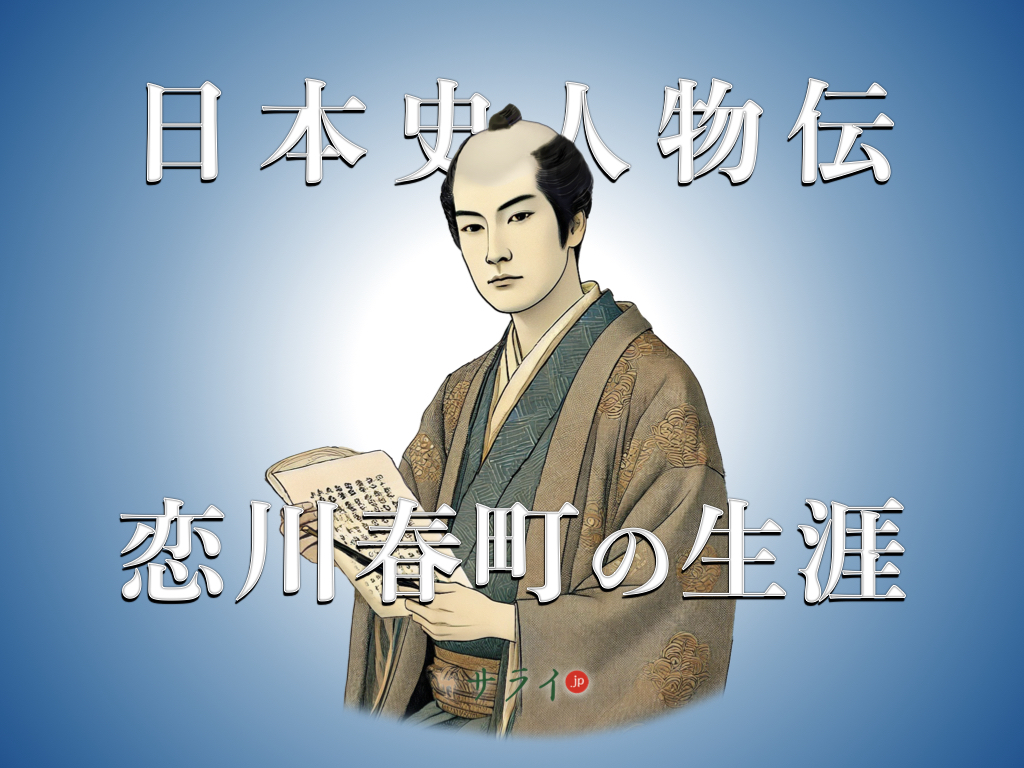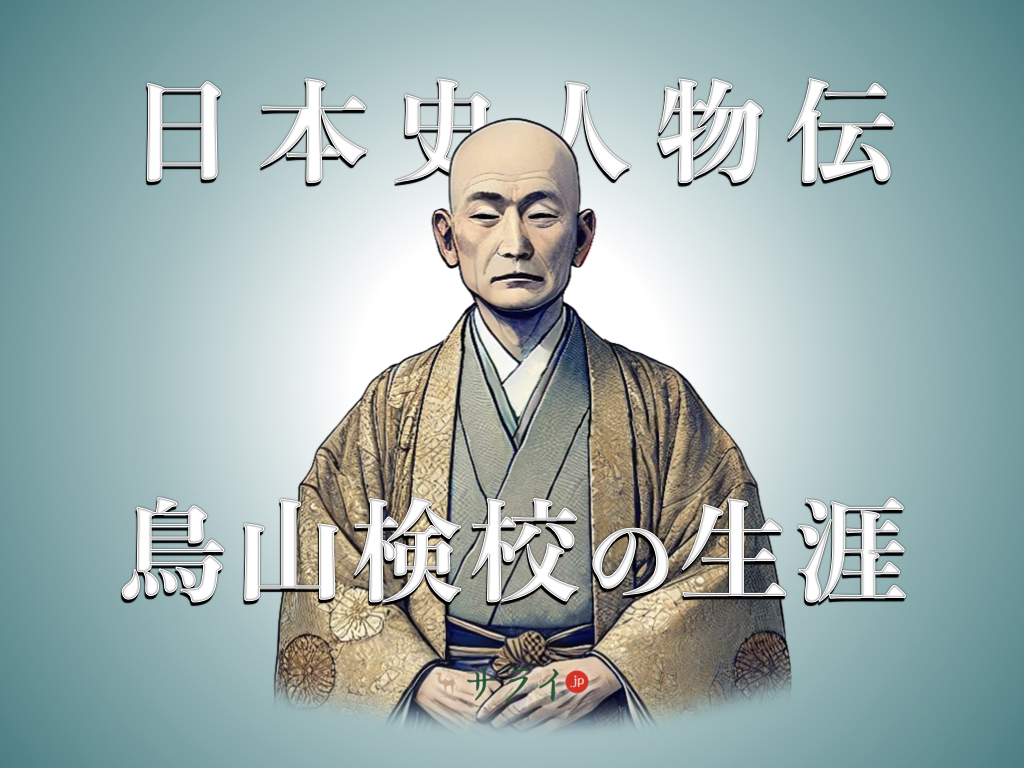大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。
しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?
【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、“大河ドラマ”や“時代劇”に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。
さて、今回は「お救い米」という言葉をご紹介します。現代でいえば「緊急食料支援」のようなものですが、江戸時代では災害や飢饉が起こるたびに幕府や各藩がこの「お救い米」を支給し、多くの命をつなぎました。
この記事では、その仕組みと意義、そしてどのような効果があったのかを見ていきましょう。

目次
「お救い米」とは?
「お救い米」の意義
「お救い米」が支給された結果
まとめ
「お救い米」とは?
「お救い米」とは、飢饉や火災、水害などの災害時に、生活が困窮した庶民に幕府や各地の藩が支給した救済用の米のことです。人々は感謝と敬意を込めて「御救米(おすくいまい)」と呼びました。
また、幕府や藩による公的支給と区別するため、町人や商人などによる民間の救援米は「合力米(こうりょくまい、もしくは、ごうりょくまい)」や「施行米(せぎょうまい)」と呼ばれることもありました。
もともとは非常時限定の支給でしたが、江戸中期以降、貧困層の固定化が進むと、災害時だけでなく日常的な救済措置として「お救い米」が施されるようになります。特に寛政4年(1792)に設立された江戸町会所では、火災などの被災者、日々の暮らしに困る町人にも支給が行われるようになりました。
「お救い米」の意義
「お救い米」は、単なる食糧支給にとどまらず、庶民の生命線であり、社会秩序を守る安全弁でもありました。
江戸時代は貨幣経済が発達していたとはいえ、米は依然として庶民の主食であり、生活の基本でした。災害や飢饉の際、米が手に入らないというのはすなわち「生きる手段がない」ということ。
そこで幕府や藩が御救米を与えることは、民の飢えをしのがせ、暴動や治安悪化を未然に防ぐ意味合いも強く持っていました。また、米を直接与えることで支援が目に見える形で伝わり、政治的な安定や信頼の構築にもつながったと考えられます。
各地の藩では、事前に救荒米を備蓄する制度を整える動きもありました。例えば、津藩では毎年5千俵(のち1万俵)を備蓄する「御囲穀(おかこいこく)」制度を設け、いざというときに備えていたのです。

「お救い米」が支給された結果
お救い米の支給は、飢餓の拡大防止や人命救助に大きく寄与しました。江戸後期には支給基準もほぼ統一され、以下のような配分が一般的となります。
・成人男性(15〜59歳):1日あたり5合
・女性・子ども(15歳以下)、高齢者(60歳以上):1日あたり3合
・支給期間:およそ10日間
また、天明3年(1783)の飢饉時には、米沢藩が男子3合、女子2合5勺を日々支給。鳥取藩でも1人あたり6勺の米を村々に分配し、飢えをしのぎました。
江戸町会所が行った調査によれば、町人全体の6割以上がお救い米の支給対象だったという記録もあり、広範な層が制度に依存していたことがわかります。
まとめ
「お救い米」は、単なる「施し」ではありませんでした。それは、江戸の町に生きる人々が互いに助け合い、支え合い、社会を持続させるための仕組みだったのです。
『べらぼう』の背景にある江戸の活気や賑わいも、こうした庶民の暮らしと、それを守ろうとする制度の上に成り立っていました。
時代劇をより深く楽しむためにも、「お救い米」という言葉の背後にある人間ドラマや制度の工夫に、少しだけ目を向けてみてはいかがでしょうか。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本国語大辞典』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)