文/原田伊織

「徳川近代」――。何やら聞きなれないフレーズを打ち出した本(『消された徳川近代 明治日本の欺瞞』)が密かに話題を集めている。著者は『明治維新の過ち』を嚆矢(こうし)とする維新三部作のベストセラーで知られる原田伊織氏。近代は明治からというこれまでの常識に挑んだ書だ。
幕末の日本でいち早く近代化を推進した小栗上野介忠順は、「徳川近代」を象徴する幕臣である。その小栗が維新後、さしたる理由もなく新政府軍に斬首されたことに「維新の実像」が見えて来る。
岩瀬忠震から小栗忠順へ
日米修好通商条約調印が早まったのは、一種の“外圧”によるものであった。
井伊大老の登場によって、一橋派対南紀派の対立が最終局面を迎えようとする中、岩瀬忠震たち開明派官僚グループは公然と井伊を批判し、松平春嶽が例によって体裁をつけてしゃしゃり出るなど、通商条約の調印が一瞬影が薄くなるほど幕政は混迷を深めようとしていた。岩瀬たち海防掛グループが、それぞれに上司を突き上げていたことも大きな原因であるが、要はそれを抑えられる「政治家」がいなかったということであろう。
そういう中、安政五(1858)年六月十四日、ハリスが重要な情報をもたらした。英仏連合艦隊が日本に向かったという香港情報である。
その頃の清国(中国)はどういう状況にあったか。
英仏連合艦隊が日本に迫る! 日米修好通商条約を締結すべし
安政三(1856)年、アロー号事件が勃発、これをきっかけにしてイギリスは清国侵略を更に推し進め、天津条約、北京条約を清国に押しつけた。アロー号事件をきっかけにして起こったこのイギリス、フランス連合軍と清国の衝突は「アロー戦争」(1856〜1860)と呼ばれるが、アヘン戦争に引き続いて発生した露骨な支那侵略戦争であるところから「第二次アヘン戦争」と呼ばれることもある。
きっかけとなったアロー号事件そのものが、後に日本に赴任してくる当時のイギリス広州領事ハリー・パークスによる、いってみれば「でっち上げ」であり、議会を解散してまで本国軍を派遣したイギリス首相パーマストンと共に、それぞれの「恥ずべきキャリア」として刻んでおくべきであろう。
また、この時イギリスの誘いに乗ったフランスは、恥も外聞もなく、何の思慮もなく単純で露骨な侵略戦争に加わっている。
この英仏侵略軍が支那侵略の勢いに乗じて日本へも連合艦隊を派遣して、条約を押しつけるという噂が香港辺りで盛んに語られ、この情報が日本へ伝わってきたのである。
この噂話を下田のハリスに伝えたのは、アメリカ軍艦ミシシッピー号で、同艦は六月十三日に下田に来航している。十五日には同じく米艦ポーハタン号も下田に入り、同じ情報を伝えた。更に、翌十六日にはロシアのプチャーチンも下田に来航、同様の情報をもたらしたのである。
ハリスの行動は速かった。十四日にはこの情報を老中首座堀田正睦に伝えている。そして、十七日にはポーハタン号で神奈川小柴へ出てきた。恐らくハリスは、条約調印のチャンスと読んだのであろう。米艦が来航したということは、ハリスにとって最後のチャンスでもあった。
幕府も迅速に対応した。十八日には岩瀬、井上清直に神奈川出張を命じている。二人は、同日夜、ポーハタン号船上でハリスと会談、英仏との間で紛争が生じた時はハリスが調停の労をとるという“保証書面”をハリスに出させて、即江戸へ取って返した。
非常に慌ただしい動きであるが、十九日未明、江戸城にて老中、若年寄だけでなく三奉行、海防掛までを召集した会議がもたれた。ここで、岩瀬が最後の熱弁をふるったのである。その主旨は以下の通りである。
・英仏連合軍は天津条約を結んだ
・天津に集結している英仏艦隊は四十数隻
・この艦隊がまもなく我が国に押し寄せ、通商条約締結を強要すると専らの噂である
・我が国が外国との条約をもたぬまま交渉に応じるのは不利
・先に日米条約を締結しておけば、英仏に同じ内容を押しつけることができる
・英仏との間で紛争が生じた時は、ハリスが調停に立つことを約している
・一刻も早い日米条約の締結が国家のためである
全体会議の大勢は「調印やむなし」であったが、大老井伊直弼が「天朝へのお伺い」をもち出し、会議での結論は出なかったようだ。
閉会後、井伊は岩瀬と井上を呼び、勅許を得るまでできるだけ調印を引き延ばすよう指示した。
この時井上が、できるだけ引延しに努力するが、「是非に及ばぬ時」は調印しても構わないかと確認する。これに対して井伊は、その時はやむを得ないが、できるだけ引き延ばせと答えた。つまり、井上は「その時はやむを得ない」という大老井伊の言質を取ったのである。
岩瀬は、やむを得ない時はなどという料簡ではうまくいかないから、何としても引き延ばすという覚悟で応接に臨む所存、などと体裁をつけてこの場を閉めてしまうのである。
これは非常に重要な瞬間であるが、恐らく岩瀬、井上の連携プレーであろう。二人とも引き延ばす「覚悟」など全くなかったのである。逆に、ここで一気に調印してしまう「覚悟」を秘めていたのだ。
その日、十九日、二人は再び横浜に急行、午後ポーハタン号船上で速やかに条約に調印したのである。
大老井伊直弼を欺くような形での日米通商条約への調印。ハリスが横浜へ出てきてから僅かに二日。堀田へ情報がもたらされてからでも僅かに五日。この数日というものは、岩瀬と井上にとってその人生のハイライトであったと言ってもいいだろう。
徳川家より日本国が重い
二人には、特に岩瀬には確固とした覚悟があった。朝廷が国際情勢を全く理解しない現状では、この条約調印が徳川政権にとって安危に関わる可能性が高い。そのことを認識しながら、彼は国家の大政に関与する者は「社稷(しゃしょく)を重し」と判断せざるを得ないと覚悟していたのだ。
即ち、今列強との戦を避け、先々列強に伍していける国家を創るためには、幕府が倒されても仕方がない、徳川家より日本国が重いとする覚悟である。岩瀬がこのような覚悟を固めていたことは、『幕末政治家』(福地桜痴)に拠っても明らかである。
日米修好通商条約は、岩瀬から小栗上野介忠順へ引き継がれる。この条約の批准使節団の目付としてポーハタン号で航米し、アメリカ国務省高官など合衆国要人と渡り合い、現地メディアからもその知力と交渉態度を絶賛されたのが小栗であった。その小栗が、やはり岩瀬と同じように「社稷は重し」という覚悟を以て横須賀造船所の建設をはじめ、徳川近代として次代に引き継ぐべき「遺産」を急ピッチで創り上げたのである。
この条約の成立に関わった岩瀬、井上、小栗といった徳川近代を代表する幕臣たちの意識は、既に「幕臣」という枠を超越しており、彼らは常に「日本国の先々」というものを判断の基準に置いていたのである。彼らが敷いたレールの上を走りながら、ようやく技術的な側面だけ彼らに追いつくや否や余計な引込線を敷き、日本国を「大日本帝国」などと称して暴走させたのが、薩摩・長州率いる明治日本であったのだ。
本節ここから以下はすべて、多少長い余談としていただいても構わないが、官軍正史に毒されたこれまでの歴史知識を矯正する上では有用かも知れない。
将軍継嗣問題は井伊の勝利、一橋派の敗北
安政五(1858)年六月二十一日、大老井伊は、宿継奉書で条約調印を朝廷に報告した。二十三日には、老中堀田正睦と松平忠固を解任した。
二人の老中の解任、特に堀田の解任は、今でも条約調印の責任をとらされたものとする主張がまかり通っているが、これはおかしい。堀田解任は将軍家定の意向であった可能性も否定することはできないのだ。調印に関する最後の詰めは、井伊と岩瀬・井上の間で行っており、井伊は堀田が岩瀬たち海防掛グループを増長させて、幕府旧来の意思決定秩序を壊したという見方をしていたのであろう。
松平忠固は誰からも信用されていなかったから、この解任は、実質的には条約調印とは全く関係がない。
同じ二十三日、次期将軍(養君)決定を祝う朝廷からのお祝い状が届いた。井伊以下南紀派にとっては、待ちに待っていた祝い状である。将軍世子が決まった時には、朝廷はこの祝い状を幕府に発するのが慣例である。
先に井伊は、誰それに決まったという固有名詞を挙げないで、ただ次期将軍が決まったという報告をしていたのである。朝廷もいい加減なもので、この報告を公式に受理している。朝廷、即ち孝明天皇は、攘夷には熱心であったが、将軍継嗣問題には実は興味がなかったのである。しかし、受理したからには祝い状を出さなければならず、井伊はこれを待ち望んでいたのだ。
祝い状が出されれば、それは一橋慶喜擁立を朝廷が認めず、朝廷は南紀派の推す徳川慶福を世子として公認したことになり、将軍継嗣問題は井伊の勝利、一橋派の敗北という形で決着がつくことになるのだ。
その祝い状が届いたのだが、これについては奇妙な話が伝わる。ただ、この話が事実かどうかは裏が取れないことをお断りしておく。
この祝い状は、九条関白主導で成立し、六月八日に京都を発したとされる。とすれば、十四日に、何かあったとしても十五日には江戸に着く。この種の通信物の駅伝については、段取り、スケジュールがきっちり決まっており、それが大きくずれることはないのだ。ところが、実際に江戸城に着いたのが二十三日なのだ。この大幅なズレは何が原因なのか。
更に、城内で具体的にこれを幕閣に届けるのは「奥祐筆」の仕事であるが、これを行った奥祐筆・志賀金八郎が七月一日に自殺しているのだ。奇妙な話ではある。
六月二十五日、幕府は徳川慶福が将軍世子に決定したことを公示した。一橋派の敗北が確定したのである。
水戸の徳川斉昭たちの「不時登城」事件
二十三日に祝い状が届き、二十五日に世子決定の公示。その間の六月二十四日に水戸の徳川斉昭たちの「不時登城」事件が起きている。
これは、水戸の徳川斉昭(前藩主、通称烈公)、水戸藩主徳川慶篤、尾張藩主徳川慶恕(慶勝)が、定められた登城日時を無視していきなり登城し、大老以下幕閣を叱責しようとした事件である。
大名の登城にはルールが存在するし、益して御三家が幕政にコミットすること自体が慣例として許されていない。この前後に、一橋慶喜や松平春嶽も登城しており、この二人を「不時登城」事件に加える書物もあるが、二十四日には二人は参加していない。春嶽は、実は井伊と頻繁にコミュニケーションをとっていたのだが、このことはあまり語られていない。
徳川斉昭は、井伊が、一橋派などが生まれて将軍継嗣問題に介入した諸悪の根源とみていた人物であるが、もともと水戸藩らしく〝公家被れ〞であり、幕閣の会議内容などを平気で京都にご注進に及ぶというような、御三家にあるまじき振舞いが多かった。典型的な攘夷派で、現代流に表現すれば右翼国粋主義の権化のような人物であった。尤も、実子である一橋慶喜に将軍世子の可能性が出てからは、急に攘夷論を弱めたという“正直な”一面ももっていた。この
激情家を中心とした、あまり論理的とも思えぬ三名が井伊に文句を言いに来たわけである。ただ、御三家の不時登城というのは例がなく、江戸城内は大騒ぎになった。
斉昭たちの“文句”は、以下の四点であるとされている。
・通商条約調印は違勅である
・しかも宿継奉書での報告は不敬である
・今、次期将軍決定を発表するのは朝廷にとってよろしくない
・松平春嶽を大老の上に置くべきである
こういう脈絡のない内容であるから、せいぜい“文句”としか言い様がなく、一体何が言いたいのか分からない。水戸の斉昭は、窮すると「越前(春嶽)を呼べ」と喚いたらしい。
要するに、水戸、尾張の論理レベルはこの程度であったということで、彼らは春嶽頼りであったようだ。ならば、もっと打合せを重ねて臨むべきであり、やることがそれこそ「児戯に等しい」と言わざるを得ない。逆に、アンチ井伊派とはこういう状態であったから、相対的に春嶽が論理家として目立ったのかも知れない。
結局、「不時登城」事件は、井伊にとっては何事でもなかったのである。逆に井伊は、七月五日、「不時登城」の処分を発表した。三名に一橋慶喜、松平春嶽を加えた五名に対して、隠居、謹慎、登城禁止などを言い渡したのである。薩摩・長州に水戸や土佐を加えた尊攘過激派による幕末テロリズムは、このあたりから激しさを増していくことになる。
徳川斉昭の無様な敗北は、岩瀬を失望させた。不思議なことだが、急進的な対外協調派であった岩瀬は、頑迷な攘夷派、国粋主義者である徳川斉昭と意外にもウマが合ったのである。
恐らく、岩瀬には斉昭が一橋慶喜の実父であるという意識があり、斉昭には若い岩瀬の激しい井伊批判が頼もしく映ったのではないだろうか。
実際のところ、岩瀬は井伊が大老に就任するや否や左遷されても全く不思議ではなかった。
本人にもその覚悟があったはずである。それが、アメリカとの通商条約調印まで外交の最前線に立っていたのだ。
ここでまた、奇妙なことが起こる。
「戊午の密勅」が「安政の大獄」「桜田門外の変」を引き起こした【消された「徳川近代」明治日本の欺瞞】2へつづく。
文/原田伊織(はらだ・いおり)
作家。京都市生まれ。大阪外国語大学卒。広告代理店でマーケティング・プランニングや番組企画などに携わる。2005年『夏が逝く瞬間』(河出書房新社)で作家デビュー。『原田伊織の晴耕雨読な日々』(毎日ワンズ)、維新三部作第一巻『明治維新という過ち』(講談社文庫)、維新三部作完結編『大西郷という虚像』(悟空出版)、『三流の維新 一流の江戸――「官賊」薩長も知らなかった驚きの「江戸システム」』(ダイヤモンド社)などがある。
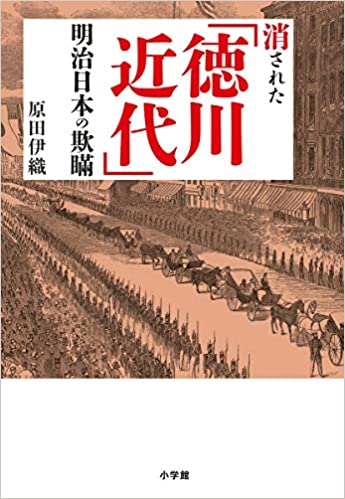
原田伊織/著 小学館刊




































