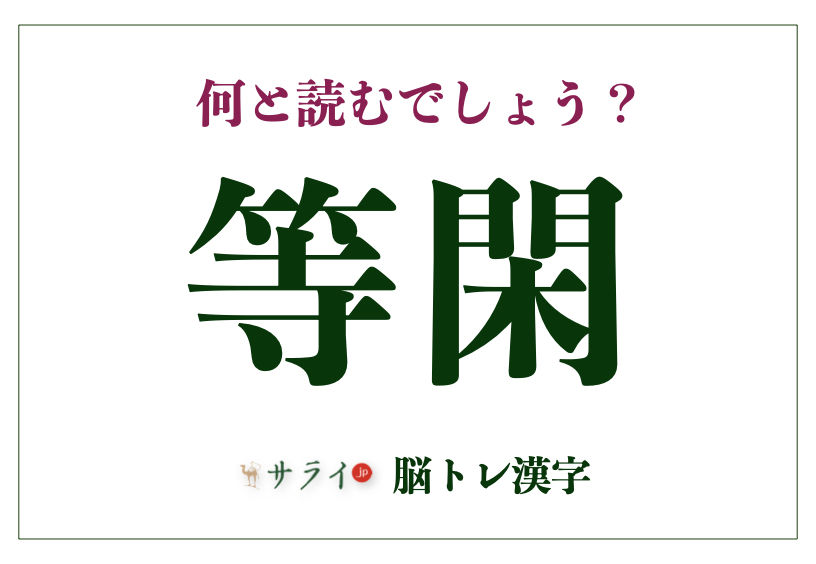祐成陽子さん(祐成陽子クッキングアートセミナー校長)
─日本初の「フードコーディネーター養成校」を開いた先駆者─
「必要な仕事や道具が存在しないのなら自分たちで研究して新しく作ればいい」

──フードコーディネーターの先駆けです。
「それまでやっていた料理教室にフードコーディネーター養成コースを開講したのが、昭和62年のことです。私が48歳の時だから、もう30年以上前のことね。以来、ここから4000人以上が巣立ちました。皆、独立して私より稼いでいるわよ」(笑)
──開講の経緯を教えてください。
「その頃、武蔵小金井(東京)で、料理教室と一緒に、『ケーキハウス』を経営していました。もう無我夢中。お菓子と料理の教室は口コミで生徒さんがどんどん増えていましたし、お店のほうも“ケーキのことなら何でも”と器具や食器の販売もしていたから、朝から晩まで休みなしでした。“こんなものが欲しい”というお客さんの要求に全部応えていたんです。作りたいけど量るのが面倒な人にはケーキごとに材料を必要なだけ量って売っていましたし、大型ミキサーや大理石の麺台も販売しました。そんな時に、ヨーロッパに留学していた娘の二葉が帰ってきたんです。二葉には『ケーキハウス』を手伝ってもらうつもりでした。ところが“料理をやりたくない”と言うんです。聞いてみると、料理よりも、テーブルコーディネートやインテリアに興味を抱いた、と。“もっと学びたい”と言うけれど、そんなことを教える学校はありません。当時、料理の撮影周りを整えるのは、洋服のスタイリストがやっていましたからね」

──どうなさったのですか?
「ハッと気づいたんです。この世に存在しないんだったら、作ればいいって。実際、教室でも、テーブルコーディネートや料理の盛り付けを教えてほしい、という声はあがっていたんです。だから、“フードコーディネーター”という新しい職種を誕生させました。当時は、珍しい言葉だったんですよ」
──ご苦労されたでしょう。
「それまでに存在していない職業ですから、正解がありません。でも、たしかに美しい盛り付けや、素敵なテーブルセッティングというものはある。仕事である以上、お客さんはお金を払って“正解”を求めてくるわけです。だったら、自分で正解にいたる方程式を編み出そう、と考えました。そこで、二葉が外国で学んできたことに、私のこれまでの経験をプラスしました。さらに外国のあらゆる料理写真を研究し、これぞ正解だという方法を確立しました」
──周囲の反応はいかがでしたか。
「そもそも、そんな職業が日本にありません。物珍しさもあって、雑誌やテレビからの出演依頼が増えました。でも最初は苦労しましたよ。呼ばれて仕事をしたのに、“カメラマンにはお金払うけど、盛り付けに金なんか出せない”と言われたり。テレビ局の人から“先生はいい仕事をするけど、田舎だから1日仕事になってしまう。次はもう頼めないよ”と言われたり。ひどい話よね、武蔵小金井が田舎だなんて(笑)。でもメディアに取り上げてもらわないと、産声を上げたばかりのフードコーディネーターという仕事が廃れてしまう。それじゃ教えても意味がないと思って」
──どう打開したのですか。
「引っ越したんです、都心のど真ん中、新宿・四谷に(笑)。ローンの残っている家を売り払い、借金をしてまで都心に居を構えました。遠いことが理由で仕事にならないなら、近くに住めばいいでしょって。ためらいはなかったかって? いいえ。思い立ったが吉日、迷ったり悩んだりした時こそ、変化を怖れず前に進んできました。たとえ失敗しても、その経験が糧になりますから」
──料理教室はいつからですか。
「これは26歳の頃ですね。結婚して3年目だったかしら。ご近所に、料理をお裾分けしていたんです。そしたらそれが評判になって“教えてほしい”という声がいくつもあがったんです。でも、教える場所もなければ、教えた経験もない。それでも、家でいいならって、団地の小さなキッチンにご近所の皆さまを呼んで、家庭料理の教室を始めました。それが口コミでどんどん広がっていったんです」
──そもそも料理はお好きだったんですか。
「4人兄弟の長女だったのですが、母があまり料理を得意としていなかったんです。いつも何かひと味足りない。だから塩をひとつまみ足したり、醤油を加えてみたり、とひと手間加えて料理の味を調えていました。もちろん、私が作ることも。妹や弟からは“お姉ちゃんのほうがおいしい”なんて」(笑)
──短大の家政科に進まれたそうですね。
「決まった時間にご飯を食べるかっちりした家で育ちました。口うるさい母から逃げたくて、すぐにでも結婚しようと、短大に進んだんです。料理に興味があるというより、単なる花嫁修業でした。でも家政科の先生の料理が上手じゃなくて(笑)。調理実習でもやっぱり最後に味を調えていました」
「10年後の開業を夫に相談すると“今すぐ始めたら”と後押し」
──お見合い結婚だと伺いました。
「20歳の頃からお見合い写真と履歴書を5部ずつ、持ち歩いていました。こうしたらいつでも渡せるでしょ? 知り合いに会うと一式渡して“いい人がいたら紹介してください”ってお願いしていました。お見合いは営業と同じだと思っていたのかもしれないわね。
今の主人? 16回目のお見合いで知り合いました。その日は、朝、昼、晩と1日3回お見合いをしていて、夜になって“話を進めたい”と連絡がありました。私、聞いちゃいましたもん。“朝の人? 昼の人?”って。そしたら昼の人でした。4つ年上の真面目そうな人。いい人を選んだわね。だって向こうのほうが私のことを好きなんだから」(笑)
──ご主人、働くことに反対は?
「料理教室も軌道に乗ってきて、36歳の時に、ケーキ専門店をやってみたいな、と思ったんです。でも当時は、ふたりの子どもの子育て真っ最中でした。料理教室ならば家の台所でできても、ケーキ専門店ではそうはいきません。お金もかかります。あと10年もしたら子育ての手が離れるから、それまでにお金を貯めて……と考えていたんです。そのことを夫に相談したら、何と言ったと思います?」
──大反対ですか?
「“あと10年もしたら”というところは、大反対だったわね。夫はこう言ったんです。“それじゃ遅すぎる”って。
経験を積んだ人が45歳から始めるならいいけど、君みたいに就職したことも、商売の経験もない人が、45歳から始めても誰も相手にしてくれないよ。今すぐにでも始めたほうがいい。夫はそう言って、背中をぐいと押してくれたんです」
──素敵なご主人です。
「そうでしょ? 私はスクールの生徒や卒業生の恋愛相談にもよく乗ってるんだけど、必ずこうアドバイスしています。“いい男は裏方体質よ”って。うちの夫なんて、今では台所に立って、私のために料理を作ってくれます。私、ずっと料理をしてきたでしょ? もう一生分やり尽くしたと思って、
60歳を過ぎた時に“もう料理を作りたくない”と言ったら、“だったらオレが作る”って、やってくれるようになったんです。
いい男は出しゃばりません。見た目も大人しそうなのですが、いざとなったら矢面に立つ気概がある。夫は、何でも私の好きなようにさせてくれました。例えば毎年、勉強を兼ねて、海外視察に行っているのですが、夫はボーナスを全額、私に手渡して、“これを好きなように使っていいよ”と言ってくれました。ちょっとのろけすぎかしら」(笑)
──ケーキ専門店はいかがでしたか。
「女がビジネスに手を出してうまくいくはずがない。そんなふうに散々馬鹿にされましたね。ようやくビジネスのテーブルについても、私の前職が主婦だと知ると、“主婦なんかと仕事をするつもりはない”とはっきり言ってくる人もいました。ええ、もちろん悔しかったですよ。“見返してやるんだ”という思いが、がんばる動機になりました。ずっと必死でしたよ。失敗したら“ほらみたことか”と言われるのがわかってましたから」
──ピンチはなかったのですか。
「もちろんあったのでしょうけど、そういうことって、忘れちゃうの。それに命が取られるわけじゃない、と思えば平気でした。人って追い詰められると、不思議とアイデアが湧いてきて、乗り越えられるのよ。
例えば、ケーキ専門店では『小麦粉キープ』というサービスを手掛けました。日頃からたくさん使う人には、小麦粉の25kgの大袋を買ってもらってそれを店で預かり、好きなだけ必要な時に取りに来られるようにしたんです。お酒のボトルキープからヒントを得たのですが、これが大好評。小麦粉を取りに来るついでに、いろいろ他のものも買ってくれるので、大助かりでした」

「ほんのちょっとした工夫で毎日が楽しく“色鮮やか”になる」

──今は順調すぎてやることがありませんね。
「何をいってるんですか。やることだらけですよ。世の中を見回してご覧なさい。まだ誰も手を付けていないことが、山ほどあります。大手が手掛けないような隙間を見つけて、アイデアを絞る。こんなワクワクすることはありません。今も、新しいランチョンマットと、ニンニクすりつぶし器を開発中です」
──充実の日々をお過ごしです。
「恵まれていますね。卒業した生徒ともスマホのラインで繋がっていて、よく相談を受けています。相談されるということは、頼りにされている証ですからね。もちろん、本気で向き合いますよ」
──世間はコロナ禍で沈んでいます。
「コロナは確かに、自由を奪いました。やりたくてもできないことが、たくさんあるでしょう。でもね、暗く落ち込んでいたら、幸せも逃げてしまう。見方を変えれば、時間がある今は勉強するチャンスなんじゃない? いろいろ学んで、じっと力をためるのはどうでしょう。コロナはいずれ、終わります。同時に景気も回復するでしょう。その時に、ためこんだ力で、一気に飛び立てばいいんです」
──若くないから、と躊躇(ちゅうちょ)する人もいます。
「私がフードコーディネーターの学校を都心に移したのは50歳を過ぎてから。トレードマークの派手なメガネをし始めたのもこの頃ね。60歳の頃は、“私はまだまだ”と思っていました。料理本を出版したのは70歳を過ぎてから。80歳の手前で、自伝的エッセイを出しました。好きなことなら、年齢なんて関係ありません」
──老いや死は怖くありませんか。
「70歳の時に子宮がんと宣告され、闘病生活も経験しましたが、死はちっとも怖くありませんでした。なぜって? だっていつ死んでも悔いがないから。ずっと悔いのない毎日を生きてるんです、私。悔いがある人って、過去を振り返ってばかりいるでしょ? あの時こうしておけば、って。私は今が大事だから、過去は振り返りません。こういう取材を受けなければ、思い出すこともないでしょうね」
──過去ではなく、今を生きる。
「そう、今がいちばん楽しい。やることもたくさんあります。生徒やスタッフからは“陽子先生は、止まると死んじゃうんじゃないですか”と言われています」(笑)
──今を楽しく生きるヒントとは?
「そうね、食卓でいうなら季節を感じさせる演出をすること。例えば、桜の花びらを拾ってきて、いつもの料理に添えるだけで、季節感が出ます。器の色を変えてみるのもいいわね。ほんのちょっとした工夫で、楽しく色鮮やかな毎日になりますよ」


祐成陽子(すけなり・ようこ)昭和14年、東京生まれ。武蔵野女子短期大学家政科を卒業後、23歳でお見合い結婚。26歳の時に自宅キッチンで料理教室を開く。37歳でケーキの器具と材料の店「ケーキハウス」を開店。
48歳の時に、日本初のフードコーディネーター養成コースを開講し、注目を集める。https://www.sukenari.co.jp/
※この記事は『サライ』本誌2021年5月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/ 角山祥道 撮影/宮地 工 )