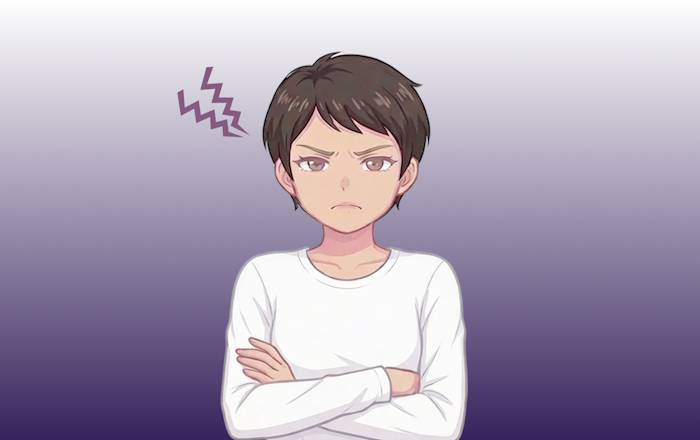談/上田諭先生(東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 教授)
認知症は、今のところ治る見込みのない病気です。もちろん、研究は進められていますが、脳の器質的な問題が回復する見込みはありません。
治そうという試みをする人がいる一方で、「超高齢化社会において認知症になることは当たり前のことなのだ」と受容し、共に寄り添い、時に慰め、時に助けようとする考え方があります。
認知症の患者さんに対してどのように向き合えばいいのか、お話しします。(なお、ここでいう認知症とは、アルツハイマー型認知症の軽度から中等度の人を中心にしています)
■周囲の人の対応によって悪化する症状がある
認知症になると、脳の海馬(かいば)という記憶を司る部分が縮んでいきます。昔のことはよく覚えているのに、つい最近のことは覚えていない。それは聞いたばかりの話であったり、さっき食べたもののことであったり、さまざまなことを思い出せないのです。
しかし、忘れたところで本人にとってはさほど困るようなことではありません。ただ、家族はその変化に対して驚き、慌ててしまいます。そして、本人が嫌がる、あるいは不本意な状態で精神科医のところに連れてくることが多いのです。
しかし、このような記憶する能力が衰えることは、認知症の症状といえるものの一部であるに過ぎません。問題はこの先、認知症を治さなければと考える家族や周囲の人の対応によって悪化していく「症状」です。
これらの症状は、気分の落ち込みや不機嫌、怒りっぽいという形で現れ、さらに進めば徘徊や暴言などがあり、認知症の行動心理症状(BPSD)と呼ぶことになっています。しかし、これらの中には、家族や周囲の接し方によって引き起こされる正常な反応としての「症状」も包含していると思われるのです。
■自尊心を傷つけられれば悪化する
来院したご家族は、時に患者さん本人を前にして困った症状を挙げ連ねることがあります。遠慮はあっても、患者さんの批判や悪口へと発展することもあります。患者さんはいたたまれないでしょう。医師によっては、そういう患者さんの心情も慮ることなく、話に耳を傾けさえしないこともあります。大変残念なことです。というのも、患者さんは何も分かっていないわけではないのです。記憶力が低下しても、思考力や判断力、理解力、そして情操はしっかりとしています。涙を流して感動したり、怒ったりすることもあれば、嬉しいという感情も豊かなのです。
そして、いきなり見ず知らずの医師の前で、嫌なことを次々に言われると、バカにされた、恥をかかされたと思う。それは人間であれば、至極当然の成り行きです。また、カレンダーを前に、「今日は何日? 何曜日?」などと毎日のように問いかけられるのは、苦行でしかありません。そもそもそのようなことを常日頃から意識しておく必要もないし、衰えていく記憶力がそれで改善することもありません。歩けない人に歩けと言っているようなもので、叱責して本人を傷つけ、それを繰り返すことによってBPSDを悪化させることにもなるのです。
■生きている喜びや張り合いを持ってもらう
よく認知症の早期発見・早期治療という言葉を耳にしますが、早期にみつけても、それで記憶力を回復させることはできません。ともすると、本人を傷つけるだけに終わりかねません。しかし、意義があるとすれば、早期発見できた場合、家族が認知症を早く受容し、BPSDにつながるような言動を慎んで、親身な介護姿勢を持つことです。それは患者さんの心の安定を生み、本人と介護者双方が穏やかな生活を送れることにつながります。
しかしながら、介護が家族にとって負担になることもあるでしょう。そんな時は、デイサービスを利用することをおすすめします。24時間顔を突き合わせないことで、家族の負担が減るだけでなく、本人も友人や仲間ができ、職員との交流も生まれます。そして何より、本人の人生に張り合いができるのです。また、昼間起きていられるので、夜間よく眠れるようになるという利点もあります。
介護に関する相談は、各地域に地域包括支援センターがあるので、困った時には相談するのもよいでしょう。
■認知症の半分は心の問題
実は、別の病気なのに認知症と診断されることも少なくありません。たとえば、肝臓の機能障害や甲状腺機能障害や脳梗塞、また水分不足による脱水、降圧剤による血圧の下がり過ぎによっても認知機能が低下することがあります。
本来、認知症は長期に渡って少しずつ認知機能が低下するのですが、他の病気や薬によるものである場合、しばしば急速に悪化します。しかし、それは認知症によるものではありません。その見極めが大切なのですが、認知症の啓発が中途半端に進んだせいで、医師によっては認知症と診断してしまうことがあります。命に関わることもあり、身体的問題を第一に考えることを医師がわきまえる必要があります。
加齢による認知機能の低下は避けられないことです。しかし、認知症を受容し、家族を含めた周囲の人たち接し方を変えることによって、BPSDは改善の余地があり、家族の負担も少なくすることができます。脳の器質的な問題は治療できなくても、認知症の半分は心の問題であると捉え、温かく受け入れることが患者さんや家族の幸せにつながるのです。

談/上田諭先生
1957年、京都府生まれ。1981年、関西学院大学社会学部卒。新聞社勤務(記者)を経て1990年に北海道大学医学部入学。東京都多摩老人医療センター内科のち精神科、東京都老人医療センター精神科などに勤務。2007年、米国デューク大学メディカルセンター‟電気けいれん療法研修”を修了。2007年4月に日本医科大学精神神経科助教のち講師。2017年、東京医療学院大学リハビリテーション学科教授。北辰病院(埼玉県越谷市)にて高齢者専門外来(週1回)。専門医・指導医:日本精神神経学会、日本老年精神医学会、日本総合病院精神医学会。著書『治さなくてよい認知症』(2014、日本評論社)『不幸な認知症 幸せな認知症』(2014、マガジンハウス)、編書『認知症はこう診る』(2017、医学書院)など。
取材・文/わたなべあや
1964年10月生まれ、大阪府出身。大阪芸術大学文芸学科卒業。料理学校で講師をしていた母と医師の叔父に影響を受け、幼い頃より食べることと健康に高い関心を持つ。グルメ、
医療関係を中心に執筆中。