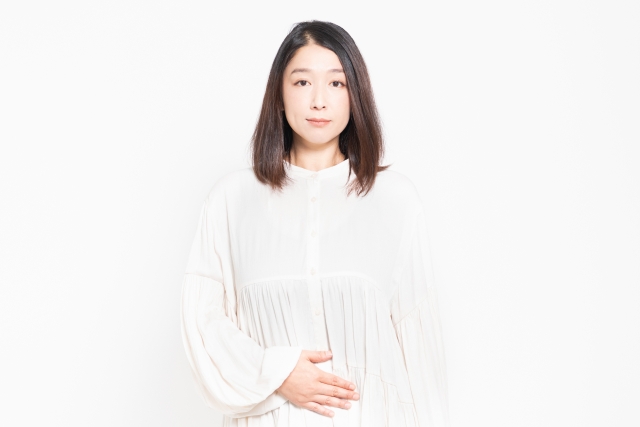30~40代半ばのプレ更年期や、40代後半~50代の更年期の女性は「なんとなくの不調」「ちょっとした違和感」を抱くことが多くなります。
なかでも多くの人が困っている悩みは更年期の冬季うつの症状です。
実は、その不調には漢方薬が役立つことをご存知でしたか?
私の悩みにも漢方薬が役立つのか知りたい! 根本解消する方法が知りたい!
そんな女性たちの疑問を、漢方の専門家に解説してもらいます。
今回は「更年期の冬季うつ」の原因や対処法について、あんしん漢方の薬剤師で、漢方薬製剤の開発研究に携わる碇純子さんに教えてもらいました。
Q.気分の落ち込みに加えて止まらない食欲、この症状の正体は?

尚子さん、52歳からご質問をいただきました。
「最近、些細なことで気分が落ち込んでしまいます。どんなことも悲観的に考えてしまい、毎日暗い気分です。
主人にも、「昔はもっとポジティブだったのに」とチクリと言われてしまいました。
また、気分の落ち込みややる気の低下のほかにも、睡眠時間の増加や、食欲が増していることも気になっています。そのせいなのか、短期間で体重が3キロ以上も増えてしまいました。
この気分の落ち込みや過眠、過食の原因はいったい何なのでしょうか?」
ご質問ありがとうございます。原因のわからない気分の落ち込み、つらいですよね。とくに尚子さんは過眠と過食にも戸惑っているとのこと。毎日がとても大変なことと思います。
尚子さんのその症状は、「更年期の冬季うつ」の可能性があります。きちんと適切な治療やセルフケアを行えば、症状の緩和をめざせます。まずは、更年期の冬季うつの原因をしっかり把握して対処しましょう。
更年期の冬季うつの症状

冬季うつは「季節性情動障害」ともいわれ、気温が低下する11月頃から症状があらわれ始めます。気分の落ち込みや気力の喪失、倦怠感など一般的なうつ病と共通する部分があるものの、過眠や過食、体重の増加など、異なる部分もあります。
まずは、更年期の冬季うつの症状について見ていきましょう。
1.睡眠の乱れ
睡眠ホルモンのメラトニンの材料であるセロトニンは、日中に太陽光を浴びることで作られます。しかし、冬は日照時間が短くなるので、セロトニン、メラトニンが十分に分泌できず、これが体内時計を乱す原因に。
睡眠時間をきちんと確保できないと、睡眠のバランスが崩れてしまい、うつ症状に繋がることがあります。
また、年末年始の繁忙期は、仕事もプライベートも忙しくなりがちです。不規則な生活が続くと、睡眠時間も安定せず、寝不足、あるいは過眠などの症状があらわれ始めます。
とくに、季節性のうつ病の場合、「朝に起きられず、日中に眠くなる」という症状が顕著にあらわれます。
2.過食
冬季うつによりストレスが蓄積すると、チョコレートなどの甘いものや、ご飯、麺類、パンなどの炭水化物が食べたくなってしまいます。とくに、甘い炭水化物である菓子パンは摂取カロリーを増やす原因になります。
うつ症状によって強いストレスや緊張を感じると、体はそれを発散させるため、脳のエネルギー源であるブドウ糖を欲します。その結果、ブドウ糖を作るために必要な甘いものを食べたくなります。
しかし、甘いものによる作用は一時的な効果しかないため、甘いものを食べ続けるという過食に陥ってしまうのです。
3.体重が増える
体重の増加も冬季うつの症状によくみられます。前述の睡眠・食生活の乱れのほか、運動量の減少もその理由のひとつです。
とくに、寒い冬は外出の機会が減る傾向にあり、屋外での運動もそれに比例して少なくなります。憂うつ感、疲労感で外に出ること自体が億劫になり、運動する気力も削がれることに。
また、体重の増加で体が重く感じられ、さらに運動する機会が減るといった悪循環を生むことになります。
ホルモンバランスの崩れが原因で起こる冬季うつは一度診療を

更年期を迎えると、女性ホルモンのエストロゲンが急減します。エストロゲンの低下は、様々な不調をもたらしますが、冬季うつ症状もそのひとつです。
更年期症状の基本的な治療方法は、生活習慣の改善と、ホルモン補充療法の2つがあります。まずは婦人科、もしくは更年期外来などで診てもらい、不調が更年期由来のものなのかどうかを検査してもらいましょう。
更年期の冬季うつを改善するセルフケア

ここからは、更年期の冬季うつを改善するためのセルフケアを4つご紹介します。
1.太陽光を浴びる
朝、太陽光をしっかりと浴びることで、睡眠ホルモンのメラトニンの材料になるセロトニンをしっかり分泌させましょう。
できれば早朝のウォーキングとともに30分~1時間ほど太陽光を浴びるのが望ましいですが、カーテンを開けて太陽光を浴びるだけでも十分に効果はあります。
曇りや雨の日でもセロトニン分泌に必要な光を得られるので、朝起きたらまず太陽光を浴びることを意識しましょう。
2.トリプトファンを含む食事を摂る
睡眠ホルモンであるメラトニンの材料であり、通称「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンは、必須アミノ酸であるトリプトファンから作られています。トリプトファンを摂取すると、セロトニンの分泌も安定し、うつ症状を和らげることができるでしょう。
トリプトファンは、たんぱく質を含む食品から主に摂取できます。牛乳、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐、味噌などの大豆製品、ごまやバナナ、卵などにも豊富に含まれています。
意識的にトリプトファンを摂取し、セロトニンを分泌させましょう。
3.ウォーキングなど運動時間を確保する
定期的に運動をすることで、更年期の冬季うつの症状を和らげることができます。筋トレのような激しめの運動ではなく、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がおすすめです。
ジムなど、室内のランニングマシンで運動するよりも、野外で運動したほうが周囲の景色も変わり、気晴らしになります。また、野外では太陽光を浴びることもできるので、早朝ウォーキングで体内時計を正常化するのもおすすめです。
4.漢方薬を試す
「更年期の冬季うつを根本から改善したい」
「いろいろと試したが症状が改善しない」
「西洋薬は一度飲み始めたら、やめられないのではないかと不安」
そんな人には、医薬品として効果が認められている漢方薬がおすすめです。
漢方薬は自然にある植物や鉱物などの「生薬」を組み合わせて作られているため、 一般的に西洋薬よりも副作用が少ないといわれています。
また漢方薬は、苦痛を和らげる対症療法だけではなく、根本的な体質の改善が可能です。「同じ症状を繰り返したくない」「症状が出にくい体質になりたい」という思いに応えてくれます。
「バランスの取れた食事や運動などを毎日続けるのは苦手」という人も、症状や体質に合った漢方薬を毎日飲むだけなので、手間なく気軽に継続できます。
更年期の冬季うつには、「自律神経のバランスを整えて、落ち込みやストレス、不安を和らげる」「消化・吸収機能を高め、体の内側から心を元気にする」といった作用が期待できる生薬を含む漢方薬を選びましょう。
更年期の冬季うつ対策におすすめの漢方薬
・抑肝散(よくかんさん):自律神経のバランスを整え、緊張をほぐして精神を安定させ、イライラや不安感・不眠を解消します。
・補中益気湯(ほちゅうえっきとう):胃腸の働きを高め、気力を充実させて、疲労・倦怠感を改善します。
ただし、漢方薬はご自身の体質に合ったものを選ぶことが大切です。体質に合っていないと、効果が出ないだけでなく、思わぬ副作用が起こる場合があります。
購入時には、できる限り漢方に精通した医師や薬剤師等にご相談ください。
「お手頃価格で不調を改善したい」という人には、医薬品の漢方薬がおすすめ。スマホで気軽に相談できる「あんしん漢方」のような新しいサービスも登場しています。
AI(人工知能)を活用した「オンライン個別相談」サービスは、漢方のプロが体質に合った漢方を見極め、お手頃価格で自宅まで郵送してくれるため、手軽で便利です。
更年期の冬季うつは放置せず、症状がひどい場合はまずは婦人科へ

更年期の冬季うつは、冬の日照時間の変化により、体内時計のリズムが崩れることによって起こります。
気分の落ち込みといった通常のうつ症状のほか、過眠、過食、体重増加といった傾向があらわれやすいといわれています。
また、更年期の冬季うつは、更年期の女性ホルモンの急減が影響している場合も。体調不良を感じる場合は、婦人科や更年期外来を受診してみてください。
<この記事の監修者>

碇 純子(いかり すみこ)
薬剤師・漢方薬生薬認定薬剤師
/ 修士(薬学) / 博士(理学)
神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。
世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=221432a9sera0237&utm_source=sarai&utm_medium=referral&utm_campaign=240111
イラスト:にゃたり