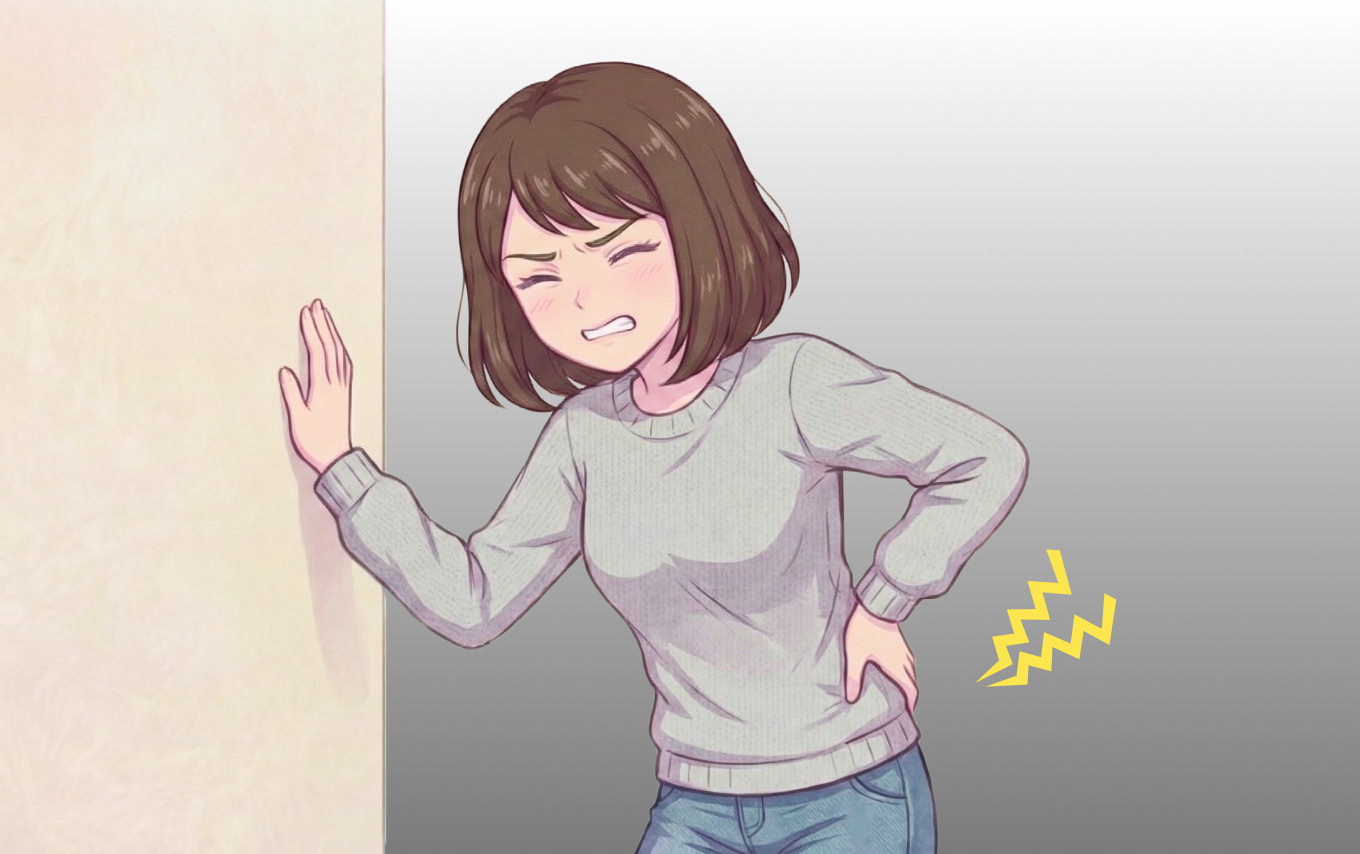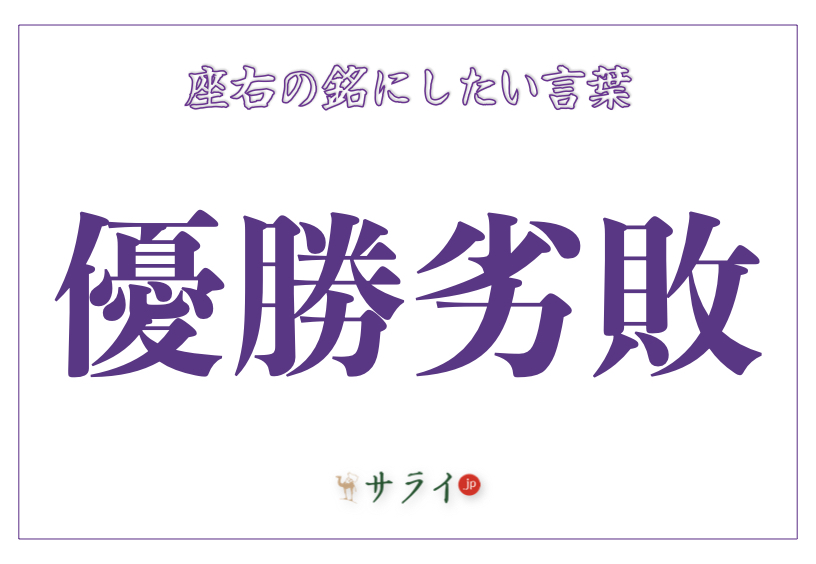山形県は果物の宝庫として知られていますが、実はその豊かな自然環境を活かした日本酒の名産地でもあります。新潟や福島といった隣県に比べると少し影が薄いかもしれませんが、日本酒の全国新酒鑑評会では上位に入る年が多い県です。2025年度は8位でしたが、2023年度には1位を獲得しています。
山形の酒造りの特徴は、質の高い「純米吟醸」の生産に力を入れていること。“吟醸王国”とも呼ばれる山形県は、GI(地理的表示)「山形」の認定を受け、独自の酵母と米作りにこだわり、フルーティーで香り高い日本酒を世に送り出しています。今回は、日本酒がはじめての方にも分かりやすく、山形の日本酒の魅力をご紹介します。
文/山内祐治
目次
山形の日本酒が醸し出すフルーティーな香り
山形の日本酒は甘口が多い? その特徴と魅力
世界が注目する「十四代」の革命的な酒造り
知る人ぞ知る山形の「レア」な日本酒たち
山形が誇る有名銘柄と日本酒文化の広がり
まとめ
山形の日本酒が醸し出すフルーティーな香り
山形県の日本酒がフルーティーな香りを持つ理由は「山形酵母」の存在です。YK-0107、山形KAなど、いくつかあるのですが、これらの県独自酵母のなかには、リンゴや洋梨を思わせる華やかな香りを与えるものが存在します。
山形県が推進する「純米吟醸」造りでは、お米を60%以下まで精米し、低温でじっくりと発酵させることで、この酵母の特性を最大限に引き出しています。
山形の日本酒は甘口が多い? その特徴と魅力
「山形の日本酒は甘口が多い」と言われることがありますが、これは分からない話ではありません。もちろんドライなお酒は数多くあるものの、山形県の酒造りの特徴である純米吟醸は、リンゴのようなフルーティーな香りと共に、ジューシーで柔らかな甘さを持つものが目立ちます。
例えば、山形県を代表する酒蔵、出羽桜酒造の「出羽桜 出羽燦々誕生記念」はいかがでしょう。このお酒は、柔らかな甘さの中に洋梨や熟した桃を思わせるフルーティーな風味があります。初めて山形の日本酒を飲む方は、まずこうした銘柄から試してみると、柔らかい甘さを感じやすいでしょう。
また「大山」という銘柄も、柔らかな甘さが特徴で、おすすめです。山形の甘口日本酒は、単に甘いだけではなく、米の旨味とフルーティーな香りがバランス良く調和しているのが魅力です。
このような特徴を持つ山形の日本酒は、冷やして飲むと香りが引き立ち、甘さがより爽やかに感じられます。料理との相性も良く、和食はもちろん、チーズなどの洋風の食材とも意外に合うのでぜひ試してみてください。
世界が注目する「十四代」の革命的な酒造り
山形の日本酒を語る上で、「十四代(じゅうよんだい)」を外すことはできません。このブランドを生み出した高木酒造の15代目・高木顕統(あきつな)氏は、日本酒業界に大きな影響を与えた人物と言っても過言ではありません。
1990年代、日本酒の消費が落ち込み、新潟の「淡麗辛口」がいまだ主流だった時代に、敢えて柔らかく甘みがあり、香り高いお酒を世に出したのです。当時としては珍しかったこのスタイルは「こんなにおいしい日本酒があるのか」と驚きをもって迎えられ、「十四代」は瞬く間に別格の存在となりました。
興味深いのは、“十四代”という名前の由来です。これは先代髙木辰五郎氏(14代目)を冠して名付けられたもの。14代目が育種した「酒未来(さけみらい)」「龍の落とし子」「羽州誉(うしゅうほまれ)」という3つの酒米は、かつては高木酒造だけで使われていましたが、現在では、他の名だたる酒蔵にも提供され(※特に酒未来)、新たな名酒を生み出す源となっています。
また、「十四代」のノウハウは県外にも広がっており、秋田の「花邑」や鹿児島の「天賦」といった銘柄は、高木酒造の技術指導によって生まれたと言われています。「十四代」自体は入手が難しいお酒ですが、そのDNAを受け継いだお酒たちが他所でも楽しめるようになっているのです。

知る人ぞ知る山形の「レア」な日本酒たち
山形県には十四代以外にも、希少価値の高い「レア」な日本酒がいくつも存在します。
例えば楯の川酒造は、2010年から全て純米大吟醸のみを製造するという徹底ぶりで知られています。同蔵は極限までお米を磨くことにも挑戦しており、精米歩合10%や7%、さらには「楯野川 光明」という精米歩合1%の驚異的な数値のお酒も生み出しています。また、SAKE HUNDREDというラグジュアリー日本酒ブランドの「百光」は、楯の川酒造が醸造パートナーとなっており、レア酒の代名詞とも言われています。
熟成酒の分野でも山形は見逃せません。出羽桜酒造は低温熟成のお酒に取り組んでおり、時間をかけてゆっくりと熟成させることで、複雑な香りと味わいを生み出しています。
地酒としての個性を強く持つ「杉勇」も、知る人ぞ知る名酒です。派手さはないものの、山形の伝統的な酒造りの良さを堪能できる一本と言えるでしょう。
山形が誇る有名銘柄と日本酒文化の広がり
ほかに山形の有名銘柄としては、「銀嶺月山」「雅山流」などもぜひ押さえておきたいところです。また「鯉川」も特筆すべき存在です。鯉川酒造は山形の海沿いに位置し、かつて“幻の酒米”と呼ばれた「亀の尾」の復活に尽力された蔵として知られています。
「亀の尾」は山形県が誇る酒米で、この米を育てた阿部亀治氏にちなんだ「阿部亀治」という銘柄も鯉川酒造には存在します。山形の酒蔵は、このように地域の歴史や文化と深く結びついているのも特徴です。
山形の日本酒文化がここまで発展した背景には、いくつかの要因があります。まず、山形は城下町であり、特に酒田などの地域は北前船の寄港地として栄え、京都からの文化の流入がありました。また、内陸部の米沢や天童などは良質な米の産地であり、街道の整備と共に酒蔵が発展しました。そして何より、山形県の醸造協会や醸造試験場のリーダーシップと、酒蔵同士の強い結束力が、「純米吟醸」という方向性を打ち出し、山形の日本酒ブランドを確立させたのです。
近隣の新潟が「淡麗辛口」で攻めたのに対し、山形は「質の高い純米吟醸」という独自路線を貫いたことが、今日の評価につながっています。
まとめ
山形の日本酒は、「十四代」に見られるようなフルーティーで柔らかな味わいがひとつの傾向であり、日本酒がはじめての方にもとっつきやすい一面を持っています。しかし同時に、酒米開発をはじめとする革新的な取り組みや、極限まで米を磨いた大吟醸など、日本酒ファンを唸らせる奥深さも兼ね備えています。
山形県を訪れる機会があれば、ぜひ地元の酒蔵巡りや利き酒を体験してみてください。また、お取り寄せや専門店で山形の日本酒を探してみるのも良いでしょう。フルーティーな香りと柔らかな甘みに、きっと新たな日本酒の魅力を発見できるはずです。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。
構成/土田貴史