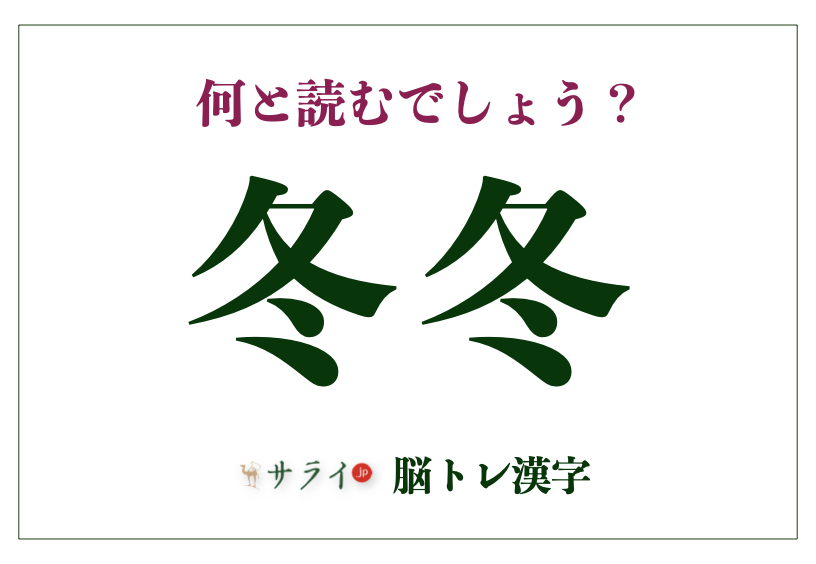出雲大社のお膝元として知られる島根県。実はこの地は、知る人ぞ知る日本酒の名産地でもあります。山陰地方に位置する島根県は、豊かな自然と古来からの酒造りの伝統が息づく土地。島根は「古事記」に登場する八岐大蛇と八塩折之酒や、佐香神社(酒造りの神)など、「酒と神話」の具体的エピソードが豊富です。島根の日本酒が持つ魅力について、初心者の方にもわかりやすくご紹介していきます。
文/山内祐治
目次
島根の日本酒が持つ独特な特徴とは
島根の日本酒に多い辛口の魅力を探る
島根の日本酒で有名な銘柄をご紹介
島根の日本酒でレアな逸品を見つける楽しみ
島根の日本酒「死神」という異色の銘柄
まとめ
島根の日本酒が持つ独特な特徴とは
島根県内には30以上の酒蔵が点在し、出雲・石見・隠岐まで個性豊かな地酒が揃います。県の日本酒を語る上で欠かせないのが、昭和から平成にかけて活躍された元鑑定官・上原浩先生の存在です。「酒は純米、燗ならなおよし」という言葉を残した上原先生は、山陰地方の酒造りに強い影響をもたらしました。その影響は島根県にも及び、燗映えする日本酒を生み出す酒蔵が少なくありません。
その結果として、特徴として挙げられるのは、ドライでシャープな味わいです。さらに一部には、若干の熟成を経たような、ドライフラワーを思わせる印象を持つお酒が比較的目立つことも挙げられます。これは上原イズムと島根の伝統が融合した結果と言えるでしょう。
しかし、島根の日本酒はそれだけではありません。燗にして美味しい純米酒がある一方で、非常に綺麗な味わいのお酒や、味わいの太いお酒など、バリエーションに富んでいます。
島根の日本酒に多い辛口の魅力を探る
島根の日本酒の傾向のひとつに、いわゆる辛口のお酒が知られています。代表的な銘柄として、まず挙げられるのが「玉櫻」(玉櫻酒造)と「開春」(若林酒造)です。これらのお酒は、ピシッと締まった味わいが特徴で、先ほどお話しした“枯れた印象”も併せ持つ製品が多いです。締まった辛口がお好きな方には、ぜひおすすめしたい銘柄です。お燗酒やひや(常温)もとても良いです。
また、「扶桑鶴」(桑原酒場)も島根の辛口を代表する一本。こちらもなかなか締まった辛さがあり、燗冷ましなどで飲むと上品さが際立ちます。日本酒通の方々に愛されています。
そして東出雲にある王祿酒造。なかでも「渓(けい)」は、蔵の酒質方針であるジューシーさと厚みを持ちながら、ドライでシャープな一面も併せ持つ、複雑で奥深い味わいが楽しめます。様々な要素が詰め込まれたこのお酒は、島根の辛口日本酒の中でも特に注目すべき一本と言えるでしょう。
島根の日本酒で有名な銘柄をご紹介
島根の日本酒を語る上で外せないのが「王祿(おうろく)」(王祿酒造)です。この蔵元は、−5℃厳守を条件に出荷するなど、品質管理も徹底し、こだわっています。低温でフレッシュさを保ちながら、適切な状態まで熟成させる技術は、まさに職人技。「王祿」「渓」のほか、「丈径(たけみち)」という密度感のある逸品もあり、どれを選んでも間違いありません。
出雲エリアからは、板倉酒造の「天穏」も見逃せません。杜氏の小島達也氏は連綿と続く出雲杜氏の継承者の一人で、神話や文化人類学にも造詣が深い方。“神前に捧げられるような、清らかで穏やかなお酒”を目指して造られるこの銘柄は、まさに出雲の地にふさわしい一本です。
同じく出雲の商店街に蔵を持つ「十旭日(じゅうじあさひ)」(旭日酒造)は、味わいに膨らみと太さがあり、熟成させることでじわじわと広がる旨味が楽しめます。熟成酒好きの方や、燗酒として楽しみたい方には特におすすめです。
このほかにも、「簸上正宗(ひかみまさむね)」(簸上清酒)など、島根には魅力的な銘柄が数多く存在しています。
島根の日本酒でレアな逸品を見つける楽しみ
日本酒の楽しみの一つは、なかなか手に入らないレアな銘柄との出合いです。島根の日本酒では、板倉酒造の限定シリーズ「無窮天穏 SAGA(むきゅうてんおん サーガ)」が特に注目に値します。これは、山陰吟醸の技術継承のプロジェクトとして、小島杜氏が師と仰ぐ二人の名杜氏の味わいを再現しようという野心的な試み。様々なアプローチで「物語」を紡いでいます。
また、板倉酒造では日本酒だけでなく、蜂蜜の醸造酒「いとなみミード」も製造しています。世界最古のお酒とも言われるミードを、日本酒蔵の技術で仕上げた逸品は、一飲の価値があります。
「王祿」も、マイナス5度の保管環境を持つ限られた酒販店でしか扱われていないため、ある意味でレアな存在。さらに季節限定品や、「丈径」の熟成酒となると、入手困難度はさらに上がります。こうした希少な銘柄を探す楽しみも、日本酒の醍醐味の一つと言えるでしょう。

島根の日本酒「死神」という異色の銘柄
島根の日本酒の中でも、異彩を放つのが加茂福酒造の「死神」です。その衝撃的な名前とは裏腹に、年間わずか60石(一升瓶換算で約6000本)しか生産されない希少な銘柄として、日本酒ファンの間で話題になっています。
「死神」というネーミングは確かにインパクトがありますが、それゆえに記憶に残りやすく、話題性も抜群。さらにレアなのが「死神の裏ラベル」と呼ばれる限定品で、これは本当にタイミングが合わないと巡り合えない幻の一本です。
名前の奇抜さに目を奪われがちですが、加茂福酒造は真摯に酒造りに取り組む酒蔵。「死神」も決して話題性だけの商品ではなく、しっかりとした味わいを持つ日本酒として評価されています。
まとめ
島根県の日本酒は、神話の時代より続く土地で職人たちが造る、質の高い銘酒揃いです。ドライでシャープな辛口から、熟成による深みのある味わいまで、バリエーション豊かなラインナップが楽しめます。
出雲大社への参拝の際には、ぜひ地元の日本酒も味わってみてください。神話の国で育まれた日本酒を、燗にして一杯。古代から続く神事と酒造りの繋がりに思いを馳せながら味わう一献は、きっと特別な体験となることでしょう。
初心者の方も、若干入手難易度は高めではありますが、まずは「王祿」や「天穏」から始めて、徐々に「死神」のようなユニークな銘柄に挑戦してみるのも面白いかもしれません。島根の日本酒との出合いが、あなたの日本酒ライフをより豊かなものにしてくれることを願っています。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。
構成/土田貴史