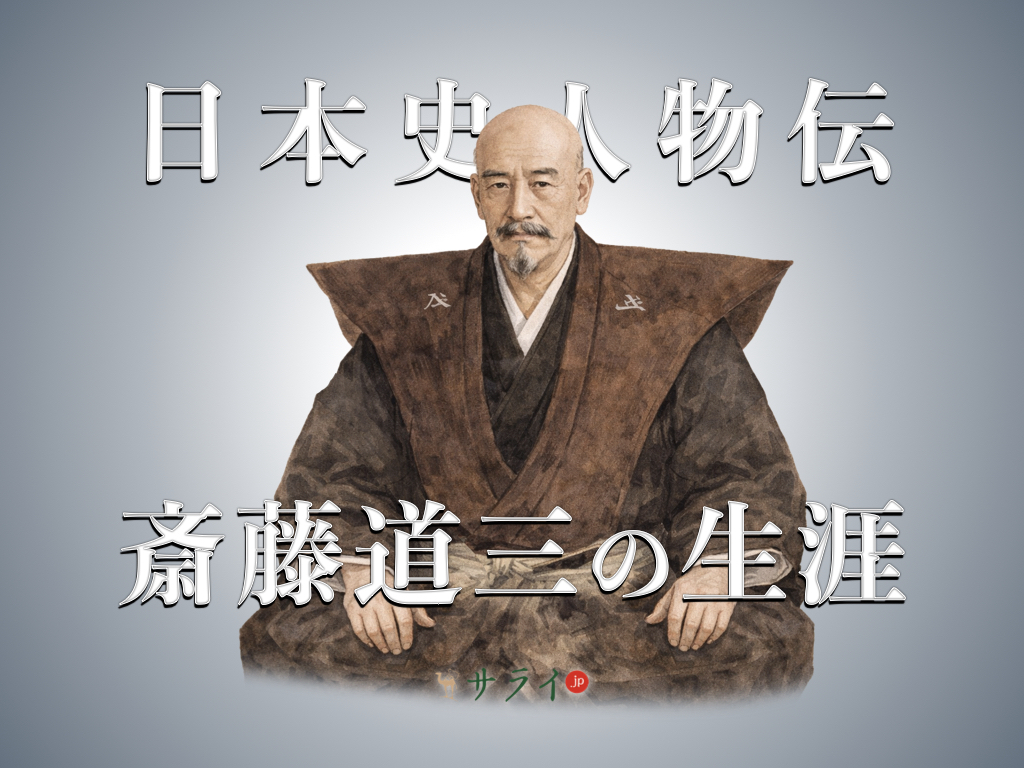日本文化と切っても切れない存在の日本酒。中でも、京都は奈良に次いで日本酒の歴史が深く、実は生産量では兵庫に次ぐ上位を誇る「酒どころ」なのです。「日本酒の歴史=京都の歴史」と言われるほど、日本酒と京都は深い関わりを持っています。そこで今回は、京都の日本酒の魅力をご紹介していきます。
文/山内祐治
目次
京都が誇る日本酒の聖地、伏見
京都の日本酒おすすめ銘柄。伏見の銘酒を知る
多彩な魅力を持つ京都の日本酒、酒蔵巡り
フルーティーな香りを楽しむ京都の日本酒
伏見が誇る日本酒の代表銘柄「玉乃光」
京都でしか買えないお酒。蔵元直売の限定酒を求めて
まとめ。日本酒文化を感じる京都の旅のススメ
京都が誇る日本酒の聖地、伏見
京都の日本酒を語る上で、伏見は欠かせない地域です。現在、京都には53ほどの酒蔵がありますが(令和4年調べ)、その多くが伏見に集中しており、伏見酒造組合にはおよそ20蔵が属しています。明治時代の御一新の折、伏見の空いた大名屋敷などの広い土地に、多くの酒蔵が居を移したと言われています(月桂冠大蔵資料館などで確認できます)。
また伏見のお酒の美味しさを支えている水として注目したいのが京都特有の「御香水(ごこうすい)」です。この名称は清和天皇が命名したと伝えられ、病人がこの水を飲んで回復したことから「御香水」になったという伝説があります(※明治時代に枯れてしまったものの、昭和57年に復元させたそうです)。
日本酒の世界では、兵庫の「宮水(みやみず)」が有名ですが、京都の「御香水」はそれよりやや柔らかい“中硬水”であることが特徴です。
昔の日本酒造りではミネラルが必要でしたが、兵庫の水が硬いのに対し、京都の水はやや柔らかいため、京都のお酒は比較的まろやかな味わいに仕上がりやすいのです。(※伏見各地で湧き出る水には個々に特色があります)。
京都には酒の神様として知られる松尾大社もあり、日本酒文化の要所としての歴史を今に伝えています。
京都の日本酒おすすめ銘柄。伏見の銘酒を知る
京都には数多くの銘酒があります。まず注目したいのは伏見を代表する銘柄、「月桂冠」です。伏見の立役者であるとともに、明治期に明治屋と組んで瓶詰めのお酒を世に広めたことでも有名です。月桂冠の研究所は、これまで様々な酵母、麹に関する研究を進めています。
また比較的規模感の小さい蔵のなかで挙げられるのが「神蔵(かぐら)」です。松井酒造が手掛けるこの銘柄は、華やかな香りが特徴で、美しいボトルデザインも魅力のひとつ。栓がパキンと開く高級な仕様もあり、見た目の楽しさも備えています。蔵人の意気込みが伝わってくる、質の高いお酒です。
また、「日日(にちにち)」も注目です。「日日」は澤屋まつもとを離れた松本日出彦さんが手掛ける銘柄です。爽やかな柑橘系の香りと、厳選された米の力強さが絶妙なバランスを生み出し、洗練された味わいが特徴です。
隠れた銘酒としては「蒼空(そうくう)」も見逃せません。後味が柔らかく、落ち着いた雰囲気のあるお酒として親しまれています。

多彩な魅力を持つ京都の日本酒、酒蔵巡り
京都の酒蔵は、大きく分けてふたつのタイプがあります。伏見や洛中といった地域では、伝統的な京都らしさを持ちながらも比較的全国区で知られる銘柄が多く、その中でも独自性の高い小規模の蔵も育っています。
一方、丹後半島のお酒は非常に個性的で、“地酒”としての特徴が顕著です。特に注目したいのは向井酒造の「京の春(きょうのはる)」「伊根満開(いねまんかい)」。なかでも「伊根満開」は、赤米を使用した珍しいお酒で、ベリー系の香りという他の日本酒にはない特徴を持っています。
さらに興味深いところでは、月桂冠グループ会社の松山酒造が2023年に再出発した「十石(じっこく)」という銘柄や、濁り酒を最初に世に出した「月の桂」、そして「玉川」「アイスブレーカー」も人気を集めています。
京都の魅力は、「月桂冠」のような全国区のブランドから、「アイスブレーカー」や「伊根満開」のようなマニア受けする製品など、幅広い日本酒が楽しめる点にあります。
フルーティーな香りを楽しむ京都の日本酒
京都の日本酒は、そのフルーティーな香りでも注目されています。フルーティーさといえば真っ先に思い浮かぶのは「神蔵」でしょう。リンゴやラ・フランスの香りを持つカプロン酸エチルという成分が特徴的に感じられ、華やかな香りを楽しめます。
柑橘系の爽やかさを求めるなら、「澤屋まつもと」や「日日」がおすすめです。これらを飲み比べると、フルーティーさのなかでも、その違いが明確に感じられるでしょう。
一方、「伊根満開」は少し異なるタイプのフルーティーさを持っています。一般的な日本酒が持つ柑橘やリンゴ系の香りではなく、甘さと渋みを伴うベリー系の香りが特徴です。カシスを思わせるニュアンスもあり、温めるとホットワインのような印象になる面白さもあります。
伏見が誇る日本酒の代表銘柄「玉乃光」
「玉乃光」は伏見を代表する銘柄の一つで、京都のお土産としても人気があります。京都駅などでもよく見かけるため、京都のお酒と聞いて真っ先に思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
「玉乃光」の特徴は純米酒の復活と、酒米「雄町」との深い関わりです。雄町は元々、岡山県赤磐(あかいわ)地方で栽培されていたお米ですが、一時期は限られた地域でしか作られず、生産量が減少していました。この貴重な米の復活に大きく貢献したのが玉乃光酒造です。そのため、「玉乃光」と雄町は切っても切れない関係にあり、岡山県原産の酒米ながら、京都の地酒を引き立てる役割を担っています。
京都でしか買えないお酒。蔵元直売の限定酒を求めて
“京都でしか買えないお酒”を探すなら、酒蔵見学がおすすめです。月桂冠の大蔵記念館や玉乃光、黄桜(きざくら)といった大手蔵元を訪れると、その場所でしか、あるいはその時期にしか購入できない限定酒に出合えることがあります。
特に「生酒」や「しぼりたて」と呼ばれる季節限定のお酒は、特約店でも手に入りにくい場合が多く、蔵元でしか味わえない貴重な体験となります。また、京都の酒米「祝」(今後は祝2号へ)を使ったものや京都市産技研が開発した京都酵母(例として京の華、京の咲)を使ったものも注目です。実際に蔵を見学し、その場で日本酒を味わい、お気に入りを見つけてお土産に持ち帰るという体験は、日本酒ファンにとって格別の楽しみです。
京都を訪れた際には、ぜひ蔵見学を予定に入れてみてはいかがでしょうか。
まとめ。日本酒文化を感じる京都の旅のススメ
京都は歴史ある観光地として名高く、日本酒という側面が埋もれがちですが、実は京都と日本酒の結びつきは非常に強いものがあります。
酒造りの神として知られる松尾大社を訪れると、お酒を飲む人、造る人、売る人など、それぞれのための特別なお守りが用意されています。また、全国各地から奉納された酒樽を見るのも一興です。さらには北野天満宮も日本酒の麹に縁の深い場所です。
京都を訪れる際には、有名な観光スポットだけでなく、これらの酒にまつわる場所も巡ってみてください。京都のお酒への理解がより深まり、新たな京都の魅力を発見することができるでしょう。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。
構成/土田貴史