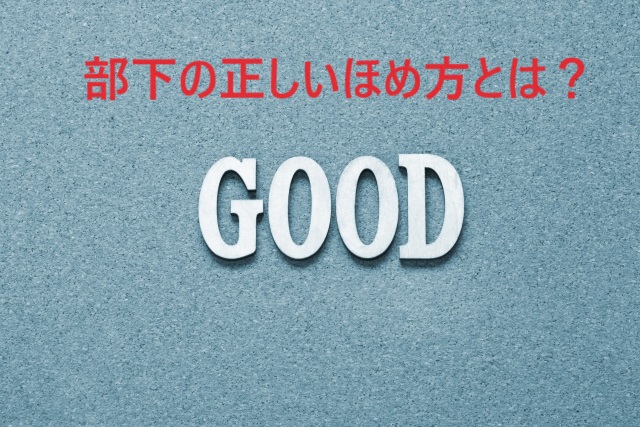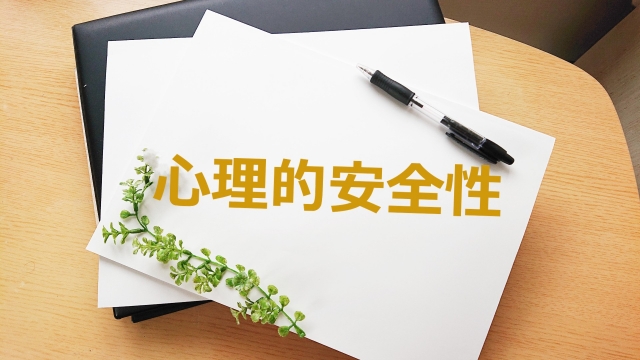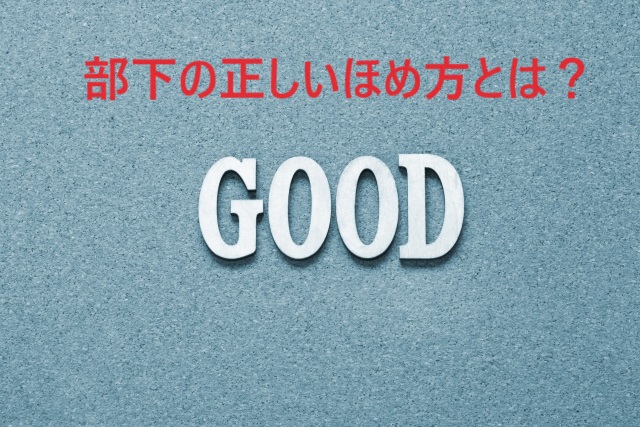
マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の問題を解説するシリーズ。部下を育成するためには、正しいほめ方があると言います。今回は、部下のほめ方について考察します。
「ほめる」という行為は、つい管理職がやってしまいがちな方法です。ですが、特に部下の経過(頑張る姿勢)をほめるという行為は、部下の経過視点を生み出します。経過視点とは、頑張ること自体を重視して自分を良く見せることに注力することを指します。
部下が経過視点になればなるほど、結果がないがしろにされるリスクが起こり、部下が正しく動かなくなってしまうのです。
・自分の頑張る姿をよく見せることに意識が向いてしまう
・結果を出すことよりも自分を良く見せる報告が中心になる
・頑張る姿をアピールしていれば評価されると勘違いする
安易にほめれば、部下の上記のような結末を引き起こしてしまうことでしょう。
今回はほめるポイントと経過視点が生み出す弊害についてお伝えします。
「ほめる」とはそもそも何を意味するのか
まず、ほめるとはどういうことでしょうか。親が子をほめる、上司が部下をほめるというように「その人のしたことや行いをすぐれていると評価する」ことを表します。
仕事において評価をするポイントはどこでしょうか。任せた仕事をやり遂げた時、期待以上の成果を上げた時に評価をすべきです。つまり、やみくもにほめればよいということではありません。
「ほめられて伸びる」人も多いと思いますが、当たり前のことをただやっただけなのに必要以上にほめてしまうと、その人の基準がどんどん下がることになります。
「ほめる」ことによるメリットとデメリット
メリットは承認欲求が満たされることです。自分の行いが誰かに評価された、認められたと感じる場面です。承認欲求が満たされることで達成感や充実感を得るでしょう。
デメリットは先ほども記載した通りで、単純なことをやっただけなのにほめてしまうことで当たり前の基準が下がったり、結果が出ていないのに頑張る姿勢をほめてしまい、部下がアピール上手になってしまうことです。
つまり、ほめること自体を否定しているわけではなく、メリットとデメリットを理解したうえでほめるという行為をしましょう。
頑張る姿勢をほめることによる危険性とは?
よく経過で評価すべきか、結果で評価すべきか、という話を耳にします。経過で評価するとは、結果に向かうための途中段階であり、まさに結果を出す為に頑張っている取り組み姿勢を指します。
頑張った果てに結果が出たのであれば、経過も含めてほめても問題はありません。しかし、結果に繋ながらなかったのであればほめてはいけません。結果が出ていない以上、取り組み方を変えなければいけないからです。それなのに、経過をほめてしまったことで、その人が満足してしまう危険性や、今後は「経過を良く見せる」、つまり頑張る姿をアピールすることに目を向けてしまいます。
営業職の例で説明します。商品Aを買ってもらうことを「結果が出た」とした際に、経過は「商品Aは買ってもらえなかったが、うまく説明はできた」や「商品Aは買ってもらえなかったが、お客様の反応は良かった」ということです。
いかがでしょうか。商品Aは買ってもらえなかったにもかかわらず、うまく説明できたことや、お客様の反応は良かったことをほめても良いでしょうか。
もし、経過(頑張った姿勢)をほめてしまっては、その部下は次回からは頑張ったことをアピールしてくるに違いないでしょう。その際に考えられる上司への報告としては「商品Aは売れませんでしたが、○○を頑張りました」や「商品Aを売るためにこのような準備をして臨みました」などの内容になるでしょう。
ですが給与はどうなるでしょうか。自分は、結果は出なかったが評価されるべき人間だと彼は思うでしょう。しかし、会社の給与は営業マンの結果から支払われますから、当然賃上げは難しくなることでしょう。これが結果として「頑張っても給与が上がらない組織」を生み出してしまう元凶になる畏れもあります。
結果に到達できない部下や新人のほめ方は?
結果が出なかったのでほめない。これも1つの意思決定です。しかし、なかなか結果が出ない部下や、新人に対してもほめないことを続けていると、心が折れてしまう人も出てくるでしょう。では、どのようにほめればよいでしょうか?
まずは結果を出すための途中のゴールを設定しましょう。先ほどの営業の例でお伝えします。商品Aを買ってもらうことが結果だとすると、途中のゴールは「商品Aの説明はマニュアル通りにできた」や「商品Aを買ってもらえない明確な理由を聞くことができた」になります。もちろん結果が出ていないので100%ほめることはできませんが、途中のゴールまで到達できたのであれば、途中のゴールに到達したことはほめましょう。
ただし、先述したように商品Aを買ってもらうことが最終的な結果ですので、途中のゴールに到達しただけで満足させてはいけません。さらに言うと、途中のゴールに到達したことを給料や待遇にかかわる評価としてはいけません。
ポイントは、簡単な目標を途中のゴールとして定め、それをクリアしたときにほめるという承認欲求を与えることで、小さな成功体験を積ませることです。そして、その成功体験を繰り返し行い、最終的な結果に向かわせることが重要です。
経過をほめることは部下を不平等に扱うことと同じ
部下の経過(頑張る姿勢)をほめたり評価することは、実は部下を不平等に扱っていることと同じです。なぜなら、頑張り度合は人によって感じ方が違います。その人の頑張りをほめるということは上司の感情、つまり好き嫌いが必ず入ります。
もし、自分よりも結果が出ていないにもかかわらず、上司からほめられている人を見た際には、結果を出している人はどう思うでしょうか。中には「結果を出すことよりも、上司に頑張る姿勢を見せることの方が大事だ」となる可能性が高まります。そうなると、頑張る姿勢をアピールする集団となり、その会社やチームは結果を出すことに注力しなくなってしまいます。
部下を平等に扱うためにも「事実である結果をほめる」ことを忘れてはいけません。
まとめ
ほめることは重要ですが、安易にほめることのデメリットもご理解いただけたのではないでしょうか。仮に部下が「私はほめられて伸びるタイプです」と言ってきたとしても、安易にほめてはいけません。ほめるポイントは「結果や目標に到達した時」です。
もしも、
・自分の頑張る姿をよく見せることに意識が向いてしまう
・結果を出すことよりも自分を良く見せる報告が中心になる
・頑張る姿をアピールしていれば評価されると勘違いする
が実際に起きているのであれば要注意です。まずは、ほめるポイントから変えていきましょう。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/