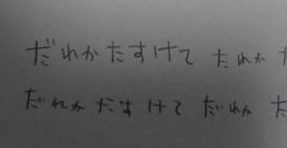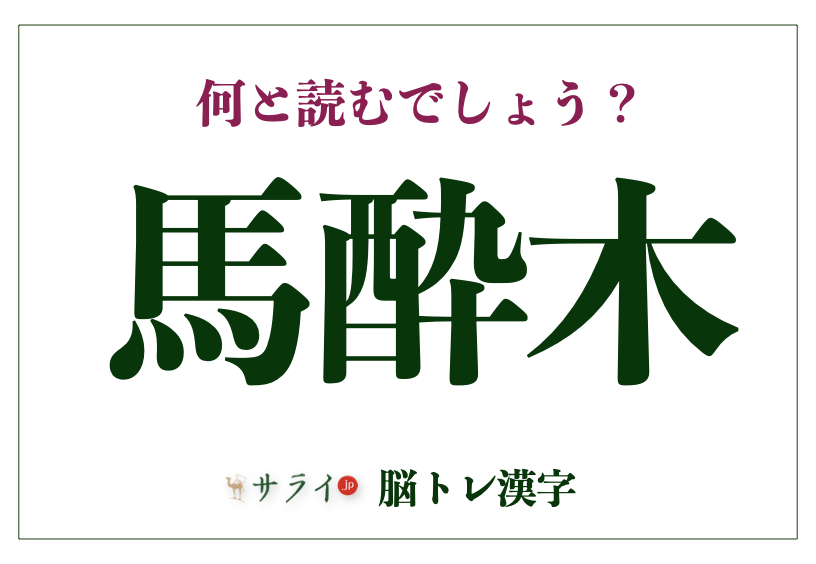取材・文/ふじのあやこ

家族との関係を娘目線で振り返る本連載。幼少期、思春期を経て、親に感じていた気持ちを探ります。(~その1~はコチラ)
今回お話を伺ったのは、静岡県で子育てを支援する地域活動などを行っている麻友さん(仮名・34歳)。静岡県出身で、両親と1歳下に妹のいる4人家族。子供を押さえつけることが親の務めだと思い込んでいた両親から、やや歪んだ愛情を受け続けていました。
「何かやりたいことがあっても、絶対に一度は反対される。それがたとえ勉強のことだったとしても、やりたいことの本気度を何度も反対され続けることで試されていました。父親に『本気でやりたいなら、お前の誠意を見せてみろ』と言われ、土下座でお願いしたこともあります。でも、何があっても子供のことを最優先してくれる両親だった。子供の頃に寂しいと思ったことは一度もなかったですから」
何に対しても一生懸命な父。遊ぶことにも手を抜くことは許されなかった
「子供との時間を最優先してくれた」とお話を伺っている最中によく口にしていた麻友さん。その愛情を実感できていたエピソードがあるとのこと。
「親に勧められて始めた習い事がたくさんあって、そのひとつにバスケットボールがありました。習っていたバスケットボールチームは、さまざまなところで試合をする機会が多かったんですが、試合の日には毎回必ず両親とも応援に来てくれていました。それに旅行も毎年ディズニーランドに連れて行ってくれて、『遊ぶ時は一生懸命遊べ』という父親の方針の下、乗りたいもの、食べたいものは全部かなえてくれていました。その時だけはどんなわがままでもかなえてくれるんです。父親の何に対しても全力で取り組むところは好きだったんですよね」
麻友さんは小さい頃から勉強ができたそうですが、高校卒業後は就職を選択します。それは両親の意向でした。
「塾を必要ないと言い切る両親だったので、どちらも勉強にはまったくの無関心。私の学校の成績を気にされたことも、勉強しなさいとか言われた記憶もまったく残っていません。周りも進学が多くて、私も大学に行きたかったんですが、当然のように卒業後は就職すると思っていた両親に反発することはできませんでした」
就職するまで反抗期もなく、一度も親に歯向かったことはなかったそうですが、なぜ我慢を続けていたのでしょうか。
「我慢、ではないんです。20歳前後になっても、それが普通のことだと思っていたから。両親はともに気分屋なところがあって、目を見て返事をしなかっただけで手をあげられることも日常茶飯事。門限を1分でも遅れただけでビンタをされて、そのまま家に入れてもらえないこともありました。今だったら虐待と問題になっていたレベルかも(苦笑)。でも、どんなに酷い行為を受けたとしても、それは私が悪いからなんだと思い込まされていたんですよね……」
【次ページに続きます】