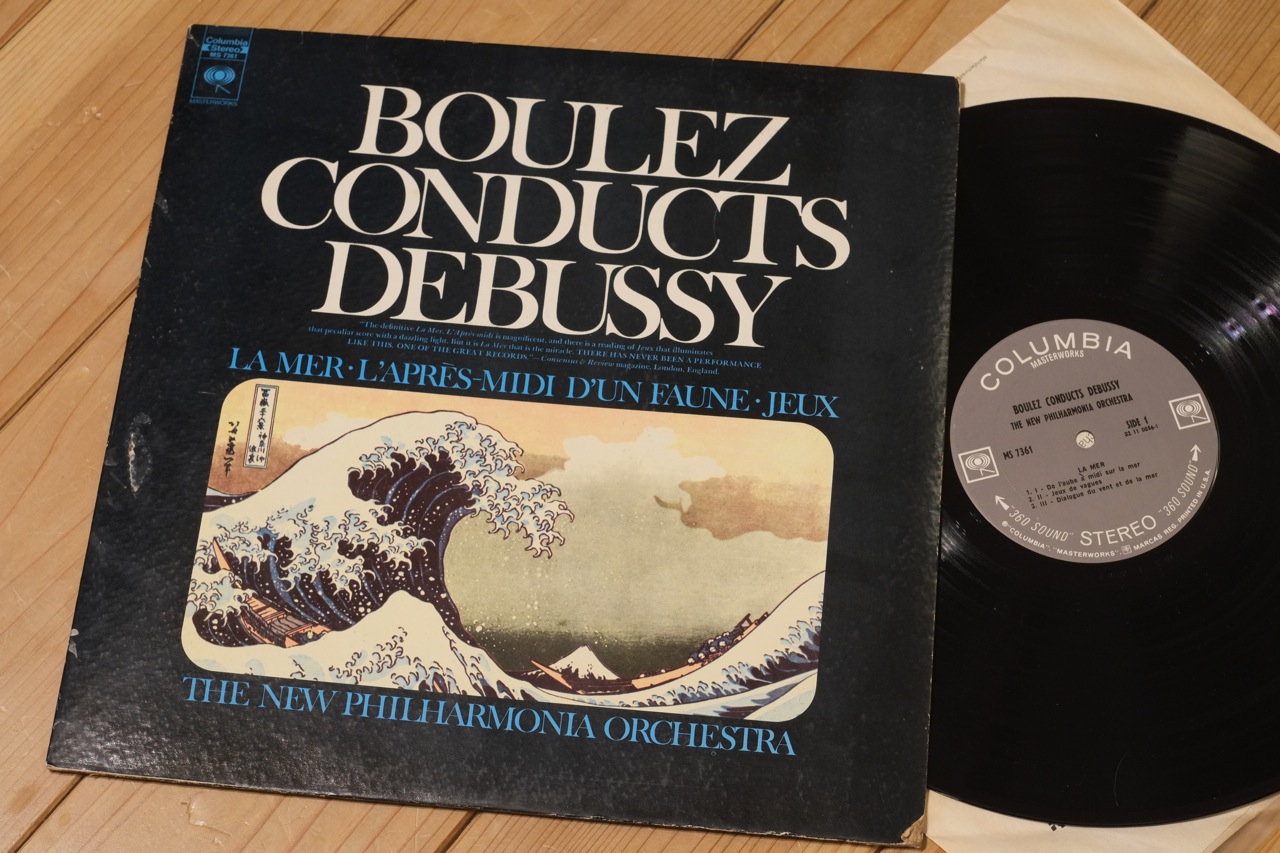取材・文・写真/小坂眞吾(『サライ』編集長)
「マカオに行ってきました」というと、必ず帰ってくる反応が「カジノですか?」というものだ。確かに、マカオのカジノの年間売上はラスベガスの7倍。世界一のカジノ集積地と言える。でもそのせいで、大切なものが見過ごされている。日本の扉が世界に向かって開かれた、16世紀の記憶だ。
たとえカジノがなくても、日本人にとってのマカオの魅力はいささかも減じない。大航海時代と、日本の戦国時代を念頭に、マカオを旅してきた。その模様を2回にわたってご紹介しよう(※前編はこちら)
* * *
前編では、マカオにおける東西文明の融合を歴史と建築から見てきたが、食べ物の方はどうなっているのか。
マカオの街には広東料理店も、ポルトガル料理店も多いが、どちらにしても海の幸をふんだんに使うのが特徴だ。前編で紹介したプリプリの海老雲呑もそうだし、ポルトガル料理には尾頭付きのイワシのグリルやタコのボイル、マリネがあり、日本人の舌によく合う。さらに、中国の影響を受けて本国とは異なる発展を遂げたメニューも多い。
その土地の食文化を知るには、市場を訪ねるに限る。というわけで、魚介、肉、野菜の全てを扱うマカオ随一の市場、半島北部の『紅街市』(ホンガイスィー)を訪ねた。

ラザロ地区にあるポルトガル料理店『アルベルグ1601』のタコ料理。赤ワインでボイルした後、グリルで皮と吸盤をカリッと焼き上げる。ワインで煮ることで柔らかくなるという。適度な歯ごたえがあり、噛むほどに甘みが出る。
耕作地のほとんどないマカオでは、野菜と肉類はほぼ中国本土に頼る。だが牛、豚は生きたまま輸入して半島北部で処理するので、新鮮この上ない(鶏インフルエンザへの懸念から、生きた鶏の搬入は停止中)。
そして魚介は毎日、マカオの港に直接水揚げされ、市場では活魚も売られている。朝から開いているが、夕方には夕食のおかずを買いに来る地元の人々で賑わう。雰囲気としては、沖縄の牧志市場に似ている。
売られているのは大小の活エビ類、ワタリガニ、アサリ、ハマグリ、マテ貝、魚ではハタ類、アマダイ、イトヨリ、舌ビラメ、サバ、クロダイの仲間、フエダイ類、ハモ、ウナギ、タチウオ等。実に多種多様だが、日本でもお馴染みのものが多く、すぐに鮨店や割烹が開けそうな品揃えだ。
もっとも高値がつくのはハタ類で、活魚ならさらに倍の値になる。

紅街市の鮮魚売場にて。左上は南方系のクロダイ、左下はフエダイの仲間。いずれも汽水域に生息するので、マカオの目の前の珠江河口部で獲れたものだろう。底の方にいる茶のブチがハタ類。
隣国のフィリピンでも、ハタは「魚の王様」と呼ばれて珍重される。沖縄でもハタは「ミーバイ」と呼ばれて喜ばれている。さらに福岡のクエ、北陸や瀬戸内のアコウ(キジハタ)も、最高の魚として食されている。
南シナ海から東シナ海を経て、対馬暖流が流れ込む日本海まで、「ハタ文化圏」が帯状に連なっているという見方もできるわけで、マカオと日本のつながりがまたひとつ、発見できた気がした。

いかにも旨そうなワタリガニ(ガザミ)。これをターメリックとココナッツミルクで炒めた「カレー蟹」もマカオの名物なのだが、今回は食べ損ねた。
大航海時代の記憶がスパイス
マカオには大航海時代以降、多くのポルトガル人がやってきた。宣教師や修道士、商人はもちろん、船の乗組員もたくさんいただろう。その一部はマカオに棲みつき、家庭を築き、骨を埋めた。
ポルトガル人の血を引きつつ、代々マカオに土着して暮らす人々を「マカエンセ」(マカニーズ)と呼ぶ。マカオの人口のわずか1%に過ぎないが、彼らの暮らしこそ、中国でもポルトガルでもない、真のマカオスタイルだ。
それを舌で実感すべく、マカオ料理の『老地方』を訪ねた。新馬路のすぐ南側、かつての花街の町並みをそのまま残す福隆新街に、その店はある。間口は2間ほど。2階への階段は狭く急勾配で、娼妓宿の造りそのままだ。
インテリアも至って簡素で、マカエンセの家庭をしのばせる。オーナーのアンナさんは、マカエンセの家庭料理をそのまま供することを旨としている。

花街の面影をそっくり残す福隆新街。今はレストランや土産物店が店子となり、夜まで賑わう。奥に見えるホテルは『ソフィテル・マカオ・アット・ポンテ16』。セナド広場まで徒歩10分ほどという立地で、世界遺産巡りの拠点におすすめ。
マカエンセの家庭料理とはいかなるものか? そのわかりやすい例が「ポルトガルチキン」だ。鶏肉とジャガイモのグラタンのような料理だが、ターメリックやココナッツミルクでカレー風味に味付けされている。その料理名に相違して、ポルトガルにこんな料理はない。
ターメリックはインドの香辛料、ココナッツはココヤシの実で東南アジア原産だ。鶏肉を使うのも、航海途上で立ち寄ったアフリカ沿岸の食習慣を取り入れたものだろう。ポルトガル本国では、肉といえば豚肉が主体だ。
リスボンからアフリカを廻ってインドのゴア、マレー半島のマラッカを経てマカオに至る、大航海時代のポルトガル人の足跡が、このひと皿に象徴されているのである。

『老地方』のポルトガルチキン。マカオ料理ではアフリカンチキンという辛みの強い鶏料理が有名だが、それに比べるとマイルドでクリーミー。
マカオ料理のもうひとつの特徴が、保存食を多く使うこと。それがよく表れているのが「バカリャウのコロッケ」だ。バカリャウはポルトガル語でタラのこと。塩蔵のタラを塩抜きし、ジャガイモと混ぜて揚げたもので、タラの旨みが凝縮している。個人的には、生のタラは大味であまり好きでなく、タラチリ鍋なども進んでは食べないのだが、このコロッケは抜群に美味い。
ポルトガルは大西洋に面しており、北洋でのタラ漁は重要な産業だった。冷蔵庫などない時代だから、タラの身は塩漬けにして保存した。本国の定番料理にはバカリャウのグラタンがあり、マカオのポルトガル料理店でも代表的なメニューとなっている。
マカオは南国だから、タラは獲れない。にもかかわらず、バカリャウ料理がマカオにあるのは、これまた大航海時代の記憶である。

バカリャウのコロッケ。干しダラの身の繊維が独特の食感を生む。自分でも作りたいと思う絶品。ただし、塩蔵タラの塩の抜き加減がすごく難しいらしい。
リスボンを出航してマカオに至るには、年単位の歳月を要する。船には日持ちするタンパク源として、塩蔵のタラが大量に積み込まれた。さらに壊血病を予防するビタミン源として、ジャガイモなどの根菜類が重宝される。
そもそもジャガイモ自体が南米原産で、大航海時代にスペインによってヨーロッパにもたらされたものだ。日本での「ジャガイモ」という呼称は、オランダによって東南アジアのジャカルタから持ち込まれ「ジャガタライモ」と呼ばれたのが語源だという。
想像してみよう。タラとジャガイモを積んでリスボンを出航した船は、アフリカで鶏を仕入れ、ゴアで胡椒やターメリックを仕入れ、マラッカで丁子やシナモンを仕入れ、飲み水としてココナッツを積み込み、さらにはそれぞれの港で乗組員を雇ったのだろう。船の上では、さまざまな言語が飛び交ったに違いない。
ポルトガル本国に由来するタラと根菜類に、アジアのスパイスとココナッツミルク、さらに南シナ海の新鮮な魚介類を加えて、マカオ料理は成立した。東洋と西洋の単純な融合では捉えられない、真のクレオール(混淆)料理なのだ。

セナド広場の近く、世界遺産に登録されている中国人実業家の東西折衷邸宅「盧家屋敷」の向かいにあるおでん屋。魚介や鶏の団子を注文ごとに茹でて供するのだが、スープはなく、代わりに牛だし、カレー、ホットチリ(辛い!)の3種のソースをかける。これも大航海時代の味だ。
ユネスコは、この世界に類のない食文化を、後世に引き継ぐべきものと認め、2017年、マカオを食文化創造都市ネットワークに加えた。日本では唯一、鶴岡市(山形県)が選ばれていて、両都市の交流も始まっている。
お土産は中国茶か香辛料を
さて、仕事とはいえ、海外へ行ったからにはお土産が必要だ。機内預けにできて軽いものといえば、マカオではお茶か香辛料である。
現地コーディネーターに案内してもらったのは、セナド広場からも近い「十月初五日街」にある『英記茶荘』。1934年創業、マカオでは最古の老舗である。値段は少々高いが、品質は間違いないという。茶葉の香りを確かめてから購入できる。
私が求めたのは「清香鉄観音」150g80パタカ(約1200円)と「龍珠花茶」(ジャスミンティー)150g92パタカ(約1400円)。清香鉄観音は発酵を抑えた緑茶に近い色合いで、味は出にくいが香りが素晴らしい。龍珠花茶も香りの高さが特筆ものだ。
普段はコーヒー党でお茶はほとんど飲まないのだが、マカオ渡航以来、中国茶の香りにハマっている。

帰国して清香鉄観音をいただく。香りは高く、渋みは少なく、ほのかに甘い。日本の緑茶と、強く焙煎した烏龍茶の中間の味わいで、台湾の清茶に似ている。
私のように、エスニック料理を自分で作るという奇特な人には、香辛料を買って帰るのをぜひおすすめしたい。今や日本でもたいていの香辛料は手に入るのだが、小袋に入って割高感は否めない。
私が買ったのはターメリックとホールの花椒(ホワジャオ)。ターメリックはカレーを作るとき大量に使うので300g買ったが、値段は25パタカ、たった400円弱である。花椒は300gで53パタカ(約800円)。これで1年間は、四川風麻婆豆腐が作り放題だろう。

家族への、というより自分へのお土産に買った香辛料。上が花椒、下がターメリック。右は中国の乾燥唐辛子で、四川料理用にスーパーで購入。75g10パタカ(約140円)と安価だったが、辛みは強くなくやや期待外れ。
いずれもコーディネーターの案内で、観光客が行かない東南アジアの食材店(広東語しか通じない)で求めたものだが、スーパーマーケットに行けば、小分けにはされているが、日本よりはるかに安く香辛料が買える。
漢字で「超級市場」と看板が出ているのがスーパーマーケット。サーディンやバカリャウのお洒落な缶詰も売っていて、こちらもお土産に向く。
* * *
以上、2回にわたって私の初めてのマカオ旅の模様をご紹介した。これからマカオを旅してみようと考えている方に、少しでも参考にしていただければ幸いである。
景観にせよ食べ物にせよ、ポルトガルと中国、インドや東南アジア、各地の文化がランダムに入り混じったカオスがマカオの魅力だ。こんな街は、世界広しといえども、どこにもないのではなかろうか。
一度では全然足りない。何度でも訪ねたい街である。
※あわせて拙稿「知ればもっと楽しめる!マカオ旅行に行く前に知っておきたい歴史的背景」のほうもぜひご覧ください。
取材・文・写真/小坂眞吾(『サライ』編集長)