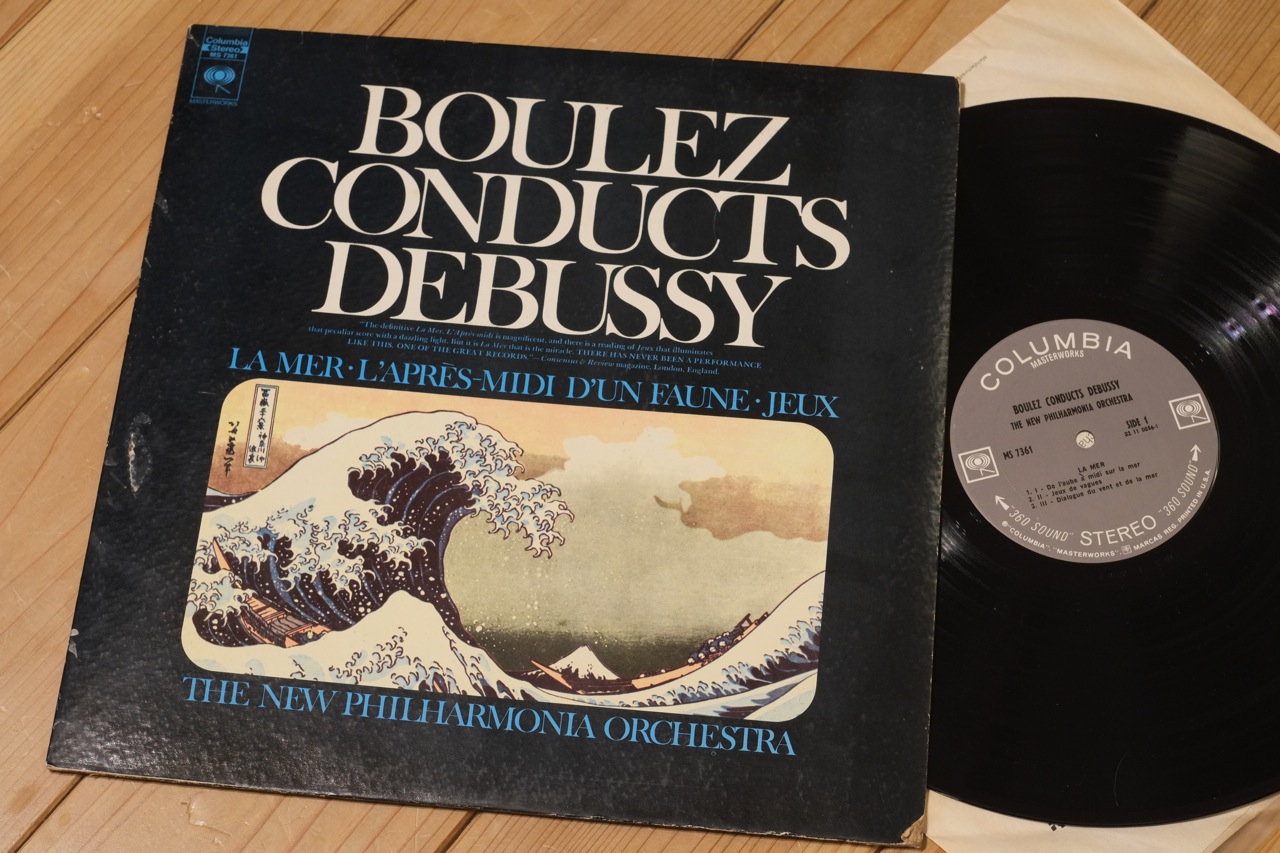取材・文・写真/小坂眞吾(『サライ』編集長)
別の記事でもお伝えしているように、初めてマカオを旅してきた。世間的にはマカオといえばカジノと相場が決まっているようだが、じつは大航海時代や日本の戦国時代にもつながる興味深い歴史の舞台でもあり、その背景を知っているだけで、マカオという地を何倍も楽しみ味わうことができるのだ。
そこで今回は、歴史や文化への関心が高いであろうサライ読者を念頭に、マカオ旅行に出かけるなら事前に頭に入れておきたい歴史的な背景について、まとめてご紹介しよう。

マンションが林立する狭い街路から、世界遺産・聖ポール天主堂跡のファサードを仰ぐ。マカオを象徴する風景。
幕開けは大航海時代から
1492年、コロンブスが新大陸を発見して「大航海時代」が本格的に幕を開けた。それまで世界の辺境だったヨーロッパが一躍、世界史の海に漕ぎ出す。日本は応仁の乱のあとで、戦国時代に突入していた。
彼らの当初の目的は、香辛料の流通を自分たちの手で押さえることだった。当時のヨーロッパは「香辛料バブル」で、胡椒や丁子に高値が付いていた。肉の臭み消しに重宝された説が知られているが、丁子は健胃剤としてももてはやされたらしい。香辛料をヨーロッパにもたらしていたのは、世界にネットワークを巡らすイスラム商人だった。
直接取引で中間マージンを省くのは、現代でもよくある発想だ。株式会社という法人のあり方も大航海時代に起源があるから(オランダ東インド会社)、資本主義とはこの時代に出来上がった、ヨーロッパ的な経済構造なのだろう。
ポルトガルが欲しかったのはあくまでも香辛料
大航海時代にいち早く名のりを上げたのは、レコンキスタによってイベリア半島からイスラム勢力を一掃したスペインとポルトガルだった。スペインはイタリア人のコロンブスに出資して1492年、西廻り航路で新大陸を発見。ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマは国王の国書を携え、喜望峰を越えて東へ向かい、1498年、インド西海岸に到達する。
これを機にポルトガルはゴアに拠点を置き、インド洋を舞台に香料貿易を始めるのだが、『サライ』本誌2018年8月号のサライ・インタビューに出ていただいた思想史家の渡辺京二さんによれば、ガマの喜望峰越えはちっとも画期的な事件ではなかったらしい。
「アフリカ回航航路は発見ですらなかった。イスラムの航海者はアフリカ南端を廻れば大西洋へ出ることをとっくに承知していた。(中略)新たな参入者のポルトガルは巨象にとまった虻にすぎなかった」(渡辺京二『バテレンの世紀』新潮社)

『バテレンの世紀』新潮社刊。本体3200円。渡辺京二さんは、幕末から明治初期に来日した外国人の残した文書から江戸期日本人の素顔を浮き彫りにした名著『逝きし世の面影』で知られる。
以下は『バテレンの世紀』の受け売りだが、イスラム商人が喜望峰航路を使わなかったのは、そんな危険を冒さなくても紅海や西アジアを通る安全な交易ルートがあったからだ。『サライ』がシンボルマークにしているラクダに乗った隊商(キャラバン)も、そのルートの一翼を担っていたことだろう。
しかも当時のインド洋〜南シナ海では、イスラム商人による交易ネットワークがすでに確立していた。彼らは国家に帰属せず、自前のルールで活動していた。
そんな世界だから、ポルトガル王の国書など役に立たない。見慣れぬ異邦人が本国から持ってきた交易品は、みすぼらしくて嘲笑されたらしいが、それでもやっとの思いで手に入れた胡椒の値段は、本国の10分の1以下だった。これは儲かる。
ポルトガルは香料貿易に注力し、胡椒の他に丁子(クローブ)やナツメグ、シナモンを求めてマレー半島のマラッカに進出。ついに丁子を産する島を探し当て、本国に持ち帰ると価格は360倍になったという。
中国には通用しなかったポルトガル艦隊
この後、ポルトガル商人は南シナ海へ進出し、中国との交易を図る。
南方で得た胡椒を、中国の生糸や絹製品と交換するのが目的だったが、当時の中国は明帝国で、海禁政策を取っていた。外国との私的交易を認めず、国民の海外渡航も禁ずる、事実上の鎖国である。

取材時は中国の中秋節が間近に迫り、地元の親子がランタンを探していた。ランタンは日本の提灯のようなものだが、近年はキャラクターものが席巻しているとか。
明と交易するには、形式的に明の属国となって「貢物」を取引するしかない。これがアジア圏独特の「冊封体制」による「朝貢貿易」だ。しかしポルトガルの場合、商人は国王の命を帯びており、王国の外交官のような立場でもある。その命はカトリックを広めるための布教と一体だから、たとえ形式的でも属国になるという発想はない。
ポルトガルは、明が朝貢貿易の指定港にしていた現在の広州市、珠江の河口部に至り、そこを拠点に皇帝との対等な国交を築こうとした。
珠江は雲南省に発して南シナ海に注ぐ2000kmの大河で、河口部の幅は60kmもある。この河口の東側が現在の香港であり、そして西側がマカオなのである。ポルトガル人がマカオに定住しはじめたのは1513年のことという。
日本は偶然「発見」された
ポルトガルの対等交易の目論見はしかし、明には通用しなかった。ゴアやマラッカは艦隊の武力で制圧できたが、中国の火器には敵わない。中国は近代のごく一時期を除けば、常に世界の先進国だった。
しかし、明が海禁政策を取ったがゆえに、密貿易はかえって盛んだった。ポルトガル商人は正面からの通商が無理と悟ると、沿岸部の海賊と組み、中国のジャンク船に乗り込んで密貿易を繰り返すうち、東シナ海の寧波の近くに拠点を得る。
寧波は古くは遣唐使の受け入れ港で、12世紀には栄西、13世紀には道元が渡って禅宗を学んでいる。室町時代には勘合貿易の拠点だったから、日本人も多く住んでいただろう。そこで初めて、ポルトガルは「日本」という国の存在を知ることになった。

マカオ半島中心部、セナド広場に面して立つ『聖ドミニコ教会』。外壁も内部もクリームイエローの美しい教会。1587年、メキシコのアカプルコからやってきたドミニコ会のスペイン人修道士が建てたものという。スペインは当時、マニラとアカプルコを結ぶ交易航路を確立していた。
ヨーロッパ人の日本到達について、マルコ・ポーロが記した「黄金の国」を目指した結果だというハナシがあるが、前出の渡辺京二さんは明確に否定する。その証拠のひとつに、ポルトガルがカリカット(インド西海岸)から広州に至るのに16年しかかかっていないのに、広州から日本へ来るのには20数年かかっていることを挙げる。
記録に残るポルトガル人の日本初上陸は、種子島への「漂着」。学校で習った1543年(異説あり)の「鉄砲伝来」である。ポルトガル人のマカオ定住から数えれば30年だ。
「彼らの眼中には日本はなかったのである。黄金の国ジパングに関するポーロの伝説的言説に、彼らはまったく関心を寄せていなかった」(渡辺京二/前掲書)
当時の日本は戦国時代。戦国大名は事実上の独立国であり、富国のために大陸との交易(や略奪)も盛んだった。東シナ海では「倭寇」(と言っても日本人の比率は低い)が猛威を奮い、戦闘力と情報収集力がモノをいう自由世界。ポルトガルはそのただ中で偶然、日本という島国を「発見」したのだった。
日本の国名は英語でJAPAN。これはマルコ・ポーロの『東方見聞録』に出てくる「ジパング」が語源とされているが、「日本」の広東語読みをポルトガル人が音写して、ヨーロッパに広まったという説もある。アルファベットを使う国で、日本と最初に接触したのがポルトガルなら、その方がむしろ自然だ。

屋台で見かけたワタリガニと海老。珠江河口と南シナ海に面したマカオでは、海鮮が豊富で美味い。
日本発見は、明との交易で成果を上げられないでいたポルトガル商人にとって大きな朗報となっただけでなく、世界地図を塗り替えるほどの衝撃を与えることになる。
日本の銀が世界を駆け巡る
当時の日本は世界有数の「銀」産出国となりつつあった。1528年に石見銀山(島根県)が発見され、精錬技術の革新もあって産出量が膨張。その領有を巡って大内、尼子、毛利が争い、秀吉の朝鮮出兵の原資にもなったという。けれども国内では金が重んじられ、銀の価値は国際的に見れば低かった。一方、中国では銀が不足していた。
日本と中国で、銀の相場が全く違う。ポルトガルはそこに商機を見出した。
折しも明の官船による倭寇の厳しい取り締まりがあり、密貿易が途絶えた日本と中国の間を、ポルトガルが仲介。中国で生糸や絹織物を買い付け、高値で日本に売る。対価としての銀を中国に持っていけば、前回よりはるかに多くの絹製品を買い付けられる。

セナド広場の向かいに立つ『民政総署』。1784年に建てられ、マカオの政庁として長らく機能してきた。壁に貼られた白地に鮮やかな青のタイル(アズレージョ)は、中国の景徳鎮や日本のイマリ(有田焼)への憧れの表れだ。
日本はもともと生糸の生産国ではなかったのか、と疑問に思われる方もいようが、国内で生糸の生産が盛んになるのは江戸時代、鎖国による貿易統制を受けてのことだ。それまでは京都の西陣織でも、中国からの輸入生糸を使っていた。
皇室による養蚕の儀式が毎年ニュースになり、古代から連綿と続いてきたような錯覚を受けるが、これは明治4年に復活したもの。開国直後の日本にとって、生糸は外貨獲得のもっとも重要な産品だった。東京の八王子と東神奈川を結ぶ現在のJR横浜線も、山間の生糸を横浜港から輸出するために敷かれた線路である。
中国のシルクと日本銀の交換。この繰り返しが日本銀の世界流通への扉を開き、16世紀半ば以降、世界の銀流通量の3分の1を日本銀が占めることになる。石見銀山が世界遺産に登録されたのは、ポルトガルのおかげとも言えるのである。
ポルトガルは1557年、マカオへの永久居留を明から認められ、日本との交易、及び布教に本腰を入れる体制が整った。

街中で見つけた「BECO DO MISSO」の標識。日本語にすれば「味噌通り」で、日本人とマカオのつながりをしのばせる。
以上、マカオ旅行に出かけるなら事前に頭に入れておきたい歴史的な背景についてご紹介した。ここまで拙文にお付き合いいただきありがとうございました。
実際にマカオに旅したくなったら、こちらから私のマカオ旅行記のほうもお目通しいただけると幸いです。
取材・文・写真/小坂眞吾(『サライ』編集長)