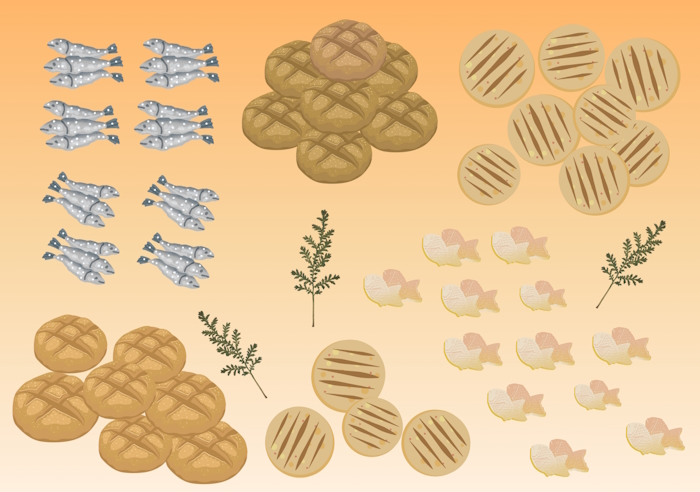文/矢島裕紀彦
今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「年を取ってから後の良人(おっと)と妻とは、美貌でもなく財産でもなく、その人たちの心情の美しさや誠実さを相互にどれだけ深く掬(く)み取ってきたか、と言う事になるのでは無いだろうか」
--石川達三
作家の石川達三は、明治38年(1905)秋田県横手町(現・横手市)に生まれた。早稲田大学英文科中退後、国民時論社勤務を経て、移民船でブラジルに渡航。この体験を基にした小説『蒼茫』で第1回の芥川賞を受賞した。
当時、国の主導で実施されていた海外移民政策は、東北地方の農民を中心とした貧困者の切り捨て策であり、移民ではなく棄民だというのが、この作品の主題であった。
石川達三は以降も、ダムの湖底に沈む村を描いた『日蔭の村』、日中戦争を現地視察して描き発禁処分となった『生きてゐる兵隊』など、社会問題に鋭いメスを入れる作品を描きつづけた。社会派作家といわれた所以である。『結婚の生態』『自分の穴の中で』など、男女関係や結婚問題をテーマとした作品でも知られた。
真面目で人に迷惑をかけるのは嫌い。原稿の締め切りは、一度も破ったことはなかった。だいたい1週間前には用意していた。その代わり、けっして安請け合いはしない。
石川家の玄関には椅子がひとつ置いてあり、一見来客のための椅子のようにも見えるが、それは違う。そこに石川達三が座って、「駄目なものは駄目です」と原稿依頼を断るための椅子だ。雑誌のゴシップ欄に、そんなふうに書かれたこともあった。
掲出のことばは、その石川達三が晩年に至って、夫婦というものについて、日記の中に書きつけた一文である。「心情の美しさや誠実さを相互にどれだけ深く掬み取ってきたか」とは、いかにもこの人らしい言い回しだろう。
石川達三はこんなふうにも書いている。
「私の結婚生活はほとんど五十年になり、私も妻も幸いに長命であったが、元々他人同志であった妻も良人も、今は何だか解からない一個になっている。(略)思うに男女とは、つながって飛んで行く二匹の蜻蛉のように偶然の関係であったと思うが、永いあいだにその偶然は必然となり、かけ替えの無いものとなる」
石川は1日「24時間勤務」で仕事に打ち込み、家事や子育て、家計のことなどは一切、代志子夫人に任せきりだった。自分の身に着けるものも、ネクタイから靴下まで、自分で買ったことはなかった。それどころか、外出するときには、夫人が着るものを順番に、下着、靴下、ワイシャツ、ズボン、ネクタイ、上着というふうに、端から着れば出来上がるようにベッドの上に並べた。一度、夫人がうっかり靴下を出しておくのを忘れたら、石川はモーニングにゴルフ用の靴下をはいて出かけようとしたこともあった。以来、靴下はズボンの裾に洗濯バサミで止めておくようになったという。
それだけ手がかかっても、夫人は苦にしなかった。インタビューに答えて、次のようなことばを残している。
「ふつうの方の結婚生活五十年とは、だいぶ違います。二十四時間勤務で、労働基準法違反だわ、なんてときどき申しましたけどね」
「五十年過ぎてみれば、それこそ退屈している暇がなかったということが、幸せだったと思います。ほかの道を知りませんので比較が出来ませんけど、張合いはあったと思います」
まさに夫唱婦随の歩みだったのであろう。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。
※「サライおみくじ」で今日の運勢をチェック!おみくじには「漱石と明治人のことば」からの選りすぐりの名言が表示されます。どの言葉が出てくるか、クリックしてお試しください。
↓↓↓