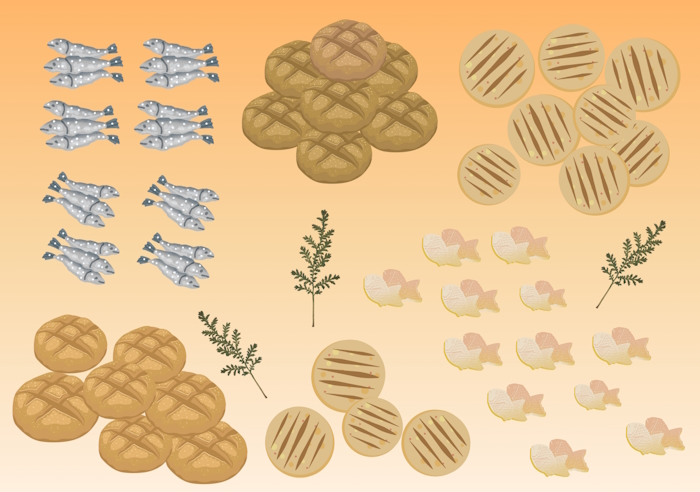今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「私の念願は二つ、ただ二つある。ほんとうの自分の句を作り上げることがその一つ、そして他のひとつはころり往生である」
--種田山頭火
漂泊の俳人、種田山頭火が、解く術もない惑いを胸に、熊本・味取(みとり)の観音堂を出て一鉢一笠、行乞流転の旅に出たのは、43歳の折だった。胸奥から吐き出されるは、五・七・五の定型にも季語にもとらわれぬ、自由律の俳句。
「分け入っても分け入っても青い山」
山頭火は明治15年(1882)、山口県の西佐波令村(現・防府市)に生まれた。生家は「大種田」と呼ばれる資産家だった。種田家はもとは土佐の郷士で、江戸期に移住。塩を扱う仕事や相場などで資産をなしたらしい。屋敷から山陽鉄道の三田尻駅(現・防府駅)まで徒歩20分余りの道のりを、他人の土地を踏むことなく到着することができたという。
9歳のとき、母親が自邸の井戸で投身自殺。このことが山頭火の心に深い傷を残した。山頭火は地元の中学を首席で卒業し早稲田大学で文学を学ぶが、神経衰弱により中退し帰郷。種田の家もこの頃から次第に衰微の道をたどる。父は先祖伝来の土地を切り売りし、明治40年(1907)にはとうとう一家をあげて隣村に移る。造り酒屋を居抜きで買いとり家の再興を期したが、思うようにいかず一家は離散。山頭火は熊本へ落ちのび、やがて出家した。
その熊本をも離れ、山頭火は流浪する。最後に落ち着いたのは、松山の地。松山は正岡子規の故郷でもあり、昔から俳句が盛んで俳人に理解のある土地柄。山頭火にとっても、どこよりも居心地がよかったのかもしれない。
句友たちが見つけてくれたのは、道後温泉から西へ歩いて20分余り、御幸寺(みゆきじ)の境内にある小さな空き家。昭和14年(1939)師走のことだった。
「おちついて死ねそうな草枯るる」
山頭火はこの住まいを「一草庵」と名づけた。一草庵の山頭火は、質朴の暮らしの中にふたつの願いを持った。それが、『私の述懐一節』と題する一文の中に綴られた掲出のことば。山頭火はつづけて、こう記した。
「病んでも長く苦しまないで、あれこれと厄介をかけないで、めでたい死を遂げたいのである。(私は心臓麻痺か脳溢血で無造作に往生すると信じている)」
その望みは、ふたつながら叶えられた。翌年10月、一草庵で句会のあった日、山頭火は集まった句友たちの傍らで蒲団の上に倒れたままイビキをかいていた。酒に酔ってこうして寝ている姿は、けっして珍しいことではなかった。
句会が終わり、寝たままの山頭火を置いて、句友たちは三々五々家路につく。家に帰りついたあと、何か山頭火の様子が気になった句友のひとりが庵に戻ると、さきほどまでと違い、山頭火の体は硬直しているかのよう。眠りも昏睡状態といった様子に変わっていた。すぐに医師を呼びに走ったが、医師が駆けつけたときにはすでに山頭火の息はなかった。死因は脳溢血。まさに本人が望んだ通りのコロリ往生だった。
そして、山頭火の遺した俳句の数々は、今も多くの人々を魅了しつづける。生前、最後の一句。
「もりもり盛り上がる雲へあゆむ」
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。