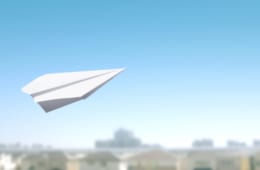文/印南敦史

ここ数年で、米粉が少しずつ定着、浸透してきました。
米粉を普段の生活に取り入れるスキルを身につければ、もっとおいしく、豊かに、健康的な食生活を送ることができます。我慢する必要はありません。小麦製品の代わりに、米粉を取り入れていけば、体質改善ができ、美容効果まで感じられます。
「最近なんだかつらい」「気持ちが落ち込みがちだな」なんていう方もあきらめないでほしいと思います。(本書「はじめに」より)
こう記している『不調が消えて心と体が整う すごい米粉』(みやなりちあき 著、横田真由美 監修、あさ出版)の著者は、11年の実績を持つというグルテンフリー・米粉研究家。なかでも「健康のための米粉」の探究に力を入れているのだそうだ。
たしかに、さまざまなメディア上で米粉の効能についての記述を目にする機会は少なくない。そんなこともあり、多少なりとも関心を抱いている方もいらっしゃることだろう。
だが“米粉生活”を実践しようとしたとき、「体にいいのはわかるけど、でも小麦を食べないのはつらい……」という思いが高いハードルとなって行く手を邪魔することも事実ではないだろうか。
しかし、本書を通じて米粉の知識と活用のスキルを身につければ、ハードルは思いのほか楽に取り除けるようだ。体調に合わせ、小麦と米粉とのつきあい方を考えるきっかけをつくることで、多くの悩みが解決できるというのである。
つまり本書を、自身の体調や健康、食の価値観などに合わせ、米粉を無理なく生活に取り入れていくための指南書として活用すればいいのだ。
米粉は基本的に白米から作られるため、玄米のように食物繊維が多いとはいえません。しかし、調理方法によって「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん) 」という腸内環境を整える成分が生成されます。(本書70ページより)
レジスタントスターチは穀類やいも類、豆類などの食品に少量含まれているものであり、普段の食生活でなにげなく摂取しているでんぷんの一種。消化されにくく腸まで届き、食物繊維に似た働きをするのだという。
冷やしたり冷ましたりすることで増えるという特徴があるため、たとえば白ご飯やおにぎりを冷ませばレジスタントスターチは増える。同じように米粉も、冷やせば効果があるわけだ。
レジスタントスターチの力によって、米粉パン、冷凍米粉パンを活用することで、お通じがよくなったり、腸内細菌や善玉菌のエサになって有用菌が増えたりなど、食物繊維と同様のいわゆる「腸活」効果が期待できます。(本書71ページより)
加えて米粉は、ご飯やパンなどの炭水化物の摂取を控えているという方にもいいようだ。腸内環境が整ったり、便通がよくなるなど、ダイエットにも充分な効果をもたらしてくれるのである。
米粉は、パンにしてもしっとり、もちもちとした食感が楽しめる。また、素朴でやさしい味わいを持つ米粉パンは、豚肉の生姜焼き、鯖の味噌煮、海苔の佃煮、きんぴらごぼう、味噌汁など、和風のおかずと合わせても違和感がないのだという。
お米には「グルタミン酸」という成分が含まれています。
たとえば、なにも味つけしていないご飯を長く噛んでいると、だんだん甘みを感じてきますよね。この甘みの成分がグルタミン酸です。
グルタミン酸は、こんぶやトマトなどにも含まれているうま味のもとになる成分で、とくに塩と合わさることで、味覚を強く刺激し、「おいしい!」と感じやすくなることが特徴です。(本書85ページより)
そんな和食の調理法を活用した米粉料理は、「AGEs(終末糖化産物)」を発生させにくいという特徴もあるそうだ。AGEsはシミ・シワ・たるみなど老化の原因となる物質で、高温で炊いたり揚げたりした料理に発生しやすい。体内に蓄積されると、肌の老化や血管トラブルを引き起こす可能性も否定できない。
しかし和食は、煮る、蒸すなどの調理が多いため、AGEsが発生しにくいわけである。
油をあまり使わずに作るオイルレスの米粉パンであれば、和食と合わせることで、自然とAGEs対策になり、アンチエイジング効果も期待できます。
この食べ方を続けることで、肌のシミやシワ、くすみが改善するなどといったうれしい変化が少しずつあらわれてきます。(本書86ページより)
また、和食のおかずと相性がいい米粉なら、自然と脂質の摂取量を減らすことも可能だ。しかも、お米に含まれるアミノ酸のうま味は、シンプルでも満足感を与えてくれる。美容と健康にいいだけでなく、おいしさも実感できるため、充実した食生活を送れるのだ。
つまり米粉食品は、和食と組み合わせて食べればAGEsも抑えられ、肌の老化対策にもなるのである。先入観を取り払って「米粉生活」を試してみれば、思っていた以上の満足感が得られるかもしれない。
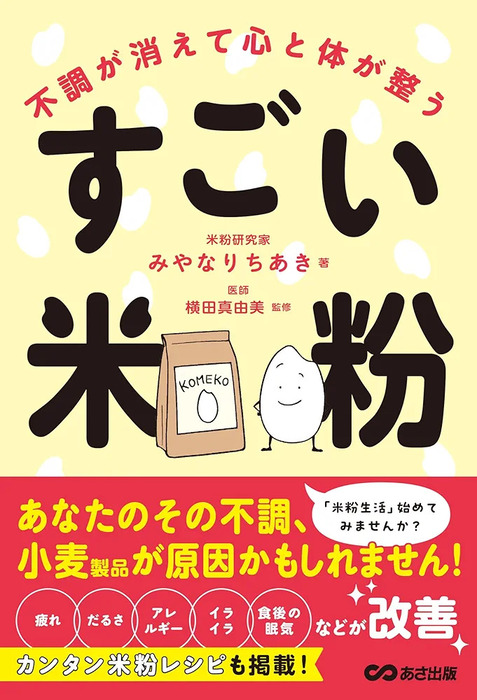
みやなりちあき 著、横田真由美 監修
1540円
あさ出版
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。