文/鈴木拓也

もう何十年も前のこと。筆者が臨んだ大学受験は、未曾有の競争倍率であった。それは、少し前の年がひのえうま(丙午)にあたり、多くの夫婦が子供を生み控えた反動だからと聞いた記憶が残っている。
受験のことで頭がいっぱいの筆者にとって、なぜひのえうまだと、生み控えするのかなんて、考えもしなかった。
それから幾星霜。2026年は60年ぶりのひのえうまと知り、ちょっと興味がわいたタイミングで刊行されたのが、新書『ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会』(吉川徹/光文社 https://books.kobunsha.com/book/b10131909.html)だ。著者は、大阪大学大学院人間科学研究科の教授で、59年前のひのえうまの生まれ。一読してなかなか面白く、長年の蒙が啓ける思いであった。
今回は、本書の内容の一部を紹介しよう。
放火を起こした八百屋お七が発端
ひのえうまとは、陰陽五行説の十干十二支の1つ。これで暦年を表し、60年で1つの周期をなしている。ひのえうまは43番目である。
東アジアでは、ひのえうまは災禍の多い年とされているが、子の生み控えにつながる迷信が生まれたのは、日本だけだそうだ。
発祥は、放火事件を起こした八百屋お七が、ひのえうまに当たる1966(寛文6)年の生まれだからというもの。その頃から、ひのえうま生まれの女性は気性が激しいという俗信が出始めた。
次の1726(享保11)年のひのえうまになると、この年に生まれた女性との婚姻を厭う風潮がはっきりと現れる。(ひのえうま生まれの女性が婚期に入る)18世紀半ばに詠まれた川柳には、そうした女性への嘲りを含んだものがいくつか残っている。
例えば、「蛤(はまぐり)にせつせつ座る丙午」という句について、吉川教授は次のように解説する。
その意は、蛤の吸い物が縁起物として出される婚礼の席に、ひのえうま女性は何度も座るということで、夫を次々食い殺すという俗説に拠って、ひのえうま女性が再婚を繰り返すことを皮肉ったものです。(本書27pより)
そのせいで今度は、ひのえうまの年は出産を忌むという方向へ展開。江戸時代においては珍しいことではなかった堕胎や間引きが、この年には一層増加するという悲惨な結果をもたらしている。
日露戦争が影響した明治のひのえうま
少し時代を下って、1906(明治39)年のひのえうまを見てみよう。意外にも、この年の出生数の減りは小さいもので、「前年比でおよそマイナス5万8千人(約4%減)」にとどまっている。
これは、日露戦争があったことが大きい。この戦争は1905年9月に日本の勝利に終わったが、それまでの間多くの成人男性が兵役に動員されていた。戦争の終結後、帰国してきた彼らは、早く子を授かりたいという気持ちが強かったであろう。また、国の人口増強政策もあって、ひのえうまを気にする人は少なかったようだ。くわえて、生まれは1906年でも、出生届を翌年に遅らせる「祭り替え」もあった。
明治ひのえうま生まれの女性の受難が顕在化するのは、いわゆる結婚適齢期になってからだ。当時、世論への影響力の大きかった新聞が、「降る縁談が皆纏(まと)まらず 丙午生まれの美人自殺」などと報道を重ねた。新聞は、迷信打破の論説を展開するものの、むしろ大衆煽動を引き起こす結果となってしまった点を、吉川教授は指摘する。
恩恵のほうが大きかった昭和ひのえうま生まれ
そして、1966(昭和41)年のひのえうまだが、出生数は前年比で25%減という激しい落ち込みを見せた。それまでの数年は緩やかな増加を見せ、翌年の1967年はいきなり30%増というから、多くの夫婦は、明らかにひのえうまを意識していたのである。
そうなった大きな要因は、やはりマスメディアであった。このころになると、新聞にくわえ、雑誌、ラジオ、テレビが人々の生活に必要不可欠な存在となっていた。もちろん、メディア各社の論調は、ひのえうまは迷信以上の何物でもないというもの。一方で、加熱気味の報道が、「寝た子を起こす」効果をもたらしたのもまた事実であった。また、この時代になると、避妊によって子の出生年をずらすことは容易となり、人工妊娠中絶に踏み切る妊婦も今よりもずっと多かった。こうした要因が重なって、史上稀に見る出生数の減少がもたらされたのである。
では、ひのえうま生まれの女性たちが、青年期以降に辛い思いをしたかといえば、概してそうでもないようだ。吉川教授は、次のように書いている。
こうしてひのえうま学年は、迷信から巡りめぐって生じた大出生減の思いがけない恩恵として、他のどの学年よりも少しだけ密度が高い初等・中等教育を受け、他のどの学年よりも全国大会出場や入賞のチャンスが多めで、他のどの学年よりも高卒就職が有利で、大学受験が広き門であるという、幸運な青少年期を歩んだのです。(本書168~169pより)
おりしも彼女らが社会に出る頃は、バブル景気が全盛。少し前に施行された男女雇用機会均等法も手伝って、就職しやすい環境にあった。直後に平成不況にさらされるものの、それより後の世代に比べ、比較的好ましい境遇に恵まれた。
* * *
さて、本書の終章では、「どうなる令和のひのえうま」と題して、来年のひのえうまについて予測が述べられている。少子化がさらに加速するのか、はたまた何か想定外のことでも起きるのか。それについては、ここでは触れないことにする。興味がある方は、ぜひ手に取られ、読んでいただければと思う。
【今日の教養を高める1冊】
『ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会』
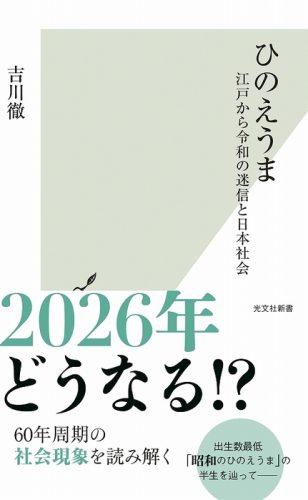
定価990円
光文社
文/鈴木拓也
老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。




































