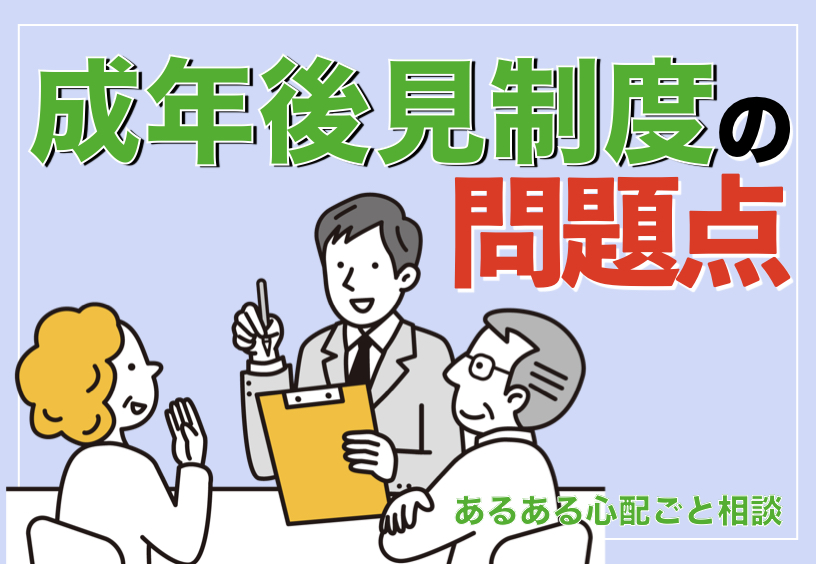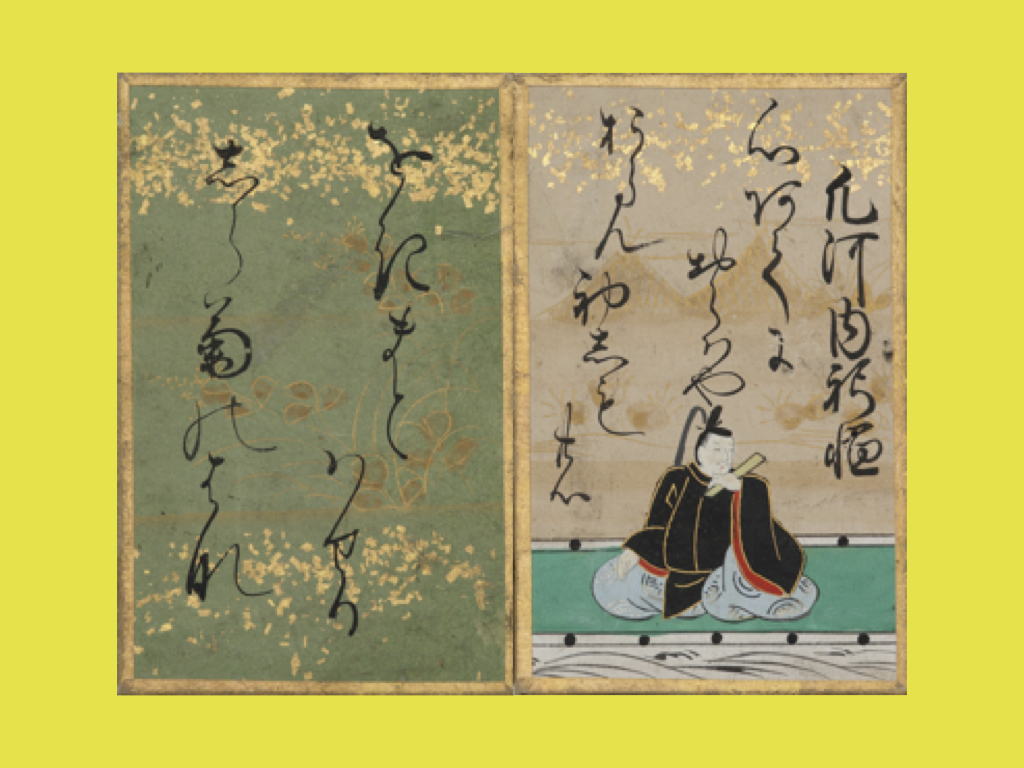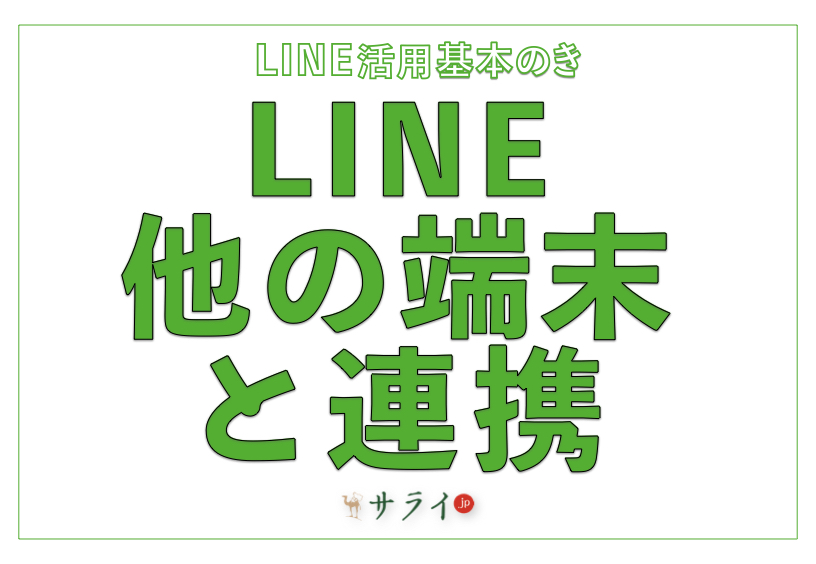note(ブログ)の記事やSNSで共感を集める作家・岸田奈美さん。デビュー作のエッセイ集『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』(小学館)は2023年にNHKで連続ドラマ化され、話題となった。新刊『もうあかんわ日記』(小学館文庫・2025年 https://www.shogakukan.co.jp/books/09407435)では、母が感染性心内膜炎のため、シビアな心臓手術を受けることになり、一家のバランスが崩れはじめる様子がリアルに綴られている。入院のために母という大きな存在がなくなり、認知症が進む祖母、ダウン症の弟とのカオスな日々を通して、すべてのタスクを背負った奈美さんは、「家族」について、新たな気づきを得る。今回、新刊の発売を記念して、岸田さんにカオスな日常とこれからの創作活動について伺いました。
頑張りを無に帰す、認知症のおばあちゃん
──どのようなきっかけで、おばあちゃんが認知症であることに気付いたのですか?
「私が大学1年のときぐらいから、少しずつ症状が出ていました。
ただ、もともとおおざっぱな性格のおばあちゃんだったので、最初は分からなかったんです。
母が仕事帰りに「ご飯ある? ないならお弁当買っていくよ」とおばあちゃんに電話する。すると、「ご飯はあるよ。買うのはもったいないから帰ってきて」っておばあちゃんが答える。母が家に帰ると、きゅうり1本と塩だけが出てきたことがありました。今考えたら、これは認知症の始まりでした。
その後、ご飯を1日何回も出したり、お鍋で奇妙な煮物をつくったりするようになりました。
私が忙しさで家のことをみられていなかったとき、その煮物を弟に食べさせていたんです。健康診断で弟が肥満を指摘されるようになって、異変に気付きました。おばあちゃんと弟を一緒にしていちゃマズイと焦って、老人ホームを探したんです。
こうしておばあちゃんはグループホームに入り、3か月に1回のペースで面接に行っています。おばあちゃんはなんとか私のことは覚えているのですが、うちのお母さん(自分の娘)のことはほとんど分からなくなっています。面会に行くと、2時間の間に30回くらい「今何歳や?」って聞いてくるんです。たまに会うのであれば笑っていられるのですが、毎日一緒に過ごしているとしんどくなってしまいそうです」
──おばあちゃんに向き合うなかで、特に大変さを感じたのはどこですか?
「いろいろなことを、忘れてしまうことですね。忘れるだけならまだマシなのですが、状況を悪化させてしまうんです。
私が仕事で家をあけるときに、おばあちゃんに沖縄そばを作って置いていったことがあったんです。でも、「おばあちゃんのご飯がない」ってヘルパーさんから電話がかかってくる。おばあちゃんに聞いたら「汁だけだったから捨てた」って言うんです。
「汁を温めて、ゆでておいた麺をあわせて食べるだけ」というところまで準備して、伝えてから外出したにもかかわらず、それを台無しにしてしまう。もう、やるせない思いでした。
ほかにも、ドラム式洗濯機で洗濯物を乾かしているときも、おばあちゃんは「機械で乾かすのが気持ち悪い」と言って、全部ドラムから引きずり出していたんです。洗濯物を外に乾かす習慣があったからだと思うんですけど……。引きずり出すのに疲れて、洗濯物を引きずり出す途中のままになっていることもありました。家の中で犬がおしっこしても拭かないままのことも、しょっちゅうでした」
──頑張りが無に帰すことは、徒労感に襲われますね。
「ええ。認知症の人を介護する様子を、ポスターやドラマなんかで見たことが影響しているのか、みんな訳知り顔で言ってくるんです。「認知症の方にはプライドがあるので優しく介護しましょう」って。でも、必死で準備しておいたことを台無しにされると、どうしても怒りが先にグワーってきてしまうんですよ。
家族に優しくできない醜い感情を自分自身で見るのは、最初、しんどかったです。「なんで私はおばあちゃんのために頑張れないんだろう」と思っていましたね」
「それぞれの正義とおせっかい」への苦悩
──認知症の家族にイライラする自分を許せないという声を、他でも聞くことがあります。岸田さんは、どうやって気持ちを切り替えていましたか?
「一旦、書いて吐き出していました。それがnoteに綴って、今回、文庫にもなった『もうあかんわ日記』です。冷静になって見つめると「おばあちゃんをみるのは嫌だ」という思いと「おばあちゃんに優しくしたい」という思い。その両方が本当なんですよ。文章にしたことで、自分の気持ちを認めることができました。
ツッコミを入れながらテンポよく日々のことを書いていくと、少し俯瞰した位置から今いる状況を見直すことができるんです。すると「ヤバ私!」と思えて、笑けてくる。
そして「ケアマネージャーさんに連絡してみようかな」とか「無理して洗濯しなくてもいいかな」という考えが浮かんでくる。自分の思いをいったん全部認めると視点が切り替わるので、それによってイライラを手放せていました。
何が辛いと言えば、その複雑な気持ちを、例えば役所とかで言っても誰も受け止めてくれないことでした。
ちょっとでもポジティブな気持ちを出すと「じゃあ、まだ頑張れますよね。あなた若いんだからフリーランスの仕事をやってないで正社員で職探してもよくないですか?」みたいなことまで言われて、私の複雑な気持ちを完全に理解してくれる人が当時はいなくて……。みんな思い込みで喋ってくるんです。「それぞれの正義とおせっかい」で話をされるのもしんどかったです……」
――「気持ちは分かるけど……」とヘルパーさんに施設入居を反対されて葛藤したという話が、ご著書にもありましたね。
「ええ。相手の気持ちなんて、1割ぐらいしか理解できないものだと、私は思っているんです。同じ状況でも人によって考えることは違うから……。
おばあちゃんはオンラインでの会議中に部屋に入ってきたり、パソコンの電源を落としたりしていました。だから同居で介護をしていると本当に仕事ができないんですよ。なので、同居するということは、結局、私が作家として仕事する道を絶つことになるんです。
私は、家族それぞれが得意なことを仕事にすべきだと思っています。
私にとっては、それが書く仕事だったんです。弟の場合は、人と関わることだと思っています。
うちの弟は、知的障害があるので世の中的にはマイナススタートです。弟に計算や漢字を教えてもなかなか覚えられないし、頑張ってもまわりのみんなよりできない。
だけど彼は人に気を遣わないのに人に好かれる能力がとても高い。自然に生きているだけで、ファンをつくってくるんです。だから、勉強よりもそっちの能力に全振りさせた方がいい。お金を稼げなくてもいいし、勉強なんてできなくてもいいから、とにかく人と関わる機会が多い場所にいてほしいんです。
それが結局は、岸田家の生存確率を上げる方法になると思うので」

壁にぶつかったことで伝える能力が開花した弟
──現在は、ご家族それぞれどのような暮らしなのですか?
「おばあちゃんはグループホームに引き続き入居しています。弟も今は知的障害のある人たちのグループホームに入って、4人ぐらいで暮らしています。私とお母さんは、それぞれが一人で暮らしているんです。
おばあちゃん以外は毎週末に家に集まり、お母さんがつくってくれるご飯を食べて1泊2日ぐらいの時間を家族で過ごしています」
──ちょうどいい距離感なのではないでしょうか。
「ちょうどいいですね! 今までは、家族同士で互いに依存していたことで、本来の力を発揮できないことや、本当にやりたいことができないことがありました。
弟もグループホームに入ってから、以前より言葉が話せるようになって驚きました。今までは、私や母が弟に代わって話をすることで、場を整えていたんです。それによって弟が傷つく場面を減らすことができました。しかし、自分で生きる力が出てくるのを抑えてしまっていたこともあったと思うんです。
もちろん、最初は弟もグループホームに入って戸惑ったり喧嘩したりしていました。でも、意思を伝えなければ、お風呂に入る順番を決められなかったり、ご飯をおかわりできなかったりする。苦しんだ結果、身振り手振りで気持ちを伝えられるようになったんです。壁にぶつかって試行錯誤することで能力が開花しました」
生まれて初めて、自分のためにジャムを煮た母
──壁にぶつかってみることが必要なときもありますね。お母さんは、今どのような状況なのですか?
「母もおばあちゃんの介護や家族のことから手が離れ、自分の人生を取り戻しています。
母は家事が好きでしたが、何をやっても認知症のおばあちゃんに台無しにされるので、うつ状態になっていました。おばあちゃんは母の料理を食べ散らかしたり、捨ててほしくない物を捨てたりしていましたから……。そこで、それまでは「自分がおばあちゃんや弟の面倒をみていかなきゃ」と思っていた母に、「全部自分が我慢すればいい」という発想を捨てることを頑張ってもらいました。そして、おばあちゃんや弟が入れる福祉施設を一緒に探しました。
現在、母は兵庫県の都会で一人暮らしをしています。20分くらい車椅子をこいで自分でスーパーに行くようになりました。以前に住んでいた家は山だらけでしたが、今住んでいる家は、買い物に出やすい環境です。
バブル期に就職したあと専業主婦になった母は、ずっと夫(私の父)の言うことを聞いて生きてきました。だから、父が亡くなったあと“自分の意思で何かを選ぶ”ことができなかったんです。
そんな母が、先日「生まれて初めて自分のためにジャムを煮た」と言っていました。
“家族のため”ばかりを考えて生きてきた母が、ようやく今、自分のやりたいことを探して挑戦しています。その姿はとても楽しそうで……。見ている私も嬉しくなるんです」
──それぞれにとっての新しい人生が始まったのですね。
「そうですね。家族がバラバラに生活するのは寂しいけど、この寂しさがあるから久しぶりに会ったときに仲良くできます。
家族の問題を家族だけで解決しようとすることが、どれだけ苦しくて無理なことなのか、今までの人生で分かりました。その経験があったからこそ、そうじゃない生き方が選べたのだと思います」
どんな子どもも親の幸せを願う
──お母さまは、車いすになってかなり葛藤した時期があったと、ご著書に書かれていましたね。
「私が高校生のときは、「歩けないなら死んだ方がマシだった」と言っていました。今でもずっと「歩きたい」と言っているし、車いすの自分に引け目を感じることも、しょっちゅうあるようです。
そんな母に対して「とにかく自分がハッピーでいられることをしてほしい。それが私の幸せだから」と言っています。
これは私の持論なのですが、どんな子どもも、親が幸せであることを願うと思うんですよ。
親が自分にお金をくれても、親の機嫌が悪くて不幸せだったら、すごく気になるし辛い。でも、親が幸せで機嫌が良かったら、親のことを気にしなくていいじゃないですか。そして、自分は、好きなことに集中して生きることができます。
人の思い込みを解くことはめんどくさいけど、幸せに生きるために避けて通れない道だと思います」
「世の中の機嫌」が良くなるために
──家族それぞれが新しい生活になり、今後はどんな生き方がしたいですか?
「今まで、一般的に家族が直面するしんどさの多くは、経験してきました。だから、家族のことはまた何かが起こったとしても、大丈夫だと思うんです。『もうあかんわ日記』で言うと、今は28日目ぐらいだな~なんて思いながら対応できるので。
極論を言うと、私が死んだ後のこともあんまり心配していません。
今までは、家族だけで頼りあって生きてきましたが、今は家族それぞれが依存できる場所を見つけています。私がいなくても誰かが助けてくれる環境をつくれたと思うんです」
──岸田さん個人の創作活動としてはいかがですか?
「今の課題としては、超個人的な岸田奈美の話ししかできていないことだと思っています。私の本を読んでくださった方に「岸田奈美さんを応援しよう」と思ってもらえることは、とてもありがたい。でも、そこでとどまってちゃダメだなぁって思うんです。私と読者の二方向のやりとりでしかないからです。
私は、世の中に「機嫌が良くなってほしい」と思っているんです。なぜなら、障害のある弟、お母さん、認知症のおばあちゃんのことを助けてくれる人って、みんな機嫌がいい人だったんですよ。機嫌がいいからこそ他人のことを想像する余裕がある。弟がやりたいことや言いたいことを把握して、手を貸してくれる人がいたんです。でも、機嫌が悪い人ばっかりだと、弟にイライラをぶつけて、逆上されたりするんですよね。
だから、世の中の人が機嫌よくいられて、そばにいる障害者や認知症の人への想像力を膨らませるためには、私以外の話もしないといけないなぁと思っています。
そういう意味で、最近はドラマの脚本を書かせてもらったり、小説でフィクションストーリーを書かせてもらったりしています。岸田奈美の個人の話だけでは伝えきれないことを、いろいろな人の視点や立場になって考え続ける。そして、私なりの答えを出し続ける場所をつくっていきたいと考えています。
そのためには、その思いをどう表現するかが大切です。怒りや悲しみだけをただ訴えるのではなく、理不尽さを描いたうえで「なんかこの人の話、笑わせてくれる」と思わせる愛嬌のようなものが必要だなと思います」
取材・文/谷口友妃
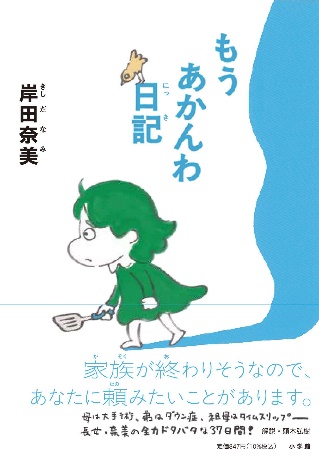
岸田奈美 著
847円
小学館文庫