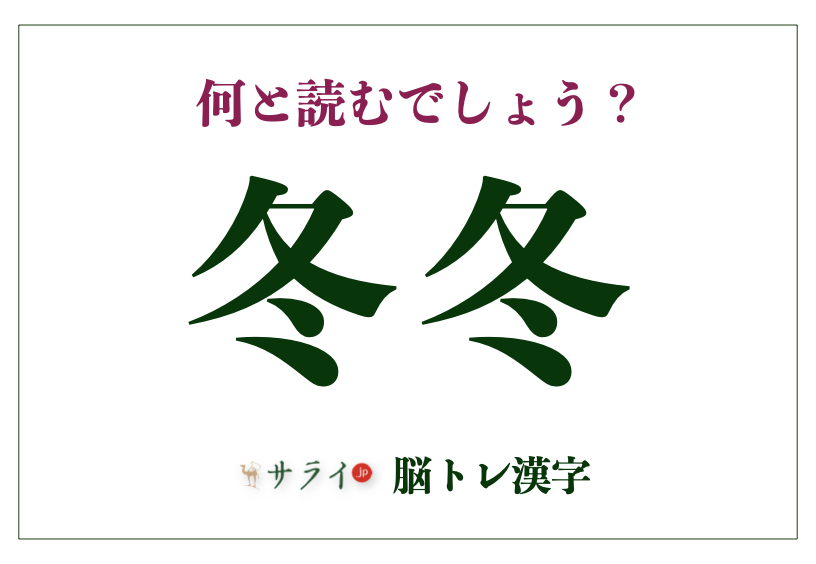「死に意味があった、という発見を広く伝えたかったのです」

小林武彦著 講談社現代新書(電話:03・5395・4415)990円
私たちにとって「恐るべき死」だったものを、「生物の進化にとって必要な死」と見方をガラッと変えてくれるのが本書だ。「死は、命のバトンを繋いでくれていたのです」と小林武彦さん。
生物はなぜ死ぬのか。
人間の本質に迫るテーマに、新書で挑んだのは、生物学者の小林武彦さんだ。
「酵母菌を用いて老化を解明する研究をしているのですが、酵母菌に“死なせる遺伝子”があることに気づきました。生物には、死がプログラムに組み込まれている、ということです。ならば、生物学的に死にも意味があるのではないか。これが発想のスタートです」
私たちは「死」を、主体的に捉えてしまう。「個人の死」が頭にあるからだ。生物学的な観点で見ると、「死」は別の様相を呈す。
「進化とは、“変化と選択”のことです。環境にあわせ、変化しなければ生き残れないわけです。例えば、砂漠化が進み、木から降りざるを得なかったヒトは、肉食獣に囲まれ、最大の危機を迎えます。このとき、多様な個体が多様な集団を作り、多くが絶滅する中で、逃げ足が速かったのか、知恵を用いたのか、たまたま生き残った集団があった、ということです。つまり絶滅=死が、進化をもたらしているといえます。生物は、次世代のために死ぬ、といってもいいでしょう」
死には、意味があったのだ。
「この発見を広く伝えたかったのです。それには、気軽に手に取れる新書がいいですよね。新書はいわば、“知のお裾分け”。みなさんにもどうぞ、という思いで新書を書きました」
老いは社会の役に立つ
コロナで死が身近になっていたことも手伝って、『生物はなぜ死ぬのか』は18万部超のベストセラーになった。
「本を読んだ80歳を超えた親戚から、“俺の仕事は、あとは死ぬだけだな”と言われましてね。老いにも価値があるんだということを、きちんと伝えなければと思ったんです」
それが続編に当たる『なぜヒトだけが老いるのか』だ。
「野生の動物は老いません。老いは、ヒトにだけ与えられた特権であり、老いが人間社会を発展させてきました」
ヒトは子育てを集団で行なってきた。このとき高齢者のいる集団は手も多く知恵もある。高齢者の知恵は、利害調整や社会の安定にも繋がったと小林さんはいう。
「老いは、社会や公共の役に立っています。高齢者の方は胸を張ってほしいですね」

小林武彦著 講談社現代新書(電話:03・5395・5817)990円
「死」は生物に等しく訪れるが、「老い」はヒトにしかやってこない。では「老い」とは?本書ではその意味を明らかにする。「社会全体で、“老い”に価値を見出すべきでしょう」と小林さんは話す。

取材・文/角山祥道 撮影/高橋昌嗣
※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。