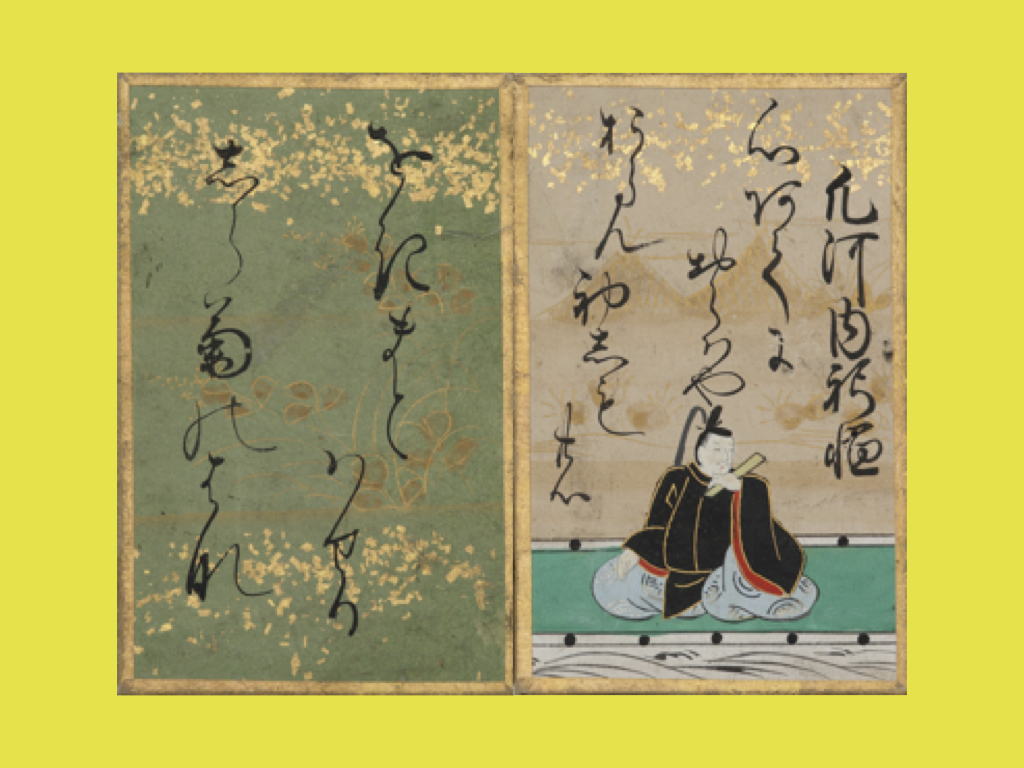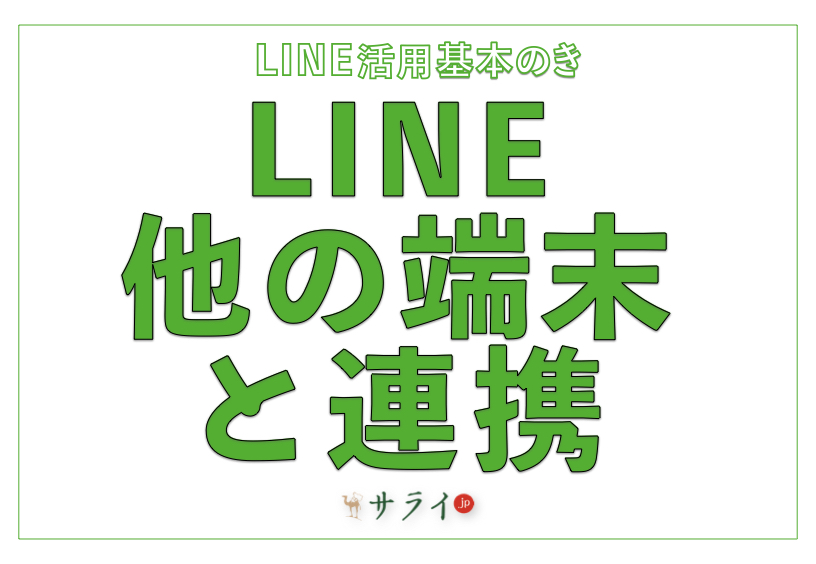■津軽に逃れた三成の次男
奥羽仕置の結果、奥羽の諸大名は、おしなべて減封となった。政宗は天正14年7月に入手した二本松領が没収された。和賀・稗貫両氏は、宇都宮に来た秀吉に伺候(しこう)しながら本領を没収された。最上・本庄領を除く出羽の大名領には、本領の三分の一の豊臣蔵入地が設定された。
ところが、秀吉の命令を無視して戦闘した安東(あんどう)氏が本領を安堵されたり、津軽氏が南部氏から攻め取った津軽を安堵されたことは注目される。豊臣国分とは、最後までこのような恣意的かつ理不尽な側面をあわせもつものだったのである。
かくも峻厳をきわめた秀吉の奥羽統一が、津軽氏の南部氏からの独立を実現したことから、弘前藩においては秀吉はもとより、様々な支援を得た三成に対する恩義は格別のものと位置づけられたのは当然であった。それは、慶長5年(1600)年9月の関ヶ原の戦いの後の三成の子どもたちへの処遇からもうかがわれる。
三成の次男・重成は、豊臣秀頼に小姓として仕えていた。同僚だった津軽信建(為信の長男)の指示を受けて、なんと若狭から日本海ルートで津軽まで逃れたのであった。さすがに姓名はそのままとはいかず、杉山源吾と称した。
その長男吉成は二代藩主・津軽信枚(のぶひら)(為信の三男)の娘を妻として家老となり、杉山家は代々藩重臣として存続する。これは弘前藩において、いかに三成に対する恩義を意識していたのかを示す史実である。
文/藤田達生
昭和33年、愛媛県生まれ。三重大学教授。織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とする歴史学者。愛媛出版文化賞受賞。『天下統一』『明智光秀伝 本能寺の変に至る派閥力学』など著書多数。